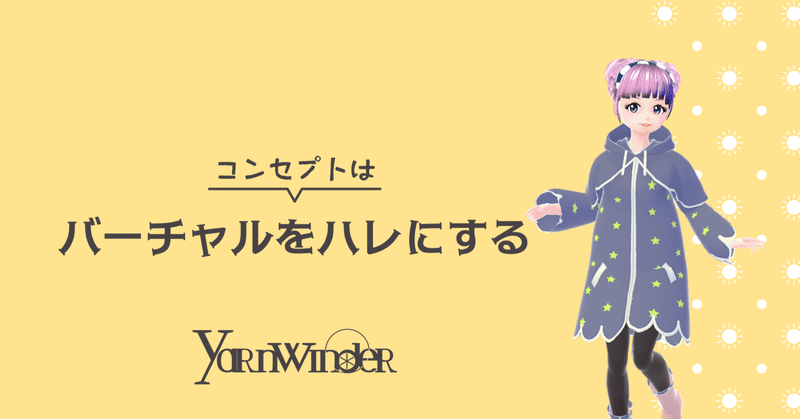
コンセプトは「バーチャルをハレにする」
こんにちは。柑酉衣豆(かんどりいと)です。
Yarnwinder(やーんわいんだー)という3Dモデル用衣装のファッションブランドで自作の衣装を制作販売しています。
3Dモデルの衣装とは?と思った方はぜひ私の自己紹介noteからご覧ください。
今日はバーチャルファッションブランド「Yarnwinder」のコンセプトのお話です。
Yarnwinderのコンセプトはバーチャルを「ハレ」にするです。
そのコンセプトに込めた想いをひとつずつ分解してお話ししていきましょう。
バーチャルって何?
昨年バズワードとして「メタバース」という言葉が一気に盛り上がりました。
とはいえ、実際のメタバース体験をしたことのある方はそんなに多くないと思います。
メタバースを(VRなどで)体験したことのある方は現実世界の「仮想」であって
現実世界と切り離されたひとつのパラレルワールドのように感じる方も多いと思います。
でもよく考えてみてください。
会議室でおこなう会議が現実だとして、オンライン会議は完全な現実世界のものでしょうか、完全な「仮想」でしょうか。
それではSNSで仲良くなった人たちは「仮想」なのでしょうか。
現実世界とメタバース?仮想世界?の境界はどこにあるのでしょうか。
実はおそらく私たちが暮らしている中で、現実とは切り離せない形で「メタバース」というのは生まれてきているのかもしれません。
現実世界=物理的・身体的生活社会ということだとしたら、メタバース=デジタル生活社会という別の社会が形成され始めているというように思います。
現実か仮想か、ということではなくて、物理かデジタルかの違いということです。
コンセプトを考えた当初は「メタバース」が今ほど認知されずバズワード化もしていない頃でした。
そのため「バーチャル」というのも「メタバース」と同じような「デジタル空間」「デジタル社会」くらいの意味で使っていました。
ですが「デジタル社会」が形成され「メタバース」と言う形で認知され始めました。
だからこそ、その中で実現できる「バーチャル=仮想」の価値を考え始めました。
「身体的制約」というのは現実世界には必ず存在して、それは「障がい」から「コンプレックス」のような様々なものが考えられます。
「メタバース」では身体的制約を限りなくゼロにします。
メタバースでのデジタルな身体を「アバター」として話を進めます。
「アバター」であれば、老いてても若者になれるし性別を変えることも可能です。
AIが「アバター」を獲得して違和感なく一緒に生活することも可能になるでしょう。
脱線しますが、鉄腕アトムやドラえもんの影響か、AIというと物理的に現実世界でロボットとして登場するように思ってしまいます。
が、デジタル処理だけで生成できるであろう「アバター」が先に「生活」するようになるのではないか?と思っています。
閑話休題。
身体的制約がないということは「アバター」はひとつでなくても良いんですよね。
現実世界でも「家族に見せる顔」「友達に見せる顔」「会社で見せる顔」それぞれちょっとずつ違う自分を作っていると思います。
それぞれのシーンや社会にあわせて、本当にまったく見た目も違う「顔」と「身体」になることができるのが「メタバース」だと思うのです。
そして「メタバース」でだけの人間関係、コミュニティを作ることもできます。
SNSで顔も本名も知らないけど仲良しとか普通にいると思うんです。
それがデジタル空間でデジタル身体で行われるだけのこと。
そこでの「アバター」の見た目はより自由です。
コンセプトで「バーチャル=仮想」を使い続けようとしたのはそこに鍵があります。
つまり「メタバース」でだけ見せる「メタバース」だけの顔や身体。
それは現実世界とはもしかしたら全く違う「仮想」の自分かもしれません。
でもきっとそれは自分の身体的制約から自由になり、自分の見た目から自由になり、新しい自分の可能性を見出す「仮想」なのだと思います。
だからこそ「バーチャル=仮想」を「ハレ」にしたいのだと思っています。
ハレって何?
「ハレ」という概念を最初に提示したのはかの日本民俗学の祖・柳田國男氏です。
著書「明治大正史 世相篇」に 初めてその考えが示されています。
「ハレ」とは日常とは違った「特別」な日・場所・衣服などを指しています。
と説明されなかったとしても
「ハレ」という言葉や考え方は日本人に深く根付いていると思います。
日本に住んでいたり、日本文化に深く触れると、なんとなく感覚的に伝わる部分があるのではないでしょうか。
「晴れ舞台」「晴れ着」などの言葉でも使っていますね。
今のようなお天気の「晴れ」を指すようになったのは最近で、「ハレ」はもともと「折り目」「節目」という意味だったといいます。
ハレの対義語は曇りでも雨でもなく、日常をあらわす「ケ」という言葉でした。
「ハレ」と「ケ」という概念は今もなお、諸説があり明確な定義はありません。
ですが「ケ」つまり日常の反対側、非日常に「ハレ」は存在しています。
諸説がある分、いろんな解釈が「ハレ」にはあります。
「冠婚葬」の「ハレ」は「折り目」「節目」ですが
「祭」についてはそれだけではない作用もあります。
「特別」もそうですが、一説には「異世界」を意味することもあります。
確かに「祭」の多くは神仏との交流をはかったり、普段は閉ざされている地に足を踏み入れるものが残っています。
一説には「ケ」は日常であり、生きる活動、生きるエネルギーつまり「気」である。
それが枯れて「ケガレ」になるという説があります。(ケガレ=気枯れ)
コロナ禍を経て、おなじ日常をずっと繰り返すとエネルギーが枯れたようになるという経験は多くのひとにあるのではないでしょうか。
そこに登場するのが「ハレ」です。
特別な、異世界の、「ハレ」に行き、日常のエネルギーを充填するという説です。
コンセプトでいう「ハレ」とは「日常のエネルギーを充填する」場所・時間・コミュニティなどを想定しています。
もちろん「晴れ着」などの視覚的な衣装モチーフとしても扱っています。
ですが、現実から離れ、エネルギーをもらうことに一番の意味があります。
参考図書
柳田國男「明治大正史 世相篇」新装版 1993年(講談社学術文庫)
桜井徳太郎 他「ハレ・ケ・ケガレー共同討議」1984年(青土社)
バーチャルをハレにするって何?
仮想(=バーチャル)と現実の関係と、ハレとケの関係はとても似ている概念のように思いました。
というよりは、ハレとケの関係のように、現実世界をより生きるための「仮想」であってほしいと考えています。
そしてそうあろうとした時に、ファッションの機能は非常に大きいと思います。
現実の身体的制約から離れた時、メタバースでアバターを手に入れた時、顔や身体自体はもちろん重要です。
さらに「新たな自分」を獲得するのには「ファッション」は欠かせません。
バーチャルファッションは「新たな自分をバーチャル(仮想)的に作る」ことに「機能」するのです。
ファッションの多くは自分自身の「見せ方」に寄与します。
こういう自分になりたいという見せ方をファッションで作ることができるんです。
それは単純にバーチャルでだけ新たな自分を実現して終わりではありません。
バーチャルで実現したことにより現実世界でのエネルギーになっていくのだと確信しているのです。
Yarnwinderは
新たな自分の可能性を「バーチャル」で発見し
現実世界でのエネルギーを得て、より喜びにあふれた日々を暮らすため
3Dモデルの衣装をファッションを生み出していきます。
そう。それが
バーチャルを「ハレ」にする
バーチャルファッションブランド、Yarnwinderです。
まずはboothの商品からでも試してくださいね〜
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
