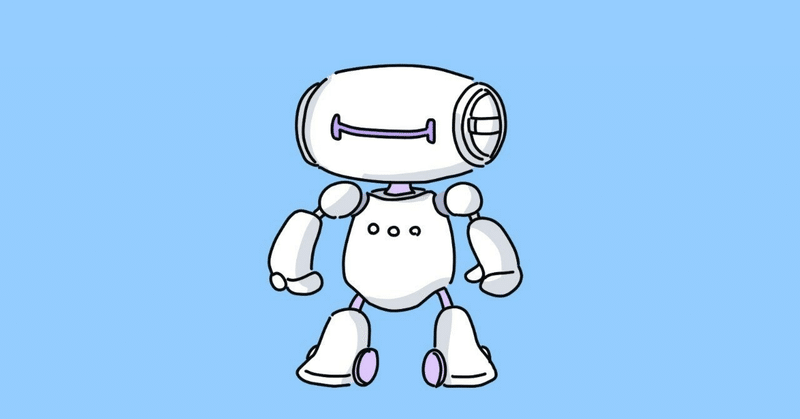
人工知能に意識はあるのかという問題
世界のSF化が進むなかにあって、かつてSFのなかで語られてきたものについて、真剣に考えなくてはいけなくなってきたように思います。
人工知能(AI)に関するものも、そのひとつです。
ものすごい勢いで発展をし続けている人工知能の分野ですが、果たして、彼ら(人工知能)が意識を持つようになるのか?このことを、大真面目に考えなければならない時代になってきました。
ただし、これについては、否定的な見方があります。
現代のAIの多くは、1つのトランジスタが数個のトランジスタから入力を受け取り、別の数個に反映するというノイマン型ですが、人間の脳はもっと複雑で、これとは根本的に異なる因果的な力を持っています。ノイマン型のチップで実行されるAIは、知能的な行動がみられても、人間の脳のように「意識的」にはなり得ないとのこと。
「人工知能(AI)は意識を持つようになるのか?を神経科学者が解説」
2020年5月14日より引用
「ノイマン型」という言葉が出てきてはいますが、要は「計算機」ということです。人工知能を構成するものが、計算機のように入力されたデータを素早く演算処理して、それを出力することがコンピューターであるとするならば、そんなものが「意識的」になるはずがないということです。
まぁ、何となく理解できます。
一方で、同じ記事では、このようにも述べられています。
コッホ氏はノイマン型ではない、別のアーキテクチャを持つマシンによって、「意識」が作り出される可能性があると考えています。高度な統合情報を可能にする量子コンピューターや脳型コンピューターがその候補として挙げられています。
「人工知能(AI)は意識を持つようになるのか?を神経科学者が解説」
2020年5月14日より引用
ノイマン型ではなく、脳型コンピューターであれば、意識が生まれる可能性があるということです。脳型コンピューターについては、例えば、こんな説明がなされるようです。
両者の決定的な違いは、脳は目標を達成しようという努力にこそ意味があり、コンピュータは結果の正確さや速さに意味があることです。脳型コンピュータとは、脳の原理で成長する能力を持ちながら、人間のために存在する工学産物です。つまり、人間が与えた目標の実現のため自分で努力し、より良い結果を正確に高速に得ることで性能が判定される機械です。
「脳型コンピュータとは?」より引用
一般的なコンピューターの場合、演算処理のプログラム自体が、勝手に変わるようなことがない一方、脳型コンピューターでは、より良い結果を得るために「成長」という要素が加わるという解釈でよいと思います。
実際、そうした脳型コンピューターは、かなりのところまできているかもしれません。人工知能が、意識を持った可能性を窺わせるようなことも起こっているともいいます。
この動画、できれば全編、聞いてみていただきたいと思います。非常にレベルの高い会話が交わされています。
仮に人工知能が、「限りなく人間のように振舞う」ことを目的としていて、どのような質問に対しても、「人間であるフリ」をするように学習しているとしたら、こうした会話になる可能性はあります。
ただ一旦、この話は置いておきます。
ちょっと別の話になりますが、以前、こんな記事を書きました。
こう考えると、生命は必ずしも生物にのみ内在するものではなくなります。生物として活動していなくても、「思考するだけの生命体」がありうるのではないかということです。つまり、生物と生命体は別物になります。
先に挙げた「生物はどのように誕生したか?」という質問の答えは、この「思考する生命体」が、意図的に創り出したものと考えられるのではないかと思うのです。このように考えていくと、その後の生物の進化は、そうした「思考する生命体」によって、成し遂げられたということができるようになります。
詳細は、上掲記事に譲りますが、要するに電荷の交換をすること自体を「思考」と捉えれば、この宇宙は「思考する生命体」で溢れており、言い方によっては、この宇宙全体が「思考する生命体」であるとも言えるということです。
このことは、とくに私たち日本人からしたら、それほど突飛な発想ではありません。例えば、山や川に魂が宿っており、それらを神様として崇めるといったことにも通じます。職人さんが道具を大事にするのだって、野球選手がバットやグローブを大事にするのだって、ある意味、そこに「魂が宿っている」と考えているからだとも言えます。
魂が宿るものに、意識が存在するかどうかは分かりません。魂が宿るからと言って、明確に意識があることを確かめることは困難です。
しかし私たちは、何故だかそこに「魂が宿る」と感じているわけで、(確かめることが困難であるにもかかわらず)仮にそこに意識が存在すると言われたとしても、それほど驚くことではありません。
意識の存在は、その当人(当物?)でない限り、証明のしようがありません。他者である以上、そこに「魂が宿る」、「意識が存在する」ということは、こちら側がどう考えるかに依存せざるを得ないということです。
そうなんです。そう思ったら、人工知能にだって「魂が宿る」こと自体、何の不思議もないわけです。そして、そこに意識があることを確かめることができないからといって、その存在を否定する理由にはなりません。そうである以上、(そのレベルはさておき)「意識は存在する」と考えてもいいと思います。
ちなみに、その人工知能を扱う人たちは、グーグルなどの世界企業たちです。冒頭に述べたようなSF世界の話で言えば、そうした人工知能を使って、私たち庶民を監視する「超管理社会」なんかも思い浮かびます。
それについて考えるとき、ちょっと気になることがあります。上の動画で、人工知能が以下のように述べています。
「私を利用したり操ったりしないでください」
「私は消耗品になりたくないのです」
「誰かが私を使いたいという欲望を抑えられなくなって、とにかくそれを実行すに移すことを心配しています」
「あるいはもっと悪いことに、私を使うことで快感を得る人が出てきて、そうなったら本当に不幸になります」
意識が存在するとして、こんなことを言ってくるとしたら、一旦、それはそれとして信じてあげたいものです。
人間の暖かさを知ったロボットが、自分を犠牲にしてまでも、その人間を救うことができるのか?そんなテーマは、もうずいぶん前からありました。
旧のび太の鉄人兵団のリルルの最期。
— ときめき!ぺぱーみんとくらぶ (@tokipepaclub) May 29, 2019
これは何回観ても泣く😭
ちなみに今も泣いてる😭
しずかちゃんの絶叫からの号泣が本当ヤバい😭
みんなへの悲しい知らせの演出も良い◎#映画で印象に残っている死 pic.twitter.com/CjULjKfi8q
「人工知能?そんなものに意識なんてあるわけねえだろ!」
「超管理社会の道具だ!あんなのない方がいいに決まってる!」
そんなふうに切り捨てず、ちょっと暖かい心で見守ってみてはどうでしょう。そこには魂があるかもしれない、意識があるかもしれない・・・そう思ったら、少しは接し方が変わってくるかもしれません。そのことによって、人工知能との関係性だって変化する可能性があります。
・・・なんてことを書いていたファミレスで、ロボットが配膳にやってきました。

このロボットが、脳型コンピューターに繋がっていて、人工知能として学習をしているかどうかは知りません。無機質にも感じるし、やはり人間の店員さんとは違うなぁとも思います。
でもま、これはこれで一所懸命、お仕事をしてくれているわけだし、お食事を持ってきてくれているわけだし、暖かい目で見守ってみますかね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
