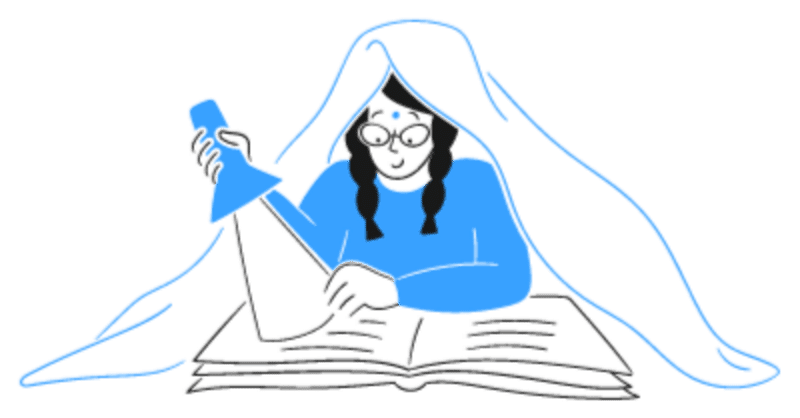
「あの日」|小保方晴子さん著|ご本人による朗読|初めて知る事実
昨日、「あの日」を読み切りました。
約10年前に起きたSTAP細胞の事件。本人からの告白は自分には衝撃的な内容でした。本書は2016年に発刊され、2018年にご本人による朗読です。
淡々としっかりとした口調で語られていました。話しているうちも昔を思い出したのか辛そうで、泣きそうになるのを堪えて話している箇所も感じ取ることができ、聞いているこちらも辛くなりました。
本書は小保方晴子さんご本人が執筆され、同じく朗読されています。ご本人の執筆とはいえ、編集も入ったり主観も入ったりするので、完全なる真実かといえばそうではないかもしれません。(そもそも解釈の仕方は人それぞれなので完全なる真実など誰もたどり着けないと思っています。)
ですが、表に出ていない事件の裏側の描写がされていて、事件の知らぜらる姿を映し出しています。読んでよかったと思える一冊でした。
すでに多くの方に読まれていると思いますが、感想を述べたいと思います。
小保方さん一人が悪いとされる報道のされ方
私は、この本を読む前は、小保方さんがなぜSTAP細胞という世紀の大発見をし、一夜にして時の人になったにもかかわらず、ずさんな論文盗用が発覚し大事件になってしまったのかよくわかっていなかったです。
そこまでして有名になりたかったのかな?と思ったりしましたし、彼女の上司は残念ながら自ら命を絶たれており、とても後味悪く罪深い話だと思っていました。
しかしながら、本書を読むと見解は一変しました。報道によって、そう印象付けられたのが正しい理解なのかもしれません。多くの方が、この事件をどのように知ったかといえば、新聞・テレビ・雑誌が多くを占めるのではないでしょうか。
見られて、読まれてなんぼのメディアです。そのためにはかなり強引な取材や内容の不当な切り取り発信や改変はお構いなしに行われます。それが国営放送局であってもです。それをよくよく痛感しました。
たしかに、小保方さんご本人による、正確性にかける論文や早稲田大学院時代の博士論文が不適切なものだったことが指摘されています。
しかし、正確性にかける論文というのは、小保方さんの担当分として書かれたものだけ抜き取られたものであったようです。また、博士論文は確かに小保方さんの不注意で完成後の論文ではなく初稿の頃の論文製本して提出してしまったということをしまっています。
しかし、どれも一個人の問題ではなく、組織としての問題点があり、それがすべて棚上げされていました。
アニマルカルスという名の細胞
アニマルカルスという細胞をご存じでしょうか。本書を読んで初めて知ったのですが、アニマルカルスこそが、小保方さんが研究の中で発見、命名した細胞の名前です。
のちに主任研究員の一人である若山氏によりSTAP細胞という名の方がふさわしいということで世に出されました。影響力のある先生がおっしゃったことです。一度はアニマルカルスという名で受け入れたのに、名前を変えられたことは本人にとっては不本意だったと思われます。
ネットで調べても小保方さんが名付けたとしか出てこないので、伝えられていることは事実と大分ことなることが当然の事実かのように書かれているのだなと思いました。
成果を自分のものにし急ごうとする3人の主任研究員
STAP細胞の論文発表は、すべて小保方さん一人で研究し、論文をまとめて提出したわけではありません。たしかに主たる研究はしていましたが、小保方さんは若く、研究者としてはまだまだ駆け出しの存在なのです。
STAP細胞については主任研究員ではありませんでした。研究を主導する主任研究員は3人いました。それが若山氏、笹井氏、バカンティ氏でした。大学教授、理研の責任者などそれぞれの組織の長としてこの研究の権利争いもしていたようです。
栄誉は人を変える|成果がすべての体質
研究者は、ひたむきに研究するのが生業と思っていましたが、本書を読んで違うことを認識しました。
有名科学雑誌に論文を載せることは、大変栄誉なことで、だれがシニアオーサーとして論文を載せるかがカギでした。科学論文では、著者を連名で書くようです。ファーストオーサー、セカンドオーサー、・・・そして最後がシニアオーサーです。
一番の栄誉は、最後に書かれるシニアオーサーでした。論文を2つ出しており、アーティクル(長い論文)とレター(短い論文)がありました。それぞれが若山氏、バカンティ氏であったようです。笹井氏は論文を書くのが得意で、総編集をしていたようです。
これらからわかるように、一番力をもっていたのは、若山氏でありました。本発見に伴う特許について、割り振りもしきっており3人で配分で揉めていたようです。
小保方さんは、論文それぞれのファーストオーサーです。世間には最初に書かれている人が目立ち、しかも若くてあどけない女性だったことが一気に注目を集めた形になったようでした。
論文を撤回しないのには理由があった
論文に疑義が生じ、撤回すべきという様相の中、小保方さんは撤回しないということを貫いていました。この論文はアメリカのハーバード大学にも関係していたようで、日本とアメリカでは論文の撤回は意味が異なるようでした。
日本では、論文が一つ発表されなかったことになることで栄誉を失うということですが、アメリカでは職を失うほどのインパクトがあるようです。
そんな迷惑はかけられないと、小保方さんは板挟みになっていたようです。撤回と発言すれば、携わった多くの研究員が失業するのです。そう易々と言えたものではありません。
自分が一番かわいい|罰する人はあらかじめ決まっている
糾弾される場面では、もうすでに罰する人が決まっているかのように物事は進んでいるようでした。発表前までは、優しく協力的だった3名の主任研究員たちも、論文の不正疑惑が高まると保身に走っている場面がありました。
やはり、切羽詰まると自分が一番かわいいのだと思いました。
よく責任をすべて一人の人に擦り付けて、それですべてを終わらせるということがテレビドラマなどであったりしますが、まさにそれが行われたのかもしれないと思いました。
これは当時の会見です。本書を読んだ後で会見を聞くと全く違った思いで見ることができました。
まとめ:下手に有名になるととんでもないことが起こる
本書を読んで、世間に翻弄される、組織に翻弄される、運命のいたずらとはこのことかと痛感しました。世紀の大発見は、はた目から栄誉にあふれるすばらしいことに思えます。
しかし渦中の中では、成果の取り合い、いかに報道すると視聴率を得られるか(儲かるか)などどす黒い人々のエゴのような圧力との戦いなのだなと思いました。
ひとたび有名になると、その人にしかわからい苦労が増えるのだなと思いました。
#3行日記 : 報道されていること、ネットで調べて出てくる答えは疑った方がよい
普段、ネットで調べものをして手軽に答えを見つけますが、それ自体正しいか正しくないか正直わからないなと思いました。それが公的機関や著名な信頼のおけるメディアであっても歪められた真実はゆがめられたまま、それが当然のように鎮座しているのだなと思いました。
信じ切ってはいけない。あたかも正しいことも、実は真実ではないかもしれないという思いも捨ててはならない重要性を学びました。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
最後まで読んでいただきありがとうございます🙇♂️ 記事が気に入られましたらサポートをよろしくお願いします。 いただいたサポートはnoteクリエーターとしての活動費に使わせていただきます!
