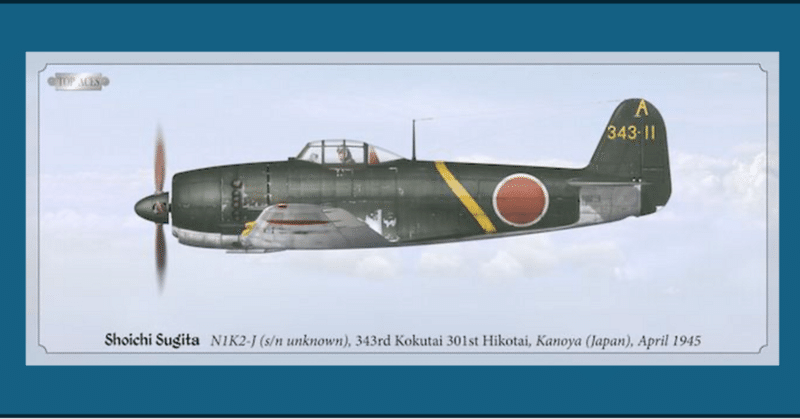
杉田庄一物語その28 第三部「ミッドウェイ海戦」 六空先遣隊ラバウル進出
少しもどって八月中旬、六空はミッドウェイ後に再編成し、木更津基地で訓練中であった。しかし、予想以上に早い米軍側の反攻により、急ぎ日本内地から航空隊を送らねばならないということになり、ラバウル方面に出動することになった。
ラバウルへの移動は、当初計画されていた空母による輸送では間に合わず、とりあえず小福田飛行隊長を指揮官として二個中隊十八機の零戦による搭乗員だけの先遣隊第一陣が木更津からラバウルへ向かうことになった。日本初の単座戦闘機による渡洋長距離移動である。木更津−硫黄島、硫黄島−サイパン、サイパン−トラック、トラック−カビエン、カビエン−ラバウルというコースである。杉田はまだ経験未熟と判断され、先遣隊第一陣には選出されなかった。しかし輸送船による第二次先遣隊に選ばれ、基地要員とともにラバウルに向かうことになった。本隊は準備が整い次第追っかけることになっていた。
零戦による先遣隊第一陣は島伝いで行くことになったが、それぞれの島の間は千三百キロメートルから千五百キロメートルを洋上飛行することとなり、海軍航空隊としても以後のラバウル進出の前例となるものであった。優秀なパイロットばかり選出されたとはいえ、このような洋上長距離飛行による空輸を単座戦闘機で行うことは、航法面からも体力面からも困難が予想された。零戦は航続距離の短い二号戦(零戦32型)である。
単座戦闘機による洋上飛行は極めて難しい。翌年ではあるが、昭和十八年四月二十七日、トラック島基地からラバウル基地へ向かう陸軍三式戦闘機「飛燕」が十三機中たどり着いたのは一機のみという多数機の遭難事故がおきている。また、六月十六日にも同じく「飛燕」で内地からラバウルに島伝いに進出しようとしたが、慎重に計画を進めたにもかかわらず四十五機中たどり着いたのが七機という遭難事故を起こしている。洋上航法の訓練を受けていない陸軍機とはいえ、なにもかも一人で機体をコントロールしなければならない単座戦闘機での洋上飛行は無謀な計画といえよう。
ともあれ、洋上航法訓練を受けている海軍搭乗員たちではあるが二機の一式陸上攻撃機を誘導機として、それに予備の搭乗員二名と整備員たちを乗せることにした。着陸地ごとに零戦の整備補給を行いながら一週間ほどの予定で進出する計画をたてた。硫黄島だけは滑走路が短く一式陸攻が着陸できないので、ここへは駆逐艦で整備員を派遣するという細かな計画であった。
八月十九日、早朝、十八機の零戦と二機の一式陸攻は木更津基地を出発し、硫黄島に向かった。このときの心境を小福田大尉は『指揮官空戦記』(小福田皓文、光人社)の中で次のように書いている。
「十八機の零戦は、ぴったりと編隊を組んで、私についてくる。部下の赤らんだ顔に、闘志と決意がみなぎっているのがよく分かる。この部下のたのもしさと、かわいさに、思わず目頭が熱くなる。心の中で、(お前たちの命はあずかった。おれについてこい。死ぬときは、いっしょだ・・・・・・)と、万感の思いをこめて、風防の中から、固く握った左手をあげて振った。元気でいこう、と叫びながら・・・・・。すると、私の近くの零戦パイロットには分かったらしく、同じようにコブシをあげ、白い歯を見せながら、にっこり答えた。おれの気持ちがわかったなと、なんともいえない心強さを感ずる。まもなく全機に合図し、開距離編隊を命じた。遙か後方、伊豆、房総の山々を、そっと振り返って見た。(これが日本本土の見おさめだな・・・・・)と。」
このとき小福田は三十三歳。部下たちは二十歳未満がほとんどで、親子というよりも若い先生と高校生の教え子のような関係だった。
当時の硫黄島の飛行場滑走路は短く八百メートルしかない上、両端が断崖だった。そのため空母の飛行甲板のように制動ワイヤーを滑走路両端に張ってオーバーランに備えていた。空母への着艦と同じ要領で機を止めようというわけだ。やはり一機が着陸に失敗し、機体が大破した。
悪天候のため硫黄島には二日滞在し、三日目におとずれた好天快晴の中をマリアナ島のサイパンに向かう。約千二百キロメートル、巡航速度で三時間半である。小福田の考えで、サイパンに先行して、誘導のために待機していた一式陸攻二機を待たずに零戦のみでサイパンに向かう。一式陸攻の往復の手間を考え、零戦隊単独行のリスクを取ったのだが、快晴だった空が太平洋を進むにつれてちぎれ雲が増え、それが層雲になり、さらに進むと雲の下層が海面近くまで垂れ下がり、上空は真っ黒という悪天候になってしまった。
小福田は島を見つけて航法を確かめるため海面近くを這うように零戦隊を率いた。やがてスコールの柱が右にも左にも現れて、それらをかわしながら進まなくてはならなくなり、チャートの確認や位置計算など何もできない状態になる。大きな不安の中に小福田は後ろを振り返ると、部下の全機がぴたりとついていた。小福田は、全幅の信頼を寄せる部下たちに重い責任感を感じていた。マリアナ諸島は大小三十近い島があり、コース前方直角一列に位置するはずであるが、悪天候で見逃して通り過ぎている可能性がある。引き返すにしても悪天候の中で硫黄島を見つける自信はない。硫黄島を出て二時間、引き返し点に差し掛かっていた。
小福田は「進むべきか?引き返すべきか?」「進むも死、退くも死」と悩みながら島を探した。そして、前方にポツンと小さな角形の島(ウラカス)を見つける。小福田は、安心すると共にぞっとしたという。ウラカスは、マリアナ諸島最北端の島だった。あと少しでも北に寄っていたら全機遭難になっていたのだ。ウラカスから列島線沿いにサイパンまで南下し、全機無事に着陸した。
八月三十一日、昼前にラバウルの飛行場に全機着陸したが、飛行機をおりてから滑走路脇にみなへたりこんでしまったという。心身ともに疲れ切っていたのであろう。小福田は、日本からソロモンまでの戦闘機による移動飛行は、これが最初であり最後だったと書いている。日本を飛びたってから二週間近くたっていた。
ところで、この疲れ切っている零戦隊に対して、所属部隊長は、「小福田君、疲れていて、大変ご苦労だが、昼食が終わったら、午後、君の部下を率い、全力をもって、敵地に空襲に行ってくれ」と言葉をかけた。この言葉を聞いた小福田は「最前線の厳しさ」というよりも都合のみを考える上官の「思慮のなさ」に憤りと危うさを感じている。小福田の嘆願により、翌九月一日から出撃ということで、午後の攻撃は勘弁してもらうことなった。
しかし、前述したように第二次ソロモン海戦後のガダルカナル島上空での制空権をめぐる航空戦は、日米ともに死闘を繰り返しており、待ち望んでいた援軍であったのだ。前日の三十日にも、空母飛行隊十八機が陸軍の川口支隊の一部のタイボ岬上陸作戦の支援に出て、米軍機十二機を撃墜したものの未帰還機九機を出していた。その中に新郷大尉も含まれていたが、ガダルカナル島エスペランス岬、不時着水後に日本軍の設営隊員に救助されている。
米軍機も大戦初期の頃とは異なり、二機が対になって編隊空戦を行うようになり、格闘戦に持ち込もうとしても急降下で逃げられ、思うような空戦ができなくなっていた。小福田の想像以上に前線の厳しさがあったともいえる。
<参考>
〜〜 ただいま、書籍化にむけてクラウドファンデイングを実施中! 〜〜
クラウドファンディングのページ
QRコードから支援のページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

