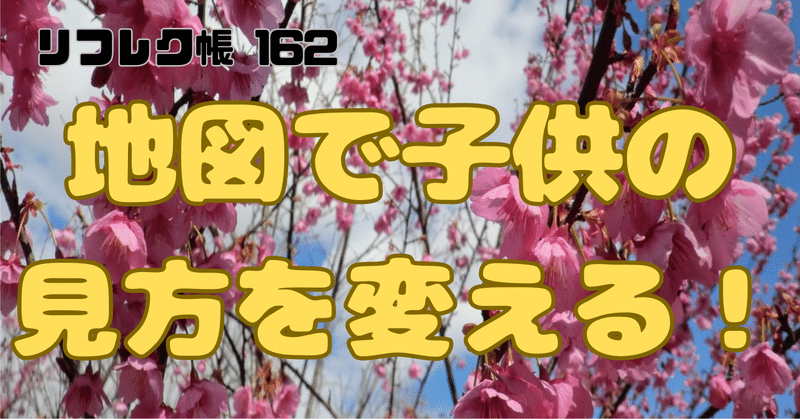
地図を使って子供のものの見方を変える!
富士吉田市の地図に驚く
過日、たまたま山梨県富士吉田市の観光地図を入手した。
そして、見て、驚いた。
何と、南が上、北が下の地図だった。
隅に、その理由が以下のように記されていた。
独特なんです。
富士吉田での地図の見方はこのマップように「南」が上になります。理由は簡単、富士吉田のシンボル、”富士山”が基準となっているからです。
この説明の通り、地図上部には、富士山の絵が描かれ、「富士山はこちらの方向です」と上向きの矢印とともにキャプションが付いている。
つまり、公的な地図のきまりにおける「方位」ではなく、「富士山」が基準なのだ。
急いで、一緒に入手した「富士河口湖みどころガイド」マップも見た(一般財団法人富士河口湖ふるさと振興財団発行)。
同じく、南が上の地図だった。
地図最上部に、富士山の絵がはっきりと描かれていた。
これは、子供の学習で使える!
そう直感した。
有田和正氏からの学び
かつて小学校社会科の著名な実践家の一人に、有田和正氏がいらっしゃった。
少しでも授業について勉強している教師なら誰でも知っていた。
近年は、某教科書会社の社会科教科書を執筆していらっしゃった。
当時、その「ハテナ帳」や教材開発・「授業のネタ」などの方法論によって「追究の鬼を育てる」実践は、多くの教師の学びの対象であった。
私もその一人として、氏の実践のステージである筑波大附属小の研究会に足を運んだり、「材料七分に腕三分」という言葉に背中を押されて、フィールドワークに励んだりした。
氏の主張のひとつに、「子供のものの見方を変える」ことの大切さがあった。
現在の「多面的・多角的な見方を育てる」ことに通じるものだと私は考えている。
氏は、そのために例えば、「昔話『桃太郎』を戦国時代に置き換えたら、桃太郎は誰で、鬼は誰か」といった発問を用いた。
見方を変えると桃太郎は略奪者として捉えられることにも気づかせる実践であった。
子供が当たり前だと思っている知識や考え方にゆさぶりを掛けたり、逆転させたりすることによって、追究力を引き出し、新たなものの見方をする力を育もうとしたのである。
「日本では、洗濯物を南向きに干すが、オーストラリアでも同じか」という発問も、よく知られている。
南半球のオーストラリアでは、北向きに干すのである。
確か、氏の執筆した5年生の教科書のオーストラリアの紹介に、サーフィンに乗ってやって来るサンタクロースの写真が用いられていたはずだ。同様の指導のねらいであろう。
子供の見方を変える地図
この「子供のものの見方を変える」ために用いる方法のひとつに「地図」があった。
そのために、氏は著書で、外国を旅行したらその国や地域の地図を購入してくることを勧めていた。
日本の世界地図は日本が中心に描かれているが、海外ではそれぞれ自国が中心にの地図になっているからである。
私は、冒頭の富士吉田市などの地図を見て、このことを思い出したのだった。
海外旅行に行く友人に地図を「お土産」として依頼し、授業で子供に見せ、「いつも日本が中心だと思ってはいけない」などと子供と考え合った記憶がよみがえった。「日米関係」と「米日関係」の表現の違いへと話題が及ぶこともあったはずだ。
さらに、南半球の国の地図は南北が逆であり、それを子供に提示したことも思い出した。
全ての地図が北が上になっているわけではないことを子供に伝えた学習場面だった。
世界の見え方はひとつだけではない。
正解主義の対極にあるのは、社会・文化・歴史的文脈主義である。
山梨日日新聞社のページだろうか。以下のアドレスで、「山梨県富士吉田市など富士北麓地域の地図には、南北を逆転して富士山を上方に描いたものが数多く見られる。『富士山を下にすることはできない』という意識があることや、日常生活の目印となっていることが関係している」と伝えている記事を見つけた。
https://www.fujisan-net.jp/post_detail/%E9%BA%93%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9B%B3%E3%80%81%E5%8D%97%E5%8C%97%E3%81%8C%E3%80%8C%E9%80%86%E3%80%8D
また、ネット上の他の記事によると、富士北麓地域において南北を逆転して表すのは、江戸時代からの慣習であるらしいとのことだ。
https://timetreeapp.com/public_calendars/kinenbi_tte/2028595846426486446
地図を見てわかるのは、単に「上下がひっくり返っている」ということだけではない。
時間軸の中で、その地方や地域、国の人々が何を大切にし、どのように暮らしてきたのかという生き生きとした姿を学ぶことに繋がると言えそうである。
