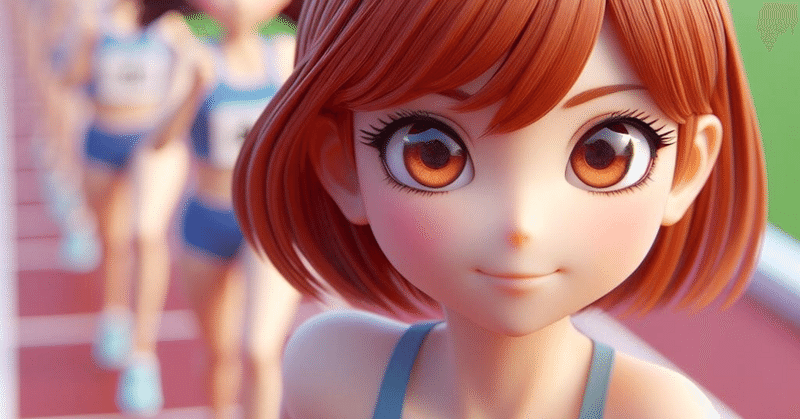
雑文(06)「プールから上がれない」
「足攣ったらお終いだな」と、足攣ったらお終いそうな表情を伊藤舞花(いとうまいか)に向けて、高部瑞希(たかべみずき)は言った。
「三人共泳ぐのが得意でよかったよ」と、三人共泳ぐのが得意でよかったそうな表情を高部瑞希に向けて、伊藤舞花は言った。
二人の会話に交じらず鈴木真由(すずきまゆ)は会話の始まりから終わりまでずっと上を向いて、二人の会話に興味がない、とは言わずに、二人の会話に興味がなさそうに、鈴木真由は思うのだ。
プールから上がれないのに、わたしはどうしてプールに入ったんだろう。
鈴木真由の心の中での独白を知ってか知らずか、高部瑞希は足を掻きながら同じく足を掻く伊藤舞花に言う。「飛び込んだのがよくなかった。わかっていたら飛び込まなかったのに」
「わからなかったから飛び込んだんだよ、瑞希。わかっていたら、たとえば殻を割って、ゆで卵だと思ったのに実は生卵でした、瑞希が言わんとしてるのはそういうことでしょ?」
「舞花」と、高部瑞希は続く言葉を溜めて、「あれ、なんだっけ」と、天然降りを伊藤舞花に披露して、伊藤舞花は柔和に笑った。
「見えるの、真由」話題を振られた鈴木真由が、眉をひそめる高部瑞希をよそに、上を眺めながら、伊藤舞花に顎先を突き出して、しゃくれ声で言う。「見えない。プールサイドは宇宙だよ」
「なんて表現だよ」高部瑞希が唇を尖らせる。
「おもしろい」と、伊藤舞花が短く言ったのを聞き逃さずに、高部瑞希は、「そうだ、そうだ。おもしろいぞ、真由」と、おべっかを忘れない。
「監視員さん来るかも」そう言うと鈴木真由はプールの中に直立のまま潜った。高部瑞希と伊藤舞花が驚くのをよそに、鈴木真由はプールの中で右腕を突き上げ、水面に出すと、藻掻くように右手の指を動かす。なにやってんの、と、高部瑞希は言わず、どうしちゃった、真由、と、伊藤舞花は言わない。
ほどなくして水面に顔を出すと息を胸いっぱいに吸って鈴木真由は浮上した。
「おい、どうした。真由」と、高部瑞希は、鈴木真由の奇行を心配してから、「さすがの阮三兄弟でも、いや三姉妹か、無理すんなよ、死んだらもう苦しくても息を吸えねえぞ」と、荒い息づかいの鈴木真由を気にかける。
「昔、そう昔、わたし、試したのよ」
「あせらないで。空気はたくさんあるんだから」と、伊藤舞花が、脳が酸欠の鈴木真由を補足する。
「地球が誕生してから、ただしくは陸上に人間の祖先が上がってから、空気はたくさんあんだから。あせって吸わなくてもなくなったりしねえからよ」
鈴木真由は呼吸を整えて話す。「小学生のとき。そう、そう小学生のとき。監視員さんを試したの。ちゃんと視てるか、溺れたらちゃんと気づくか。監視員さんを試した」
鈴木真由の途切れ途切れの話の意図を見抜いた高部瑞希は、要するにと人差し指を立てて、鈴木真由にたずねる。「真由が言いたいのはつまり」
「だからわざと溺れたふりして」伊藤舞花が横取りした。
「そうです、そうです。さすがです。舞花、舞花。万歳、万歳だ」おべっかを忘れない高部瑞希は意外に偉いのかもしれない。
「怒られたけど」鈴木真由は笑った。
「で、きょうは来なかった」高部瑞希は冷静にそう言った。「監視員、なにさぼってんだよ。溺れてるんだぞ、わたしたちは」
「見えてないんだよ」と、伊藤舞花は冷静にそうも言った。
「あーあ」と、急に高部瑞希が高い声を出す。「高二夏デビューしてさ、二学期から金髪で登校して担任が泡吹くとこ見るの楽しみだったのに」
「彼氏ができるのが、担任が泡吹くのが、どっちが」伊藤舞花はたまらずそう言った。
「担任が泡吹くのが」高部瑞希は伊藤舞花の顔を見て、真顔で言った。「なに笑ってんだよ、舞花。それに真由」
「別に」と口元を手で隠して伊藤舞花は笑い、「なんでもない」と、白い歯を見せて鈴木真由は笑う。
「舌打ち」と明瞭に言ってから舌打ちし、高部瑞希はしょげる。
静かになると、高部瑞希、伊藤舞花、鈴木真由の直立のままの足掻きは、水中であったが、水面に昇ってくる細かい小さな泡が水面で弾ける、三人共足掻き必死にしてるのがわかるくらいの必死が、水面にさざ波になって伝わってくる。
「まどろっこしい表現は好かんが、わたしたちどうすれば助かるんだろうな。港区で高級寿司も食ってないのに、死ねねえよ。こんなところで、プールの中で」
「三人仲よく溺死なんて。さすがの小中高いっしょの幼馴染みの三人でも、ちょっと嫌だな」と、鈴木真由が言い、「ちょっと、ちょっとか、そうか」と、伊藤舞花が鈴木真由の発想に感心する。
「プールから上がれない。まさかプールから上がれない日が来るなんてよ、思ってもみなかったぜ。三人共泳ぐのが得意だったからよかったけど、得意じゃなけりゃ、とっくに溺れ死んでいたぞ、まじで」
「えっと。阮なんちゃら三姉妹だから」と、なれない名前を言うように、鈴木真由はなれない名前を言い、「阮だよ、阮。水滸伝。漁師だよ、泳ぎの得意な、わたしの好きな漢だよ。湖の畔の物語に出てくる泳ぎの得意な豪傑で、最期はまあ、残念だったが、まあそうだな、足攣ったらお終いだ。お終いだよ。ったく」
突如真夜中に襲われた。
なんだ、と、高部瑞希が驚きの声を上げる間もなく、どうした、なにが起こったの、と、伊藤舞花が状況判断する間もなく、真っ暗、真っ暗、と、訳のわからないことを鈴木真由が繰り返す間のなく、真っ暗になった。
真っ暗の中、舞花、と叫ぶ高部瑞希の声がして、えっえっ、と、戸惑う鈴木真由の声がしたら、突如明るくなった。
伊藤舞花は消えていた。いや、高部瑞希が目撃した。鈴木真由はもはやなにもわからない。伊藤舞花は、彼女の身体をまるっぽ包み込む巨大な網に掬われ、水飛沫と共に、水滴を垂らしながら伊藤舞花はプール上空へ連れて行かれ、明るくなる頃には、、伊藤舞花は連れ去られた。
「声にならない」と、声にならない表情で高部瑞希は、声にならないと言った。
「舞花」喉の奥底からなんとか引っぱり上げてきた単語は、鈴木真由はそうとしか言えなかった。
「真由、」と、高部瑞希が言いかけて、突如また真っ暗になり、鈴木真由が目を開ける頃には、高部瑞希は消えていた。
「瑞希」喉の奥底からなんとか引っぱり上げてきた単語は、鈴木真由はそうとしか言えなかった。
二人を突如失った鈴木真由は泣きたかったが、あまりの絶望に泣けず、足を掻くので必死だった。伊藤舞花が、高部瑞希が、消えてしまった。鈴木真由にはまだ信じられない。さっきまで馬鹿話をして危機的状況の緊張を紛らわせていた二人が、真っ暗になって明るくなると消えてしまったのだ。
考察したかったが、鈴木真由は悟った。
突如また暗くなった。
巨大な網で身体をまるっこ掬われ、プールの上へ急上昇し、頂で浮遊感を抱くと下降し、鈴木真由は木の板の上に叩きつけられ、強打したせいで、痙攣する。
ここは、と、考える余裕もない。
舞花、瑞希。声を出すのを忘れたように、声を出せずに、左右に横たわった変わり果てた二人を涙目で眺めるだけだ。
わたしの番だ。そう思ったのが、最期で、いや、まだ意識は続いていて、どこかへ運ばれる移動感があった。
瑞希、舞花と、わたしはどこかへ運ばれている。
真由、と、舞花の声がした気がし、真由なのか、大丈夫なのか、と、瑞希の声がした気がしたが、気のせいかもしれない。
襖が開き、大きなテーブルの上に、わたしたちは載せられた。
襖が閉まり、わたしたちは部屋に残された。
「おっ、まだ生きてるぞ」
「痙攣してる、すごいすごい」
「新鮮なんだ、美味しそう」
と、立て続けに、男の低い声と、女の高い声と、子供の幼い声がした。
わたしたちは、横並びに並んで寝かされていた。
痙攣か、庖丁で捌かれ、開かれた肉体を電気信号の度に痙攣させ、喜色を浮かべる父母息子の三人家族の夕ご飯の大皿に出されてしまった。
お終い
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
