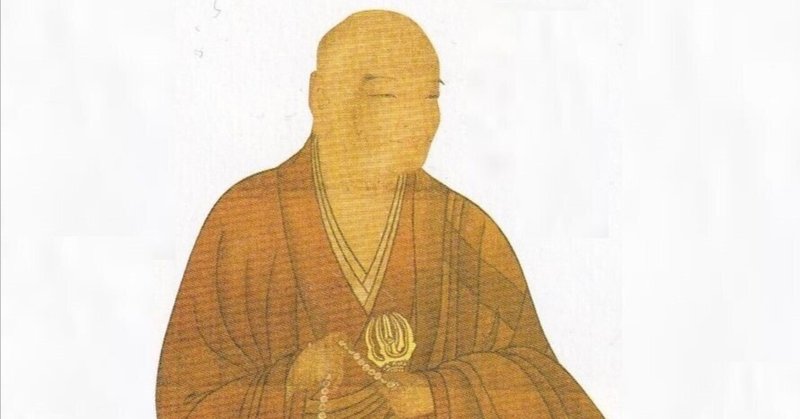
花山法皇ゆかりの地をゆく③〜元慶寺、比叡山延暦寺、書写山圓教寺編〜
旅と称して花山法皇のゆかりの地をストーカーのように追っていて、その旅行記を二度、note記事に書いて公開してきた。振り返ると、これまでの旅は行先の決め方を、あまりにも思い付きの気が向くままの行き当たりばったりであったと自省するようになった。
誰に批判される謂れのない、きわめて個人的な旅行なのだから、自分の思うように好きな時に好きな場所へ行けばよいのだが、歴史上の場所を尋ねる際には、事前に歴史を十分に調べて時系列に沿って訪れないと、現場を見ても大事な点を見落としてしてしまい、的外れな考察をしてしまう可能性があるように思えた。
とくに下にそのリンクに示した前回の旅行記では、いつどこへ行った、昔こういう事件があったと、事実だけを淡々と書き連ねた記事を書けばよかったものを、つい筆が滑って末尾に素人の珍妙な歴史考察を書いてしまった。ズブのド素人であっても、実在の人間が生きた歴史の考察を書いて公開するからには、結論が的外れで間違うのは仕方ないとしても、考察の過程においては歴史に対して真摯に向き合うべきだと思うのだ。
そのようなわけで、花山法皇という歴史上の人物を追うには、まずは彼の歴史的な原点に立ち返るべきだと、思いを新たにした。花山法皇においては寛和の変という謀略事件によって、数奇な運命を辿ることになった。したがって、今回の旅にあたっては、寛和の変を花山法皇の原点としてその歴史をきちんと調べ、関連する場所を訪れる旅をするべきとした。
ということで、まずは改めて寛和の変についてを調べ直した。
曰く、寛和の変に関連する事件については、おそらく旧暦の日付が正確に記されていて、以下の様な事件が寛和の変とその後にあったことが史実として伝えられている。
寛和二年(西暦986年)
6月22日 花山天皇 元慶寺にて出家(寛和の変)
7月21日 宗子内親王(花山法皇の実姉) 死去
7月22日 花山法皇 書写山に出発
一条天皇 即位礼
7月27日 花山法皇 書写山の麓に到着
7月28日 花山法皇 性空上人と会合
7月29日 花山法皇 書写山から船で帰京
9月16日 花山法皇 比叡山延暦寺にて受戒
寛和の変の概要を改めて記すと、当時、右大臣であった藤原兼家が孫の懐仁親王を天皇とするために、息子の道隆、道兼、道長を使って、当時の天皇であった花山天皇を騙して退位、出家させてしまった事件だ。
騙されて出家したと言っても、要は寺に連れて行かれて頭の毛を剃られただけなのだから、現代の感覚では、「いや〜、昨日は騙されちゃったよ〜」と、ツルツルになった頭をカキカキ、戯けてみせて、何食わぬ顔で天皇を続けても良さそうだが、そうは行かないのが古代・中世の世界なのだろう。つまり、中世のヨーロッパでも同様だが、軍事や治安や文化技術を統べる朝廷政府と、同等かそれ以上の権力を宗教が持っているのだ。それだけ、民衆の信仰心が強かったということなのだろう。今でも宗教法人の優遇が取り沙汰されて議論の的になるが、それとは比べものにならないくらい、当時の宗教の権力と影響力が強かったのだ。
この事件によって、懐仁親王が一条天皇として即位し、天皇の外祖父となった兼家は見事に摂政の座を勝ち取った。即位時の一条天皇はわずか七歳であるから、即位当時の一条天皇を補佐する役職の摂政は、ほぼ天皇と同等の権力を手に入れたようなものだろう。おまけに、兼家は仲の悪い兄の兼道が全盛であった時期に右大臣の職を奪われる降格人事を受けており、出世争いにおいて辛酸をなめているから、念願の摂政の就任した際は格別の思いであっただろう。これで兼家は貴族社会の頂点に登り詰めたと同時に、藤原義懐といったライバルの失脚にも成功し、貴族間の権力の均衡がなくなったおかげで、兼家が朝廷の権力をほぼ独占した。この兼家の摂政就任から息子の道長の現役時代が、摂関政治の最盛期であった。
藤原道長と言えば、自信過剰、傲慢、怖いもの知らずの性格を浮き彫りにしたようなエピソードが残されている。その中でも、道長の三女である威子が中宮となって自身の権力を盤石とした晩の祝宴で詠まれた、摂関政治の象徴でもある例の和歌が有名だ。
この世をば わが世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば
日本史や古典が大嫌いだった私でも、さすがに藤原道長の「この世をば~」の和歌は覚えていて、当時の権力者はずいぶんと傲慢なものだと思ったし、時の権力者がこのありさまでは、平安時代とはひどい時代だなと偏見を持ったものだった。
ともあれ、この寛和の変によって本格的に藤原家の摂関政治時代に切り替わり、藤原道長の全盛時代にもつながった、古代末期の権力史における重要なターニングポイントと言えるだろう。
また、花山天皇個人にとっても、この事件をきっかけに天皇という立場から出家して僧侶になったわけだから、人生の上で大きなターニングポイントとなった重要な事件であった。
花山法皇は寛和の変の一か月後、一条天皇の即位式の当日でもあった7月22日に、十名程の従者を連れて京から姫路の書写山へ向かった。目的は書写山に住む性空上人との会合であった。出発前日に宗子内親王を亡くしているが、それが花山法皇の書写山行きと関連があるのかはわからなかった。京から6日もかけて書写山に着いたが、性空上人との会合は一泊二日で終えて、会合翌日には船で京へ帰ってしまった。
今回は、寛和の変とその後の花山天皇の足取りを追うために、寛和の変の舞台となった平安京内裏跡から元慶寺の道程と、比叡山延暦寺、書写山を目的地として、例によって新幹線とホテルの予約を取り、12月9日(土)と12月10日(日)の二日間で訪れることにした。
新幹線で京都へ

2023年12月9日(土) 6時24分、時間通りにのぞみ285号は東京駅を出発した。今回はグリーン車を使った。贅沢ではあるが、今回はネット予約で指定席の1500円プラスでグリーン席が買えたので、つい買ってしまった。移動という成果に対する違いはないグリーン車に、1500円プラスの料金を払うのが高いか安いかは議論のあるところだが、旅を計画・準備をしているときというのは大抵舞い上がっているものだから、予約をした時の私は「グリーン車やすぇー、とったれ」と思ったのだ。今回の新幹線は、私が乗ったグリーン車8号車に限ってだがガラガラで、乗車率は20%程度といったところ。前回2回の新幹線がいずれも朝早い便であるにもかかわらず満席状態であったから、肩透かしを受けたような気分になる。12月に入って、週末に旅行なんて手合いは少ないということだろうか。新横浜を出発して、新幹線が本気の走りを見せだしたのを確認して、東京駅で購入した駅弁を食べる。本日は昼食をとる時間がなくなる可能性が高いので、普段は食べない朝食を食べておくことにする。駅弁を食べ終わると、音楽を聴いたりして無為に新幹線内の時間を過ごした。
8時32分、新幹線は予定通り京都駅に到着した。京都駅からは地下鉄で京都御苑を目指すつもりだが、京都の地下鉄に乗るのは初めてだった。幸い、京都駅に乗り入れている地下鉄線は一本しかなく、駅の標識に従って簡単に地下鉄駅にたどり着けた。

8時51分、丸本町駅着。この地下鉄駅を出ると目の前が京都御苑であるが、この中にある御所の内裏は、今回の目的地ではない。しかし、まずは京都御苑に入り、花山法皇が出家後の京の自宅としていた花山院邸跡を訪ねる。丸本町駅から最も近い間之町口から入ると花山院邸跡の石碑はすぐに見つかった。花山院邸跡全体が神社として残されているようで、その神社内に花山院邸宅跡の石碑と、花山稲荷なるものがあった。この神社丸ごとが出家後の花山法皇の京都での邸宅であったとすると、花山法皇は出家後もやはり良い暮らしをしていたな、と思う。神社自体はこじんまりとした、大して見るべきものもないようなものであったが、12月だというのに暖かいせいか、紅葉が赤く色づいていて美しかった。自分の家ではなくても、こういう景色を自由に見れるというのは素晴らしいのだと思う。花山院邸跡を後にすると京都御苑も一度出て、平安京内裏跡を目指す。平安京内裏跡は京都御苑より西に1kmほど行ったところの新出水通近辺らしく、看板が何件かあるらしい。

実際に付近まで訪れてみると、油店という古い商店と屋敷が併設された珍妙な店が目に入る。創業二百年の老舗で、食用油を専門に扱っていることだが、油専門店というのは現代の感覚ではずいぶんと尖った商売だ。内裏跡については、その山中油店よりさらにもう一区画北に進んだ通りにあった。看板以外はいたって普通の京都の古い住宅街。特に内裏を思われる建物などないから、適当な場所から、寛和の変をなぞる意味で、およそ10時頃に元慶寺を目指して歩き始めた。
平安京内裏跡から元慶寺を目指す
今回、内裏跡から元慶寺までは、全て徒歩で移動した。少しでも、寛和の変の主人公である、花山天皇と藤原道兼の当時の心情に近づきたい、現代風に言い換えれば「ライブ感を感じたい」からだ。

内裏を出ると、寛和の変である花山院の出家では、安倍晴明宅の前を花山天皇と藤原道兼は歩いたと記している。安倍晴明は自宅内にいたのに、花山天皇と道隆の晴明宅を歩いただけで、天皇の危機を感じたそうだが、現代の感覚ではどうにも嘘臭い。しかし、例えばいまだに清盛の首塚は東京都心のど真ん中で開発もされずに保存されているし、数年前には国会前で数人の僧侶に呪殺祈祷をされていた政治家が暗殺された。千年前当時の信仰心やスピリチュアルも、バカにできないものがある。
現在も安倍晴明宅跡を示す石碑があるらしく、GoogleMapにも表示されているのでそれを目指したが、石碑は見つからなかった。もしかすると民家の敷地内にあるのかもしれないが、そこまでする気はない。代わりに、京都ブライトンホテルという、宗教施設のような不思議な形をしたホテルがあった。おそらく、安倍晴明の法力で、そのようなホテルが未来のこの世に建ったのだろうと、ひとり納得する。

今度は、鴨川を目指すために蛤御門から京都御苑に入ると、京都御所がすぐ目の前に鎮座していた。思った以上に京都御所の塀と、塀の上からわずかに見える建物の屋根は巨大で圧倒される。今の京都御所ができたのは1331年とのことだから、すでに世の中は武家の時代になっていただろうに、それでも天皇のためにこれだけ巨大な建築物を作り、今まで維持しているのだから、日本という国は大したものだ。御所内の参観もできるようだが、今日の目的ではないので通過して京都御苑を二度あとにして、鴨川を目指した。

鴨川沿いを歩きながら、花山天皇と藤原道兼が、当時どのような会話を交わしたのだろうかと、想像を巡らせる。私は、とにかく酷い弱虫、臆病、甲斐性なし、無才の者であるから、見知らぬ土地を巡ったり歴史を辿ろうとすると、勝者より敗者、偉人より愚者、天国より地獄に目が行く。今私が追っている寛和の変は、花山天皇が陥れられて敗れ、藤原兼家の親子が謀略に成功して勝ったわけだが、兼家親子の中でも花山天皇を内裏から元慶寺まで連れ出すという、最も重要な役割を担ったはずの藤原道兼は、黒幕の藤原兼家からその功績に見合う恩賞を与えられなかった。それにより道兼は、兼家の死後に関白になれないとなるとヘソを曲げて喪に服さなかったり、生前の道隆を大層憎んだりしたようだ。そんな道兼も、最後は道隆の死後に頂点の関白まで上り詰めるが、それも「七日関白」と揶揄されるように、わずか十日程度で死去により終わってしまった。そうなると、俄然、騙された花山天皇より、父の命令に従ってリスクを冒して裏切り騙しても報われず、後世にあまり良い評判も残せなかった藤原道兼の方が気になる。彼はどんな心境で花山天皇を元慶寺までお連れしたのだろうか。
帝はバカだ。もう、帝なんて呼ぶ価値もありゃしない。こいつ呼ばわりで十分だ。こいつは何も知りやしない。何も解っちゃいない。俺はどうにかうそ泣きまで演じて見せて、こいつを宥めすかして内裏から鴨川の飛び石を渡って堤まで連れ出してはみたが、こいつはいつ日和って踵を返して内裏へ戻ってしまうかもしれない。そうなれば、堤の陰に隠れている源満仲の連中が、帝を切り捨てる手筈になっている。その先のことは聞かされていないが、帝を切った謀反人の汚名を着せられて破滅するのは俺だ。罪人としてひっ捕らえられるのは俺だけだ。この陰謀が成功しようが失敗しようが、同じように陰謀に参加しているはずの、黒幕の親父も、内裏で待機している兄の道隆も弟の道長も、明日も何食わぬ顔で昨日と同じように暮らすだろう。和歌に武芸に蹴鞠、何事につけても兄弟の中で負けてきた才能もない俺が、捨て駒のような役割を押し付けられたのは当然なんだ。俺の横を呑気に歩いているこいつは、そんなことすら解っちゃいない。俺は、今日をもって裏切り者か謀反人として後世に名を刻む。俺は、それでいい。これが負け続けた俺の宿命だと、受け入れたのだ。即位したての頃の帝は、積極的に政(まつりごと)に参加されて、貴族たちの贅沢を止めさせたり、荘園の整理を命じたり、寺院の祭事では的確に役人を配置して首尾よく祭事を催したり、お高く留まっている年増の大臣たちが舌を巻くような活躍をして、蔵人としてお仕えしている俺も自分のことのように鼻が高かったのだけれど、まだ残暑がひどい昨年の秋に、帝にとって最愛の女御だった藤原忯子(ふじわらのよしこ)がご薨去(こうきょ)されて以来、帝はすっかり腑抜けの様になってしまい、力を落としてしまわれた。そもそも、お二人は毎日夜を共にしていて、そんなご様子であったから早々に忯子はご懐妊をされて、宮を下って実家で静養をしなければならないという時期になったのに、帝と忯子は二人でメソメソ泣いて離れたくないと我儘を言って、関白まで出てきて二人を叱っても手を付けられず、我ら蔵人も女官と相談して、どうにか帝と忯子のお力になろうと、はらはらしながらどうにか忯子が日に日に弱っていくのを宮中でもご回復できるように、八方に手を尽くして薬や食事を用意したり懸命に看病をしたのだ。そんな我々の気持ちや苦労なんて帝は何も知らず、いざ忯子がお亡くなりになると、これまで必死に看病した女官や蔵人のことなど何も気にかけず、今度は一人で毎日メソメソ泣いては、この世を去るだの出家するだの、世迷い事ばかりを仰るようになった。皆も流石に帝の辛さを哀れに思い、年の暮れくらいまでは同情していたのだが、年が明けて桜が散って新芽が萌える季節になっても、いまだに出家したいなどと一日に一度は呆けた顔で呟いて、公務も疎かにしている。女官たちは相変わらず哀れに思って一緒に泣いているが、俺を含めた蔵人たちは、もう、帝はだめだと見限っていた。それでも、こいつは出家をしたところで、叡山で相変わらず何不自由のない暮らしができるから、いい身分なんだ。俺なんぞは貴族といっても、何か一つでも阻喪をしたり、政敵に陥れられれば、あっというまに太宰府や土佐や伊豆の僻地に飛ばされて、官位に似つかわしくないような一兵卒か僧侶のような扱いで終身を過ごすか、官位を取り上げられて荘園や着物や宝物の類もすべて売り払って、朱雀門外のみじめな長屋暮らしが待っている。今の立場と未来の出世の希望を失うような不用意な発言をしないよう、俺を陥れるような不穏な空気があればすぐに察して先回りできるよう、一日一日を薄氷を踏むように慎重に慎重を重ねて、必死に周囲へ目を凝らして観察して、一時でも無駄にしないように、後悔しないように大切に生きているのだ。それなのに、こいつはそんな俺の境遇などどこ吹く風、知ったことではないというように、阿呆のように思ったことを何の思慮もなく言いたいように言い散らかしている。貴重なはずの毎日を粗末にして生きていやがる。こいつは周りの人間を、何もできない、何も考えていない木か草かのようにしか見ていないのだろう。もう、付き合いきれない。そんなに出家したいのならば、出家させてやる。こいつを引っ張り出すために、忯子様がご成仏なされますよう、不肖の私めも帝とご一緒に仏道に帰依しとうございます等と涙を流す猿芝居をかましてやったが、これはこいつが望んだことなのだ。いつまでも、甘ったれて引き留めてもらえる、なんて思うな。親父が俺に加えて兄の道隆と弟の道長も集めて、帝を出家させる陰謀策を俺たちに告げたときは、そんわざわざ謀りごとをなさらなくても、放っておけばあと数か月もすれば勝手に出家しますよ、と喉の入口まで出かかったのを抑えたものだった。なんなら、京の陰陽師を集めて叡山ではなくあの世に送ってやれば、帝にとっては楽になれて良いのに、と思った。
こいつが出家をしたら、いつも周りでベタベタしている女官や女御はいなくなるが、女を欠いた生活をこいつは知らないだろうから、好色のこいつはさぞや困るだろう。いい気味だ。出家となるとこれからは自重せねばなりますまい、と俺が嫌味を言うと、こいつは、朕も不淫につとめないといけませんね、などとしたり顔で宣いやがる。うそつけ。こいつは叡山に入れば、見境なく稚児に手を出すだろうし、女官の中務(なかつかさ)なんぞは子持ちの年増の癖にいまだに帝に色目を使って、帝もまんざらではない様子だから、出家して叡山に籠っても、ほとぼりが冷めたらこそこそ京に下りてきて逢引を重ねるに決まっているのだ。そもそも、なんだってこいつは忯子なんて碌に口も利かないければ滅多に祭事にも顔を出さない不愛想でつまらない女に、熱心に手紙を送って口説き落としてまで女御にしたのだ。おまけに、忯子の父親の為光からもこいつは嫌われていて、忯子を入内させるつもりなど全くなかったのだ。そうでなくても、こいつの周りにはいつも女官が何人もいて、皆、こいつのお手付きだろうに、不平もなさそうに楽しく暮らしていやがる。俺にだって妻はいるし、これからこいつを首尾よく出家させれば懐仁親王(やすひとしんのう)が天皇になるのだから、親王に嫁がせるための娘をまだまだ産まなければならないのに、妻は普段でも邸宅では俺と居ると不機嫌な顔しかしないうえに、褥を共にすると妻は目を背けて苦しそうな顔をするばかりだ。今日は妻と寝ないだけ、良い夜だ。女なんて嫌いだ。これからも夜は妻と過ごさねばと思うと吐き気がするけど、出世のために、将来の摂政関白の地位のために俺は耐えているのだ。俺は解っている。俺は、肌が浅黒く身体は毛深い醜男なんだ。鏡や水面に写る自分の姿が憎い。妻だって、こんな男に抱かれるのは辛かろう。帝は産毛も生えていなければ黒子の一つもない真っ白の綺麗な肌に、達人が一筆で描いたような切れ目、鼻はすっと延び、頬から顎への曲線は優美としか言いようがない、どこをとっても欠けることのない美男子で、帝の和歌はあはれで風流、和歌を詠んでいなくても口から出る言葉は慇懃無垢で優雅、女たちがそばに居るだけで夢のような心地になるのはわかる。わかるのだが、女たちだって、ここまで露骨に俺と帝を差別しなくたっていいじゃないか。生まれの貴賤には大きな隔たりがあっても、雄と雌にそんな大きな違いはないはずなんだ。それでも、こんな俺にも、花のようにかわいらしい笑顔を向けてくれる女がいた。藤原姚子(ふじわらのとうこ)。姚子は俺より10歳も歳下だが、忯子のような不愛想な女と違って、社交的で快活、高貴な家の娘だがどこでもかいがいしく働き、俺のようなものにでも笑顔を向けてくれていた。いつか、姚子を嫁にと心に決めていたから、姚子が女御として入内すると知った時は狂いそうになるほど、苦悶した。帝には忯子がいるが、好色の帝のことだから、姚子にも手を付けるだろう。これから、姚子が帝に抱かれて、嬉しそうな恍惚の顔を帝に向けていると思ったら、苦しくて自分の胸をかきむしって身体をズタズタにして、肝を引き抜いてぐちゃぐちゃにしてしまいたくなった。実際、帝は姚子と何度か夜を共にしたようで、その時俺は内裏にはとても居られず鴨川のほとりで頭を川にざぶんと漬けて、息苦しくなっては顔を上げてはまた顔を漬けてを繰り返してどうにかやり過ごした。叶わぬ恋ならば、せめて姚子には女御として帝の寵愛を受けて、将来は皇后として幸せになってほしいと思っていたが、帝はすぐに姚子に飽きてしまい、一月と足らずに姚子は宮を後にしてしまった。こいつに姚子のことを聞くと、あの人は情が薄かったのです、とバカにしたようなことを言いやがる。本当は、姚子は俺にも笑顔を向けてくれる、情の深い女なのだ。俺のところに嫁げば、余程幸せになれただろうに、宮を出て行った時の姚子の衰弱した顔は、亡くなる直前の忯子より酷い顔をしていた。俺がそっと姚子の肩に手をかけて慰めようとしても、姚子は宮に入る前までは見たこともないような、まるで鬼のような恨めしい顔で俺をにらみつけて去っていった。一体、こいつはどれだけ人を不幸にしてきたのだろう。やはり、この人はダメだ。地獄道行きだ。いますぐにでも、出家して禊を果たしていただかねばならぬ。
三条からは鴨川を離れて東国へ続く街道に入る。街道を進む前に鴨川を振り返ると、満月が鴨川を照らしていた。月にかかっていた雲が晴れてしまったようだ。内裏を発つ直前、こいつは満月の明かりで人に見られるのが恥ずかしい、とか宣いやがった。どうにか月が雲に隠れてこいつも納得して内裏から連れ出せたが、また月が雲から顔を出したとなると、こいつは逃げ出すかもしれない。ここで逃げ出せば、俺もこいつもお終いだ。それなら、それでも構わない。俺だって、こんな愚かな出世争いなんてさっさと辞して、すべてを投げ捨てて、はるか東国の伊豆の海岸で富士の山を眺めながら日々和歌を詠う日々を送れるのならば、そうしたいのだ。しかし、あの忌々しい満月をみると、なぜか弟の道長を思い出す。道長も帝と同じくらい忌まわしいやつだ。道長といえば、帝が俺と兄の道隆、弟の道長が集まっていて、五月雨の夜に飽き飽きとしていると、帝が度胸試しに道隆は豊楽院(ぶらくいん)へ、道兼は仁寿院(にんじゅいん)へ、道長は大極殿(だいごくでん)へ行ってこいと仰る。夜遅くひとりでそんなところまで出歩けば、悪鬼怨霊や幽霊の類に遭遇しないともかなわない。帝のお戯れに俺は兄貴と二人で絶句をしていると、道長は堂々と私一人で大極殿まで参りましょうと、帝から小刀を借りて独り夜道に消えていってしまった。俺も兄貴も仕方がないので夜道を一人歩くことにしたが、巨大な人影が見えたような気がしてすぐに怖くなって引き返してしまい、兄貴も俺と同じように怖がって引き返してきたせいで、俺と兄貴は帝に大層笑われてしまったが、道長は大極殿で柱を小刀で削ってきたといって、木片を差し出した。翌日、木片を大極殿で柱の傷に合わせると一致したので、帝は大層喜んで、俺と兄貴をさらに罵った。あいつら二人はこれで満足したかもしれないが、あいつらこそが、怖いものを知らない世間知らずのバカなのだ。幽霊や怨霊のような物の怪の類が本当はいないことくらい、俺だってわかっている。物の怪の類がいなくても、闇夜に紛れて潜んでいる夜盗の類に襲われて、無残に死体を打ち捨てられるとも限らないではないか。世の中には、孤独、零落、貧困、暴力、病苦、飢餓、怪我、死別、失恋。世の中には、辛いこと、苦しいこと、恐ろしいことが山ほどあるのだ。不慮の事故や病気で、これまでの労苦が報われずにすべてお終いなんてよくあることで、危機を事前に察知して避けるのも、危うき所に近づかないのも、知性と分別のある人間の賢い所業ではないか。俺は生きて帝に仕えたいのだ。こいつらは子供のころから恵まれ過ぎてなんでも与えられて守られていたから、危険を知らないだけなのだ。危険や苦痛を避けようとする人間の本性がわからない、下品な野蛮人なのだ。
こんなこともあった。俺は道長と一緒に休暇と荘園の視察を兼ねて摂津国の温泉で静養をした帰り道、農民夫婦が俺たちに訴えかけてきやがった。大峰山に潜む山賊に娘をさらわれてしまいました。山賊はいつもいつも農作物を奪っていて手に負えなかったのですが、つい先日には、やっと年頃にもなろうかという娘までさらっていったのです。あの山賊は私たちから何もかも奪ってしまいます。それでも、せめて、あの娘だけは助けてほしい。郡司様に訴え出ても相手にされない。国司様にはお目通しすら叶わない。有馬の温泉には荘園主の偉い貴族様が来ていると聞いて、失礼は承知で藁にも縋る思いでこうしてお頼み申し上げているのです。と、夫は涙ながらに訴えった。妻は袖で目の涙を拭いて嗚咽をこぼすばかりだ。俺たちはいくつもの荘園を抱えている。いちいち、荘園の農民の訴えを聞いていたら身が持たないばかりか、たまたま聞こえた訴えだけを聞き入れていたら、声の大きいものだけが得をしてしまう。政は常に公平でなければならないのだ。馬鹿々々しいから去るぞと俺が道長の袖を引っ張ると、道長は俺を払いのけてその農民夫婦の前に出ると「それは絶対に許せません。すぐに娘さんを取り戻してまいります」と、道長は鬼神のような剣幕になって叫ぶと、あまりのことに圧倒されてしまった俺を捨て置いて、道長は一番近くの駅家に駆け込んで馬を奪い、京まで駆け抜けていってしまった。兵衛佐(ひょうえのすけ)の道長は、首尾よく京で兵を集めたようで、すぐに兵を連れて取って返して大峰山の大捜索を始め、例の夫婦の訴えから一晩明けた頃には山賊たちを皆殺しにして彼らの髪を乱暴に掴んで切り落としてきた首をぶら下げ、娘を取り戻してしまった。俺はあまりのことにあっけに取られて、ひとりで京に帰ることもできずに、近くの中山寺に留まって一部始終を眺めていた。娘を助け出した道長が兵たちと一緒に得意満面に打ち取った首を掲げて勝鬨を上げると、例の農民夫婦を先頭に里の農民たちが集まって皆で涙を流して手を取り合って喜んでいた。京に帰ると、帝も大喜びで道長を迎え、夜の酒宴は遅くまで続き、彼の英雄ぶりをたたえ続けていた。こいつらはバカだ。例の農民だって、農作物を盗まれたといっても租税はきちんと納めていたし、夫婦とも丸々太っていて、さらわれた娘以外にも元気な子供はたくさんいるようだから、食うに困っていたわけでもあるまい。さらわれた娘だって、いずれは親の言いつけで好きでもない男に嫁いでいくのだから、さらうほど目をかけていた山賊に囲われた方が、大切にされて幸せになれたかもしれない。もっとも哀れなのは、山賊たちだ。道長のようなバカにはわからないだろうが、彼らは生まれながらにして農民として田畑を耕すことも赦されず、僧として寺院で修行に励むことすら拒まれた、どこにも受け入れてもらえない、もっとも哀れで助けが必要なひとたちなのだ。秩序を守るためというのならば、生けて捕えて、ほとぼりが冷めるまで一年程は別の土地に移っておけと、こっそり追い出しておけばよかったものを、何も皆殺しにして首を晒す必要なんてなかったではないか。朝廷では死罪といった無学で野蛮な刑を、もう何百年も執行していないのを知らないのか。そもそも、山賊と朝廷、盗みと徴税、何が違うというのか。剣や弓で脅して、農民たちがどうにか苦労して収穫した農作物を奪うのは、俺たち朝廷も山賊たちと大した違いはないではないか。皆、生まれ持って与えられた才能と身分を嫌々でも受け入れて、不条理な掟や柵(しがらみ)に従って精一杯生きているのだ。それを、山賊だからと皆殺しにして、正義を成したと皆で大喜び。これが学のない里の農民であれば許されるだろうが、天下を預かる帝と、仮にも将来の大臣候補がこれでは、この世はダメだ。見込みがない、真っ暗闇だ。道すがら、こいつにあの時の話をすると、あのときの道長は大変に勇敢でしたね、とか宣う。この帝は、やはりダメなのだ。天下を統べる器ではなのだ。
九条山を越える直前に俺は、帝、ここを過ぎると京の街が見えなくなりますぞ、と振り返らせた。後生に、思う存分見ておけ。九条山を山科方面に降りていると、急に帝は立ち止まり天を仰ぐと、朕も君も大人たちに粗末にあつかわれた道具でしたね、と幽かな震えた声で仰られた。俺は急に頭を殴られたように感じて、今度は嘘ではなく涙が溢れて止まらなくなった。いくら心の中でこいつと呼んで見下そうとしても、本心ではやはり手の届くはずのない、はるか遠くの雲の上の人だと見上げていたあの帝が、ご自身をまるで俺と同じ境遇だったと見てくださっていた。俺も、所詮は親父に道具のように使われて、都合が悪くなったら切って捨てられるだけの不肖の息子。そんなことは解っていたが、意地を張って強がって、誰にも怯えている自分を見せないようにしていたのに、そんな自分を、帝は見てくださっていた。天上の天衣無縫をまとった天子さまが、地の底を這いつくばっている俺の元に降りてきてくださった。蔵人に就任した初日の初々しかった時の様に、いや、それよりはるかに、今は帝をお慕い申し上げております。もう全てが満たされたような気分になって、帝を裏切るなんて、何をバカなことを考えていたのだろう。私は帝に生涯を尽くすのだと思うと、自分でも不思議なくらいスラスラと口から言葉が発せられた。帝、わたしたちは使われて捨てられるだけの道具でした。もう、道具として生きることなど止めて、このまま本当に二人で出家をしてしまいましょう。京からは遠いですが、備前国には私が父から譲り受けた荘園で、小さい領地ですが小島が浮かぶ海を見下ろす絶景を見渡せる山寺があります。そこに二人で隠遁をして、私は晴れた日には里に下りて畑を耕しますので、帝は美しい海を眺めて和歌を詠んでくださいまし。私は帝の歌が何より好きなのです、愛しているのです。帝の和歌を下賜していただけるだけで幸せなのです。雨が降ったら、本堂で帝の好きな横笛や琵琶を、思う存分奏でてくださいまし。山寺から半日も歩けば鞆の浦があります。鞆の浦はいつでも賑やかで、市場には万国の珍しいものが集まっていますから、寺での暮らしに飽きても退屈などございません。帝をお慕いしている女官たちも付いてくるでしょう。女官たちはみな、京での暮らしを鼻にかけない器量の良い女たちですから、里の民たちともすぐに馴染んで仲良く暮らせるでしょう。出家をしても、私めが帝には何の不自由もかけないようにいたします。天下も名誉も地位もどうでもいい。私たちの目に映る人たちだけが幸せならば良いのです。誰かを蹴落として蹴落とされての出世競争はもうおしまいです。二人で心穏やかに暮らしましょう。俺は、こう言ったつもりだったが、声が震えてどれだけ帝に聞こえたか、わからない。それでも、俺は初めて他人に包み隠さぬ本心を話したのだった。渾身の、精一杯の、必死の訴えだった。しかし、帝はしばらく俯いた後、子供のような屈託のない笑顔で答えた。朕は叡山で忯子の成仏のために毎日お経を読みながら、上人に教えを乞うて仏教を真面目に学んでいきたいのです。備前国には君独りで行くとよいでしょう。
ああ、馬鹿々々しい。みっともない。悔しい。こいつを裏切るつもりでいた俺は心を改めたというのに、俺がこいつに裏切られた。こいつはやっぱりバカだった。もう出家させるだけでは許せない。俺の言うことは何でも聞く蔵人頭の実資(さねすけ)が日記をまめにつけていて、帝の言動も事細かに記しているから、即位式にこいつが乱心したと当時の日記を書き換えさせて、こいつの評判を千年後の未来まで地に落として辱めてやるのだ。今日は満月が殊更、眩しくて仕方ない、この鬱陶しい眩しさは、帝や道長のようだ。俺には眩しすぎて、ちくしょう、目が痛い。ああ、目が痛いのは、さっき泣いたからか。俺らしくない、バカな涙だった。天皇天子、太政大臣に摂政関白といえど、果ては宋の皇帝であっても、あの月の下では人間などちっぽけで矮小な存在。憧れても、憎んでも、とても相手にならないのだ。しかし、道長、あいつは、この世はあの満月の様に全部俺様のものだと、摂政関白にまで成り上がったりしたら、得意になって和歌にして詠うだろう。道長の摂政関白など、万が一にでもあってはならないが、あいつは風流も優雅もありゃしない、恥さらしで傲慢に満ちた和歌で周りの歌人たちを呆れさせるに違いない。あまりにも下品すぎて末代まで笑い種として語り継がれてしまい、藤原家の名誉も功績も、親父が泥水を啜って築き上げた地位も全てが汚されて、千年後の未来でも藤原家は笑いものになるはずだ。俺は確かに帝や道長より歌を詠むのは下手だが、いましがた通り過ぎた俺の山荘では、俺の少ない蔵人の位禄もなげうって、何度も有数の歌人を集めては歌会を催してきたのだ。俺は誰よりも風流を知っているのだ。愛しているのだ。我欲にまみれた政治家なんかではない、もののあはれも無常のはかなさも自然の優雅も人の心の痛みも、誰よりも理解している風流人なんだ。こんな俺の今日の苦渋に満ちた決断の裏切りだって、道長の下品で傲慢な振る舞いで上塗りされて、ちんけな小物の謀反ということにされてしまう。あの満月に照らされていると、そんな恐ろしい未来が現実になりそうで、ぞっとする。民もこいつらの傍若無人の政と贅沢三昧の放蕩に振り回されて疲弊して、この世は朝廷へ向けられた怨嗟の声で溢れるのだ。親父は五十歳を過ぎて長くはないだろうし、道長と違って兄貴はまだ見込みがあるが酒ばかり飲んでいるから長生きはできないだろう。この世を、民を、藤原家を、北家を、俺が守るしかない。そのためには、まずは目の前の帝を騙して出家させるしかないのだ。こいつはせいぜい悔しがるといい。なんとしても、京で生き抜いて出世して、俺がこの世を守るのだ。それしかないのだ。嘘をつく。騙す。嫌な言葉だ。もう色々と汚いことには手を染めて、清廉潔白ではいられなくても、せめて公明正大ではありたい、と思っていた。しかし、それも今日でおしまいだ。俺が死んだら、閻魔様でも俺のことなど理解できずに、地獄道か良くて餓鬼道へと連れていかれるのだろう。これから起こすたった数分間の所業によって、俺は何億年もの責め苦を受けることになるのだ。俺は、権利欲にまみれた裏切り者の従者、天子に弓を引いた逆賊という汚名を永遠に着せられるのだ。そうだ、結局俺はただ自分が苦しんで、自分が蔑まされるのが嫌なだけだった。あの世などないのだから、俺はこの世で出世して、登り詰めて、天皇も貴族も下々の民も全てが怯えて俺の前にひれ伏して、俺は誰も逆らえない大号令を天下に出して、誰であっても俺への口ごたえも許すまい。この世の富も宝物も、全て俺のものにしてやる。それこそが俺の本望だった。そのために、俺は生まれてきたのだから。帝、ここが元慶寺です。出家ですから早速、髪を切り落とさなければなりません。剃髪なんてすぐに済みますからご心配いりません。私は粟田の山荘に居る父に、出家前の最後の姿を見せて赦しを請うてきますので、へへへ、そのままお待ちください、花山天皇。
思えば私は、眼前の重要かつ大切な人の心情すら推し量れず、学業、仕事、家庭の全てにおいて失敗した敗残の男である。他人に誇れるのは、せいぜい他人よりは苦労した、という程度のものだ。そんな私が、千年前の、身分も全く違う人達の心情の、一体、何が解るというのか。
そのように思うと、なにか考えを色々と巡らせるのもアホらしくなって、無心で元慶寺まで歩くようにつとめることにした。

12時ちょうど、元慶寺の隣にある華山寺に着いた。その華山寺は妙に子供の声でにぎやかなようで、何かと境内に入れば、華山マルシェなる移動販売車や屋台を境内に入れて、バザーのようなものが催されていた。このような、観光客など訪れようもない、いかにも地元の寺院が、法事の類でもなく地元の人たちでにぎわっている姿を見るのは、なんだか嬉しくなる。ちょうど昼時だが、すでに予定の時間を過ぎているので、すぐに買えて食べる時間もかからなそうな、クレープを買い食いして昼食とした。
元慶寺

元慶寺は華山寺のすぐ裏手にあるはずだが、崋山寺を出て裏手に回ってみても小さい民家ばかりで寺のようなものが無い。奥まで進むと段ボールのようなものに手書きでぶっきらぼうに「寺」と書かれた看板があったので、その看板の矢印に従い、未舗装の小道に入ると元慶寺が見つかった。門が二階建て構造になっていて、二階部分では寺の住職と思われる方が掃除をしている。

境内は先ほどの崋山寺とは違って、参拝客も少なく静かであった。以下にも古い寺院らしく、墓地が併設されているわけでもないから、用のない人以外は訪れることもない寺だろう。花山法皇に関する看板が建っており、出家時の石が同の等と書かれている。まあ、それだけだよな、と思い本堂にお参りした後、ろうそくと線香に火をつけてお供えをした。元慶寺については、二時間以上も歩いて訪れてみたが、特に大きな感慨もなく、それだけであった。感想と言えば、寛和の変以後、数か月は花山天皇改め花山法皇は元慶寺に滞在していたようだが、皇室をお泊めするには小さすぎる寺だな、といった程度である。所詮は、裏切り者の兼家か道兼が用意しであろう寺だから、皇族をもてなしたり丁重に扱うなんて意図も無かったろうし、当たり前ではあるのだが。
元慶寺を出ると、来た道を戻り御陵(みささぎ)駅から京阪の京津線と石山坂本線、それに坂本ケーブルカーを乗り継いで比叡山延暦寺を目指す予定だ。花山法皇は、元慶寺で出家の後、比叡山延暦寺で受戒を受けて正式な僧侶となり、その後、しばらくは比叡山延暦寺で修行生活を送ったようだ。おそらく、花山法皇が元慶寺から比叡山延暦寺へ向かった際は、今回の鉄道ルートと同じように琵琶湖側の陸地沿いを進み、坂本ケーブルカーの近辺の山道を徒歩で登って比叡山に入ったと思われる。峰沿いを歩くのは無駄に苦しいし、京都側に出るのは知っている人に鉢合わせするのも気まずいだろうからである。
比叡山延暦寺へ
12時45分、御陵駅発の京津線に乗った。京津線は鉄オタには名高い、地下鉄と山岳と併用軌道の3つを通る珍しい鉄道路線だ。私も今回初めて乗車するが、正直、元慶寺より楽しみにしていた。地下の御陵駅を出ると列車はすぐに地上に出て、国道1号横のワインディングロードを、車輪をきしませながら走る。勾配もかなりきついようだが、京津線の車両は新幹線車両と同じくらいコストをかけているらしく、力強くぐんぐん進む。終点のびわ湖浜大津駅手前の数百メートルが、道路の上を走る併用軌道になる。併用軌道は外から見る分には珍しくて面白いのかもしれないが、併用軌道を走る列車に乗ると、路盤が弱いので揺れは酷いし、スピードは出ないし、信号で止まるしで、あまり良いものではない。それでも道路上の景色を列車内から眺めるのは、珍しいので面白かった。
13時6分、びわ湖浜大津駅から石山坂本線に乗り換えて、終点の坂本比叡山口駅を目指す。電車は、前々回の嵐電のようには混んでいない。やはり、今日は観光客は少ないのか。二両編成の短い電車は、13時21分、何事もなく終点の坂本比叡山口駅に到着する。坂本比叡山口駅からケーブルカー駅までは徒歩で15分ほどかかるらしい。バスもあるのだが、徒歩15分であればバスに乗る必要も無かろうと、歩いてケーブルカー駅を目指した。
13時32分、ケーブル坂本駅に到着。時刻表を見るとケーブルカーは毎時0分と30分に出発とのことだった。つまり、ついさっきケーブルカーは行ってしまったばかりで、30分近く待つことになった。この後、京都側にケーブルカーと嵐山鉄道を乗り継ぐ際にも、乗り継ぎの悪さに悔しい思いをし続けることになる。

14時00分、ケーブル坂本駅からケーブル延暦寺駅を目指す。この坂本ケーブルには車内放送で、よほど自慢なのか、日本一長いケーブルカーであることを、しきりにアピールした。おまけに途中駅もあるらしい。ケーブルカーで途中駅を設けると、ケーブルカーは2台の車が連動して昇降しているから、片方は不要な停車をしなければならない。なんかつまらない話であるなと思ったら、途中駅の上側のもたて山駅の近くには、紀貫之の墓があるらしいことを車内放送で紹介していた。
比叡山延暦寺

14時11分、ケーブル延暦寺駅着。駅から延暦寺を目指して参道を歩くと、引っ切り無しに鐘の音が聞こえて、荘厳な感じがする。しかし、どうも鐘の音が安定しているように思えない。花山法皇は、比叡山延暦寺の西塔という場所で過ごしていたらしい。別に西塔という塔があるわけではなく、どうも比叡山というのは東塔と西塔にエリアを分別しているようで、どちらのエリアにも複数の施設がある。本来の目的であれば用があるのは西塔だけだが、延暦寺の主だった建築物は東塔にあるらしく、せっかく来たのだからと貧乏根性をだして、参拝料1000円を払って東塔エリアに入った。坂本ケーブルカーも乗客は少なかったから、今日の比叡山延暦寺は空いているのかと思ったが、東塔に入るとピーク時には及ばないのだろうが、やはり、それなりに観光客がいて賑わっているた。東塔は根元中堂というのがメインの本堂らしいのだが、残念ながら改修中。巨大なプレハブに覆われて改修工事をしていた。文珠楼、大講堂、阿弥陀塔と一通りを見る。例の鐘の音は、大講堂の横にある鐘楼の巨大な鐘を、参拝客が自由に突けるようになっていたからだった。開運の効果があるそうだが、もう開く運も無い私は辞することにした。
さらに、徒歩で西塔へ進む。冬場は西塔へのシャトルバスが無いらしく、西塔に行くには徒歩で行くしかないようだ。無舗装の砂利の敷かれた山道をあるいて、西塔へ分岐するためのドライブ道を跨ぐ歩道橋を渡る。西塔は行き止まりになっているので、入ったら来た道を戻ることになるが、西塔に入るといきなりの長い下り坂である。これを登り返すのかと思うと憂鬱になるが、西塔を目的に来ているのだから、引き返すわけにもいかない。進む。

まずは、浄土院という伝教大師御廟に入る。京都の寺院によくある、箒で波打った模様を描いた庭園があり、奥には延暦寺では珍しく朱色で塗られていないお堂があった。花山法皇を滞在させるには、ここが丁度良いように思えたが、御廟に人を住まわすものだろうか。

さらに西塔の奥へ進むと、にない堂と呼ばれる常行堂と法華堂の二つのお堂を渡り廊下でつないだお堂がある。おそらく、西塔内で最も絵になる建造物だろう。

渡り廊下を潜ってさらに進むと、釈迦堂。最も大きい建造物で、なかには帝釈天像など多数の仏像がある。一番立派な建物だけど、建物内は広いし仏像の圧迫感も強い。ここで寝泊まりするのは嫌だなーと思い、結局、花山法皇についてはなにもわからないまま西塔をあとにした。

比叡山からは、往路の坂本ケーブルではなく、比叡山頂駅からロープウェイとケーブルカー、叡鉄を乗り継いて京都まで戻った。上でも書いた通り、ロープウェイこそ駅に着いたらすぐに臨時便を出してくれたおかげで、本来は毎時00分と30分の出発のみであるところ、15時40分に山頂駅を出発した。しかし、その後のケーブルカーは30分待ち、叡鉄は15分待ちと、それぞれ各駅ではインターバルいっぱいに待たせてもらい、京阪の出町柳駅に着いたときは疲れ切っていた。しかし、今日はこれから予約したホテルのある姫路まで移動しなければならない。京阪で京橋駅まで移動し、京橋駅でJRに乗り換えて大阪駅で新快速に乗って、19時12分に姫路駅に着いた。

姫路駅の北口は、正面にライトアップされた姫路城があり、街路樹も建物も目一杯イルミネーションが飾られていてにぎやかだった。それに比べてホテルがある南口は、かろうじて最低限の街路灯はあるが、廃墟街のような暗さであった。そのホテルは、暗い北口の駅通りを5分ほど歩いた、大通りの奥まった場所にあった。姫路駅周辺で、そのホテルが妙に安かった理由がわかったような気がした。
書写山圓教寺
寛和の変から一ヶ月後に花山法皇は書写山の性空上人の元を訪れている訳だが、それについて、花山法皇研究の第一人者と思われる、今井源衛氏の「花山院研究」という論文によると、以下のようにある。
しかしその直接的な原因は、やはり一条摂政一門の上に執拗に襲いかかった死の咀いの恐怖だったと思われる。
つまり、一条一門とは花山法皇を含めたその親族であり、出発直前の姉の死により死の呪いの存在を確信し、死の呪いをかけているのは藤原兼家一門であろうとして、その呪詛を解くのが目的だったということらしい。平安時代当時、確かに信仰心が強く呪詛の類も信じられていたのかもしれないが、京都にも安倍晴明をはじめとした陰陽師はいた訳だし、わざわざ六日間もかけて書写山まで行くだろうか。しかも、呪詛を解くのであれば一週間でも一ヶ月でも居て良いと思うが、わずか一泊で退散したのも、どうにも真偽の程が怪しい。
おまけに、1002年には花山法皇は引退した性空上人の元を訪れて、当時暮らしていた弥勒寺に立派なお堂を建てている。
未来にそのような恩返しをするのだから、寛和の変直後の986年の御幸で性空上人は花山法皇にけんもほろろな扱いをした訳はなく、むしろ、一泊のわずかな時間で開眼させるような何かを性空上人は花山法皇へ与えたのではないだろうか。
ともあれ、書写山圓教寺は、ちょうど花山法皇が生きた時代の性空上人が開山した寺院であるから、花山法皇が訪れた当時と現在とでは、大きく違う様子であったろう。花山法皇の目に当時の書写山がどのように映ったかは、実際に書写山を訪れて知りたいところだ。
姫路のホテルで目が覚めたのは午前5時であった。年を取ったせいか、旅の高揚感か、どうにも目が覚めるのが早い。今回はホテルで朝食を取ったが、朝食の食堂は混雑というひどではないが、満席に近い賑わいであった。外を見れば駐車場は満席で、おそらく今日は満室なのだろう。関西は特に観光客が多くホテルはどこも満室で、価格も高騰していると聞くが、その様子が改めてよくわかる。
朝食を食べ終えたら、今日のバスの時間を確認してホテルをチェックアウトした。
12月10日(日)の本日は、姫路駅からまずはバスで書写山圓教寺に向かう予定だが、姫路駅のバス停を見渡しても、どのバス停がどこ行きかの案内板がない。一つ一つ調べていくと、歩道橋を何度も渡って降りてを繰り返すことになる。余裕を持ったつもりであったが、ギリギリで書写山ロープウェイ行きのバスを見つけた。
8時35分、書写山ロープウェイ行きバスは姫路駅前を出発した。バスは部活動の通学と思われる女子高生が多い。すると、書写山まで行く客はほとんどいないのか。実際、女子高生たちは姫路高校前なるバス停で全員降りて、終点の書写山ロープウェイバス停まで乗っていた客は私ともう一人だけであった。
バスの到着予定は9時4分であったが、実際はかなりの早着だったようで、9時ちょうど発のロープウェイに乗れた。

書写山ロープウェイを降りて、ほどなく進むと参拝料を払って、さらに奥へ進む。参拝料を払った入口から摩尼殿までは、バスがあるとのことだが、500円をケチって謝辞したので、山道を歩く。道沿いには観音像が並べられていて、並々ならぬ宗教的な雰囲気がある。
途中で、木々が開けて姫路の市街地を見下ろせる場所があった。比叡山の西塔には京都を見下ろせる場所は無いから、仮に花山法皇が書写山を訪れた際に、すでに比叡山に移っていたとしても、山寺から眼下の里を見下ろす体験は、ここが初めてだろう。花山法皇は、最後に里を見下ろせる花山院菩提寺を、隠遁の地と決めた。それはきっと、この書写山の風景が頭にあったからではないだろうか。
さらに山道の参道を進むと、摩尼殿が正面に見えてくる。でかい。山の中のしかも斜面に、よくもまあ、こんなでかいお堂を作ったものだと思う。石段をのぼり、摩尼殿の中に入る。中は、お守りなどの売店と、飾られている神仏の像を見ることができた。本来、このような目的で建てられた建築物ではないだろうが、時代が、観光施設にしてしまったのだろう。

摩尼殿の次は順路に従えば食堂(じきどう)と呼ばれる建築物が奥にあるので、さらに進むわけだが、山道を進むルートを取ると白山権現なるものがあるらしい。白山信仰は花山法皇にも縁があるから、白山権現を目指して山道を登る。意外と、この道を歩く人も多い。前にはトレランの格好をした登山者、後ろにも登山の格好をした人がいる。私だけ普段着だ。
白山権現は何ということもないと言っては失礼だが、普通の山中にあるような神社であった。もちろん、敬意を表して手を合わせる。

白山権現を下りると、食堂に着く。ここは、映画「ラストサムライ」のロケ地にもなった場所で、たしかに実際に訪れると、他の寺院とは異なる印象を受ける。
まず、大講堂、食堂、常行堂という三つの機能の異なる建物が、中央の白砂利のひかれた広間を囲むように、カタカナのコの字に建っている。現在の円教寺は観光客向けの寺院だから、お堂がどのように建てられても構わないのかもしれないが、建築当時は、実際に多数のお坊さんが生活して修行をした場であるだろうから、生活と修行とイベント開催の建物が機能的に配置されたように見える。大講堂の看板を見ると、大講堂は花山法皇の命によって建てたとあり、花山法皇は青写真を描いただけかもしれないが、建築設計にも才能を発揮したというから、この三軒の建物の配置を花山法皇が立案したのであれば、相当な才能だったと思う。
正面の食堂には入れるので、靴を脱いで入場する。二階に数々の小さい仏像が飾られており、一種の博物館のようである。本来は、多くの修行僧が寝泊まりをしたフロアであろうに、私のような無信仰の観光客が立ち入るのは不相応な気分になった。

食堂からさらに奥へ進むと、奥之院の開山堂についた。一通り写真を撮り終えると、丁度10時になったからであろうか、本堂内のお坊さんがお経を唱え始めた。
お経は亡妻の葬式を思い出すので聞きたくないのだが、なぜか聞きたくないように思えず、本堂の庇に立ってお経を聞いた。お経を聞いていると涙が溢れてくる。亡妻を思い出して、ここで嗚咽を漏らして泣き叫んで気でも違えてしまえば、それで終わりにできるだろうか。狂いそうになるのを「まだ、その時ではない」とじっとこらえる。二十分ほどお経を聞いて、次の予定に差しさわりが出ることに気づき、般若心経を聞いて奥之院を後にした。

奥之院からロープウェイ駅までは一気に戻ろうと思ったが、摩尼殿の前で微妙に空き時間があることに気づき、茶屋で抹茶をいただいた。おまけで付いていた和菓子が旨かった。
通宝山弥勒寺
今回の旅の最後の目的地は通宝山弥勒寺である。
弥勒寺は上でも紹介した通り、圓教寺を引退して里に庵を構えて過ごしていた性空上人の元を、1002年に花山法皇が訪れて立派なお堂を建てさせた始まりだ。
弥勒寺のWebサイトは、今は珍しいページに入るとカーソルの後をついてくる画像があったり、アクセスカウンターがあったりと、Web黎明期を思い出させる作りであった。httpではなくhttpsなのだけは現代的か。
それより問題は、弥勒寺のWebサイトのトップにも書かれているように、弥勒寺に行く公共バスが無いことだ。一応の案内では、又坂と呼ばれるバス停から徒歩30分とあるが、GoogleMapで調べると徒歩では44分かかるらしい。それであれば、レンタカーを使えばよかったのだが、徒歩30分でも歩いていけるのであれば歩こうと、計画時に思っちゃったので、バスで行くことにした。
書写山ロープウェイを下りてから、姫路駅に戻るバスで姫路駅までは戻らず、途中の横関東口というバス停で降りて100mほど移動し、横関バス停で前之庄行きというバスに乗ればよいらしい。
11時30分、6分遅れでやってきた前之庄行きバスに乗る。
バスはほどなく又坂バス停についたので降りる。降りた客は、もちろん私一人であった。又坂バス停で、手持ちのスマホのGoogleMapで弥勒寺を目的地に案内を開始して、Google先生に従って歩き始める。地図を見ても気づかなかったが、又坂バス停から弥勒寺へは、車道の軽い峠越えがあった。やはり、花山法皇のゆかりの地を行くのは楽ではない。峠を越えると、おだやかな山のふもとに広がる里の風景が見れた。こういう景色は好きだ。寺院を尋ねるより、こういう場所を歩くために旅をしているのかもしれない、と思い始める。

12時20分、弥勒寺に到着した。弥勒寺にいたる道には、まだ気の早い「初詣」の真っ赤な幟が何本も建てられていて、意外ににぎやかだ。
境内には、私の先客で一組の家族の参拝客がいた。大きい寺院ではないので、写真を撮って参拝だけ済ますと、早々に弥勒寺を後にした。

さいごに
花山法皇のゆかりの地を訪れる旅も今回で三回目となったが、前回からなんとなく、普通の旅とは違う不思議な違和感を感じていたのに気づいた。
通常の旅であれば、京都を訪れれば清水寺や金閣寺、姫路であれば姫路城、山口県を訪れれば秋吉台など、その土地の名所を訪れるものであるし、それらを如何に効率的に巡るかを思案するものだ。しかし、何かしらの史実や人物を追って、当時の場所を訪れようとすると、訪れた土地の、それ以外の名所名跡をスルーすることになる。旅としてそれなりの金額を使って移動、宿泊をするのならば、その土地の有名な箇所はすべて回ろうとするのは通常であろうが、今回のような旅の形式をとると、そうはならないのだ。
これは、実際にやってみると何とも不思議な感覚を覚える。京都という今や世界でも有数の観光地において、あまり観光客も訪れない場所を訪れたかと思うと、観光客でごった返す寺社を横目に通り過ぎ、ある場所からは突然、観光客の大混雑に巻き込まれるのだ。このような旅で受ける感慨は、私の筆力では表現できないので、ぜひ、奇特な趣味をお持ちの方は、試していただきたい。
今回の記事については、珍妙な紀行文どころか奇行文と呼ぶべきものとなったが、この馬鹿々々しい記事に付き合っていただいたことに、感謝を述べたい。今回は型破りな形式をとったが、極々一部の奇特な趣味の方に喜んでいただければ幸い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
