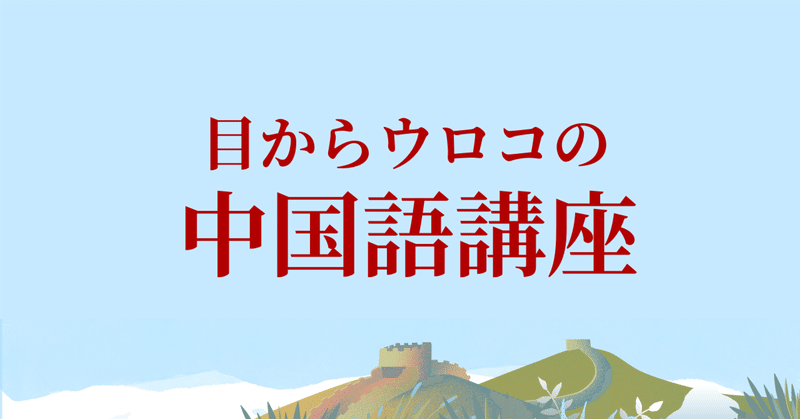
【中国語講座】固有名詞の仮名
NHKの中国語ニュースに携わっていていつも困るのは、日本の地名や人名に含まれる仮名文字です。
中国語的には、できるだけ漢字にしたいわけですね。当たり前ですが。なので、中国のメディアを見ていると、結構漢字を当てているようです。
例えば旧社会党の「土井たか子」さんの場合は、本名が「多賀子」という漢字表記なので、中国のメディアではそれをきちんと調べて“土井多贺子 Tŭjĭng Duōhèzĭ”と表記していました。
つくば市は、元々は「筑波」という漢字表記がありましたので、中国のメディアでは“筑波市 Zhùbōshì”と書いていますね。
このように、元々の漢字表記がある場合はそれを使えばいいので、楽ですね。
でも元々が仮名文字である場合は困ります。
例えば、拉致被害者の「横田めぐみ」さん。こちら、戸籍上のお名前も「めぐみ」というひらがな表記のようです。拉致被害者の代表のようになっておられるので、どうしてもニュース等で時々名前が出てきます。
中国のメディアで取り上げられる場合は、たいてい“横田惠 Héngtián Huì”と書かれているようです。多分「めぐみ」は「恵」という字が使われることが多いからだと思いますが、勝手に決めてはいけませんよね。ご両親に了解をとったのかもしれませんが。
ちなみに、NHK中国語ニュースでは、こういう場合はローマ字を使っています。つまり“横田Megumi”と書きますし、読むときも“Héngtián Megumi”と読みます。
以前、昆虫食に関するニュースで、昆虫の素揚げの入った缶の自動販売機が登場したというニュースがありました。(ひええええ)
この自動販売機が登場したのは佐賀県みやき町というところでした。このニュースは中国語ニュースでも報じたのですが、地名をどうするかということで、わりとあっさり「ローマ字で」ということになったようです。僕は担当していなかったのですが、暇だったので(笑)、ちょっと調べてみました。つくば市のように元々漢字表記だったとしたら、漢字で書くべきなのではないか?と思ったからです。
いろいろ調べてみると、こちらの町が属する郡の名前が「三養基郡」という名前で、「三養基」の発音がまさに「みやき」だったのです。だったらこの「みやき町」の「みやき」も元々は「三養基」と書いていたのではないか?と思って更に調べてみました。すると、、、
この町は昔からあった町ではなく、わりと最近いくつかの町が合併して誕生したようなのですね。で、この新しい町が出来た時、名前を公募して「みやき町」という名前(表記)にしたらしいのです。つまり、元々この町は最初から「みやき町」なのですね。もちろん、その音は「三養基郡」から取ったのだとは思いますが、「三養基町」という町はこの世に存在したことはないのです。だからやはり“三养基町Sānyăngjī dīng”とすることはできなかったな、と思いました。残念!(笑)
名前の書き方は気を使いますね。特に日本の人々は結構書き方に愛着を持っていることが多いので、勝手に漢字表記にしたり、簡体字表記にしたりすると、時としてクレームが来ることもあるようです。慎重にしないといけませんね~。
通訳・翻訳家 伊藤 祥雄
大阪外国語大学外国語学部 中国語学科卒業、在学中に北京師範大学中文系留学、大阪大学大学院文学研究科 博士前期課程修了。通訳・翻訳業に加え、明治大学、東洋大学等の中国語講師を務める。NHK国際放送の中国語ネットニュース番組元キャスター。
著書に『すぐに役立つ中国語の基本単語集』(ナツメ社)をはじめ、『中国語検定対策2級問題集』(白水社)などの中検対策書多数。NHKテレビ「中国語!ナビ」のテキストで「中国語お悩み相談室」好評連載中。
