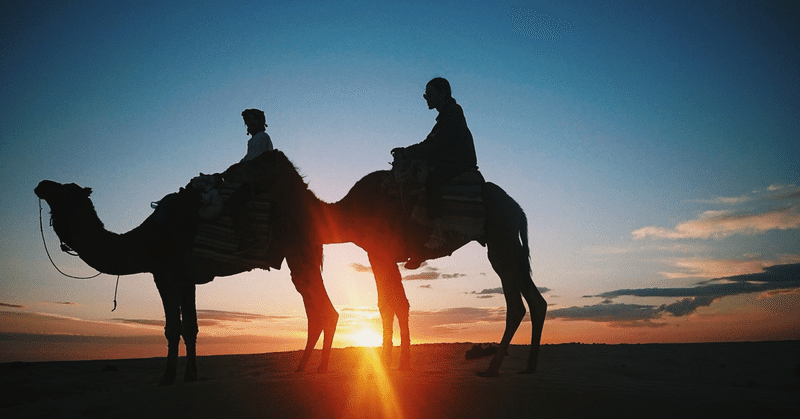
『一神教と戦争』ポスト近代への水先案内人としてのイスラーム(世界の歴史)
現代国家とイスラームは折り合いが悪い。国民国家(ネーションステート)が構成しづらい。「法人」の考えがない。自然法の考えもなく、代表や主権国家の考え方もない。利子も認められない。社会学者の橋本大三郎氏とイスラム学者の中田考氏のこの対談は、この特性は近代を通り越した、ポスト近代で折り合いがいい可能性があるという。すべてはないだろうが、ヒントがあることだけは確かだ。
イスラム教の立場は、ユダヤ教とキリスト教それぞれの偉大な預言者としてモーセとイエスを位置づけたくさんのメッセージ(預言)が送られたが、預言者がいなくなると教えが歪曲されていった。その後に最後の預言者であるムハンマドがあらわれて最終的にそれを正したというものだ。
キリスト教とイスラム教の大きな違いは、キリスト教にはキリスト法なるものがないこと。王様が勝手に国を作ったり、勝手にビジネスをやったり、勝手に戦争をしたりしても神学的にも哲学的にも説明しょうがない。イスラームでは戦争は三つに分類されている。
1)異教徒との戦い(ジハード)
2)イスラム教徒同士の正統性のない戦い
3)イスラム教徒であっても正統性のない戦い
キリスト教徒にとり教会が大事なのはそこの精霊が宿るから。法人概念も精霊が法人に宿ることで法人となる。キリスト教の精霊の概念はユダヤ教にはない。ユダヤ教にとり霊(精霊でなく)は「風」であり、「生命」だ。どうしてキリスト教に精霊の概念があるかというと、イエスが昇天した後に精霊が降りてきたと『使徒言行録』に書いてあるから。(ただし、正教の精霊は教会を通してでなく直接信者に降りる)
このような、キリスト教とイスラム教の考えの違い対談になり明らかにされていき、読者が参考になると思われるクライマックスに入る。
ヨーロッパ型、西洋型の植民地主義は、フランス語は文明の言語であるからそれをしゃべるのが当然と押し付ける。しかし、オスマン帝国ではアラブ地域ではアラビア語をしゃべっているのと同じように、他の地域ではその土地の言語が使われる。クリスチャンであるギリシア人も深く行政にかかわる。陣所的なことにおいても、あるいは宗教的なことにおいても、差別はない。アメリカやヨーロッパからすると、キリスト教でない他の文明は猜疑心の太陽となる。ロシアもそう見える。インドも不思議に見える。中国も警戒する。戦前の日本もそうだった。
ジハードの呼びかけは、まずイスラム教徒になるかと聞いて、ならないと相手が答えた場合、では税金払うかと聞いて、払えばそれで終わり。その意味で壊滅戦にならない。戦争になった場合も、勝てなければ最後までやらずに講話することもできる。イスラームはもともと、理解できない人間、価値観を共有しない関係を前提としている。
これは国民国家という枠を超えた人間を包摂するという意味でイスラーム的な考え方が、ポスト近代に大きな意味をもつのだろう。
日本人がひどく苦手なのがイスラム教だが、それを知ることは未来につながることだということを、本書は分かりやすく伝えている。
Creative Organized Technology をグローバルなものに育てていきたいと思っています。
