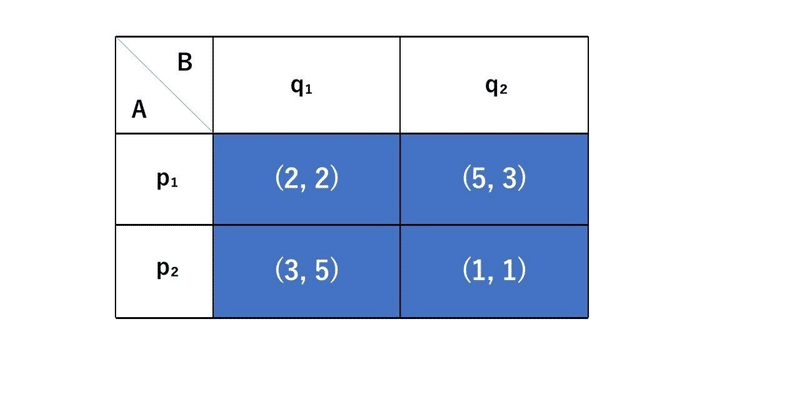
『実戦のための経営戦略論』社名で逆引き活用するのがオススメ(業界・他社・自社の歴史)
本書で一番参考になったのは、経営学者が「経営の概念モデル」を外界(戦略)と職場(組織)にわけ中間に経営を置き、競合に対する競争戦略と顧客の対する立地戦略を外界、経営と社員のマネジメントと社員と社員のマネジメントを組織論と位置づけていることだ。
どうやら著者は戦略が得意なようで、本書はその事例を整理したものと言える。たとえば、イノベーションは再現性に乏しいうえ、売上高を一時的に引き上げて終わり。他社による模倣が相次ぐなかで成長を長らえ、利益を確保する手段が戦略だとしている。
本書を手に取る経営者が、どのような読み方をするのかが想像できないが、ケーススタディーが多いため、そこから逆引きした方が、イメージがつかみやすのではないだろうか。
たとえば、3社仮説として、トヨタ、ホンダ、日産、三菱UFJ、三井住友、みずほなどの3社に収斂されることはよくあることだが、JagdishとRajendraの理論によって説明されている。2社の業界、5社の業界もあるが、それは長ければ四半世紀で3まで落ちる傾向があると戦略を紹介している。
Amazonは規模の経済に依って立つ、TesraのMuskは口八丁手八丁、Appleはエコシステムに依って立つとし、競争原理戦略を解説している。ホンダとヤマハ発動機の競争、紙オムツ戦争、信越キノコ競争など、事例は新しさを基準にせず、過去の歴史からも考察している。
したがって、本書は索引から読むとアプローチしやすいと思う。海外の企業はABCの索引から、日本の企業はアイウの索引から逆引きできる構成になっている。企業の事例を読み、その体系的戦略を読むことができる。同じ業界で国内海外と比較する。あるいは類似の他業界の会社名から事例を知り体系的戦略を読む、という流れの読み方がオススメだ。
700ページを超える本書を1ページから順に読むことで頭に整理体系化されるのであれば問題ないが、逆引きで他社の戦略分析、他業界の戦略分析をすると価値を高めやすい1冊ではないだろうか。
Creative Organized Technology をグローバルなものに育てていきたいと思っています。
