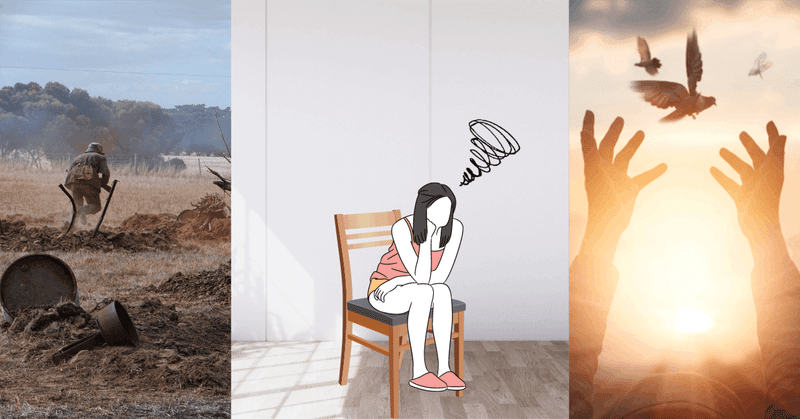
【戦争と歴史】 書評#112
みなさん、いつもお世話になっております!
本日は、私の投稿の軸とする一つ「本」「読書」に関して書かせていただきます。
自己紹介に書いたマイルールを守りながら、私の大好きな本について書いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします!
今回は、戦争についてです。
明治維新あたりから、戦後までを振り返ります。
ヘッダーは、ここまろさんの作品を使わせていただきました!
ありがとうございます!!
目次
基本情報
半藤 一利(著)
幻冬舎 出版
2018年3月30日 第1刷発行
全213ページ
読書所要期間6日
私が本書に出会うきっかけ
これは、明らかにタイトル買いだ。
「私の気になるキーワードが二つ並列されているものがあるなんて!」
といった感覚である。
しかも著者の本は、もうすでに何冊か読ませていただいている。
これもまた”買い”要素だ!
出会うべくして出会った、そんな一冊だ。
私が思う、この本の本質
それにしても、ページを開いてみて驚いた。
まず、「まえがき」がない!
これは、結構珍しいのではないか?
古い本、岩波文庫みたいな歴史ある本ならよくあるが、2018年に刊行されているものとしては、かなりレアだと感じている。
昨今の活字離れに配慮してか、本の冒頭「この本はどういった本なのか?」というその本の性格を明らかにしてくれているものが非常に多いからだ。
しかも、本文もめちゃくちゃ独特!
これはぜひ、直接目の当たりにして欲しいのだが、短歌集とまでは言わないが、短いセンテンスの集合体といった感じ。
それらは、これまで著者が著してきた本などから抜粋し、寄せ集め、一つの本としてまとめられたものである。
アルバムと言っても良いかもしれない。
とにかく、不思議な本だ。
そして、いったん読み始めれば、一気に引き込まれる。
私が感じたこと
1点目 〜日本人の気質? 人間の気質?
国家の歩みがどっちに向かって踏みだそうと、同時代に生きる国民の日々というものは、ほとんど関係なしに和やかに穏やかにつづいていく。
何か前途に暗い不吉なものを感じ警告されていても、「当分は大丈夫」と思いこむ。
これらは、著者が国連脱退について書いた文である。
今も私は、現在進行形でこの局面に差し当たっていないだろうか?と感じる。
気候変動(地球環境)と、なくならない戦争にこれを思うのだ。
「当分は大丈夫」や
「今ここは大丈夫」は、
果たして本当にそうなのだろうか?
この先の保証や努力は、いったい誰がするのだろうか?
自分自身、一人ひとりであると私は思う。
「塵も積もれば山となる」
「千里の道も一歩から」
何でも”放題”の時代。
果たして、このままでいいのだろうか?
一歩ずつ、一つずつ、踏みしめて噛みしめる時代が、これから益々必要なのではないだろうか。
地球は、使い放題でない。
戦争は、し放題ではない。
戦争は、地球を大きく消費する。
2点目 〜「戦争というものの恐ろしさの本質」
本書P110にこの文がある。
これは、いったいどういったことを指すか、皆さんは想像がつくだろうか?
要約すれば、『人間が人間でなくなること』だと書かれていると私は捉えている。
言い換えれば、
「非人間的なことを、何も感じずできる人間になってしまう」
ということだ。
しかも、これが一人や二人ではない。
非人間的行為をする人間が、国内のニュースなどで見聞きするが、そういった人数のレベルでない、全国民がそれに近い状態になる・・・
これが、戦争の本質なのだ。
人を殺し合う当事者だけでなく、日本に待つ家族もまた、非人間的思考に飲み込まれていくのだ。
人間が人間であるために、戦争は放棄すべきことなのだ。
だとすれば、私たち人間が人間であったことが、これまでの歴史の中であったのだろうか。
おそらくないと言っていいのではないだろうか。
むすびに(まとめ)
フィクションの時代
著者は、1930年生まれ。
いわゆる戦時下に生まれた。
国家総動員法という信じがたい、人権が相当制限された法律下で、日本が一丸となって世界の頂点へ登りつめようとでも言わんばかりの振る舞いを続けていた時代だ。
著者は、これを『フィクション』と表現していた。
全くその通りだと思う。
フィクションをフィクションと思うことができない時代、フィクションを簡単につくり出してしまう時代。
命を、人権を失わないのなら良いのかもしれないが、全くそうでないフィクションの時代を絶対に繰り返さないために、私たちは学ばなければならない。
著者もその使命を本書に託している。
その想いを、やはりこの先も生きる私たちが受け取らずして、誰が受け取るのか。
そうした責任感のようなもので、本書を読むことができた気がしている。
以上です。
最初はちょっと、これまでにない独特な造りに違和感を感じたというか、読むのを止めようかなぁと思った自分が情けないです。
でも諦めず、読み進めて本当に良かったと思っています。
読み始めてしまえば、もうこっちのもの!
毎日帰宅して、寝る前に本書を開くのが楽しみで仕方ありませんでした。
戦争の本を”楽しみ”と表現するのは不謹慎かもしれません。
しかし、戦争に対する私なりの理解を深めることに対する好奇心が、私を本書に向かわせた、飽きずにそうさせたくれたということが”楽しい”と表現したということで、どうかご容赦いただきたいと思います。
新たに一つ学びとなったのが、「ゴジラ」についてです。
昨今、オスカーを受賞された作品としても再び脚光を浴びている、いや、浴び続けているといった方が失礼ではないでしょうか。
そのゴジラが、実は戦争に関連したエピソードを元に生まれたということを初めて知りました。
確かに考えてみれば、ゴジラが吐き出すのは”放射能”でしたよね?
あまり詳しくはないのですが、「なるほど、そういうことだったのか!」と心に刻まれました。
パレスチナ-イスラエルの問題
ウクライナ-ロシアの問題
などなど。
早く収束してほしい。
そしてもう二度と、殺し合いで悲しむ方が増えないでほしい。
悲しみの上に得るものなど、本来は何もないのだと思います。
本日も、ご覧いただきありがとうございました!!
もしサポートしていただけるならば、現在投稿の軸にしている本の購入やパピーウォーキングにかかる経費に充てさせていただきたいと考えています。
