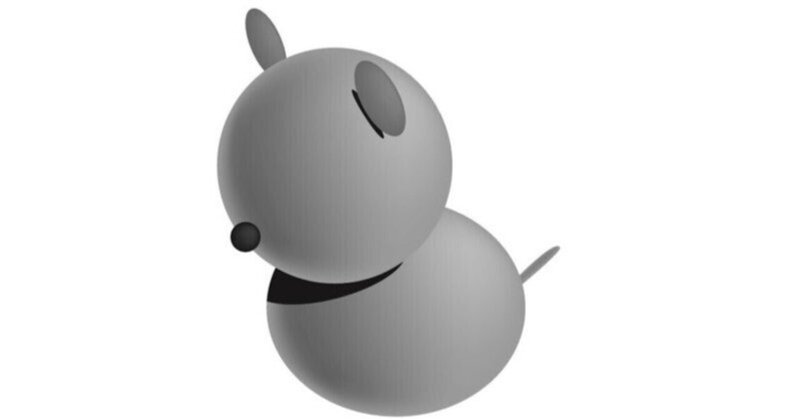
記事紹介:皮膚免役②
以前紹介した皮膚免役についての記事の続きで、やはり勉強に丁度良い記事があるので紹介しておこう。
表題は皮膚免役としているが、今回はメインのテーマとしてアトピー性皮膚炎など皮膚領域も含めたアレルギー反応全般に関する話題である。記事ではアレルギー反応のメカニズムを専門的かつ分かりやすく解説しながら、近年アレルギー疾患が増加している背景を考察している。その一つが「衛生仮説」と呼ばれるものだ。
現在、有力視されているのが「衛生仮説」という考え方です。現代になり、衛生環境が劇的に改善された結果、現代人が細菌やウイルス、寄生虫や汚染物質の少ない、清潔すぎる環境で生活するようになったことで、免疫が訓練されなくなり、特定のアレルゲンに対して過剰な免疫反応を起こしやすくなったという説です。
記事にある通りアレルギー反応の機序を理解する為にはTh1細胞とTh2細胞について理解する必要がある。初期の私の記事にもある通り、これらはヘルパーT細胞の小分類の一つであり、それぞれが得意とする免疫反応の種類が異なるのだ。Th2型の反応は主に液性免疫や寄生虫などに対する免疫応答に重要だと考えられているのだが、寄生虫などに触れる機会が殆ど無くなったことでTh2反応が起こるべきタイミングを見失い、無害であるはずの抗原に過剰な反応を示しているのではないかという仮説だ。このあたりについても記事の方に良い説明が記されているので是非勉強してほしい。
また、記事では下記の様に腸内細菌とアレルギー反応の関係についても触れている。これも私が最近紹介したテーマであったが、それについても併せて読んでみてほしい。
たとえば、抗生物質を乳児や幼児に過剰に投与すると、腸内に棲む常在細菌叢(じょうざいさいきんそう)が変化するため、アレルギーになりやすくなるという報告もあります。私たちの腸内には、諸説ありますが、約40兆個、重さにして1~1.5kgの細菌が棲み着いており、免疫応答にも深く関与しているといわれています。抗生物質を投与すると、腸内で共棲しているこうした常在菌が取り除かれて、複雑な生態系を形成している常在細菌叢のバランスを崩し、その結果、腸内の免疫応答が異常をきたして、アレルギー反応が起きるという説もあります。
抗生物質と腸内細菌の話については皆さんよく覚えておいてほしい。これは有名な話でもあるのだが、当然ながら抗生物質を投与すると腸内細菌は当然ながら減少する。抗生物質でお腹の調子が悪くなる場合は主にこれが原因である。また、記事にある通りアレルギー反応に対する影響もある。抗生物質を飲んでいると、ヨーグルトやビオフェルミンなどで善玉菌を取り込むor増やすなどの効果も見られなくなる。このことは併せて覚えておこう。
最後にTh1/Th2バランスの概念も記事にあるので覚えておくと良いだろう。
Th1細胞とTh2細胞は、それぞれの体内環境に応じて、お互いの機能を制御し、一種の平衡関係を保っており(Th1/Th2バランス)、このバランスがどちらかに傾くことにより、特有の疾患が発症しやすくなります。アレルギー疾患の患者さんでは、このTh2細胞が優勢になることで、アレルギー症状が出ると考えられています。 実は、前述の衛生仮説も、衛生環境がより清潔になることでTh1/Th2バランスが、Th2優位になるという考えに基づいたものです。 一般に、環境が清潔すぎるとTリンパ球がTh2タイプのものに分化してアレルギーが起こりやすくなり、一方、環境に細菌などの汚染物質が多いとTリンパ球がTh1タイプに分化してアレルギーが起こりにくくなるといわれています。
Th1反応とTh2反応は互いにお互いの反応を抑制し合う性質を持っており、これら2つの細胞や反応はシーソーの様にバランスを取り合っている。免疫はバランスが大事だということをいつも言っているのだが、Th1/Th2バランスは最も古典的な免疫バランス概念の一つである。古くからこのバランスが偏るとあらゆる疾患の原因になり得ることが研究されてきたのだ。IgEによるアレルギー反応に関して言えばTh2側に偏ると起こりやすくなるが、Th1型に偏っても臓器特異的自己免疫疾患などのリスクに繋がる。いつも言っているが、免疫はバランスが全てである。それについて、どの様なバランスがあるのかを知っておくことは重要である。今回の記事はアレルギー反応や免疫系の基礎的な知識をよく含んでおり、この記事の内容を全て理解出来れば免疫学的な基礎知識はかなり高いと言える。逆に言えば、私の過去の記事を全て学んでいれば、この記事の内容は全て理解出来る筈だし、よくまとめられている復習材料となるだろう。
(参考)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
