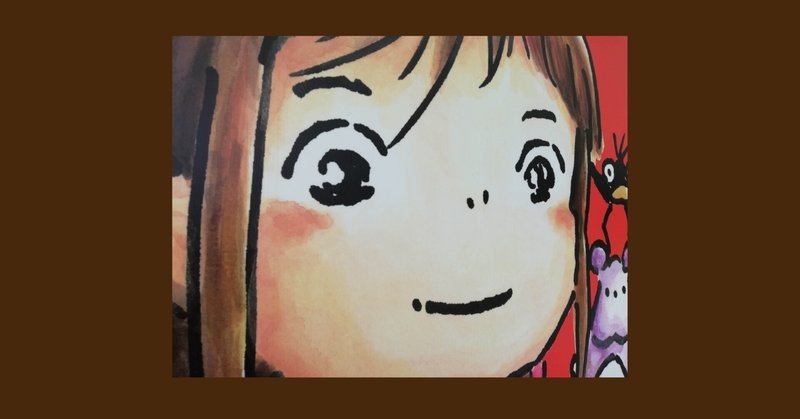
横須賀でジブリプロデューサーを追体験【鈴木敏夫とジブリ展】(体験レポ編)
4月22日公開した記事の続き。今回は、展覧会や美術館の内容・中身について書きます。約4000字、写真56枚。写真メインですが文量もそこそこ。かなり長い記事になったため、お時間あるときお読みいただくと良いかと思います。
間に別の記事(埼玉県立近代美術館「アブソリュート・チェアーズ」展。もうすぐ5月12日で終了する展覧会なので)を挟んだが、横須賀のジブリ展とその会場である横須賀美術館について、予告通り今度は体験レポを書く。一部記憶だよりなところもあるので、そのあたりはご容赦ください。
(前の記事)
なお、私はこの展覧会を観るまで、鈴木敏夫についてはジブリ作品のクレジットに名前があるな~程度しか、知らなかった。コアなジブリファンの方々なら、私とはまた違った見方、味わい方があるかと思う。以上、まえおき。

まず、この展覧会の構成
第1章「四半世紀の原風景〜少年時代の思い出〜」
第2章「東京へ〜激動の大学生活〜」
第3章「アニメージュへの道〜雑誌記者・編集者として〜」
第4章「時代を読む眼〜ジブリとメガヒットはこうして生まれた〜」
第5章「プロデューサーからクリエイターへ〜書家、作家としての多彩な才能〜」
第6章「鈴木敏夫の本棚~蔵書8800冊を一挙公開~」
新 章「鈴木敏夫の映画コレクション 約10000作品を一挙公開」
以上が章立て/展示割り。その後、アトラクション的エリアがあり、最後にお約束の特設ショップが待ち構えている。
新章「鈴木敏夫の映画コレクション~」は、前の巡回の福岡展から追加された新コンテンツの模様。
前回の記事で、公式図録でこの展覧会の内容は概ねカバーされていると書いたが、図録とは少し構成(章立て)が違っている。念のため。
会場光景
写真が撮れるのは、前述のうち5章、6章、アトラクション的エリア、ショップ。あと、ピンポイントで3章か4章に一か所フォトスポットが設けられていた。↓それがこちら。

ここから、章別に紹介する。
1章から4章にかけて
このエリアは、前掲のトトロのフォトスポット1ヵ所を除き、撮影不可。
ということで文章で雰囲気をお伝えすると、1章から4章までの章タイトルどおり、「鈴木敏夫評伝」。鈴木敏夫の生い立ち、ジブリプロデューサーになるまで、ジブリプロデューサーとしての活躍。基本はパネルによる解説テキスト+それを裏付けるモノの陳列。解説テキストだけでなく年表や当時の様々な文物(写真、ポスター、新聞・雑誌記事、本人手記等)を、トピックに合わせ適材適所うまく展示しており、パネル展示にありがちな「落ち着いてるがややもすると単調・退屈な雰囲気」は、微塵もない。
観る前は、オーソドックスに、ジブリ作品を全面に押し出しそれを通じて鈴木敏夫の人生や活躍を示してくるものと思っていた。ところがどっこい、完全に「文学館」「アーカイブ」的フォーマット、主役はあくまで「鈴木敏夫」。しかもその完成度が非常に高く(手法全般としては圧縮展示的ではあるが)、冒頭数分で唸ってしまった。ほんとに。
これは他のレビュー記事でも触れられていることだが、ジブリ以前のアニメージュ等編集者だったころも含め、鈴木敏夫の手によるメモ書きや企画書などがこれでもかというほど大量に、しかしよく整理して展示されており、「ジブリ作品はどのように生み出されたのか」「アニメ映画プロデューサー業とはどのようなものなのか」両面が、雄弁かつ明瞭に語られる。あるいは、読み取れる。
とくに後者の、「鈴木敏夫的アニメ映画プロデューサー業」については、最終成果だけでなく途中プロセスや具体的なテクニックまで惜し気なく公開されており、「こんなこと教えてもらったの初めて&嬉しい」としかいいようがない体験だった。
たとえば「映画を宣伝する」というテーマでは、効果的なポスターの作り方とはタイトル・コピー・ビジュアルの三位一体で、個々具体的には云々 といった塩梅。
率直に、ライター・プロデューサー・編集者(あるいはその要素のある仕事)になりたい人は必見。すでにそれらに足を踏み入れた人にも、自己点検や気づきを得る場・機会として大いに価値があるのでは。
5章
ここからは、撮影可。なので以降は、写真で。文章は補足的に挟む。








宮沢賢治「雨ニモマケズ」の書
鈴木敏夫 揮毫


ワタシモナリタイ

6章







ウィリアム・モリス的。

全巻だろうか。
この棚、夢。




グッズ好きにはたまらない空間


これ、個人的に凄くいいと思った。
新章
ここは撮影不可。
前章6章が「書斎=本のコレクション」だったのに対し、ここ新章は「映像コレクション」部屋。要は鈴木敏夫が視た集めた(さらには録った)DVD等映像作品一式。
ここで、個人的に超刺さるトピックに遭遇。
コーナー展示「これが鈴木の録画術だっ!」
AM7:00 ソファーでコーヒーを飲む
AM7:03 番組表を開く
AM7:10 録画予約をする
・・・といった毎日のルーティン/タイムスケジュール。
実際に焼いたメディア(DVDやBlue-ray)の展示。
実際に録画している具体的な番組タイトルも紹介。職業柄おさえているものから、NHK高校教育(なんと全て!)、日曜美術館、趣味系ではプロ野球中継(中日ドラゴンズ)まで。手の内を明かした鈴木敏夫を師匠と崇めたい&この小企画の企画者は神。テーマは何でもいいが、仕事だろうと趣味だろうと、本気で物事をやるなら、これぐらいせねば。
惜しむらくは、最近この巡回展に追加された内容のため、図録にこの章やこの小企画のことは全く載ってない。興味ある人は注意されたい。
なので、展覧会に「行かねば。」
アトラクション的エリア&ショップ








* * *
ここまで、私の撮った写真で(撮影禁止の場所については代わりに文章で)内容をご紹介した。補足すると、プレス・広報系の記事には撮影禁止の場所が幾つか映ってるものもある。参考までに、いくつか確認した具体的なソース(リンク)を以下に記しておく。もしかしたら公式SNSでもそのような画像が流れているかもしれないが、そこは未確認。
※去年の夏の東京展(寺田倉庫)のレビュー記事。わずかに今回と違う部分はあるが、ほぼ共通。
コレクション展@横須賀美術館
谷内六郎〈週刊新潮 表紙絵〉展 足もとに目をむけると
https://www.yokosuka-moa.jp/archive/exhibition/2024/20240406-832.html
この地観音崎ゆかりの作家。動線(導線)上、特にジブリ展/美術館本館からの誘導・引き込みはなかった。そのため、このコレクション展にまで足を運んだ人は、明らかに少なかった。その恩恵(?)で、同時開催のジブリ展の喧騒とは打って変わってスイスイじっくり鑑賞でき有難くないわけではなかったが、それよりも、純粋にアート体験としてもったいないなぁ、と思う。
ここに足を運びやすい地元の方などであれば、今回はジブリ展に注力し、こっちはもっと余裕がある時、という思考行動パターンになりがちなのは、理解できるが。
なんとなく、もし鈴木敏夫だったら、こっちもきっと観てくと思う。







鑑賞途中に一度外の光を浴びるというのも、
なかなか面白い趣向だと思う。


とくに良かった作品
この絵葉書を、買って帰った。

美術館の光景
一般論として外観・内観・景観に分けて考察することができると思うのだが、ここは敷地全体が非常に広く景観として造りこまれており、かつ、家屋外観と一体化したデザインとなっている。建築設計と言っても、家屋だけでなく造園的要素・思考も濃い。土や樹木だけでなく、鉄やガラスの建材まで使った「造園」とでも言おうか。たしかに、堂々たるビュースポット/フォトスポット。
少し脱線するが、考えてみると、「海に面した美術館」というのが、なかなか他に思い浮かばない。海外ならそれなりにありそうな気もするが。


美術館HPにこれの説明あり

ここに来てこのポスターで知った。。。









* * *
この横須賀美術館の建築についてはHPの以下ページに詳しい。興味あれば。わたしも建築に明るいわけではなく、勉強になった。
~おまけ~
実は今、岩手でもう一つの「鈴木敏夫とジブリ展」が開催されている模様。
この記事を書いてて視界に引っ掛かった。
今回鑑賞した「神奈川展」で、数枚展示されていた鈴木敏夫の風景写真には刺さるものがあったので、より写真作品に光を当てたこの展覧会に、とうぜん惹かれる。だれか感想note書いてくれないだろうか。新聞社ニュースサイトの関連記事までは出てきた。
~締め~
最後に、この展覧会を観、図録を読み、いたく感銘・納得した言葉。
これまで、大胆な発想、前人未到のやり方でまわりを驚かせ、記録的な興行収入をあげてきたのはまさにその勝負強さで、いくらそのノウハウを盗んだとしても、ふつうの人が鈴木敏夫とおなじことができない
「この歳になって、はじめて自分のことを出してもいいかなと思えるようになった」
* * *
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以 上
誠にありがとうございます。またこんなトピックで書きますね。
