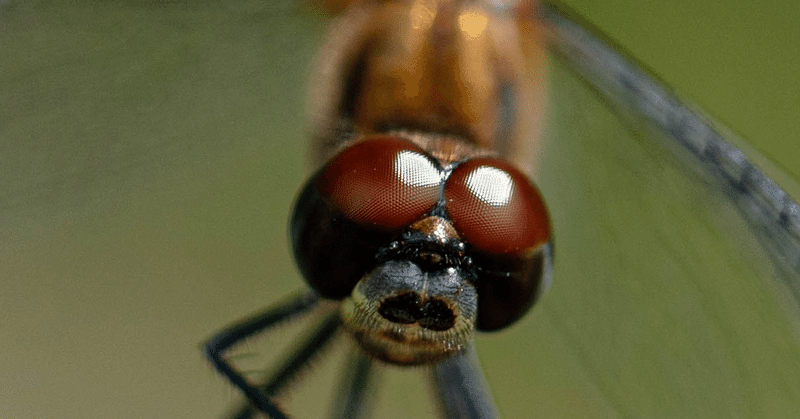
苅谷剛彦「知的複眼思考法ーー誰でも持っている創造力のスイッチ」
「人の意見を簡単に受け入れてしまわずに、批判的に捉え直すには、どうしたらいいのか」
このフレーズを見た時に、誇張ではなく、リアルに鼓動が速くなるような、本を閉じたくなるような感覚に襲われました。
多分私は、批判、が嫌いなのです。
その場にいない人のことを、愚痴ったりする事はあるくせに、真っ向から、意見を述べることが苦手なのです。そして、誰かに批判をされようものなら、その場では、ろくに返すこともできずに、後になって悔しくて眠れない思いをしたり、どう言い換えそうかと延々と考えたり。
特に私の中で批判はそういうものでした。
特に著者は考える力をつけるには、本を読むのがベストだと言っています。このノートを書いているから、と言うのもあるのですが、本の中からは、プラスのものしか受け取りたくない、と感じていて、ただただ、目の覚めるような考え方を示されたり、心揺さぶられるような情熱を受け止めて、そこに浸り、読書日記の形で、自分の日常と結びつけること、そしてそれを発信することを楽しみたいと思っていました。だから、知的複眼法なんて事はできなくてもいいかな、と思いました。
そもそもなぜこの本を手に取ったかと言えば、私の信奉している木下斉氏が勧めていたからです。
木下斉氏の書くことは、まさに無批判に受け入れているので、閉じたくなる気持ちを抑えて読み進めました。すると、こんな言葉も出てきました。
「批判的」というと、何か攻撃的な、手に取った本を、初めから非難するような気持ちで接することだと思う人もいるかもしれません。しかし、ここでいいたいのは、非難するかどうか、攻撃的かどうかということではなくて、著者の思考の過程を、きちんと吟味しながら、読もうとすることです。
確かに私は批判=攻撃的という意識があって警戒していたのだなと気付きました。批判と攻撃は全く別物です。むしろ、知的複眼思考法を身につければ、攻撃的でなくなるということなのだと思います。
この本では、知的複眼思考法を身につけるため、本を読む時にどのように考えながら読めばいいのか、ということを示してくれています。さらに批判的読書のコツとして、20のポイントをあげてくれています。
さらに、いくつかの文章を引用し、どのように批判的に読めば良いのか、実践にも取り組めるようにしています。
さらに、批判的読書で身につけたことを批判的議論に応用することについても、書かれています。
まず、問いの立て方。
学生の頃は、みんなの前では質問できず、後からこそこそ教壇で片付けをしている講師のところに行き、質問したりしました。自分の問いが立てるべき問いなのか、聞き逃した問いなのか、そもそも見当違いの話なのか分からなかったりして、人前で尋ねたくなかったからです。
今の時代は、講演会などではslidoで質問できることもあって、質問へのハードルが低くなった気がします。もちろん、仕掛けがあるからといって、著者のいう「問いの立て方」が簡単にできるようになるわけではないですが、でも、ふっと頭に浮かんだことを恥ずかしいから訊けないかなと思うよりは、実際に言葉にすることで、問いを立てる力が活性化するかなと思いました。
また、個別の事象にとらわれるのではなく、概念として捉えることが大切とも言っています。個別レベルと概念レベルを自由に行き来することで、ものごとを広くとらえることができるのです。
この本を読み終えた後にネット記事を読んでいたら、急にいくつも指摘したいことが出てきてびっくりしました。身構えたわけではなく無意識だったし、たまたまその記事はちょっと議論の進め方に飛躍があるかな、という感じではあったのですが。今までの自分なら、うん、この人は私とは会わなそうくらいで流していたかもですが、この部分が、とか考えてしまい、苅谷氏の良い影響を受けられたと思いました。
この本は1996年に書かれたとのこと。その後文庫化されたのも2002年とのことです。事例は古いかな、とは思いましたが、すごくフレッシュな感覚を覚えました。
複眼思考法を身につけるのに、書評を書くことも大切とありました。
「試みにこの本の書評を書いたらどうなりますか?」
とありましたが、全体的に伝わるようにすごく丁寧に書かれていて、ただただ敬服するばかりです。敢えて言うなら、後半の事例が教育分野の例が多く、特にいじめの話などは、つい感情がとらわれて、抽象化する難しさがありました。もちろん、抽象的に考える過程も提示されています。自分に取り込むには実践が必要だと思いますが、その入り口は示されていると思いました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
