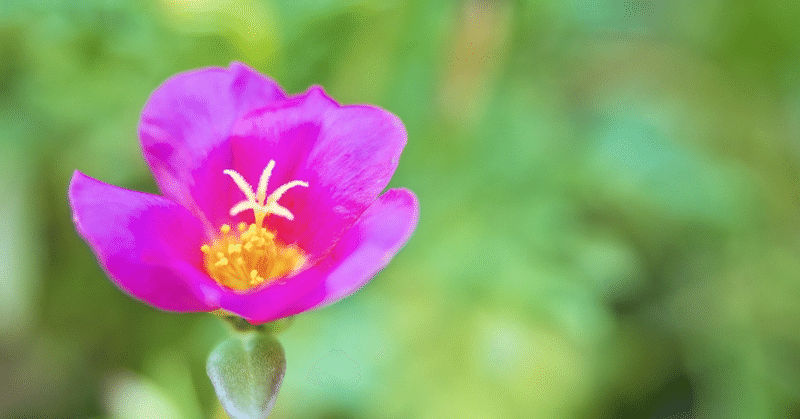
海老原宏美「わたしが障害者じゃなくなる日 〜難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた」
次男は夏休みの最後に、お寺で2泊3日の子供修行体験に参加したのですが、ADHDの子と一緒だったそうです。どんな子だったの?と訊いたら、おしゃべりでめっちゃコミュ力高かった、ということでした。
「でも僕、結構コトバきついこと言うタイプだから、今まで気付かずに、誰かを傷つけたりしてなかったかって心配になったよ。だから、もっと小中学校の教育で、障がい者はたくさんいる、色んなタイプの人がいるということを教えるべきだと思うんだよ」
そういえば、昨年度の授業参観では、障がい者のことについて各自で調べて、それをプレゼンするという授業を公開していました。そのことをいうと、次男はすぐにこう返してきました。
「やってるって言っても時間が少なすぎだよ」
ちょうど読み終えたこの本を渡したら、どんな風に感じるだろう、と思いました。
この本は、脊髄性筋萎縮症で車椅子、人工呼吸器をつけながら、やりたいことをどんどんやっていく女性、海老原宏美さんのお話です。
各章の最初に、小学生との対話が挿入されています。子どもたちの疑問がまっすぐで、気になるけれど、大人だったらとても訊けないようなこともはっきり訊いていて、でも一方で、発想がとても豊かなのに驚かされます。
それに応じるように、海老原さんはいろんな話をしてくれます。子どもの頃から、周りとどう接してきたか、どんなチャレンジをしてきたか、日常の中でどんなことを考えているか。
最初の方で、障害に対する考え方を2つ紹介しています。
【古い障害の考えかた】
階段しかない建物に入れないのは、あなたが車いすに乗っているせいです。
【新しい障害の考えかた】
車いすの人が入れないのは、階段しかないこの建物のせいです。
これはそれぞれ、個人モデル、社会モデルといわれています。
個人モデルは、本人の努力や補装具、医学的なアプローチなどによって、解決すようとするものです。他方、社会モデルは、「誰でも不自由なく暮らせるように多様性に配慮した社会にする」ことを目指すものです。
著者はこんな風に言っています。
わたしは今まで、人に会うたびに「がんばってください」と言われてきました。車いすだし呼吸器もつけているから、たいへんそうに見えるのでしょう。
「海老原さん、がんばってね」
「えらいわね。おうえんしているからね」
でも、本当はおうえんなんていらないの。わたしはがんばる必要はないのです。
どんな障害があってもくらしやすくなるように、あきらめなくてすむように、社会ががんばらなきゃいけないのです。
がんばってください、おうえんしている、という言葉は、一見優しい言葉のように感じますが、実は寄り添っていません。自分からは近づこうとせず、あなたががんばるのを見ているから、という感じにも捉えられます。まさに個人モデル前提なのだと思います。
「障害を乗り越えて」みたいな言葉も私はあまり好きではないのですが、完全に個人モデルに立った考え方なのだと理解しました。
さらにに、こんな話もしています。
思いやりより「人権」
障害のある人もない人も、思いやりじゃなくて「人権」です。
人権とは、すべての人が生まれながらに持っている、人が人らしく生きていくための権利です。(中略)
でも、車いすの人を助ける時に必要な気持ちは、「かわいそうだから」ではありません。障害があっても、健常者と同じようにふつうに生活する権利がある。だから助けるのです。(中略)
イやなヤツでも、ゆるせない相手でも、どんな人でも人間として生きる権利があります。尊重される権利があるのです。
がつんと頭をなぐられるくらいの衝撃を受けました。
心のバリアフリーとか、そういう問題じゃないんです。そもそも権利をふみにじっていることがあるかもしれない、という前提で、考えなければいけないのです。
これこそが、社会モデル前提の考え方ということなのだと思います。
海老原さんは、「すべての人は対等に生きるべき」という信念を持ったお母さまの5つの教えを守っていたといいます。
①だれかのせいにしない
②兄弟をたよらない
③なんでも本気でやる
④困ったときは「手伝って」という
⑤差別をされたときは社会のせいにしていい
こんなお母さまの下で育ち、いろんなことにチャレンジしてきたから、こんな風に考えられるようになったのではないかなと思いました。
この本を読む前に読んだ「私はないものを数えない」の中でも出てきたのですが、「手伝って」とは言う、けれど、スルーされたり断られたりしても「忙しかったのかな」と思って気にしないというのは良いな、と思いました。むしろ私など、初めての店に思い切って入ったときに満席だと断られたくらいでちょっと落ち込んでしまうくらいで、何だかそれもとんでもない考え方だったな、と思ったりもしました。
自分の重度障害者としての役割、というか、使命、みたいなものを感じて、それを全力で伝えているのだな、と思いました。
もしかして、おなじ、がんばってくださいね、でも、そのメッセージとその趣旨を受け止めた上で、これからも全力で発信してください、がんばってください、というのだったら、喜んでもらえたかもしれない、などと考えました。
私にできることは、このメッセージを受け止め、咀嚼して、日常の中で意識することだと思うし、また他の人にも伝えていくことなのだと思います。
そして障がい者からチャレンジしたいことを告げられたら全力で一緒に考えたいです。
寺から帰ってきた次男が話してくれたように、まず知ること、知る機会がたくさんあることが大事なのだと思います。
そしてもっといえば、実は私にも、次男にも弱いところ、苦手なことがたくさんあるわけで、周りの人にもあるわけで、お互いの苦手なことをどう補うか考えた上であらためて、この本に書かれているようなことを考えると、実は、どこからが障がいとかそうじゃないとか、区切って考えることはおかしなことであるように思えてくるのではないかな、と考えたりします。
この本を知ったのは、先月読んだ高浜敏之氏「異端の福祉 『重度訪問介護』をビジネスにした男」の中で紹介されていたからです。なので海老原さんの現在について既に知っていたのですが、本の中の海老原さんがあまりにも元気がよくて、生き生きとして、希望に満ち溢れていたので、近場で講演されていたらな、生のお話を聞きたいな、などと考えてしまいました。
今はもう動画で見ることしかできないのが、とても残念な気もしますし、こうして動画や本からメッセージを受け取ることができるのをありがたく思ったりもします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
