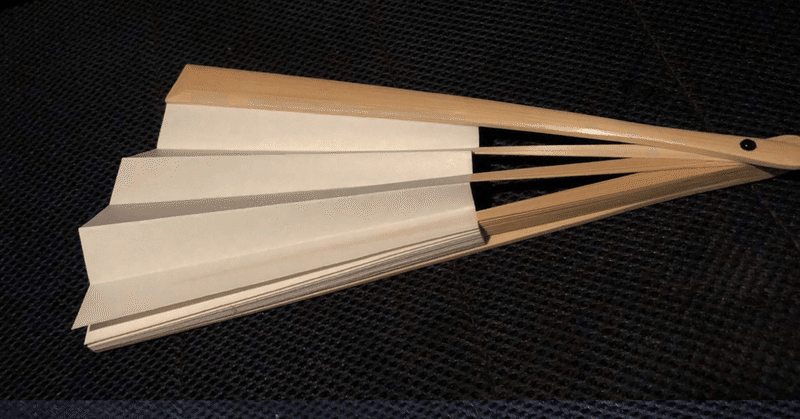
書籍レビュー『落語と私』桂米朝(1975)落語の奥深さを知る

中高生向けに書かれた
落語の入門書
桂米朝(3代目)は、
私が敬愛する落語家でした。
戦後、没落しかかっていた
上方落語(関西)を
復興した功労者の一人で、
人間国宝にまでなった人です。
落語の世界では
「米朝にはじまり米朝に終わる」
という言葉があるくらい、
初心者から熟練者まで
惹きつける落語をする方で、
私にいたっては、
この人の落語が好き過ぎて、
他の人の落語をほとんど
聴いたことがないほどです。
そんな米朝師匠が、
'70年代に書いたこの本は、
中高生向けに書かれたもので、
落語の入門書とも
言うべき内容になっています。
なんせ、博識で知られる
米朝師匠が書いた本ですから、
落語のことを知らない人は
もちろんのこと、
それなりに
知っている人が読んでも
新しい発見が多い本
と言えるでしょう。
落語の奥深さを知る
本書の構成は
以下のようになっています。
第一章 話芸としての落語
第二章 作品としての落語
第三章 寄席のながれ
第四章 落語史上の人びと
エピローグ
言いたりないままに
シンプルな構成で、
全体のボリュームも
200ページ程度、
サクッと読める内容です。
もちろん、中には、
古い時代のことを
書いたものも
多く含まれているので、
多少、難しく感じるところも
あるかもしれません。
しかしながら、前述したように
中高生に向けて書いた本なので、
誰が読んでもわかりやすい
明快な文章です。
第一章
「話芸としての落語」では、
「落語」とはなんなのか、
ということが書かれています。
ここではおもに、
落語家が落語を演じる時に
どのような配慮をしているかが
細かく書かれていました。
この本を読むまで、
私も知らなかったのですが、
例えば、米朝師匠が
落語をやる時には、
物語の中に出てくる
屋内の広さや間取りまで、
想定した演じ方を
しているそうなんです。
建物の広さが違えば、
そこに複数の人がいる場合、
間の取り方や視線の位置も
かなり変わってくるのは、
当然のことですね。
そういう設定まで、
細かく計算したうえで、
リアルな芝居をするからこそ、
観客はひっかかることなく、
その世界の中に入っていくことが
できるわけです。
第二章
「作品としての落語」では、
落語を「作品」と捉えて、
解説がされています。
第一章では、
おもに演じ方などについて、
細かく書かれていましたが、
ここでは落語の
「内容」について、
文学との比較も含めて、
丹念に考察されていました。
以前、私も他の記事で
書きましたが、
「芸術」と言われるものには、
普遍性があります。
やはり、米朝師匠も
落語の「普遍性」について、
同じような着眼点で
指摘されているのが
嬉しかったです。
(古典落語の方が長持ちして、
新作落語の方が早く古くなる
という話)
何をやっても所詮、ウソの話
第三章「寄席のながれ」では、
落語の歴史がどのようにして
はじまったか、
また、寄席という場所が
どのようなもので、
いかにして発展したのかが
書かれています。
第四章
「落語史上の人びと」では、
落語史に名を残す
数々の名人について、
解説されています。
私などはまだまだ落語のことを
よく知らないので、
出てくる名前は知らない人の方が
多かったです。
しかし、さすがは米朝師匠です。
そんな私にもよくわかるように、
わかりやすく丁寧に
教えてくれました。
やはり、当時のことを
よく知っていて、生の高座を
観たことのある人の話は、
その場の空気も
伝わってくるようで、
読んでいて臨場感がありましたね。
最後はエピローグとして、
米朝師匠の落語との出会いや、
その想いを語っています。
米朝師匠自体は、
人間国宝にまでなった人
(落語家としては二人目)
ですが、米朝師匠自身は、
落語が「芸術」の方ではなく、
もっと気軽に
楽しめるものであってほしい
という思いがあったようです。
エピローグでも
そういうようなことを
語られています。
たしかに芸術
といってもいいほど、
素晴らしいものではあるのですが、
どう演じても、
それはウソの話なので、
ただただそこを楽しんでほしい
という思いなんでしょうね。
マンガ家の神様と言われた
手塚治虫が、
「マンガは落書きの精神が大事」
と言っていたように、
米朝師匠も落語に対して、
同じような思いが
あったのかもしれません。
何度も言いますが、
何も知らない初心者が読んでも、
よく知っている人が読んでも、
魅力的な本です。
これからも多くの方が
気軽に手に取ってほしい
本の一つですね。
【作品情報】
初出:1975年(文庫版:1986)
著者:桂米朝
出版社:ポプラ社、文藝春秋
【著者について】
1925~2015。
旧関東州(満州)
大連市生まれ。兵庫県出身。
1947年、桂米團治
(4代目)に入門。
1996年、人間国宝に認定。
【関連記事】
サポートしていただけるなら、いただいた資金は記事を書くために使わせていただきます。
