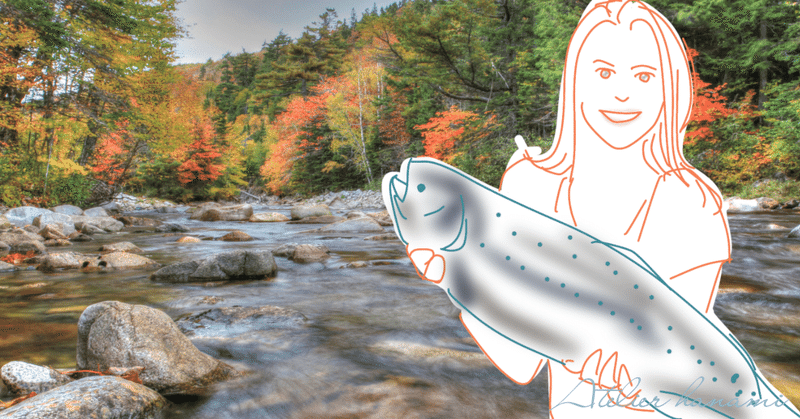
「縄文時代は争いがなかった」といわれるのは食糧事情が原因か!?~ヒトの本能と外部環境と~
1.縄文時代の人口は8万人!?
縄文時代は、1万4000年くらい前から、約1万年続いた時代とされます。その次に長い弥生時代が、600年から1000年と言われますから、その圧倒的な長さに驚きます。意外と知られていないのがその間の人口推移です。考古学者の鬼頭宏氏は、最大時でも人口は26万人程度で、寒冷化が進んだ時期は、8万人にまで減ったという説を唱えています。鬼頭説は数ある学説の中でも最も人口を低く見積もったものですが、私たちの感覚値からいったら、圧倒的に少ないと思います。一般的な学説でも、多くて2~3百万人とされます。
新石器時代から青銅器・鉄器の時代に移った時、そして、産業革命以降、人類の歴史には何度か技術革新に支えられた人口爆発が起こっています。それに引き換え、縄文時代の約1万年間は爆発的に人口が増えることはありませんでした。それよりも、8万人と言ったら絶滅寸前のように思います。縄文時代の課題は人口の維持にあったとみるべきです。
2.自然のイベントの影響をダイレクトに受けた生活環境
縄文人の生活スタイルについては、どの資料を見ても大差はないように思います。ということで、ChatGPTを参考にしてみたいと思います。
狩猟と採集: 縄文時代の人々は、狩猟と採集を主な食料調達手段としていました。彼らは森林や川岸、海岸などの自然環境から、獣や魚介類、植物を採取しました。狩猟の対象には、イノシシ、シカ、シカク、クマ、ウサギなどが含まれていました。また、海や川での漁労も重要な食料調達手段でした。
食物の保存: 縄文時代の人々は、食物を保存するためのさまざまな方法を用いていました。例えば、食材を乾燥させたり、燻製にしたり、塩漬けにするなどして保存しました。また、土器やかごなどの容器を使って食物を貯蔵することも行われました。
火の利用: 縄文時代の人々は火を使って調理や暖を取るだけでなく、狩猟や採集の道具を作る際にも火を利用しました。また、火を使って野生動物を追い払ったり、食材を調理したりすることも行われました。
居住形態: 縄文時代の人々は、集落を形成して暮らしていました。集落は主に海岸や川沿い、湖畔、または平野部などの自然環境に依存した場所に建てられました。また、一部の地域では竪穴住居と呼ばれる地下式の住居が採用されました。
上記から、縄文時代は、豊かな自然環境を利用して食料を確保していたことが考えられます。しかし、その一方で、自然災害や気候変動から大きな影響を受けていたことが伺い知れます。ちょうど、縄文時代は氷期後期から暖期に移行する時代であり、気候変動が激しく、自然災害も頻繁に発生していたとされます。特に、大規模な火山噴火や地震による被害、急激な気候変動によって収穫が損なわれたり、狩猟や漁労の場が影響を受けたりすることはあったはずです。また、1年のサイクルの中では、穀物や鮭など、秋の収穫に過度に依存していたため、干ばつや長雨の影響は冬季の食料不足に直結したと言われます。
3.言葉に残る食糧事情
縄文時代の食糧事情は「やまと言葉」に中に残っていることが分かっています。
上のリンクページの内容から、食糧事情が分かる言葉を取り上げます。
カラダ=「カ」+「ラ」+「ダ」=苦しい+空間+らせん状の(内臓)=空腹を訴えてくる場所
オナカ=「オ」+「ナ」+「カ」大きな+音+苦しい=おなかが空いて、ぐうぐう鳴る様
「体」や「おなか」など身体を表す言葉が、機能や位置関係ではなく、「状態」をもって名詞化しています。それほどひっ迫した様子が伝わってきます。一説によると、一日三食というのは、明治以降の文化だそうです。縄文時代は獲物が捕れたとき、つまり、食べれるときに食べる、といった生活だったのでしょう。それ以外のほとんどの時間はずっと空腹だったということは、少しの飢饉でも餓死者が多く出たことが想像されます。
4.ヒトの脳の構造と支配本能
縄文時代は戦乱のような大きな争いはなかったとされます。食糧の備蓄ができるようになり、富の蓄積に偏りが起こり始めた弥生時代になって初めて戦争が起こったとされます。作家の橘玲氏は著書『スピリチュアルズ』の中で、ヒトの持つ競争本能について、興味深い分析をしています。
まず、橘氏は、社会心理学でいう、「権威主義的パーソナリティ」や「社会的支配志向性(SDO)といった、支配や服従に対応するパーソナリティはないとした上で、脳の報酬系について、その働きを説明しています。なんでも、自分を下の階層と比較する時には、金銭的報酬でも活発化するという腹内側前頭皮質が活発化し、また、上の層と比較する時には、身体的苦痛や金銭的損失のような負の出来事を処理する際に活発化する前帯状皮質背側部が活発化するのだそうです。つまり、上下関係というヒエラルキーでしか関係性を感じ取ることができないというのは、人間の所与のものであるということです。橘氏は、「支配と服従のパーソナリティ」は、長い進化の過程を通して、ヒトが身に付けたものであると結論付けています。
なせ、その本能が抑制されたのか?橘氏も言っていますが、食糧の確保と生命の維持、そして種族の保存が優先されたため、争う余裕がなかったということです。食料の備蓄が可能になり、生活環境が大幅に改善したことで、本能が表面化し、それによって、争いが始まった-これが結論です。
これを書いている時も、ウクライナやイスラエルでは戦闘が続いて大勢の人が亡くなっています。ヒトは生来、争いを好む種族である、ということは否定できません。
ただ、ヒトは、社会性の動物です。常に本能むき出しで生きているわけではありません。ゲマインシャフト(人間が地縁・血縁・精神的連帯などによって自然発生的に形成した集団)という言葉がありますが、それも社会性を抜きにして説明することはできません。ヒトは社会的な動物ゆえに、「支配と服従のパーソナリティ」は制御可能であると信じたいです。
最後まで読んでいただいて、どうもありがとうございました。
