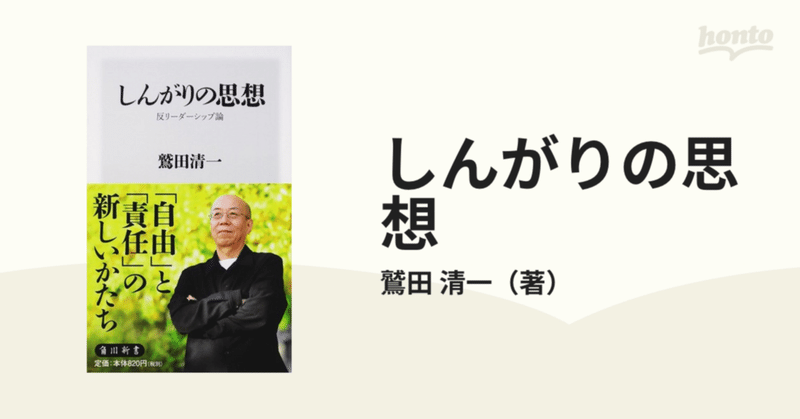
鷲田清一『しんがりの思想』を読んで
友人に感想を聞かせて欲しいと言われて、鷲田清一の『しんがりの思想』を読んでみました。今回はその感想を書いてみました。
著者はこの本の中で2つのことを言っています。「しんがり」の務めと「押し返し」のアクションです。それらに自ら「責任」を引き受けようと言っています。
大きく言うと、経済の右肩下がりとともに、なんでもかんでも「自己責任」というネオリベラリズムの方向に進む日本に向かって、庶民レベルで抵抗しようという主張に聞こえました。
「成長」が前提にあった「右肩上がり」の時代が終わり、何かをあきらめざるを得なくなった「右肩下がり」の時代に入った。ニュータウンなど、人間関係に縛られない暮らしが理想とされた時代はあったが、そんな「消費」のためにデザインされたまちでは、人間は「無縁」となってしまった。その、「無縁」に対し、相互扶助のセーフネット的なネットワークを準備していこうと。そのことを著者は「押し返し」と表現しています。
「しんがり」については、著者がそれを端的に説明しているので、その個所を抜粋した方が分かりやすいでしょう。
社会がいやでも縮小してゆく時代、「廃」炉とか、「ダウン」サイジングなどが課題として立ってくるところでは、先頭で道を切り開いていくよりも、むしろ最後尾でみなの安否を確認しつつ進む登山グループの「しんがり」のような存在、退却戦で敵のいちばん近くにいて、味方の安全を確認してから最後の引き上げるような「しんがり」の判断がもっとも重要になってくる。
そして、そのような存在を、「いつも全体に目配りできているそんなフォロワーの存在が、ここでは大きな意味を持つ」とフォロワーシップの説明をしています。
この一文を読んで、私は著者のことを「新聞好きのかわいそうなおじいちゃん」と思うようになりました。すみません。情報源が新聞のような現象を書いたものに偏っていると思いました。そして、何が「かわいそう」なのかは以下を読んでいただけたら分かると思います。
そもそも、「しんがり」と「フォロワーシップ」を結び付けることは良いとは思えません。「しんがり」とは、本来、撤退戦における味方が撤退できるまでの「時間稼ぎ」が役目です。そのために、少数の部隊を率いて、戦場に戻ります。そして、十中八九、部隊はそこで全滅します。一部の部隊が全滅することで、多くの味方を救うのが目的です。
では、著者のいう、「敵」とは何か、そして、「味方」とは?「敵」がネオリベラリズムで、「味方」が仮に国民だとします。どっちにしても、時代に対抗して、潔く死んでください、としか言いようがありません。そして、部隊の将兵、おそらく考えを同じくする人に、一緒に死んでくださいと言って、フォロワーシップではなく、強烈なリーダーシップを発揮するのです。
仮に、「右肩下がり」の時代のことを指して「撤退」する時代としているならそれも分からないではないですが、まずは、時代を受け入れなければなりません。「撤退戦」とかいって、戦っても得るものはないでしょう。なぜ、犠牲になりたがるのか、あるいは英雄になりたがるのかよく分かりません。戦って名誉の戦死をして英雄になるのは、まさしく、「右肩上がり」の世界観です。「右肩下がり」での戦いは、少ないパイを奪い合う、消耗戦にしかなりません。いずれにしても戦うことは得策ではありません。
「しんがり」ともう一つ言っている「押し返し」も同じ発想です。時代の大きな流れに向かって立ちはだかり、果敢に「押し返し」ても、きっと瞬殺されるだけです。
だから一回流れに乗らなければなりません。時代の内側からしか働きかけることはできないのです。時代の「中」にあって、相互扶助のネットワークを築いていくのです。フォロワーシップではなく、リーダーシップをもって!
最後まで読んでいただいて、どうもありがとうございました。
