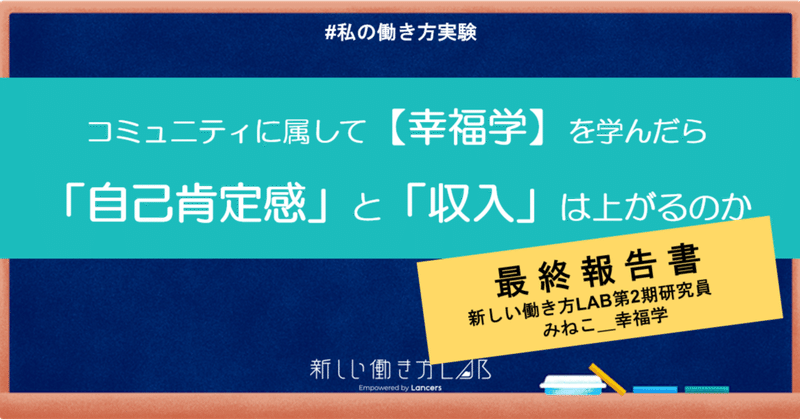
コミュニティに属して【幸福学】を学んだら「自己肯定感」と「収入」は上がるのか #研究報告書
本記事は、ランサーズ新しい働き方LABの「研究員制度」の活動の一環として、私個人が行う「働き方実験」についてまとめたものです。
◆実験の目的と背景
私が参加したのは、指定企画の【幸福学】「幸せを追求した活動で、幸福度は高められるのか(協力:慶應義塾大学 前野隆司教授)」です。
2022年6月に始まった新しい働き方LAB第2期。
子どもと一緒にいることを選択して、自分で選んだ在宅ライターの仕事なのに「やりたい仕事ができない」「やりたい仕事につなげるために何をしたらいいかわからない」「私はみんなのように働けない」と思い悩む日々。
そんな中で目にしたのが”ランサーズの新しい働き方LAB第2期の応募締切がもうすぐ”というTwitterでした。
そのとき、普段ならスルーする「幸せ」という文字に、強く惹かれて【幸福学】に応募しました。
◆検証したいと思っていたこと
当初、私が実験したかったテーマはこちらです。
【幸福学】を学び、自分の生活を「心から幸せと言える生活に近づけたい」「生き生きと毎日を送る私になりたい」
◆研究活動の概要
前半の6~8月は、以下のことに取り組んできました。
◆全体プロジェクト
・週2回の「ハピネスチャレンジ」(前野先生の研究結果に基づいた、幸福度を高めるための問い)に取り組む
・課題図書の「幸せのメカニズム」「幸せな職場の経営学」「ウェルビーイング」を読む
◆マイハピネスプロジェクト
・毎日の自分の幸福度を○△×で表す「カレンダーマーキング法」
・定期的な幸福度診断と振り返り
・幸福度を高めるための4つの因子を意識した行動
♡ 躊躇することでも「やってみよう」
♤ 人から言われた言葉は素直に「ありがとう」と受け止める
♧「ありのままに」自分のペースを大切にする
♢「なんとかなる」と一歩を踏み出す
もともとコミュニケーションが苦手な私は、とにかく「みんなについていかなきゃ」「ZOOMに慣れなきゃ」「参加しなきゃ」という思いで必死に参加しては「うまくしゃべれなかった」「全然ついていけなった」と落ち込んでの繰り返し。周りと比べて「私は何もできていない」と焦りも感じていました。
【幸福学】の「ハピネスチャレンジ」「幸福度診断の振り返り」は自分の嫌な面に向き合わなければならないときもあります。
うまく活動できず、コミュニケーションを取れず、自分と向き合うことに苦しさを感じ、とうとう、7月後半から8月にかけて、子どもの夏休みを言い訳に、あたLABの活動から少し距離を置きました。
夏休みも終わりに近いころ、何とか今の状況から脱さなきゃと思った私は、
「周りと自分を比べていてもしょうがないじゃないか。もともとのスキルもキャパも違うんだから」
「自分にできることをやればいいじゃないか」
「自分に自信を持つために、ライターで経済的自立をめざそう!」
と覚悟を決めました。
中間報告書では、自分自身が前を向けるようになるために変えたいと思う「自己肯定感」と「収入」にフォーカスしたテーマに変更しました。
中間報告書から新しく取り組んだ活動は次のとおりです。
◆全体プロジェクト
・小グループでのハピネスチャレンジ対話に参加(自己肯定感)
◆マイハピネスプロジェクト
・仕事の効率化を図るための行動(収入)
♤ コワーキングスペース・タスクシートの活用
♢ 企業から業務委託の仕事を受注
♧ ランサーズのパッケージを出品→受注→継続受注
・やりたい仕事につなげるための活動(自己肯定感)
♤ 気になっていた有料の学会やウェビナーに参加
♢ あたLABインタビュー企画の記事作成に参加
♡ 地域の支援学級の交流会やOTコミュニティに参加
♧ 子どもが苦手な促音のワークの構想を作成
◆結論と根拠・気づき
2022年6月~2022年12月にかけての幸福度、収入、自己肯定感の変化の結果から結論・根拠を示します。
<結論>
「自分が何をしたいかを明確化し、行動する」ことによって幸福度は上がる
自分が向上させたい要素を意識した活動を行うと幸福度アップにつながる
<根拠>
・幸福度診断にて総合値22.1Ptup、自己肯定力21.4Ptup、収入力28.6Ptup
・扶養範囲内の収入から月30万円をコンスタントに得られるようになった
<気づき>
「自分のことを知る→自分の新しい側面への気づき→自分が変えたい、こうなりたいを明確化→具体的な行動→結果」につながる。
自分が何をしたいか、何をするか(doing)があって初めて変化が訪れる。


◆研究の成果と今後の方向性
今回の指定企画【幸福学】への参加、そして、新しい働き方LABの「私の働き方実験」に参加して得られた成果、そして今後の方向性をまとめます。
<得られた成果>
・収入の軸ができたことで、自分のやってみようと思う気持ちと、挑戦するために必要な経済的な余裕を得ることができた。
・ZOOMへの恐怖自分の、自分の意見や考え方を話すことが怖くなくなり、仕事や活動の幅を広げることができた。
<経済的に自立してから挑戦できたこと>
・作業科学学術研究会への参加
・発達関連の有料ウェビナーへの参加、書籍の購入
・校正講座への申し込み
今までやりたいと思っても挑戦できなかった理由のひとつに経済的な問題がありました。扶養範囲内の稼ぎしか得ていなかったので、自分のためにお金を遣うことに罪悪感があったのです。
収入の基盤を得てからは自分の興味のある勉強にお金をかけられるようになりました。これは非常に大きな成果のひとつです。
<今後の方向性>
◆仕事
・仕事効率を上げ、現在の収入を保持しながらやりたいことにかけられる時間を捻出する
・願わくば、あと月10万収入を増やして規模の大きな学びにも挑戦したい
・校正講座を受講し、ライターとしての質向上と校正の仕事へも幅を広げる
◆やりたいこと
①支援が必要な子どもの生活や学習に役立つ情報を載せたサイトの作成
②支援が必要な子どもの保護者の会に参加し、できることを探す
③作業としての書道に向き合い、読み書きが苦手な子の支援としてつなげる
今後、やりたいことについて少しだけ紹介します。
①支援が必要な子どもの生活や学習に役立つサイト
実際に私の子どもが困っている生活の動作や学習でのつまづきに対して、工夫してきたことや、100均材料などを使って作成したおたすけグッズ、私がつくったひっ算ノートや学習ワークブックなどを紹介する予定です。
もともと対象者に合った環境づくりや自助具の作成も行ってきた作業療法士という職種のため、子どもに合った消しゴム、鉛筆、定規、リコーダーなどの学習用品の選び方や保護者が学校の先生に困りごとを伝えて支援につなげるためのポイントなどを掲載したいと思っています。

小さな小さな「っ」の場所がわからないわが子のためにつくったワークブックです。
ブラッシュアップ予定です。

学校の授業でひっ算の線を定規で引くことに時間がかかり、計算の時間が取れなくて困っていたわが子用につくったノートです。マス目のズレも起こりにくくなりました。
②支援が必要な子どもの保護者の交流会に参加、できることを見つける
支援学級の交流会に参加してけっこう赤裸々に語ってまいりました。参加していた保護者の方からの切実な声もたくさんお聞きすることができ、皆さん共通しているのは「同じ立場から安心して話せる場が欲しい」ということでした。そういった場での情報交換を通して、たとえば、専門機関と学校との橋渡しなど、自分にできることを探したいと思っています。
③書道を読み書きが苦手な子への支援につなげる
病院勤務時代に「せっかく書道やピアノという特技があるんだからそれを活かした作業療法をしてみたら」と上司から言われたものの、書道を作業活動として患者さんに提供するにとどまっていました。
読み書きが苦手で身体の不器用さがあるわが子の習字の授業を心配していたのですが、予想に反して「習字が楽しい」という声を聞き、書道の特性を改めて振り返ってみました。すると、読み書きが苦手な子どもも楽しく字に触れる経験ができるのではないか、字の形を捉えるためのきっかけとして使えるのではないかと思ったのです。
ただ、作業として提供するにあたって線を描く、形を捉えるだけじゃ面白味がありません。そこで、書道アートなどから支援につなげるヒントを得たいと思っています。

◆全体振り返り
あたLABに入る前は「働きたいのに働けない」「在宅でできる仕事をしているけれども、胸を張ってライターといえない」と自分の置かれた環境に対する不満の中で生きていました。
ライターという仕事に本気で向き合い、収入の柱として確立し、さらに「やりたい」と思うことに向かって投資をできるようになったのは、あたLABの運営の皆さま、やりたいことに向かって行動している研究員の皆さまのおかげです。本当にありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
