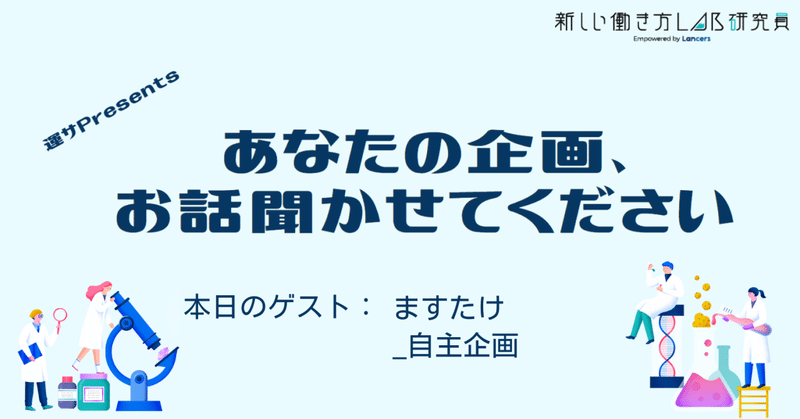
あたらぼ研究員インタビュー企画:第6弾 ますたけさん「『晴耕雨読』を実践。『働く』のやめ方とは?」
本日のインタビューのお相手は、研究員制度で自主企画に参加されているますたけさんです。10月定例会の中間報告授与式では「すでに人生変わったで賞」を受賞されています。
多くの研究員が「どう”働く”か」を追求する中、「”働く”のやめ方」として『晴耕雨読』を実践。その注目すべき実験内容や現在の生活について、そして、ますたけさんの考える「”働く”とは何か」をお聞きしました。
-現在、仕事はセミリタイア中
サンチェスさん(以下、敬称略):今はお仕事は引退されているんですか?
ますたけさん(以下、敬称略):セミリタイアみたいな感じですかね。月に2~3日は働いています。仕事は企業研修講師として、企業に呼ばれて、新任管理職向けのマネジメント研修や経営戦略研修、ビジネスプランを考えて発想力を鍛えるワークショップの開催などを行っています。
講師業の前は、エンジニアとして商品開発の仕事をしていましたが、いろいろあっていつの間にか研修講師になっていた感じです。
サンチェス:エンジニアから研修講師になられた過程も興味深いものがありますね。人によって、一つのことに打ち込み続ける人もいれば、働いている中でやっていることが変化していく人もいますよね。
ますたけ:人のタイプですよね。まっすぐ目的地に向かいたい人もいれば、ドラクエのダンジョンで全部の道をひと通り行ってみたい人もいる。
いろんなタイプがあると思います。
-自主企画「晴耕雨読」は家庭菜園とPython
サンチェス:今回、研究員制度はどちらで知りましたか?
ますたけ:おそらく、ランサーズのメルマガだったと思います。最初は指定企画の大学のプロジェクトに興味があって応募したんです。
あとから自主企画も応募していいというのを知って、ちょうど畑を借りて家庭菜園をしようと思っていたことを「晴耕雨読」の自主企画として出しました。結果的に自主企画が採用されたという経緯です。
サンチェス:「晴耕雨読」の具体的な活動内容について教えてください。
ますたけ:広さ100平米ほどの畑を借りて、家族が食べる量の野菜を作っています。学習の面では、プログラミング言語のPythonを学んでいる最中です。
ゆくゆくは人が話している動画のデータから、その人がどんなことに興味を持っているのか、どんな考え方の人なのかなどを導き出すAIを作りたいと思っています。
-企画が次々と生まれるあたLABに注目
サンチェス:研究員制度の3カ月を通して、興味を持たれたことはありましたか?
ますたけ:研究員の方々が自主的にいろいろなイベントを開催したりなど、企画が次々と生まれているのが面白いと感じます。会社のコミュニティでは「飲みに行こうぜ」みたいなのはあっても「メタバースやりたいから美術展やろう」というのはなかなか起こらないと思うんです。
サンチェス:そうですよね。運営サポートメンバーの「研究に参加していること自体を楽しんでほしい」という想いを研究員が素直に受け止めているのが大きいと感じます。それから、運営サポートが行うイベントがきっかけとなって、研究員の新しい企画へと派生していっているようにも感じます。
ますたけ:種を撒いていっている感じがいいですよね。絶対に作りきって納品しなきゃいけないとなるとハードルが高いですけれども、楽しむだったらいくらでもできますから。
一通りslackも目を通していますが、むらこさんの企画力にはすごくバイタリティを感じます。
slackに時系列でいろいろな情報が羅列してあるのがいいんですよね。ビジネス系、アート系など、ディレクトリで整理されていたら、自分の興味のある分野しか注目しませんが、ランダムに並んでいると視野が広がって自分の興味の幅や関心が深まる気がして面白いなと。時間がたつと過去のものが消えていって、最初から辿れないというのもまたいいと思っています。
サンチェス:なるほど。面白い考え方ですね。今、現在のものが雑多にあるというのがいいという。
ますたけ:世の中いろいろある。それがいいと思います。
-「晴耕雨読」は心の豊かさにもつながる理想の生活
サンチェス:ますたけさんはすでに「晴耕雨読」を実践されているわけですが、これから先にやってみたいと考えていることはありますか?
ますたけ:家庭菜園は続けていく予定です。楽しいですし。来年は作る野菜の種類を増やそうと思っています。でも、家庭菜園を極めて農業をやろうという気にはならないですね。個人の楽しみとしてこのまま続けたいと思います。
晴耕雨読の生活ができるなんて昔は思ってもみなかったです。ある種、理想の生活ができているかと。自分が食べるものを確保できているというのが、人としてのいい在り方というか、生き物として大事なところをおさえていると感じます。自分で作ったものを自分で食べるというのが心の豊かさにつながるのかなと思いました。
学習面は大学でPythonを勉強して研究をして、5年くらいかかる計画で進めています。
-生きるうえでの「働く」の割合は人それぞれ
サンチェス:それでは、最後にお聞きします。ますたけさんにとって「働く」とは何でしょうか?
ますたけ:「お金を稼ぐこと」ですね。
昔、仕事だけをしていたときは、ごはんを毎日食べていくために働いてお金を稼いでいたので「働く」と「ごはんを食べていく」はほぼ同じ意味でした。
けれども、家庭菜園をやり始めて自分で食べ物を生産できるようになったら「働く」の比重が小さくなったんです。そしたら「究極的には働かなくてもいいんじゃないかな」「そんなに働かなくてもご飯は食べていけるかもしれないな」と思うようになって。もちろん全員が当てはまるわけじゃないですけど「命を削ってまで働かなくてもいいのでは?」と思います。
私は今、長野県に住んでいるんですけれども、昔は地方には仕事がなかったんですよね。今は時代が変わって、地方にいながら東京の仕事が東京のレートでできるというのがすごくいいですよね。家賃も安いですし。
仕事によっては現場でないとできない仕事もいっぱいあるんですけれども、先輩方の時代ではできなかったことなので、時代が変わってラッキーだなと思います。
私は「働く」は「お金を稼ぐこと」って言いましたけれども、働くことが生きていくことっていう人も当然いていいですし。生きていくうえでの「働く」の割合をどれくらいにするのかって人それぞれですからね。
インタビュー記事作成を担当させていただいて
ますたけさん、サンチェスさん、お二人の対話があってこそ、生まれているんだろうなと感じる心に響く言葉をたくさんお聞きすることができました。
「”働く”の割合は人それぞれ」「世の中いろいろあるのがいい」など、自身のことだけではなく、一人ひとりの働き方、生き方を認めるますたけさんの言葉の一つ一つに心地よさを感じると同時に「自分にとっての”働く”」を考えるきっかけもいただきました。「ヒトとしての本来の生き方」こそが「ヒトが心豊かに暮らすこと」につながるのかもしれないとも感じます。
「“働く”のやめ方」。働くを必然と捉えていた私はそのタイトルに衝撃受けたのですが、経済成長を追い求める社会で、ヒトが”働く”をやめたら、そこにはヒトの生き方として新しく視えてくるものがあるのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
