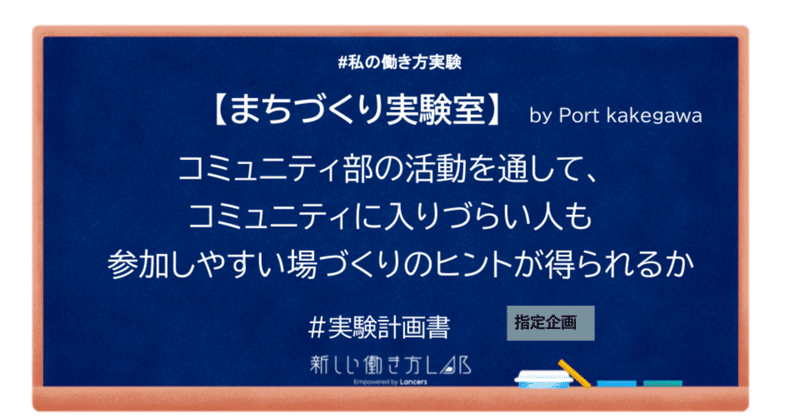
コミュニティ部の活動を通して、コミュニティに入りづらい人も 参加しやすい場づくりのヒントが得られるか【まちづくり実験室】by Port kakegawa #実験計画書
新しい働き方LAB・第3期・指定企画【the Port kakegawa × CreativeLAB × ワークキャリア】 〜掛川市後援〜に参加することになりました。
◆実験の目的と背景
まちづくりに参加したいと思ったのは、社会とのつながりやコミュニティに興味を持ったのがきっかけです。
1.コミュニティに属しにくい人も入りやすい場を考えたかった
ここしばらくの間、支援が必要な子どもを育てる母親からが発する「孤独」という言葉について考えていました。
地域には障害のある子どもの親が集える会などもありますが、悩みを抱えながらもそういった会に参加していない人やできない人はたくさんいます。
社会との繋がり、人と話すことは大切なことだけれども、そこにたどり着けない人がいる。私もそうでした。
「ここなら安心して入れそう」
「ここなら自分がなにか一歩踏み出せそう」
という思いを持って入った「あたLAB・2期」が私を地域につなげてくれるきっかけとなりました。
思い悩みながらも、どこにも繋がっていない人が、まずは安心して過ごせる場、地域に繋がる一歩になる場をつくりたいと思うようになりました。
そんなことを考えているときにkakegawaのまちづくりのプロジェクトを見て、コミュニティを学んでみたい、関わってみたいと思ったのです。
しかし、子どもたちを置いて家を空けられないし、環境の変化に弱く、身体の弱い子どもを連れての遠出は難しい。。。
”1回は現地へ”という条件が到底叶えられそうになく、初めは応募を諦めました。ですが、どうしても気になって説明会の動画を拝聴させていただき、やはり、コミュニティに入りづらい人も入りやすい場を考えていくために必要だと思い、外野から何か関わることができればと思って応募に至りました。
説明会の動画であった、オフラインとオンラインを行き来できるバーチャル空間のコミュニティも、さまざまな社会背景を持っている人たちのコミュニティ参加へのきっかけとなり、外へと繋がりを広げていくモデルになりそうな気がしています。
2.すべての人が安心できる場に所属し、満ち足りた人生を過ごせるように
作業療法士として訪問リハビリをしていたころに感じたことです。
年を重ねて身体は不自由になっても、自宅のベッドの上で過ごす時間が増えても、昔から近所の繋がりを持っている人、社会的な活動を続けている人は、日常的にご自宅にいろんな方が訪ねていらっしゃって、おしゃべりされている姿が印象的でした。とってもいい笑顔で話されていて、周りには自分の知識や経験を教え伝え、好きなことに打ち込み、さらなる勉強を続けている。素敵だなと思える方たちが多かったのです。
社会の繋がりは年をとってから急に作れるものではありません。
家族以外の繋がりを持ち、自分らしく過ごせる場を見つけることが大切な気がしています。
◆活動の概要・実験の測定方法
1.指定企画全体の全体のゴール・アウトプット
本実験では豊かさの指標として「エコノミー」「リレーション」「エピソード」の3点を計測します。
エコノミー(目標値:300万円)
エコノミーは”経済効果”を計測する指標です。
プロジェクトを通じて実際にどのくらいのお金が動いたのか、今回は直接効果を計測します。
例)イベント参加者の参加費や交通費、宿泊費など
リレーション(目標値:延べ人数1,100人・純人数550人)
リレーションは”関係人口”を計測する指標です。
プロジェクトを通じて生まれた出会いや人とのつながりを「延べ人数」と「純人数」の2軸で計測します。
例)オンラインイベントの参加人数、研究員のミーティング参加人数など
エピソード(目標値:100件)
エピソードはthe Port kakegawaや掛川と結びついた”想い”を計測する指標です。
実際に自分が体験したり目にしたりしたことで、うれしかったことや感動したことなどを文章の形で集計します。
以上、上記3点の指標を毎月計測し、活動プロセスと結果をレポートにまとめます。
コミュニティ部として、
・コミュニティに入りづらい人も入りやすい仕組み・魅力的なコミュニティとは・安心できるコミュニティとは・ヒトの繋がりはどうやって広がっていくのかなど、ポートカケガワの部のつながり、人とのつながり、街とのつながりの広がり方をみながら、よりつながり、広がる方法や仕組みを考えていきたいと思います。
2.個人的に考えたいこと
➀コミュニティに入りづらい人が入りやすいコミュニティとは
自らが「コミュニティに入りにくい人代表」となり、街づくりに参加しながら、より心の動いた方法や仕組みを評価していく。同時に心の移り変わりについてもメモしていく。
指標は次の5つ。それぞれ5段階で評価し、五角形のパラメーターで表示します。
1.活動への参加のしやすさ
2.場の安心感
3.活動の楽しさ
4.自発的行動
5.人とのつながり度
これらのデータから、コミュニティに入りにくい人が入りやすい要素をピックアップして考察します。
当初はkakegawaに興味はありながらも躊躇していた人がどれくらい行けたのかも興味があります。アンケートで測りたいと思います。
➁「何をする」かによってコミュニティは「どう変化する」か
自分も含めてコミュニティのメンバーが「何をする」とどうコミュニティが「変化していく」のかに注目し、作業・活動とコミュニティの繋がりを考えていきたいと思います。
※作業的存在
doing(何をするか)ーbeing(何者か)ーbecoming(将来何者になるか)―belonging(どこに所属するのか)
「ヒトは何をするかによって、何者かになり、何者かになっていき、どこに所属するのかが決まる」
kakegawaのまちづくりに所属して、何をして、何者になるかは、自分の行動次第です。所属する人たちが何をするかによってもコミュニティは変化していくはずです。
コミュニティに所属する人がそれぞれのしたいことに取り組み、コミュニティ自身も柔軟に変化していく、それが理想の姿だと考えます。
作業的な視点からもコミュニティを見つめてみたいと思います。
◆スケジュール・進め方
・6月〜7月/オリエンテーションに参加・評価
・7月~12月上旬/月に1回の全体定例、部門ごとのオンライン会議やslackでのコミュニケーションに参加・評価
・12月後半/取り組みの結果をレポートにまとめる
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
