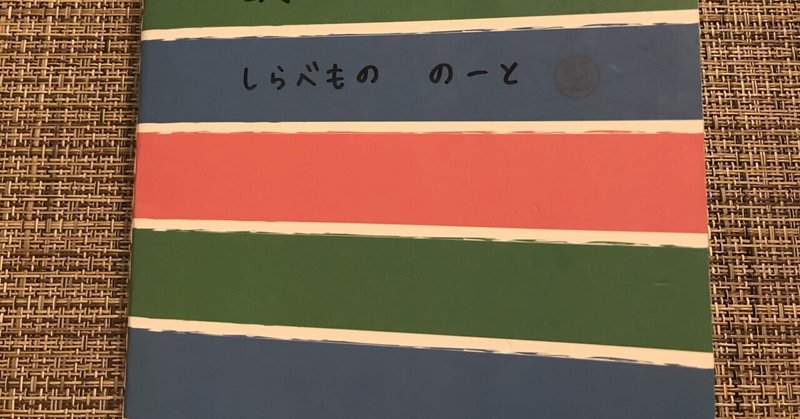
小2、「しらべもののーと」の立場が逆転した話
息子@小2・未就学児の頃から理系 は
保育園のころから非常にロジカルな男子でした。
そして典型的な「なぜなぜ坊や」でした。
「どうして〇〇なの?」
「なんで〇〇は××ってなってるの?」
という質問を、1日に何度も何度も繰り返される毎日。
親としては、息子の知的好奇心には
できるだけ応えてあげたいと思っていたので
「おぉっ、いい質問だね~、あとで調べてみよう!!」と伝え、
実際に(一緒にor私ひとりで)調べるつもりもあった。
あったのだが、
使用年数40年を過ぎた脳みそを保持している身には、
「あとで」という時間は「永遠に来ないこと」を意味する。
実際に「よし!じゃあさっきの息子の質問、調べてみよう!」と
思い立つ頃には、質問の中身を、きれいさっぱり忘れてしまっていた。
せっかく息子が良い質問してくれてるのに、
今のこの状況じゃあ、親も子も、ぼろぼろ取りこぼしまくってる・・・!!
そこで「とにかく質問だけでも何かに書いておかないと!」と思った結果
誕生したのがこの 「しらべもののーと」 です。

記念すべき問題提起の第1問は2020年12月。
いまから2年前なので、息子が年長のときの質問ですね。
で、その第1問はというと、
Q1「自転しない惑星はあるのか?」
・・・うん、難しかった。なので調べた。
なんてったって「しらべもののーと」ですし。
結論としては、 自転しない惑星はない そうです。
では次の質問。
Q2「摂氏0℃は華氏何度?」
・・・「The・文系」の母には、こちらも、とっさには答えられませんでした。
そもそも「華氏」の概念自体、一体どこから取り入れた??
答え: 摂氏0℃は華氏32℉ だそうですよ!
未就学児からこんな質問が寄せられるなんて、
「ドラえもん学習シリーズ」やら「サバイバル」やらの
昨今巷にあふれる科学漫画の影響なんだろうか、
令和・・・おそろしい子!とか思いながら
調べに調べてようやく答えにたどり着くわけですが、
ようやくゴール!!と思ったそばから
さらに高度な質問が飛んでくる、という無限スパイラル。
その後も息子の「どうして?なんで?」はすくすくと成長し
Q8:どうして「コンゴ」はふたつあるのか?
Q15:佐渡島はなぜ雷の形をしているのか?
Q21:山を買う場合の値段はいくら?
(栃木県宇都宮市 標高150メートル程度の山と仮定する)
など、どう頑張って想定していても
「斜め上」の質問ばかりが飛んでくる。
・・・これは、謂うなればもう、
「知の千本ノック」だッッ・・・!
どんどん難しくなる息子からの質問に
時間をかけて回答する。
そのたびに親の教養も蓄積されていくので、
私も「なるほど!」とか、「そうなのか!」とか思いながら
息子とのコミュニケーションを楽しんでいたのです。
が、
息子が小2になってから、どういうわけか、あまり質問をされなくなった。
そしてある日、ふと気が付いたのです。
質問されなくなったのは、息子に知的好奇心がなくなったからではなく
逆に、息子が、
学校や学童で読んできた本(漫画含む)から得た知識を
私に教えてくれるようになったから だということに。
子「ママ、『オールトの雲』って知ってる?太陽から1光年ぐらいの距離にあるって言われている、彗星が生まれる場所なんだよ」
私「えっ、あっ、 そう、なんだ・・・?」
子「日本独自の暦を作った渋川春海さんってねぇ、江戸時代の人なんだけど、77歳まで生きたんだよ。長生きだよねぇ」
私「へぇ~、そうなんだ、・・・た、たしかに、当時にしては長生きだね!」
まぁ一言で言うと、私、完全に知識量で負けてますよね。息子@8歳に。
そんなある日、息子からクイズを出された。
子「ママ、バミューダトライアングルって、なんで船の事故が起こりやすいか知ってる?」
私「え、なんでだろう? ・・・偏西風?」
子「ぶー。正解は、
海底に存在しているメタンの泡によって船が影響を受けるから、
でしたー!!」(※ 諸説あります)
へぇーそうなんだ、これも「しらべもののーと」に書いておこー
って思ってページをめくったら、
なんと、2021年の夏に、もう「のーと」に書いてあった。

ということは、
「海底に存在するメタンの泡によって船舶が影響を受ける」というのは、
一度は私が息子に伝えた内容 のはずなのです。
1年半を経過した今、それをしっかりと自分の知識にしていた息子。
それに対して、残念すぎるぐらいに何も覚えていない母。
息子のために作りはじめた「しらべもののーと」ですが
どうやら、いまや、息子ではなく私の方が必要なようなので、
これからは、「親の教養用」として使う機会の方が多そうです。
可能な限り息子の知識と並走できるように、
アラフォー母、精一杯がんばりまーす!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
