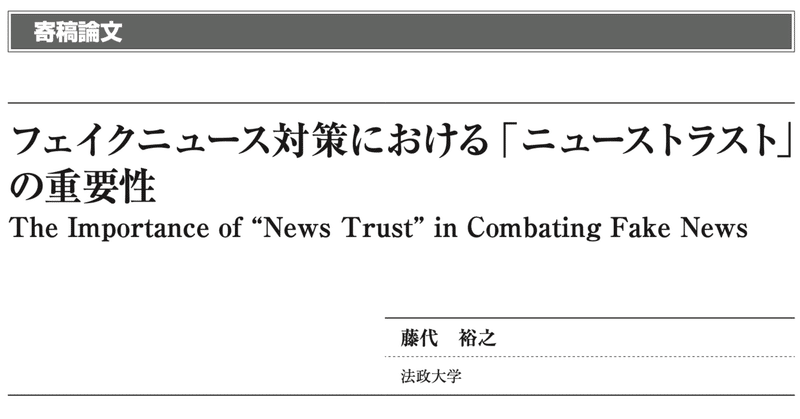
日本の情報エコシステムの構造からフェイクニュースと誤・偽情報対策について論じた論文
考えてみれば当然のことだが、フェイクニュース=誤・偽ニュースと、誤・偽情報は似て非なるものだ。ニュースはメディアから発信され、誤・偽情報はSNSを始めとしてどこから誰でも発信できる。近年、フェイクニュース・パイプラインなどが横行するようになり、両者の違いは曖昧になってきたものの、そこにはまだ違いがある。
今回、ご紹介する藤代裕之の論文はその違いと、分けて考えなければならない理由からフェイクニュース=誤・偽ニュース対策としての「信用」の重要さを紹介している。
フェイクニュース対策における「ニューストラスト」の重要性
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsicr/41/4/41_69/_article/-char/ja/
●概要
まず、フェイクニュースの問題は、ニュースが生成され、拡散するニュースの生態系の構造問題であるにもかかわらず、国内ではそれと誤・偽情報が混同されている現状が紹介される。このふたつを混同することで生じる問題のひとつは、誤・偽情報対策ではSNSプラットフォームが重要な役割を果たすことである。
現在、SNSプラットフォーム各社は誤・偽情報対策を後退させており、SNSプラットフォームに依存した対策の限界を示している。
そこで藤代が提案するのは信頼性の高いニュースの伝達である。現在、世界的にニュースの信頼性は下がっているが、本邦においてはそれほど下がっていない。
日本ではネットニュースはヤフーが圧倒的なシェアを持っている。一般のニュースではBPOなどチェック機構が存在するが、ネットニュースにはそれがない。
そこでNewsGueardやGDI、Trusting News、EUのJTIのような試みをあげ、第三者機関による評価、ニュースメディアの信頼性向上支援、認証制度の可能性を示唆している。
●感想
この論文はそのまま読んでもとても参考になるし、納得できるものであるが、視点を変えると情報エコシステム全体の組み替える提案であることがわかって驚く。
以前の記事で誤・偽情報対策のフレームワークを紹介した。ファクトチェックやリテラシーといった手法は3次対策、2次対策にあたる。しかし、この論文で提案している第三者機関による評価、ニュースメディアの信頼性向上支援、認証制度は基礎的対策に他ならない。現在、対策が集中している3次対策、2次対策の方法論を変えることで基礎的対策を実現する形になり、かなりバランスがよくなる。

好評発売中!
『ネット世論操作とデジタル影響工作:「見えざる手」を可視化する』(原書房)
『ウクライナ侵攻と情報戦』(扶桑社新書)
『フェイクニュース 戦略的戦争兵器』(角川新書)
『犯罪「事前」捜査』(角川新書)<政府機関が利用する民間企業製のスパイウェアについて解説。
本noteではサポートを受け付けております。よろしくお願いいたします。
