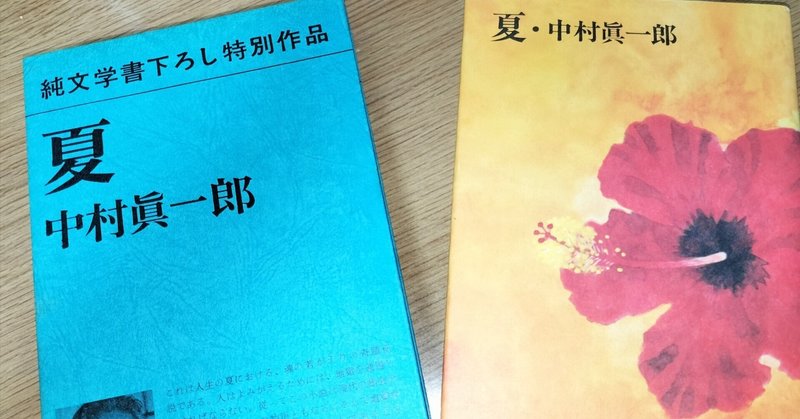
中村眞一郎『夏』
これは人生の夏における、魂の若がえりの奇蹟伝説である。人はよみがえるためには、地獄を通過しなければならない。従ってこの小説は現代の都会のなかでの地獄めぐりの物語ともなる。そして地獄からの脱出を可能とするものは愛の導きであることは、いつの時代でも真理だろう。だからこの作品は愛の神話としての姿もおのずから示していることになる。
この作品は、神経症の治癒のためといふ大義名分のもとに、主人公が遍歴する女たちとのエロスと、永遠の女性であるA嬢に於ける形而上学的にまで高まった愛とを、日本式回遊庭園をそぞろ散策するやうに、「意識の多層性」に応じて回想の中に明滅させたものである。といふより、彼女たちをまづ現象学的に考察し、次いで解剖学的に分析して、愛とエロスとを比較研究した独創的な小説である。想像力の葉叢を茂らせた中村眞一郎の生命の樹が、プルーストと源氏物語とを両極とする読書体験に栄養を得て、今や滋味あふるる果実を産み出したとでも言へるだらうか。から
曼陀羅に似た記憶の密室を開いていくと、さまざまな女たちが現れてくる。死と老年の影を帯びた主人公が、暗い神経症の穴蔵から王朝を思わせる濃艶な情事へと超え出ていく様子は、重層する時間をたぐりだす、独創的な文体によって定着されている。無意識と意識、狂気と正気、欲望と愛、過去と現在、西欧と日本、それらの相対立する万華鏡の世界が、小説の面白さを満喫させてくれる。
と、引用を続けたのは、読み終えてこの小説とはいったいどんな話だったのだろうかと、途方に暮れているからである。未読の読者は、これらの文章からこの作品の輪郭を掴み取って欲しい。以下に記す文章は「全く分からなかった」という告白でしかない。
福永武彦が言う、“愛とエロスとを比較研究した独創的な小説”という表現が一番しっくり来るかなあ。
前半は、主人公が繰り広げる、幾人もの女性たちとの愛情なき性愛について、まさに“解剖学的”な描写が延々と続く。著者言うところの“地獄めぐり”なんだろうけれど、その割に主人公はちっとも苦しんでいないので、とても地獄めぐりをしているようには感じられない。
愛のないセックスを咎め立てするような謹言居士ではないけれど、描かれるセックスがいったいどのような文学的興趣を生み出しているのかと考えても、何にも感じられない。
7章以降、“地獄から脱出する愛の導き”が描かれる際には、さすがに主人公の精神の高揚も描写されるんだけれども、やはり全体的に分析的で、とても愛の導きというようなものには思えない。
不幸な夫婦生活の破綻に起因する神経症(著者の中村眞一郎自身の体験でもあり、作中の主人公にも適用する)からの快復がテーマらしいけれども、どうも最後まで作品世界に入り込めないままだった。
この作品に果たして愛は描かれていたのだろうか。そんなふうに感じてしまうのは、僕の中の“ロマンティック・ラヴ・イデオロギィ”が邪魔をしているせいなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
