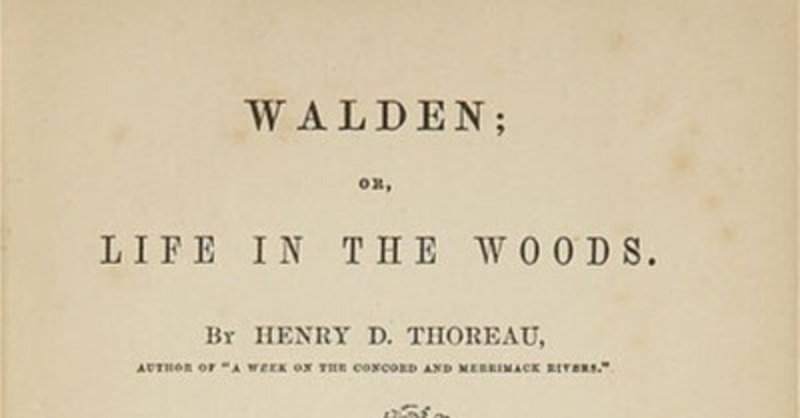
WALDEN 森の生活と北の国の生活。
誰もが(とも断言できないが)森の生活に憧れる。
自給自足、お日様と共に起きて、お月様の許に眠り、鳥のさえずりに耳を傾けたり、池の畔で釣り糸垂れたり、訪ねてくる動物や虫たちを歓迎したりする時間などない生活。
ヘンリー・D・ソロー著「WALDEN 森の生活」
ソロー27歳、1854年19世紀半ばに刊行された名著。
故郷マサチューセッツ州コンコード、ウォールデン池の森で2年間を過ごした記録。
自由定住者として、森に小さな小屋を建て、畑をつくって実験をします。暮らしに必須な物として、食物と避難場所(住居)に衣服と燃料という4つの項目を挙げています。
それ以外に若干の道具(斧やナイフ等)ですべてです。
■暮らしの心配事は無視していい。
物にあふれた文明社会で生きる私たちにも、未開の辺境の暮らしを経験すれば、本当に必要な物は何かを自分で知ることができます。
それにもっと素晴らしいことに、本当に必要な物を自分で手に入れる方法も習得できます。
■お金をふんだんに稼ぐ人は汽車に乗れます。
ただし、十分に稼げるだけ長生きすればの話です。
長生きすれば頭が固くなり、旅したい気持ちは失せます。
人生の最良の時期をお金を稼ぐために費やし、稼いだお金を、人生の最も価値の少ない残りの時間の怪しい自由を楽しむ人を見ると、私はインドでお金を稼いで青年期を過ごし、のちにイギリスに戻って詩人の暮らしをしようとしたあるイギリス人を思い起こします。
詩人になるなら、今すぐ屋根裏の安アパートに暮らすべきです。
ソローによると、一年間のうちほんの少し(6週間ばかり)働けば、後は必要最小限の生活が送れると言い切っている。(もちろん贅沢は無しで)
それ以外の時間は自由に研究できるわけです。
例えば、住居を建てること。
■私たちは家を建てる楽しみを、大工に譲り渡したままでいいのでしょうか?
私たちは分業をどこまで細分化したら気がすむのでしょうか。
■家のドア、窓、地下の貯蔵庫、屋根裏部屋は、人間の本性の何と関係しているのかよく見極め、私たちが普通に言われる世俗的な理由とは別の、もっと根源的な理由なしには作りません。
人間が自ら住居を建てるからには、あらゆる行為に、巣を造る鳥と同じ必然性があるはずです。
要するに彼の実験というのは、お金では買うことのできない生き方であり、法則であり、心の豊かさなのです。
インドのヴェーダやインディアン、哲学者、詩、神話などを引用しながら、ウォールデン池、村や町、鉄道と街道、農業、湿地、季節、鳥や動物たちを、彼の澄んだ目線を通して語られます。
特に、この時代(大量生産、農工業、鉄道の発展)急激な速度で進められる文明化に否定的です。
南北戦争後、インディアンとの紛争、(ソローは黒人奴隷制度反対運動に参加し、先住民の知恵なども学んでいた)そして急速な鉄道幹線網、工業化による自然破壊、絶滅した動植物を危惧していた。
■私は、森で暮らす実験から、少なくとも次のことを学びました。
人は夢に向かって大胆に歩みを進め、心に描いた理想を目指して忠実に生きようとするなら、普通の暮らしでは望めない、思いがけない高みに登ることができます。
かつての生き方の不要な部分をすっかり捨て去り、見えない心の境界を越えることができます。
そして新たに、どこでも通ずる広く自由な法則が、環境と心の中に打ち立てられます。
あるいは、すでに知っている法則も、自分にいっそうかなった形で、広く、より的確に理解することができます。
■人は暮らしを簡素にすればするほど、当たり前の法則のより多くを素直に受け入れることができます。
独り居は独り居ではなく、貧乏は貧乏でなく、弱点は弱点ではない、とわかります。
あなたが空中に理想の城郭を描けたなら、それは素晴らしい成果です。
でも夢は頭の中に描くだけではなく、実現したらいいでしょう。
あとは理想の城郭の下に基礎を築けばいいのですから。
とても共鳴することの多い書籍だった。
もちろん彼のようにストイックには生きられそうもない。
お酒も嗜みたければ、音楽や映画だって、僕には必要だ。
それでも、約170年前の偉人は、本当の人間の暮らしを模索した。
本当というのは、真実ということである。
それは、法や時代や宗教や常識や倫理や紙幣や経済では推し量ることのできない、自然が開示した法則であった。
こんな現代にも、そんなような人がいたなァ。
それはちょうど「北の国から」スペシャル版を見終えたところだった。
当然、この著作も根底にはあったことだろう。
説明するまでもなく、このシリーズは、1981〜2年テレビ(全24話)から2002年までのスペシャル(8回)が制作された倉本聰・脚本の傑作ドラマ。
長きに渡るこのシリーズも、生活と自然、滅びゆくもの、新たな価値感と古きものとの格闘だった。
合理的なるもの、利便性だけを追求した社会は、容赦なく五郎さんを追い詰めていく。
最後のスペシャル「遺言」での台詞にハッとさせられた。

■金なんか望むな。幸せだけを見ろ。
自然はおまえらが死なない程度、十分食わしてくれる。自然から頂戴しろ。謙虚に慎ましく生きろ。
何故こうも僕が、これらの物語に固執するのかといえば、資本経済や、どんどん加速していくそんなに必要でもない、いなむしろまったくいらない、そんな快適さや便利さがとても不純に思えるからなのだが、もしかするとそんなように感じる者は少数かもしれない。
ということは、まさに五郎さんのように、不適応者ということになるのだろう。
どうもね、しっくりいかない、というのであれば、社会を変える前に自分が変わる必要があるわけだ。
だって死んじゃうもん、殺されちゃうもん。
そんな者に、ソローは語る。
人は同じである必要はない、多種多様であった方が面白い。
いろいろあるからこそ、そこに新しいものが生まれる土壌が育まれる。
どんどん変わっていこう、という禊(みそぎ)であり、試みであり、目論見であり、日和見でもあって、同じ場所にはいないこと。
年齢は関係なしに。
そうすれば、死なない、という可能性もあるのかもしれない。
「知るとは、本当に、知ったということを知ることです。
知らないことは知らないと、はっきり知ることです。」
【archive】2019
