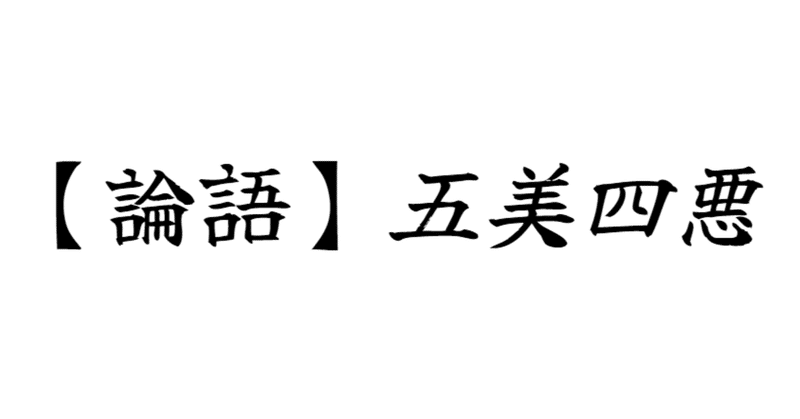
【論語】五美四悪 上司・リーダー・指導者の心得
とある勉強会で論語の「五美と四悪」について教わる機会があった。
これは指導者、リーダーに必要な心得である。
論語では、弟子たちが孔子に対して質問し、孔子がそれに答える、そのやり取りが記されています。
「五美四悪」とは、とある弟子が「政治を立派にするには何が大切か?」と問うた際に孔子からでた教えです。
五美を尊び四悪を屏くければ、これ以て政に従うべし。
つまり、「五美」を大切にし、「四悪」をしなければ良い政治が行えるということである。
ではこの「五美」と「四悪」と何なのか?
①五美
1.恵して費やさず。
恵(けい)して費(つい)やさず。
恵みを与えるが、それによって貧しくならない。
→民の利益となること(仕事)などでしっかり稼げるようにする。
恵する・・・与える。
費やす・・・減る。無駄にする。
2.労して怨みず。
労(ろう)して怨(うら)みず。
民を働かせても恨まれることがない。
→恨まれるような働かせ方をしない。
→やりがいのある仕事にする。
労する・・・働かせる。
3.欲して貪らず。
欲(ほっ)して貪(むさぼ)らず。
欲はあるが、貪らない。
→金、名声など必要以上に貪らない。
→賄賂、裏金、裏工作をしない。
貪る・・・欲張る。
4.泰にして驕らず。
泰(ゆたか)にして驕(おご)らず。
落ち着いていて、高慢、傲慢な態度をとらない。
誰に対しても態度を変えることがない。
→相手の肩書で接し方を極端に変えたりしない。
泰・・・ゆったりしている。落ち着いている。
驕る・・・思いあがる。威張る。
5.威にして猛からず。
威(い)にして猛(たけ)からず。
威厳はあるが、威圧感はない。
→服装はもちろん。振舞、品性を磨く。
威・・・威厳。
猛・・・荒々しい。たけだけしい。
②四悪
1.教えずして殺す。これを虐と謂う。
教えずして殺(ころ)す。これを虐(ぎゃく)と謂う。
教えないのに、罪を犯したら罰すること。これを虐という。
2.戒めずして成るを視る。これを暴と謂う。
戒(いまし)めずして成(な)るを視(み)る。これを暴(ぼう)と謂(い)う。
指導や注意をせず、そのくせ成果を出すことを求める、強いること。これを暴という。
3.令を慢くして期を致す。これを賊と謂う。
令(れい)を慢(ゆる)くして期(き)を致(いた)す。これを賊(ぞく)と謂(い)う。
あやふやな指示を出しておきながら、突然期限を言い渡す。これを賊という。
4.之を猶しく人に與うるに、出内の吝なる、これを有司と謂う。
之を猶(ひと)しく人に與(あた)うるに、出内(すいとう)の吝(やぶさか)なる、
これを有司(ゆうし)と謂(い)う。
出さなければならないものを、ケチって出し渋る。これを小役人根性という。
所感
特に四悪は日常的に様々な職場、組織で起こっているものと感じ、印象に残った。
善悪、良し悪し、評価の基準が曖昧であるにも関わらず、そこから外れたとたんに罰せられる、評価を下げられる。突然の抜き打ちで一場面をチェックされる。
こんなことをしていては、まさに「労して怨まれる」。自身の振る舞いがどうなっているか、常に自問自答したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
