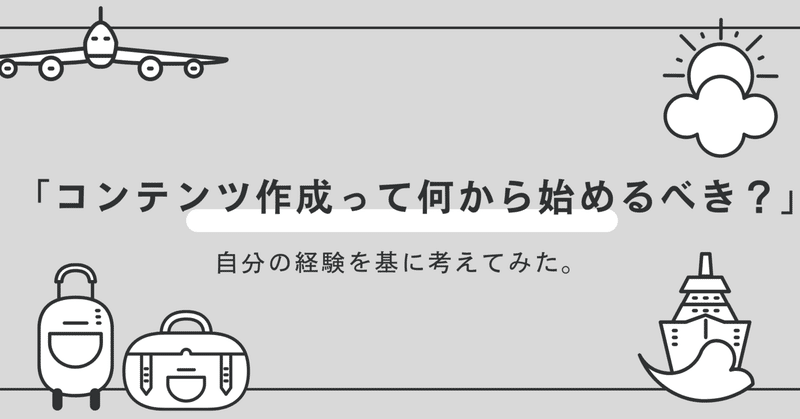
コンテンツ作成って何から始めるべき?を自分の経験を基に考えてみた。
「マーケティングでは質の高いコンテンツが重要」
とよく言われますが、
「実際に質の高いコンテンツってどうやって作るの?」
まで明確にされていないことが多いなと感じています。
というのも、コンテンツ作成力はかなり属人的な能力なので、明確に言語化される機会が少ないことが原因なのでは?と思っています。
だからこそ、作れる人はとことん作ることができるけど、苦手な人はとことん苦手な分野であるとも思っています。
そこで今回は
「コンテンツを作ろう!と思ったときはまずこれをやろう」
というガイド的役割を果たせるような記事を書いていきます!
※今回の「コンテンツ」は記事・SNS投稿・ホワイトペーパーなど「広義のコンテンツ」を指しています。
現在、30分の無料SEO分析を実施しております!「無料のSEO分析お申込みフォーム」より日程調整と必要事項の記入をしていただけますと幸いです!
「一次情報を入れていこう!」は正直しんどい

コンテンツを作るうえで
「質の高いコンテンツって何なんだろう?」
という疑問が真っ先に浮かぶと思います
結論「一次情報が入っているコンテンツ」は質が高いです。
この一次情報というのはいわゆる「自分が直接体験をすることで得た情報、もしくは自ら行った調査や実験で得た情報」を指しています。
確かに自分にしかない体験や実際に足を動かして得た体験は、信頼性も高くオリジナリティあふれるコンテンツになります。きっと質の高いコンテンツになるでしょう。
しかし、正直なところ、いきなり一次情報からコンテンツを作るというのはきついのですよね…
まずコンテンツにできるほど一次情報を持っていない人の方が大多数です。仮に一次情報を保有していたとしてもコンテンツに落とし込めないということも起こります。
よって、一次情報を基にしてコンテンツを作成していくというのは、あくまで一定経験を積んできた中上級者だからこそできる技だと思います。
コンテンツ作りに取り組むときに使える汎用的な考え方

では、「これからコンテンツを作っていきたい!」という人は、まず何を実施していけばいいのでしょうか?
それはずばり「ナレッジコンテンツを作りまくる」ことだと考えています。
これは私自身の経験にも基づいています。
私自身、学んだ事、本で読んだこと、先輩や同僚に教えていただいたこと、すべてを1年間コンテンツ化しまくりました。
学んだり、教えてもらったときの腹落ちした感覚を忘れずその場でコンテンツ化します。
コンテンツの形は文章でまとめるでも、パワポやCanvaでグラフィック化するでも、声で録音するでも何でもよいです。
とにかく
「知らなかったことを知った瞬間」
を大事にしてコンテンツを作り続けることが大事です。
ただ、中には
「これって自分にしか需要がないのでは?」
と思うものも出てきます。
例えば
「Excelのvlookup関数を組むときのポイント」
「タスク漏れをなくすためにはTrelloを使うといいこと」
のような少し自分ゴトなものや、みんなすでに知ってそうなものです。
しかし、そういったナレッジもすべてコンテンツ化してしまいましょう!
理由としては
「刺さる人には刺さる」
からです。
例えばTwitterのフォロワーが1000人の人が
「Twitterのフォロワーを1000人にするまでしたことを大公開!」
という投稿を作ったとします。
きっと、すでにフォロワーが3000人、5000人のような人からはきっと無視されるでしょう。
しかし、Twitterのフォロワーが300人しかいない人やこれからTwitterを始めたい人にとっては、ノウハウをゲットできる質の高いコンテンツと認識されるのではないでしょうか?
どんなに当たり前と思えるナレッジでも「誰かにとっては刺さるコンテンツ」なのです。
コンテンツは「発信するチャネル」で質の定義が変わる

では、実際にここから作ったコンテンツを発信していくフェーズに移っていきます!
ここで重要なのは「コンテンツは発信するチャネルで質の定義が変わる
」ということです。
これはどちらかというと評価基準が変わるよりも、各チャネルで求められているコンテンツの形が変わるというイメージを持っていただきたいです。
例えば、検索エンジン。
検索エンジンでは、狙っているキーワードで上位に表示するためにクローラーからちゃんと評価されることが大切です。
そのためよく起こりがちなのは、情報の網羅性を担保するために1万~2万文字の膨大な記事コンテンツが出来上がるという事態です。
正直なところ、1万~2万文字の記事はよほど興味がないとすべて読了することはないでしょう。

しかし、検索エンジンで上位に表示するためには情報の網羅性を高め検索エンジンから評価される必要があります。すると、記事に入れ込むコンテンツ増やす必要があるため、必然的に記事の文字数が膨大になってしまうのです。
検索エンジン上でのコンテンツ発信では「シンプルでわかりやすいコンテンツ」ではなく、「ちゃんと情報が網羅できているしっかりとしたコンテンツ」がより評価される傾向にあるのです。
それとは反対に、X(Twitter)では「シンプルで端的な140文字でわかりやすいコンテンツ」が好まれます。


サクッとわかりやすく、簡易に情報収集しているユーザーが多い傾向にあります。アカウントの知名度が高かったり、テーマ性が目を惹くものでない限り長文投稿はスルーされることが多いでしょう。
そのほかにも
インスタグラムは雰囲気やグラフィック、色使いなどの定性的な部分が評価される傾向がある
Youtubeは視聴することで得られるメリットが明示されているサムネや20分以内の動画がよく見られる傾向がある
等チャネルにも好まれるコンテンツの傾向があります。
「どのチャネルでコンテンツを発信するか?」
によってコンテンツの形を変えながら発信することが重要なのです。
私個人では、
まずは作ったナレッジコンテンツをTwitterで発信していく
事をお勧めしています。
Twitterは拡散力も高く、シンプルな文章でコンテンツを発信できるので、多くの人に比較的簡易にコンテンツを届けることができるからです。
私自身もまずはTwitterでのコンテンツ発信を始めました。
投稿を継続すればするほどインプレッションやエンゲージメントが高まっていき、次第にリプライやDMをいただけるようになりました。
最後に
今回はコンテンツの作成についてお話してきました。
まずは
ナレッジコンテンツをひたすら作りまくる
それらをtwitterで発信し続ける
の2つを実践する事をお勧めします。
一点最後に気を付けていただきたいことは
「コンテンツ発信の領域だけはブラさない」
事を意識していきましょう。
webマーケのコンテンツを発信をしていたのに、いきなりおいしいケーキの作り方を発信していると一貫性がなくなってしまいます。
できるだけ発信するコンテンツの領域はブラさないようにしましょう!
今回の記事が皆さんの何かしらに役立てられれば幸いです!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
