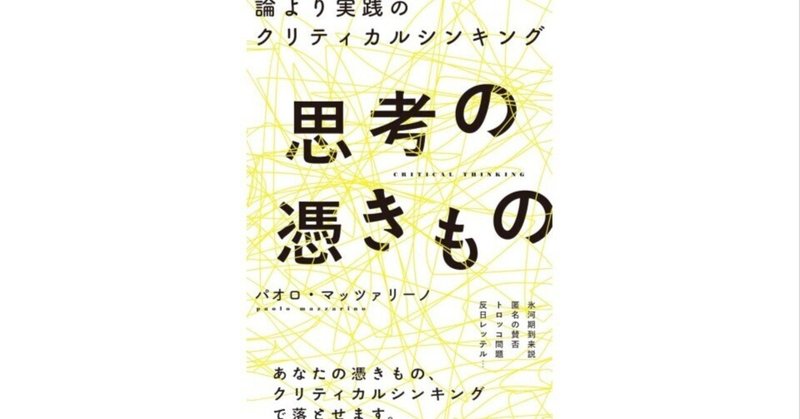
反社会学者の奇妙な変節
さて、みなさんもう飽きているでしょうが、パオロ・マッツァリーノ師匠です。ちなみに師匠、今週の『文春』に書いていました。
内容はまあ、一応は松本人志バッシングですが、ワイドショーについて語ったものであり、近著の『読むワイドショー』の宣伝かなと。
「勇気あるなあ」というのが感想です。
というのもこの『読むワイドショー』、実のところ――。
・コドモダマシ
今までもご説明してきたように、パオロ・マッツァリーノ師匠は「反社会学者」を名乗り、社会学の欺瞞を指摘してきた人物です。かつては(そこまで明確ではないものの)フェミニズムへの懐疑も吐露していたことも、動画で指摘した通りです。
ところがそんな師匠が松本人志の性加害疑惑をきっかけに(ではないのですが、それは後に述べます)、おかしなフェミニズム的迷妄を垂れ流すようになりました。
師匠の記事は頭のてっぺんから尻尾の先までデタラメと嘘と矛盾の詰まったものでしたが、中でも「性犯罪の中で裁判にまで漕ぎ着けるのは全体の2%」という(舞田敏彦師匠発の、おそらくこれ自体はそれなりに信頼できる)データをねじ曲げ、「それは警察が門前払いをするからだ」とミスリードしたことは、絶対に許されるものではありません。
(ちなみに、師匠は卑劣にも批判者がこのデータ自体を否定していると称することで、自身のデマを正当化していますが、少なくともぼくは上にも書いたように、データ自体否定しているわけではありません。師匠の最初の記事を見る限り、「2%」の原因として「警察の門前払い」を持ち出しているとしか読めず、そこを批判しているのです)
さてこの2%について、師匠は当初、ソースを出していませんでした。
ぼくがツイッター上で直接問い質し、またその主張が実情と齟齬があることを指摘した後、師匠はブログでソースが舞田師匠の記事であると明かしたのですが、上に書いたように、パオロ師匠はそのソースをねじ曲げていたわけです。
そこを指摘された師匠はまた新たな記事で、前回採り挙げた牧野雅子師匠の著作を持ち出したのですが、読んでみれば案の定、これまたソースとして成り立っていない。
それなりに長年活動してきた作家が、ここまで右往左往していい加減なことしか言えないとは、驚くべきことです。
・「昔はよかった」人
いえ、動画でも「前はいい人だったのに」と形容したように、パオロ師匠はやはり、どこかのタイミングで「変節」したと考えるべきでしょう。
師匠は新たなブログ記事(「松本さんについての記事への反響など」)でも、「前はいい人だったのに」といった評をされていることに対して、いたくご立腹で、以下のように言い訳しています。
私は社会学もフェミニズムも全否定などしていないのですが、それについては以前のブログ記事で説明しています。
この以前のブログ記事というのは、 2023年6月9日に公開された「『読むワイドショー』のレビューについて思うところをお話しします 《前半》」というもの。読んでみると以下のような記述に行き当たります。
自分が好きなマンガやアニメがフェミニズム社会学者に批判されたことでアタマに来て、社会学を全否定して溜飲を下げている、という程度の人が多いのでしょう。
ええええええええええええ!?
パオロ師匠って、この程度の認識なんだ……。
まずフェミニズムは漫画やアニメ、そこで描かれるセクシュアリティの全て、全人類のセクシュアリティの全てを否定するために存在している学問です。
師匠はご存じないでしょうが(この人、フェミを擁護するために知らぬフリをしている部分もありましょうが、本当に知識に欠けているんではないか……と思える節もあります)、当noteの読者のみなさんは、即座にでも師匠を論破できることでしょう。
この「全否定していない」という言い方がいやらしく、なら部分的には否定的なのか、それはどこなのかが、さっぱりわからない。
普通ならば、「これこれの部分は問題だと思っているが、これこれの部分は否定しない」と論点を整理するものですが、上の記事においても以降は批判者への子供じみた罵倒が並ぶだけで、(フェミについても社会学についても)それをしません。
できるはずがないんですよね、「変節」したんですから。
・過去の発言を消すな
もう一つ、上の記事はタイトル通り、2023年刊の『読むワイドショー』に対する批判への反論という形をとっています。が、不思議なことに同書には別にフェミニズムへの言及はないのです。上の記事でも一応、「デビュー作の頃から(社会学を、フェミを全否定していると)誤解されている」と言っており、この点は同書とは関係がないのかも知れませんが、なら何故このタイミングで(同書のレビューへの反論を意図した記事の中で)そんなことを言い出したのかがわかりません。
同書の内容自体は、昭和の芸能人が政治批判をしていたことを語る最終章など、タレントが自民を叩けば快哉、共産党をからかえば真っ赤になって怒るという近年の師匠にありがちなもので、まあ、保守寄りの人の不評を買っても不思議はありませんが、いずれにせよフェミは関係ない。
これは一体どういうことでしょうか……?
実は同書には、他にも気になる箇所があります。
昭和の時代、とある有名歌手が殺人事件を起こし逮捕され、出していた曲が回収されるという騒動があったのです。そう、今の世においても芸能人が事件を起こすと、自主規制で曲や番組がキャンセルされるのはよくあることですが、師匠はそれを腐し、以下のように言っているのです。
じつに不思議な慣習だと思いませんか。歌手の罪は作品である楽曲にまで及ぶのでしょうか。歌詞で犯罪を勧めているわけでもないのに、歌っているのが犯罪者というだけで、歌が犯罪を助長するのでしょうか。
(73p)
え……?
それじゃあ、師匠があれだけ嬉しげに松本人志氏をキャンセルせよと絶叫していたのは何だったんでしょうか。
このリクツなら、少なくとも松本氏が勝訴するなり敗訴して賠償金を払うなどした後ならば、テレビに出ても文句はないはず。ところが師匠はそれを「笑えないでしょ」と全否定していたのです。師匠の愚劣さ、軽率さにただただ、哀しくなります。
(ただし、松本氏についても「You Tubeでの活動なら文句はない(大意)」と言ってはいます)
・政治の憑きもの
さらに遡り、2022年の著作、『思考の憑きもの』を覗いてみましょう。
(この書名、意味がわかりにくいですがイデオロギーという「憑きもの」が思考に憑くと、正確な判断ができなくなるという、極めて優れたブーメランタイトルなのです)
実はここでも、パオロ師匠は「フェミにアニメや漫画を貶されたファンが自分のことをフェミと戦う勇者だと勘違いしていて迷惑だ(257p・大意)」などと言っているのです。
つまり、師匠をアンチフェミと考えていた人が、この時期からいらっしゃるようなのです。
幾度も書く通り、かつての師匠は今と論調は違ったけれども、積極的にフェミと戦っていたとは思えず、何故そのように考える者がいるのか不思議です。
ぼくが未発見なだけで、そうした発言がかつてあったのかも知れませんが、いや、むしろ……と意地悪な想像もしてしまいたくなります。
もうちょっと師匠の発言を引いてみましょう。
学問としてのフェミニズムや学説にはあまり興味が持てないし、ちょっと皮肉ることもありますが、私が皮肉や批判を向ける対象はフェミニズムに限ったことではありません。
(257~258p)
動画でもご説明した(そして本稿でも後に述べる)ように、比較的近年まで、師匠は「サブカル」同様に、言うなら「不良キャラ」として女性に対しても結構な暴言を吐いていた。同じ変節者でも町山師匠たちは何の能もなくただ、過去をなかったこととして扱っていますが、パオロ師匠ともなると自身のかつての発言を(今、ぼくがしているように)蒸し返されることを恐れる注意深さがあった。
そこでムリヤリに「自身の著作を曲解した者」を仮想し、「皮肉っただけだ」と自作自演の「反論」をすることで、極めて自然に(いや、全然自然じゃない気もしますが)変節宣言をしおおせた……とまあ、そんな裏事情が、或いはあったという気も、しなくはありません。
そう考えれば、先の『読むワイドショー』でキャンセルカルチャーを批判した後で、フェミの味方であると自称しだしたのも頷けます。師匠には過去ロンダリングをする必要があったのですね。
さて、『思考の憑きもの』に戻ると、師匠は(ネット上の、萌えキャラに対する攻撃などに対し)フェミの言い分も行きすぎの面もあるが、オタク側も過剰反応だ、などと中立派を気取ります。
(もちろん、フェミという人類の文化の全てを否定するウルトララディカルな思想に対し中立派などあり得ないのですが、みなさんご存じでしょうから、措きます)
もし、批判に理があるのなら対処法を考えて実行すべきだし、批判を受け入れがたいのなら、正々堂々と反論すればいいだけの話です。
(259p)
あの~~、書くならちょっとくらいは事実関係を調べましょうよ。
例えば青識亜論師匠が石川優実師匠とトークショーを開くなど、これなどは左派のプロレスに過ぎずぼくは全く評価しませんが、少なくとも表現の自由クラスタは幾度もフェミと対話を試みてきました。
また、左派寄りでないアンチフェミだって「反論」はいくらでもしているでしょう。
物事をホンの僅かも知ろうとはせずに、政治的に強い側につき、提灯記事を書く。
それがパオロ師匠のスタイルです。
私が見たところでは、知的好奇心が低いひとほどフェミニズムを毛嫌いする傾向があります。知的好奇心がないから、フェミニズムについて知ろうともしない。無知なまま全否定してしまうのは、知的怠慢、思考停止です。
(259p)
パオロ師匠を見る限りでは、知的好奇心が低い人ほどアンチフェミを毛嫌いする傾向があるんじゃないでしょうか。知的好奇心がないから、アンチフェミについて知ろうともしない。無知なまま全否定してしまうのは、知的怠慢、思考停止です。
後、師匠が言うには八〇年代には世界中でフェミへの「バックラッシュ」があったそうで、アンチフェミはそうした「プロパガンダを鵜呑みにして」フェミを叩いているのだそうです。
八〇年代のバックラッシュなんて、ぼくは聞いたこともありません。いえ、「バックラッシュ」については九〇年代にも言われていたので、あったにはあったんだと思います。しかしその「プロパガンダ」とやらを、ぼくは聞いたことがない。日本にそんな情報が入ってきたことを、ぼくは過分にして知りません。本当にごく僅かな例外はないでもないですが、それを「ネットのアンチフェミ」の多くが知っていると、師匠が何を担保に確信しているのかは、さっぱりわかりません。
・何も調べなかったパオロペテン史
パオロ師匠の「変節」ぶり、どうも赤木智弘師匠などを思わせ、正直気味が悪い。
ぼく自身、十年ほど前に師匠の本を追うのを止めていたところ、本件(というのは松本氏疑惑を巡る師匠の一連のデマについてですが)を知り、唖然となったので、少々気になっているのです。
師匠はいつ、「変節」してしまったのでしょう?
もうちょっと探ってみようと、師匠のブログを「フェミ」で検索してみました(あ、師匠の著作っぽい展開)。
が、意外にヒットした記事は少なく、以下の四つのみ。
・「被害者の存在を消すな」
・「松本さんについての記事への反響など」
・「『読むワイドショー』のレビューについて思うところをお話しします 《前半》」
・「それは説教ではない。きみは論破されたのだ」
上二つは松本氏関連であり、まだ言及していないのは一番下のものだけ。
ちなみにこれは2021年1月11日に公開されており、「フェミ」への言及があるモノの中では最古の記事です。
見てみると、テレビドラマ『逃げ恥』に対しSNSで「フェミの説教みたいだ」といった感想が溢れていることに憤慨する内容(このオッサン、ヒマなのかとにもかくにもひたすらテレビばっかり観てます)。攻撃的な記事タイトルは、要するにドラマを正当化しようとしてのものなのですね。
もっとも、その肝心の『逃げ恥』、ぼくは観てないのでパス。
ところがこのドラマを一くさり擁護した後、パオロ師匠は呆れたことに『ミステリと言う勿れ』を持ち出します。
「一年ほど前にとある漫画の感想を読んでいて、やはり似たことが言われていた」と、このロートル少女漫画家のとんでもない非常識ぶり、反社会ぶりがこれでもかと現された怪作を引きあいに出すのです。
フェミの説教などと批判されてることに、私はビックリしました。え? あのマンガがフェミニズム? そんな印象、まったく受けなかったけどなあ……? そこでもういちどマンガ喫茶で1巻を読み直しました。
で、久能は刑事たちに何を告げたのかといいますと、娘が父親のニオイを嫌うのは近親交配を避けるための本能とする生物学の仮説を披露したり、刑事が奥さんを怒らせてるのは、ゴミをゴミ置き場に持ってくだけで家事を手伝ってるつもりになってるからだと忠告したり、アメリカの野球選手は奥さんの出産やこどもの卒業式のときに試合を休むことを父親の権利だと思い、世間も認めてるが日本ではなかなか認められない……とか、その程度の話です。
批判レビューを書いたひとたちは、この程度の内容をフェミニズムだと誤解して唾棄してるわけで、それは単なる無知、勉強不足ですね。
家事を手伝え、育児を手伝えと(男がいかに会社で酷使されているかも考えず)主張するなどはどう考えても単なるフェミニズムでしょう。その程度のことも知らずに誤解してるわけで、それは単なる無知、勉強不足ですね。
何より、この一巻だけを読んだというのがいかにも片手落ちです。デタラメなデータをドヤ顔で担ぎ出す三巻、男が戦争で殺されても自業自得だなどと絶叫し、痴漢冤罪で苦しむのは(疑われた男性ではなく)女は男に冤罪を着せるものだなどと偏見の目で見られる女性だ、などと泣き叫ぶ八巻など、師匠がチェックすべき巻は他にもあったのですが。
いえ……一巻の「説教」の中でも師匠が華麗にスルーしているものがあります。
ここで主人公の久能整は「男は社会で悪いことをするものだ」と決めつけ、男性への抑止力を、当初は「女性」が発揮するべきと言っていたのですが、話の途中から抑止力として「第三の性」があるといいなどと言い出す。
おそらく作者もその場のノリで書いていて、論理的整合性が保てていないのでしょう。
この下りは、この回のヒロインと呼ぶべき婦警をエンパワメント(大爆笑)するというドラマの肝の部分であるように思われ、そこをスルーする師匠は極めて不誠実です。
師匠は「久能はつねに合理的な視点で物事を見ています。」などと書いていますが、本作を絶賛しつつ都合の悪いところは隠す師匠自身が、「(久能に比べれば)合理的な視点で物事を見」る能力をお持ちなのでしょう。
・偽言のトリセツ
――さて、しかしブログでは、これ以前にフェミへの言及はない。
もう少し、著作の方を調べようということで、2020年刊の『サラリーマン生態100年史』(17年刊の『会社苦いかしょっぱいか』の新書版なのですが、今回挙げる箇所についての改訂はないと思しい)を借りてきました。
パオロ師匠はNHKの大河ドラマに対する、戦前の実在した人物のドラマでは妾がいたことについて伏せて欲しいという要望について揶揄し、以下のように言います。
じゃあ戦国時代の男色や戦前のこどもの間引きなんかを忠実に描いたら? 視聴者どん引きまちがいなしです。そういうのに比べたら妾なんてかわいいもんじゃないですか。
(35~36p)
実は本書、妾について一章割いており、もちろん諸手を挙げての大肯定ではないのですが、上にあるようにトーンとしては極めてソフトなのです。
あんなに松っちゃんに正義の刃を振り下ろしていたのに~~~!
男色をどん引きというのも(当時の衆道と今のホモは全然別物ではあれ)大首領にバレたらいろいろとおしおきされそうですね。
何しろ二一歳の女子大生が「月三〇万もらえばどんな男の愛人にでもなる」と言っているのに対しても「身の程をわきまえぬ」、「このバカ女子大生はいま六五歳のババアです。老後破産してればいいのに。(44p)」とばっさりです。恐ろしいミソジニーに震えます(もちろん1970年代のことで、貨幣価値を考えても、身の程をわきまえていないこと自体は事実ですが、それは本件には関係ないでしょう)。
他にも大正時代の大会社の重役が二二歳の秘書を手籠めにし、愛人同然に扱い、時計や指輪を買い与えていた事件についても、秘書本人が被害を訴えたわけではなく、この女性の母親が警察に相談に行ったために発覚したことであり、「どうでもいいこと」とばっさり。
二二歳の大人の女性で、一流企業に勤めるくらいなら、それなりに世間ずれしてるでしょ。仮にきっかけは手籠めにされたことだったとしても、高価な装飾品をくれるおじさまとの割り切った関係を続けていたのではないかと。
(48p)
言っておきますけど「手籠め」ってレイプですからね。それを師匠は平然と「女も割り切ってただろ、騒ぐようなことか」と断言しているのです。
あ……あんなに松っちゃんにぐうの音も出ない正論をぶつけていたパオロ様が~~~!!
・これは批判ではない。きみは一蹴されたのだ
何があったかは知りませんが、同書の出た20年12月から、先のフェミへの帰順を高らかに謳い上げた21年1月のブログ記事に至る、たった一ヶ月の間に師匠は変節したわけです。丁度、ポリコレが異常な勢力となり始めた頃ですね。
今までの記事や動画をご覧になって、それでまだなお師匠を信頼に足るとお考えになる方はよもやいらっしゃらないでしょうが、それでも強調しておくならば、師匠はこうした、極めて機を見るに敏な、勝ち船に乗るのがお得意な、しかし思考に憑き物が憑いており、クリティカルシンキング(批評的思考)が一切できない方なのです。
知識もない。
論理もない。
根拠もない。
結論は常に妄想によって導き出される。
その戦術は徹底したレッテル貼りによる「思考停止」とデマの流布による「プロパガンダ」。
その目的はあくまで政治的に有利な側に追従するという「事大主義」であり、「論より党派のポリティカルシンキング」の実践。
それが、反社会学の本質だったのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
