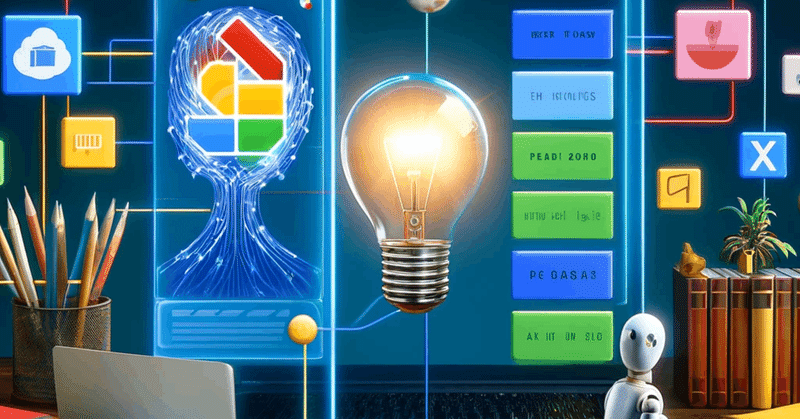
AIに触れること |AIと私の今 '24.4 ① #031
前回の記事で話題に出たAIについて、現時点での考えを何回かに分けてまとめておこうと思います。
実践ベースでAIに接する
私は今後のAIの進化を捉えることを、かなり高い順位に位置づけています。今やAI関連の情報は得ようとすれば溢れかえっていますよね。これだけ進化が早い世界なのでそれは当然です。
社会構造やビジネスの変化を捉える意味では、情報を得て考えることに意味がありますが、自分自身が活用するミクロの部分では実際に触れて活用するのが一番です。
私が意識しているのは、多少強引にでもAIを活用する場面を作ることです。自分にとってAIはあくまでもツールだということを忘れてはいけません。
前回紹介した「note記事のサムネイルは全て画像生成AIで作る」はその一つです。サムネイルは私のnoteではそこまで重要な要素ではないので、画像生成AIの実践練習をする場にしてしまいました。
あとは普段私が地域で開催している読書会のInstagramの投稿画像も、昨年の夏頃から全て画像生成AIで描いています。
やはり実際に使ってみると、生の知見がどんどん貯まっていきます。実践する方が身に付くことを改めて実感しますね。
アンテナは張っておく
実践ベースとは言いつつも、AIに関しては「知ること」自体が目的になり得る状況です。そのためアンテナだけはしっかり張っています。
大きな流れを理解したり、新しい潮目を知ることにはVoicyを一番活用しています。
私がフォローしているチャンネルを2つ紹介します。流し聴きする中で気になった話題があれば自分で調べたりしています。
この他はご存知キングコング西野さんのチャンネルでも画像生成AIをはじめIT・AI関係の話題が多くあり大変勉強になっています。
あとはnoteでも発信している方は数え切れないほどいますが、私はIT nabiさんの記事を見ることが多いです。
おわりに
今回の記事はここまでにします。
やはりどんなものでも触れてみることでその実体がつかめてきます。皆さまも何か一歩踏み出して活用・実践してみることをおすすめします。
次回の記事では、私が具体的にどんなAIサービスやプロダクトを活用しているかを書いていきますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
