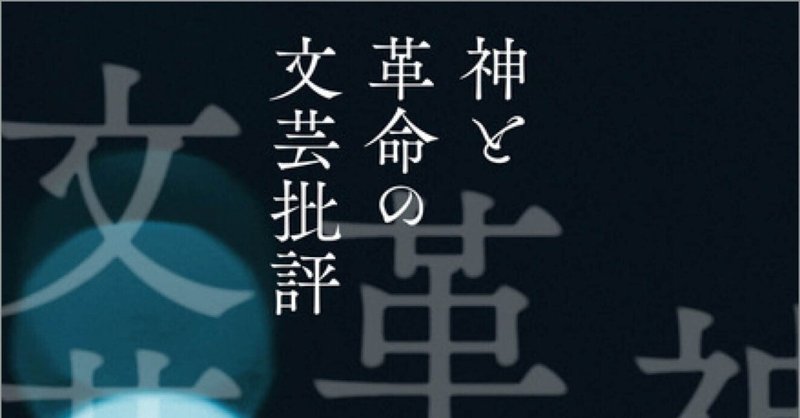
杉田俊介 『神と革命の文芸批評』 まえがき
このたび(2023年12月)、川口好美著『不幸と共存 魂的文芸批評』を〈対抗言論叢書4〉として刊行することになりました。
この叢書は、「反ヘイト」のための言論・文芸雑誌として、すでに3号までを刊行ずみの『対抗言論』誌(2019年末〜)の関連叢書です。同誌の編集委員や、理念を共有する関係者のみなさんによる著作を収めるシリーズとしてスタートしました。これまでに、
〈1〉杉田俊介『神と革命の文芸批評』(2022年5月)
〈2〉川村 湊『架橋としての文学 日本・朝鮮文学の交叉路』(2022年8月)
〈3〉室井光広『エセ物語』(2023年9月)
という、いずれもたいへん中身の濃い、ユニークな本を刊行できました。今後も少しずつ、収録書を増やしていく予定です。
これを機に、叢書第1号の『神と革命の文芸批評』の「まえがき」を掲載いたします。
《国家と資本の暴力のもと、労働や生存がますます非正規化され、抵抗への努力は冷笑される世界で、文学や批評はまだ可能なのか。自他への憎悪を解体する言葉、未来を変えるための言葉はどこにあるのか。ロスジェネ論壇以来、無能力や弱さ、複合差別と加害の問題に向き合い、新しい協働の道を模索してきた批評家の到達点。『すばる』『ユリイカ』『新潮』などへの掲載文を集めた初の文芸批評集。》
https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-46018-0.html
まえがき
……思えば、大学生時代に柄谷行人の初期の文芸評論集『畏怖する人間』や『意味という病』、あるいは三浦雅士の批評集——『私という現象』や『メランコリーの水脈』や『小説という植民地』などのいかにも「ポストモダン」な書名を目にしただけで時代的ノスタルジーに溺れかけてしまうのだが——などを愛読していた人間として、雑多な批評文やエッセイを寄せ集めた評論集varietybookを刊行するということは、ささやかな夢だった。
なるべくごちゃごちゃと、雑然とした評論集であるのがよい。興味の引っかかりのあるところを、気ままにページをめくっていく。肩肘をはることもない。最後まで律儀に読みとおさずとも当然かまわない。中途で放り出して、すべてを忘れたころに、気まぐれに読み返すのもいい。もちろんそのまま忘れたっていい……批評の本は、雑文たちのおもちゃ箱であって、個人雑誌のようなものくらいであるのがちょうどよい……。
本書に収録された文章たちは、基本的に、さまざまな雑誌や書籍——『すばる』や『新潮』『文學界』等の文芸誌、青土社の『ユリイカ』『現代思想』、河出書房新社の作家特集、あるいは小さな手作りの文芸誌『てんでんこ』『練習生』など——からの依頼に応じて、即興的に、その時その時に応じて書いたものである。それらの星屑のような文章たちの中から、広い意味での文芸評論と呼びうるもの……と、わたし自身が判断した文章を選んで、今回、一冊の本にまとめてみた。
最も古いものは2010年の浅尾大輔論であり、最も新しいものは亀山郁夫『ドストエフスキー 黒の言葉』の書評である(例外として大学院生時代に書いた2001年の『死霊』論)。
おおよそ2010年代の10年間にわたる仕事を結集した……ということになるようだ。どうせならと、できるだけすべての評論的な文章を雑然としたままに寄せ集め、ぶち込み、ごった煮にしてみようと考えた。原稿用紙1200枚(45万字弱)ほどにもなった。文芸評論の氷河期、あるいは絶滅期と言われて久しい凍えるような時代に、こんな破格な、記念碑のような本を出せるとは。望外の幸運であり、喜びである。
せっかくなので、青くさい本心を述べておこう。わたしにとって、批評を書くことは、その時々の己の人生の全身全霊を込めて、他者(作品)と正面から対峙し、対決することであり、魂的に切り合うことであり、そこから生まれる血と汗と涙の結晶体——である。これは比喩でも冗談でもない。ほとんど恥知らずのように、今でもそんな風に考えてしまっているのだった。
この十数年の間、断続的に、依頼に応じて、身体と生活の欲望に駆り立てられて、批評文を持続的に書いてきた。そこにははっきりした方法論もなければ、理論もなかった。昔ながらの、古色蒼然たる印象批評(のようなもの)であるだろう。とはいえ、いわゆる人生や言葉の達人なんてものからもほどとおいから、なかば自嘲ぎみに「竹やり批評」などとも称してきた。対象と素手で対象と取っ組み合う、というほどカッコつくものでさえなかった。
にもかかわらず、『神と革命の文芸批評』等という大げさな書名を選んだのは、今回まとめるにあたって、この10年の自分の批評文≒雑文たちをゆっくりと読み直して、その堆積物の全体をあれこれと見まわして、この10年の自分の主題が「神々」と「革命」という二つの焦点へと集約されていくのを、確かに感じ取ったからである。
過去の自分の仕事に向き合い、それをなかば——あくまでもなかば、ではあるけれども——自分以外の他人が書いたもののように読み、自分の批評文の読者に自分がなって、それらを丹念に熟読してみたのだった。そうした「読み直し」の作業をとおして、わたしにとって文学とは何か、文芸批評とは何か、そのことを少しでも根本的に、原理的に考え直してみようとした。今もはっきりとした答えがあるわけではない。ただ、少しはわかってきた。あるいはわかってきたような気だけはする。
自分にとって、文学とは、神と政治、信仰と革命が交差して縺れ合う場所——そんな場所から人間たちが全身全霊で呼び求めるものであり、飢え乾いて欲動するものである。
とはいえそれもまた大袈裟なこと、崇高で正しいことでは少しもなく、むしろ惨めで卑小なこと、無知で無能な「この自分」の足下を見つめ、それを問い直さざるをえないことであり、問い直されてしまうことなのだとも思った。たとえばわたしはかつて、最初の本の中で「一生フリーターで生きていくとはどういうことか」と問うたのだったが、今現在もまだフリーター≒プロレタリア的な暮らしの不安定さの中にあり、この年齢でフリーターだということは、一生このままだ、ということだろう。依然として、生活と日常の労苦と泥にまみれて足掻き、日銭を稼ぎ、蚯蚓(みみず)のようにのたくる自分を見出だす以外ない。
しかし蚯蚓のように土に根差すこともできない。一生懸命に流す血と汗と泥にすら、薄っぺらいもの、どこかうっすらと嘘っぽいもの、弱々しくて仕方のないもの、「偽善」(有島武郎)的な何かが混じってしまう。そうした根源的な自己疎隔と違和感をどうにもできない。そういう人間が、それにもかかわらず、あるいはそれゆえに、神と革命を乞い求め続けるとは、どういうことか。そうした内省的な言葉と生の記録として、わたしにとっての文学というものはあるらしかった。
それならば、批評とは何だろう——わたしにとって、このわたしにとって。
批評とは。文芸批評とは。
このわたしにとって、批評とは「文学と運動」の交点でものを考え、かつ生きることである。そう信じてきた。ひとりで単独的に作品(テクスト)に対峙することと、協働的で相互批評的な活動の空間を生きること。それらを決して切り離さないままで、その緊張感を消さずに、生き生きと保守し続けること。それがわたしにとっての批評の原点であり、失敗や挫折のあとにいつでもそこに立ち還って全てを始めなおすべき場所、「はじまり」(アレント)の場所なのだった。
協働と言っても、それは狭義の社会運動や組合やアソシエーションであらねばならないとも思わない。拡張家族や動物的な群れであるかもしれない。あるいは、「友よ、友はいない」(アリストテレス)、「敵よ、敵はいない」(ニーチェ)という隣人愛ならぬ遠人愛としての友愛かもしれない(デリダはそれらをすら男性中心主義的であると批判したのだが)。
自己批評(内省)が先か社会批判(外部)が先か、ということではない。重要なのは、むしろそれらの自己/社会、内部/外部という構図の悪循環を「何」が打ち砕くのか、である。垂直的な自己反省でも水平的な社会変革でもなく、その「何」かはいわば斜めから到来する力であり、それこそが自己批評にも社会批判にも回収されえない運動=協同の力である。そのように考えた。内省なき外部の絶対化は享楽的なテクスト主義に堕落し、外部なき内省への耽溺は傲慢な自己欺瞞に閉じていく。そのようにも考えた。
過去のわたし自身の批評的な雑文たちを10年越しに整理し、並べ替え、加筆修正していくことは、その地道な作業を通して「自分とは何者か」を発見してみることだった。いや、自分とは誰なのか、あらためて創造することだった——そう言ってみてもまだ弱いかもしれない。それは、過去の自分の仕事と対峙することで、この自分を新しく産み直すことだった。そういう言い方がしっくりくる。
ただし、テクストを持続的に読むことを通して自らを新しく産み直すこと、それは、「自己発見」などという能動的なものではありえない。それぞれの批評文を即興的に書いたときに、対象のテクスト(あちら)の方からこちらに差し込んできた他者たちの力、複数的で偶然的な力によって乱反射的に刺し貫かれるということだった。それこそが必然的な「宿命」(小林秀雄)なのだ、というのとも少々違う。主体があるから対象があり、対象があるから主体がある、という解釈学的な循環でもない。
一対一(作者と作品)で対峙し真剣勝負をしていたつもりが、無数の先人や先行者たちに見つめられていた、という歴史的な受動性にあらためて気づき直していった。今はただ不思議な驚きを感じる。目の前のテクストを、一冊の本を読むということすら、本当は、このわたし一人の力では、孤独な黙読と精読によっては、もとより不可能だったのだ。それが文芸批評というジャンルを通した、あるいは「言葉」(言の葉)という平凡でありふれたモノを通した歴史と伝統の意味だったのだ。そうした歴史と伝統とは、複数的で、偶然的で、雑然たる「はじまり」の力のことだったのだ。
この本のどこを切り取っても、金太郎アメのように、ほとんど同じ声と顔の断面しか出てこないだろう。ただ、似たようなこと、ほとんど同じことをひたすら反復し、変奏し、自己模倣を持続的に繰り返してきたからこそ、テクストという他者の力に突き動かされて、わたし自身も知らなかった「自分」という未知の、異形の存在が見えてきた。実感された。そんなささやかなことくらいは言えるのかもしれない。
最初は、すべての原稿をシンプルに、時系列でならべてみた。しかしどうにもしっくり来ず、これでは本当の意味での雑多=アナーキー——見えない理念によって個々の小品が星座的に照応していくという非秩序的秩序——とは言えず、ただたんに乱雑なだけのカオス(無秩序)なのではないか……そう感じて、あれこれ悩んで試してみた結果、多少なりとも一冊の本としてのまとまりを付けるために、「文学について」「神について」「政治について」「書評集」という四つの章に分類することになった。
とはいえ繰り返して言えば、この本はやはり、基本的には、べつにどこから読んでもいいし、どこで読むのをやめても別に構わない、そうしたヴァラエティブックになっているはずだと作者としては思う。
本書に収録した原稿たちのうち、多くのものは、語句の修正を行った程度で、大きく手を入れてはいない。ただ、発表から時が経ち、現時点の目ではそれなりの改稿が必要と感じられたものについては、手を入れた(加藤智大論、村上春樹論、スティーヴン・キング論など)。明らかな事実誤認があり、ブロックごと消した部分のある原稿もある(「ロスジェネの水子たち」)。簡単な外科手術によっては手の施しようがないと感じられたものについては、本書への収録を断念した(「長渕剛と三島由紀夫——その日本浪曼派的な命脈」など)。
初出一覧に「未発表原稿」とあるものの多くは、かつて書いてみたものの、発表の場がなかったか、そのまま放置していたものである。必要に応じて、各原稿の「後記」に簡単に事情がしるしてある。
わたしは本書を自分にとっての「第一文芸評論集」として刊行したいと思った。学生時代はもともと文芸批評、特に日本の近現代の文芸批評を学びの原点、はじまりの場所としてきたにもかかわらず、これまでに文芸批評の本を出すことができないままできた。
わたしはこれまで、「批評家」を肩書にしてきたが、「文芸批評家」を名乗る資格はない、と考えてきた。広義の批評よりも狭義の文芸批評の方が重要だという話ではもちろんない。どうでもいいような微妙な違いにすぎないのだが、わたしにはこの微細な違いがとても重要であり、それを踏み越えるには困難な一歩の踏み出し(踏み外し?)が必要だった。
本書は対象としては映画や歌(詩)などを雑多にふくんでいるが、一貫して文芸批評の精神によって書かれている。通読しながら、やはりこれは文芸批評の本なのだ、と自分でも驚いた。だから書名に「文芸批評」という言葉を冠した。この年齢で、今更ながらに、やっと出発点に立ったばかりの初心者の、「アマチュア」や「素人」の、あるいは「練習生」の気持ちである。
この本は、わたしにとって初めての、文芸批評の本である。
(後略)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
