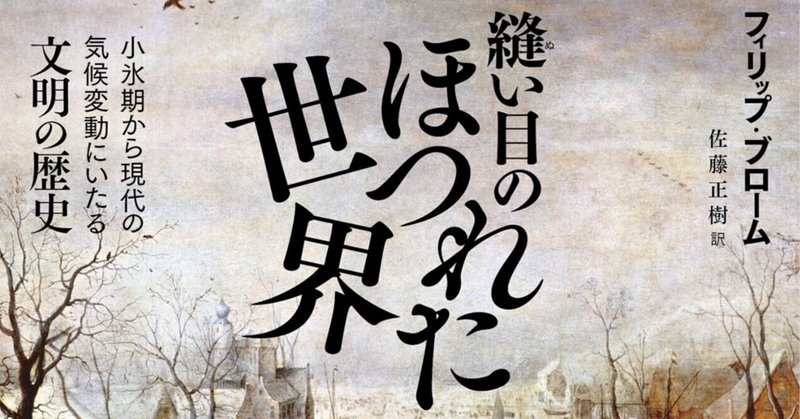
フィリップ・ブローム『縫い目のほつれた世界』より「プロローグ」を一部公開!
2024年4月刊行の新刊、フィリップ・ブローム著/佐藤正樹訳『縫い目のほつれた世界──小氷期から現代の気候変動にいたる文明の歴史』より、「プロローグ」の一部を公開いたします。
フィリップ・ブローム氏はドイツの人気作家・歴史家・ジャーナリストです。その著書の多くがベストセラーとなり、各国で翻訳されています。
2021年刊行の翻訳書『あるヴァイオリンの旅路──移民たちのヨーロッパ文化史』(佐藤正樹訳、法政大学出版局)は、出所不明のヴァイオリンの作者を探す旅というミステリー仕立ての語り口でヨーロッパ300年の歴史を描き、各紙誌の書評で話題を呼びました。
本書のテーマは「小氷期」、16世紀後半から17世紀にかけて世界を覆い尽くした大寒波です。気温の低下は飢饉と疫病を蔓延させ、戦争を引き起こしました。しかし、生き延びるための人びとの創意工夫はやがて技術と社会の革新に結実し、凍える大地からやがて近代の扉を開く新しい文化・思想が開花したのです。気候変動がいかに社会を刷新するか。小氷期下の人びとの営みを学ぶことは、現代の環境問題を考えることにもつながるでしょう。
*転載にあたり一部のふりがな、正字表記、図版を省略し、本書収録のモノクロ図版をカラー版に差し替えております。本書にカラー図版は収録されておりません。
プロローグ──冬景色

1608年頃、アムステルダム国立美術館蔵、パブリック・ドメイン
いかにもうれしそうにみえる。氷上を勝手知ったるわが家よろしくと動いている。世界はぴかぴかに磨き上げられた舞踏場だといわんばかりに、スケートに興ずる者がいる、馬橇に乗る者もある。小人数で談笑する様子もみえる。裕福な殿方はマントを片方落とし〔訳注1〕、婦人方はレースの縁取りをした帽子や鬘を着けている。庶民は短い上着だ。冷えた手足を温める焚き火は見あたらない。凍えている様子もなさそうだ。
冷気のなかを所狭しと活発に動きまわる人々の様子にはつい見とれてしまう。個々の場面はどれ一つとして同じものがなく、そこへ風景が溶け込んでいく。ここには村人がそれぞれの暮らしぶりに応じて余すところなく活写される──干し草の山での媾曳(あいびき)(男同士だろうか)から始まり、壊れた舟から突き出た剥き出しの尻まで、それからもう一艘、持ち主が柳の根元にしゃがみこんでいる舟から始まり、前景の子どもを連れた母親、ゴルフに興じる男たち、刈った葦の大きな束を担ぐ男、そうして手に手をとって氷上を滑る若い男女にいたるまで。女がジョッキを傾けながらわたしたちのほうへ近づいてくる。こちらに顔を向ける数少ない人物の一人だ。ほとんどの村人は鋼の刃をはかせたスケート靴で観る者から遠ざかり、地平線のかなたを目ざして滑っていく。ほんのおぼろげに素描してあるだけの未来に向かって。

画面中央やや右寄りに金糸の刺繍をほどこした高価な着衣の粋な人たちが集まっている。女性は骨でふんわりふくらましたスカートと盛り上げた鬘を着用し、男性はダチョウの羽根を帽子の飾りにしている。鼠色の服の物乞いは同情をひきたげだが、見向きもされない。どこかの村の氷上で、馬車もお付きの者もなしに何をやっているのだろう。ここまでどうやって来たのか。いや、そもそもここにいる人たちは氷の上で何をしているのだろう。とくに縁日でもなさそうだ。クリスマスや謝肉祭でもない、日曜日でもない──教会は陰気に、人気もなく背後に控えている。

この全景は見れば見るほどわけがわからなくなる。一見して写生だと思われたものが、たちまち寓意に転ずる。氷上の群衆、金持ちと貧乏人、男と女、子どもと年寄り、主人と奉公人、凍てつく寒さにそんな区別もどこへやら、しかも皆がみな、そんな寒さなど我関せずの風情である。ただ左手前の獣の死骸だけが、死もまたのどかな田舎の情景にきまって口を挟む条理を暗示する。その横に仕掛けられた古い戸板の鳥の罠は、この屈託のない楽しみごとがたちまち雲散霧消しかねないことを教える。その手前にころがっている籠形の蜜蜂の巣箱は、満ち足りた夏の日々と色とりどりの花との名残である。箱庭めいたこのあわただしい世界のはるか高く、中ほどに一羽の鳥が浮かんでいるが、それは羽ばたきつつしだいに空高くかなたへ消えていくようにみえる。ありふれた鳥類の一つであろうか、それとも守護の聖霊かなにかの最後の見納めなのだろうか。
この風景画を描いた人物、ヘンドリク・アーフェルカンプ(一五八五─一六三四年)は冬の情景を得意とした。一年中アムステルダムの、後年はカンペンのアトリエにこもり、ひたすら冬景色を描いた。絵の世界では寒さなどこれっぽっちも感じぬふうに打ち興ずる陽気な人物たちは、画家その人の憧憬の表現である。みずからは聾唖者で、母と一緒に引きこもりの生活を送り、母の死から何カ月もしないで世を去った。幸せそうな世の賑わいを描いたが、それはきまって自分以外の人々の暮らしぶりだった。
あの時代の画家がひとしなみにそうであったように、アーフェルカンプも粗い写生と記憶とを頼りに制作した──そういう事情もはたらいていただろう、この風景画は個々の人物集団と登場者とがたくさん寄せ集められ配置されて一つの全体像へと組み立てられた、そういう作品になっている。そこに表現されたものは、現実ありのままを記録する再現画法として考案されたのではない。ただそれでも、登場するもののうち現実をまるで反映していないものも存在しない。だとすれば、ここで社会の平和と一体感との寓意として、屈託なくはしゃぎまわる人々はまちがいなく画家の空想の産物だとしても、風景そのものまで一から考え出さねばならなかったかというと、そうではない。
絵に記された一六〇八年という年がそれを暗示する。直前の冬は史上もっとも寒い季節の一つだったからだ。ネーデルラントだけのことではない。各地の河川と運河は、アーフェルカンプが寄り集まった大勢の人たちを演出してみせたような氷の舞台へと様変わりしていた。テムズはロンドンの市中まで氷に閉ざされ、そのため氷上に物売りの店が並ぶほどだった。フランス国王アンリ四世はある朝目覚めると髭が凍っていた。葡萄酒は樽の中で凍り、東欧では飛ぶ鳥さえ凍りついて固い地面へ落下した。イタリア、スペインの各地が雪に覆われた。ヨーロッパは氷の国となった。
このような大陸全体にわたる突然の寒冷化は、絵にもはっきりその痕跡をとどめている。十六世紀まで雪は、そもそも描かれることがあったとしても、有名な『ベリー公のいとも美しき時祷書』(一四一二─一四一六年)をはじめとする時祷書の月暦図に見られる程度だった。ところがその後、一五六四年から六五年にかけて厳しい冬が訪れたのをきっかけに、北ヨーロッパの画家は凍てつく寒さと冬そのものを発見した。この年、ピーテル・ブリューゲルは「雪中の猟人」を描いた──これは四季連作の一つにも仕立てられたが、いずれ大作の栄誉に浴することとなる。また、他のキャンバスに三博士礼拝図とベツレヘムの嬰児殺し図を描いた──が、ブリューゲルは空想をたくましくして両図をフランドルの雪景色の中に配したのだった。冬が氷のような冷たい覇権をほしいままにしてヨーロッパを席捲しているあいだに、冬景色はとくにネーデルラントで独自の絵画部門として確立し、十七世紀にはよく知られる名手が輩出した。ヘンドリク・アーフェルカンプもその一人である。

アーフェルカンプの風景画はこの冷たい世界を活写し、いずれそこからどのようなものが生み出されることになるのかを早くも暗示している。氷上の人はみなこの厳寒と闘わねばならない。凍結した運河の広々とした平面上では、人々の見分けがつかない。品(しな)よき殿様がたと三叉の長い銛を持つ貧しい鰻捕り、白毛の馬にひかせた橇と農民の群れ──だれもが等しく同じ寒さに難儀をし、今や新しい生活法を見つけるしかない、命を脅かす事態には新しい発想で立ち向かうしかあるまい、そんな挑戦を受けて立っている。
*
この本のはじめにあるのは、打ち消しようもない現代の課題をはらんだ一個の単純な問いである。もし気候が変化したら、社会の何が変わるのか。大枠となる自然界の条件に変化が生じたとき、その枠内にある文化、情と知との領域に、それはどのような作用を及ぼすのか。長い十七世紀は、気候変動が人間生活のすべての局面に及ぼす影響を探究し、さらにはそれを理解する姿勢を身につけるのにうってつけの時代である。
歴史家が小氷期と名づけ、十七世紀前半に頂点に達した気候史の一時代は、ヨーロッパの人々の暮らしを変えただけではない。一五七〇年から一六八五年にかけて平均気温が摂氏二度ほど下がると、それが海洋の潮の流れをねじ曲げ、気候の循環を乱し、世界中で気象に度を超した妖異をひき起こした。凍てつく寒さと雪、夏の降雹、暴風、数週間単位の長雨や何年も続く旱魃は、中国に破局的な飢餓を、北アメリカ大陸に生命を脅かす冬を、インドに戦慄すべき凶作をもたらした。オスマン帝国は有史以来もっとも過酷な寒さに見舞われた。
この本は話題をヨーロッパにおける小氷期の効果という一点に絞っているが、それには三つの理由がある。第一は、現在の研究水準に照らせば、気候変動が文化に及ぼす効果に関してヨーロッパにはとくに資料が細部までよく整っていること、第二は、日本、中国、あるいはインドの文化史をヨーロッパに匹敵するほど深くひもとくだけの語学力と知識とがわたしには欠けていること、第三は、まさしくこの時代のヨーロッパが、社会、経済、知の世界に革命を体験し、またそこから、一方が他方とどれほど深く結びついているかという問いも生まれてくることである。
〔中略〕
黒死病、ルネサンス、宗教改革、宗教戦争、これらはヨーロッパ社会の発展を杜絶させる惨状を招くか、新しい方向へ導くかした。新しい発明はなかった。中世の温暖期といわゆる小氷期とのあいだの気温の急激な低下といったただ一つの原因から、たちまち因果の法則どおりに導き出せるようなものは何一つないといっていい。しかし気候変動はこの間の過程を速める触媒である一方、その後の大変革をうながし、あるいは強いる、執念深い圧力要因としての側面ももっていた。古い、それまで安定していた構造が破綻したからである。
わずか四世代のうちに一つの世界が変貌を遂げた。神学者が解釈の最高権威として君臨し、医学と科学が古代の遺産を寓意として理解することに終始していた世界、経済全体が穀物の作付けに依存し、太陽が地球を周回し、社会が封建制度として組織され、それをわざわざひっくり返すには及ばないと皆がみな思い込んでいた世界、それが一変して、わたしたちが自分自身のことをそれまでよりもはるかに容易に自分だとわかる世界、歴史を顧みたとき、ものごとの発展にどれほど時間のずれがあり、遅々として進まなかったり不均衡であったりしても、すでに現代の特色を帯びる世界になった。
あとから振り返ると、これらの発展は必然であったかのようにみえる。なぜならもろもろの出来事が因果の連鎖をなして現代につながっているからだ。とはいえ歴史の視点からみると、多くの変化の背後にあらかじめ計画も意図も隠れてはいなかった。これらの変化はまず実験と新しく現れた背景とから生じ、事件の圧力をうけたとき臨機応変にふるまうことで、社会の慣行と理念とに、計画性はなくても影響さえなかったとまではいえない刷新として展開していった。こうした実験の多くは、いや、ことによるとそのほとんどは水泡に帰して跡形もなく消えたか、せいぜい歴史学の脚注にその痕跡をとどめたにすぎないのかもしれない。しかし成果をあげえた実験は、本書でいずれ明らかになるはずだが、今日なおわたしたちの生活に決定的な影響を与えている。
本書の第一部は、一五七〇年ごろヨーロッパに突如発生した気候変動について述べ、それが人間と自然界に直接及ぼした効果を、時代の証言者の視点を活用しながら素描する。あの時代の人たちは寒気の襲来と度重なる荒天に見舞われたとき、それにどう反応し、何を考えていたのか。その原因をどのように自分に納得させ、どのように反応したのか。
十七世紀の初めごろ、この事態を目のあたりにした多くの人は、そのことに自然界がどんな役割を演じているかまではわからないながらも、ヨーロッパが深刻な危機に直面していることをはっきりと悟った。この苦境は農業にとどまらない広汎な変革をうながし、あるいは強要した。本書の第二部が、十七世紀前半の農業、経済、社会制度、軍事、文化の各分野の発展に、また、そのことと、変わってしまった気候および社会の基本条件との多様な関係に取り組むゆえんである。
第三部ではさらに一歩進めて、気候変動に端を発した社会制度の大変革がヨーロッパ人の思考と世界像にどのような効果を及ぼしたのか、その過程を追う。というのも十七世紀の衝撃から新しい知識の領域が開け、とりわけまた自然の観察と考察とを契機として生まれた新しい思想傾向が進展したからだ。
エピローグではいくつかの主題の道筋を束ね、これらを気候、政治、文化に変動が現れた現代という時代に関連させて考察する。わたしたちは十七世紀から、一目でわかるどころでない多くの遺産を受け継いでいる。なかでも、当時ヨーロッパに世界随一の勢力をかなえたある要因は、今日では人類の存在を脅かすものになりつつある。わたしたちも先人のひそみにならい、避けがたいかずかずの大変動とともに生き、それらに適応するべく知恵を絞り、新しい状況を受けて立ち、それらが突然わたしたちに襲いかかってくるまで逃げまわっているのではなく、むしろあえて相手にすることを学ばねばなるまい。
*
アーフェルカンプの何枚かの村の情景に描かれた、うようよと寄り集まる人物は、一種独特のごく狭い世界であり、凍てつく寒さを主題とする一個の絵画部門を構成していた。一五六五年のとくに厳しかった冬の季節に、父ピーテル・ブリューゲルは「雪中の猟人」を描いた。冬景色図は絵画の用語として確立し、市民の家庭でも、ぱちぱちと燃える暖炉の火と好一対をなす心地よい取り合わせとして愛好された。十七世紀をとおしてネーデルラントの相当数の画家が、凍結した川、雪に覆われた木と家、そこに不思議と緊張のほぐれたのんきな様子の小さい登場人物たち、陽気な祭を描いたが、そこには凍てつく寒さなどどこ吹く風といった風情が感じられた。
〔訳注1〕マントを片方の肩にだけ掛けてもう一方の腕を出し、威風を誇示する風俗。

フィリップ・ブローム 著/佐藤正樹 訳
縫い目のほつれた世界──小氷期から現代の気候変動にいたる文明の歴史
四六判並製・414頁・定価(本体3,600円+税)
ISBN 978-4-588-35237-9
2024年4月25日刊行
詳しくは以下よりどうぞ。

好評既刊書
フィリップ・ブローム 著/佐藤正樹 訳
あるヴァイオリンの旅路──移民たちのヨーロッパ文化史
四六判並製・366頁・定価(本体3,400円+税)
ISBN 978-4-588-35235-5
2021年2月25日刊行
詳しくは以下よりどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
