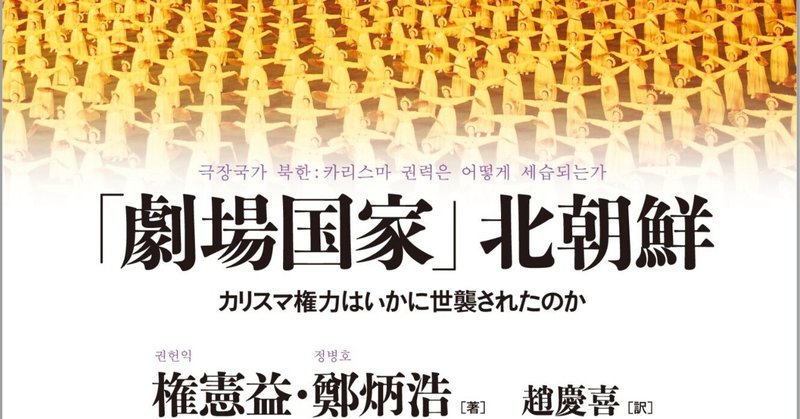
権憲益・鄭炳浩『「劇場国家」北朝鮮──カリスマ権力はいかに世襲されたのか』訳者あとがき(趙慶喜)
訳者あとがき
本書は、Heonik Kwon and Byung-Ho Chung, North Korea: Beyond Charismatic Politics (Rowman & Littlefield Publishers, 2012)の全訳である。翻訳に際しては、著者自身による本書の韓国語版、권헌익・정병호『극장국가 북한: 카리스마 권력은 어떻게 세습되는가』(창비, 2013) も合わせて参照した。
本書の韓国語版は刊行当初韓国で大きな話題となり、メディアでもたびたび取り上げられた。その主な理由はおそらく、(著者たちが何度か語っているように)「劇場国家」という言葉のインパクトにあるだろうが、もちろんそれだけではない。韓国で北朝鮮を扱った学術書は主に政治・外交の分野で見られたのに対し、本書は歴史学と社会科学を大胆に横断し、さらに文化人類学的アプローチで北朝鮮の政治文化を魅力的に再構成した。マクロな国際政治とミクロな人間の行為を交差させながら、北朝鮮の歴史と現実を立体的に描きあげたという点で特異な本であったのは間違いない。このようなユニークさは、何よりも本書が二人の人類学者の協働作業の産物であるという事実からきていると思う。
ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジのシニアリサーチフェローである権憲益は、旧ソ連のシベリアやベトナムの農村、また韓国の済州島などでフィールド調査を続けてきた。朝鮮戦争やベトナム戦争での虐殺の悲劇を、上からの冷戦史ではなく、犠牲者をめぐる家族や親族の記憶、あるいは儀礼や追悼文化などのレベルで解明してきた。After the Massacre: Commemoration and Consolation in Ha My and My Lai (2006)は人類学界で有名なクリフォード・ギアツ賞を受賞し、Ghosts of War in Vietnam (2008)はジョージ・カヒン賞を受賞した。彼はまた、グローバル冷戦史やポスト社会主義の歴史を研究するなかで、冷戦がいかに西洋中心的に語られてきたのかを繰り返し論じてきた。アジアの民衆にとって冷戦とは何かを問いつつ、世界史を多元的に再構成することに寄与してきた稀有な研究者である。
他方で、漢陽大学名誉教授の鄭炳浩は、ひとつのジャンルでは括れないほど多岐にわたる研究活動をおこなってきた。日本文化や共同保育の専門家であった彼は、1990年代末から人道支援活動の一環として北朝鮮を何度も訪問し、中国国境付近における飢饉の被害状況を研究するとともに、救護活動家としても活発に動いてきた。脱北青少年のための教育機関である「ハナトゥル学校」の校長をつとめるなど、脱北者支援にも尽力した。2022年に青土社から翻訳出版された『人類学者がのぞいた北朝鮮:苦難と微笑みの国』には、これまでの研究と実践から生まれた知見が詰まっている。さらに日本の仲間たちと共に北海道の朱鞠内で1997年に始めた朝鮮人労働者の遺骨発掘プロジェクトは、その後日本、韓国、在日の若者たちが大勢参加する東アジア共同ワークショップへと発展していった。鄭の研究の基底にあるのは、移住労働者や難民など疏外された人々への関心と連帯、そしてその子供たちの教育の問題である。それを具体的な出会いの場につなげていく優れた実践力を備えた研究者である。
このような異なるキャリアを持つ著者たちであるが、それぞれが欧米で学び活動してきたディアスポラの知識人であるという共通点もある。朝鮮半島やアジアの歴史的現実のなかに凝固した分断や冷戦という問題を、下からの視点で練り直していくという点では大きく通じる部分があったのかもしれない。こうしてポスト社会主義体制についての比較論的研究を行ってきた権憲益と、北朝鮮についての実証的な知識を蓄積してきた鄭炳浩が、ある種の危機意識を共有するなかで生まれたのが本書である。
著者たちは西洋的な冷戦史の枠組みに内在している朝鮮半島の歴史をめぐる知の歪みに対して、とりわけアジアの社会主義国という二重のバイアスを伴った北朝鮮認識に対して、別のより豊かな枠組みを提示することを大きな課題としていたと思われる。それはつまり、北朝鮮を例外的で奇妙な国家として特殊化するのではなく、社会主義の歴史における一つのパターンとして、理解可能なものとして理論化する試みであった。本書によれば、北朝鮮という国家はカリスマ権力の永続化という不可能な問題を克服するために、公共芸術や建築物などのあらゆる象徴を通して演出され、そして同時に人民の儀礼的な参与を引き出していった。劇場国家という概念化は、北朝鮮を単に硬直した独裁体制として見るのではなく、国家と人民の間の相互的でパフォーマティブなものとして再構成するのである。
本書の枠組みがマックス・ウェーバーとクリフォード・ギアツの理論的遺産に多くを負っているのは明らかだが、社会科学や人類学の概念を演繹的に当てはめた議論と一線を画すのは、北朝鮮の現代史に対する歴史学的成果を丁寧に取り入れているためである。もっとも、前近代的な政治体制の分析から生まれた劇場国家パラダイムを、脱植民地化と冷戦が同時に進行したポストコロニアル地域の激動の現代史に当てはめた本書は、歴史学的には論争的であるかもしれない。ただ、儀礼やシンボル、記憶やメタファーなどが過剰に動員されてきた北朝鮮の政治を理解するためには、それが封建秩序への回帰などではなく、きわめて現代的な政治の発現であるという見方がまず前提となるべきであろう。
北朝鮮における政治の過剰を考えるうえで、本書で繰り返し述べられているのは、北朝鮮がポストコロニアル国家であるという、ある意味では当たり前の事実である。朝鮮戦争や分断、そして韓国の国家形成が脱植民地化の挫折のプロセスとしてあったように、北朝鮮の社会主義革命の現代史もまた帝国主義や植民地支配への抵抗の経験と切り離せない。本書では、金日成の満洲パルチザン闘争の記憶が北朝鮮のアイデンティティの核となる過程を重層的にとらえ、繰り返し記述している。もちろん、それが目的論的な権力になっていった過程についても批判的にとらえている。北朝鮮ではポストコロニアルな闘争が今日まで続いているという本書の観点は、しかしながら、ほとんど考慮されることがなかった。日本の言論状況については言うに及ばない。西洋的近代の規範から逸脱した異常な王朝国家と見なすことで、私たちは知識体系から北朝鮮を排除してしまっている。ポストコロニアリズムを欧米から学んだ私たちは、この言葉を自らの重なり合う歴史に十分に内在させることができずにいる。植民地支配の旧宗主国であり、(にもかかわらず)アジア冷戦を他人事のように眺めてきた日本において、本書のこうした視座が多くの知的刺激をもたらすことを期待している。
ここ十数年の間に北朝鮮は政権交代とともに多くの変化を経験している。本書で主に扱っている金正日時代の先軍政治の方針は弱まったが、劇場国家としての性格やポストコロニアル国家としてのアイデンティティは、また新たなステージを迎えているといえる。ロシア・ウクライナ戦争が長期化するなかで、金正恩自ら新冷戦を語りロシアへの支持を強めつつあるが、こうした危機の中でこそ善悪二元論に陥らないための歴史への視座が求められている。
〔中略〕
翻訳の始まりから終わりまで頭をもたげたのは、北朝鮮という呼称の問題であった。本書は朝鮮民主主義人民共和国の国名を、現在の日本でもっとも通用している用法にならって「北朝鮮」と表記している。正式名称が長いために略すのだとしたら、本来は「朝鮮」と呼ぶべきである。北朝鮮の人々も自らの国を「朝鮮」や「共和国」と呼んでいるため、「北朝鮮」は(そして韓国で使われている「北韓」もまた)一方的で政治的な呼称である。ここには朝鮮民主主義人民共和国を正統な国家として承認していない現状や、日韓関係と日朝関係にある非対称性が反映されている。さらに、2002年の日朝会談における拉致問題の発覚と国交正常化交渉の中断によって、日本の言論は北朝鮮という呼称を全面的に解禁し、この呼称に敵対と憎悪の情動を重ねることを容認してきた。本書はこうした日本の文脈に省察を迫るものであるが、他方で本書もまた、もはや別の呼称で語ることが困難になってしまった日本社会のリアリティを前提としている。その意味で北朝鮮という呼称を用いた翻訳には、ある種の自己矛盾があると思う。こうした点について読者の方々が受け止め、批評してくれるならばとても幸いである。
〔後略〕
2023年11月
趙慶喜
注[1] 脱北者は韓国の公式用語で「北韓離脱住民」と呼ばれる。彼らはまず韓国入国後に統一部が運営する「ハナ院」と呼ばれる施設で教育や職業訓練を受けることになる。ハナトゥル学校はこのハナ院のなかの青少年教育機関である。ハナ、トゥルとは、一つ、二つの意味である。民族が一つになることにこだわる統一部の方針に対して、二つでもいいという意味が込められている。
権憲益・鄭炳浩『「劇場国家」北朝鮮──カリスマ権力はいかに世襲されたのか』
四六判上製・334頁・定価(本体3,400円+税)
ISBN 978-4-588-60372-3 C1322
詳しくは以下よりどうぞ
https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-60372-3.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
