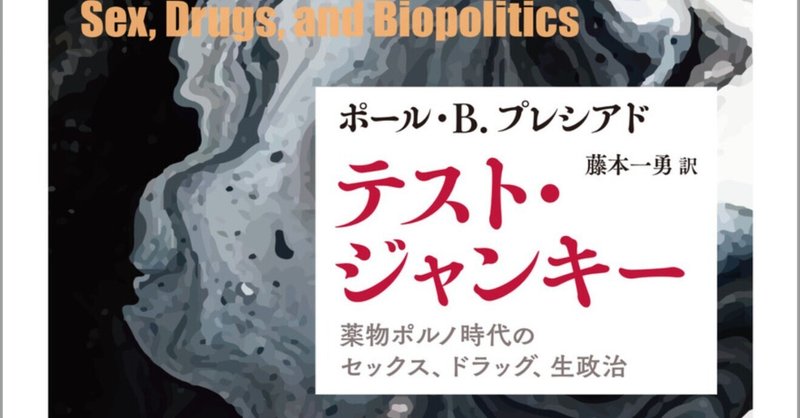
ポール・B.プレシアド 『テスト・ジャンキー』 訳者あとがき(藤本一勇)
3冊目の邦訳書のあとがきを公開します!
『テスト・ジャンキー』は、ベアトリスという女性名で育てられた著者自身が、テストステロンの服用を通じてトランス男性となり、ポールとしての自己を獲得していく体験の過程をさまざまな角度から思索し、記述した稀有な書物。それはまた、哲学の書でありながら、同時にかけがえのない友愛の記録であり、性愛の記録でもあります。
いま・ここで、セクシュアリティの問題に苦しんでいる人たちの多くが、プレシアドのマニフェストをそのまま受け入れられるとは思いません。数十年間にもおよぶ、欧米文化圏での膨大な議論と運動の積み重ねの上で書かれている書物だからです。けれども、相当に厳密かつ豊かな思考によって、日本でも〈トランスジェンダー問題〉と呼ばれるものをめぐっての突破口の一つが開かれてくれることを、望みたいと思います。
《現代資本主義世界を統治する薬物ポルノ体制とは何か? トランス男性にしてフーコーやバトラー、ハラウェイ、ドゥルーズ=ガタリやデリダらの遺産を引き継ぐ著者が、テストステロンによる性別移行の実践と、補綴技術を介した性愛の限りない変容、そして〈悦びの力〉を肯定する衝撃のテクスト。差別を受けてきた性的実存の尊厳を根底から擁護する、新たなカウンター薬物ポルノ革命到来のために。》
https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-01162-7.html
訳者あとがき
本書は、Paul B. Preciado, Testo Junkie : Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era, translated from the French by Bruce Benderson, Feminist Press at the City University of New York, 2013の全訳である。元になったスペイン語版、フランス語版はともに2008年に出版されている(フランス語訳版は著者プレシアド本人が訳している)。プレシアドの邦訳書としては、『カウンターセックス宣言』、『あなたがたに話す私はモンスター』に次いで3冊目であるが、本書『テスト・ジャンキー』がプレシアドの主著と言ってよい。とくに本書は「薬物ポルノ権力」という概念を打ち出し、フーコーが精密に分析した近代の「規律訓練権力」、ドゥルーズが指摘した「コントロール権力」に続く(前二者をさらに深化させた)現代と未来の新たな権力システムとして提示。その成立の政治的・歴史的なプロセスと理論的なメカニズムを解明した。その意味で本書は、2000年に『カウンターセックス宣言』を出版して注目を集めたプレシアドが、彼/彼女の哲学の内実を明らかにし、トランスセクシュアルの思想家として自己を確立し、21世紀の、新世紀の哲学者の一人として世界に躍り出た重要な本と言ってよい。本書の翻訳が出版から15年も遅れた(『カウンターセックス宣言』にいたっては20年以上も遅れた)ことは、人文社会学系アカデミズムの「怠慢」もあるが、日本という国・社会の、性問題に関する(人口に膾炙した言葉で言えば、LGBTQI+問題一般に関する)閉鎖的な体質の問題も大きいだろう。
薬物ポルノ体制
薬物ポルノ体制とは何か?この考察の土台にはフーコーによる「生政治」の「系譜学」の作業がある。フーコーは、西洋における権力体制の変化を、中世までの見せしめ刑を中心とした処罰権力(神権に代表されるようなトップダウン方式の「至高権力」)から、近代において、むしろ人々の日常的な生(生活)を「草の根」レベルから作り出し(構築、工作し)、「生産」していくミクロな政治・社会権力への変化として分析し、それを「規律訓練(discipline)」権力と呼んだ。それは単純に脅したり、抑圧・弾圧し、殺すだけの権力ではなく、むしろ人々により良い生のあり方を提案し、教育し、選び取らせることで、人々の生を創造・創出するというかたちの支配である。その場合、権力の肝は、人々にその支配に「積極的」に「参加」させ、支配的な価値や通念(社会常識)の確立・規律に向けて「努力」・「訓練(自己鍛錬)」する「立派な」主体を社会に生み出す(生産する)ことである。こうして主体はみずからの生の力(プレシアドの用語で言えば〈悦びの力〉)を訓育・飼育された従属主体となる。フーコーは、こうした〈主体的に従属する主体〉こそが、近代が称揚した主体性や近代的個人の真の姿であると喝破し、権力によるこの飼いならしの具体的かつ普遍的な装置として「パノプティコン」というシステムを分析した。
政治・経済・哲学における近代主義を代表する思想である「功利主義」の代表者ジェレミー・ベンサムが考案したとされる「パノプティコン」システムを、フーコーは近代社会全般の特徴(Idea)とみなし、この「生政治」的な管理体制という問題意識から、近代を「大監禁時代」とも呼んだ。この環境では、発展した近代的な知(医学、生理学、心理学、教育学、運動学・体育学、統計学、建築学、等々)、また拡大するマスメディア(当時は活字中心だが)や言論(言説)などを使って、ある特定の(近代的な)価値観、行動パターンや心理状態、認識論(物事の認識フレーム)、身体のあり方(セクシュアリティも含む)が刷り込まれ、人々はそのように工作された環境で得られる「利益」(政治的であれ経済的であれ社会的であれ文化的であれ)のために環境に順応し、そのフィールドで輝くプレーヤー、ゲーマーになろうと努めるのである。
しかしフーコーが批判的に分析した規律訓練権力は、まだそのメインターゲットを人々の意識や思考(考え方)や意志やモラルに(広く意識に)置いていた。知 (頭)、心、身体のなかでも前二者(とくに知)を重視し、その意味では「教養」的であり、「教育」に力を入れていた(e.g. Bildungsroman)。しかし、ドゥルーズが指摘したように、1970年代以降(とくに1980年代以降——すなわち、かつて「ポストモダン」時代と呼ばれたこともある時代以降)、生政治の支配権力のあり方・戦略に変化が生じる。高度に発達した情報や記号、イメージを使い、私たちの日常のさらに微細な環境を、単に物質レベルだけでなく、情報・通信といった非物質レベルで工作し、人間の感覚や思考や行為を操作する環境管理型あるいは環境工作型権力が登場する。ドゥルーズはこれを「コントロール権力」と呼んだ。このタイプの生権力のターゲットは、もはや人々の主観性(知識、思考、意識、意志)そのものではなく、それを取り巻く私たちが生きる環境、その「生態系」である。同様のことをわかりやすく指摘したアメリカの憲法学者ローレンス・レッシグによれば、人類社会をコントロールするには、伝統的に三つの方法があった。モラル的(道徳的)管理、法的管理、経済的管理である。飲酒運転の例で言えば、飲酒運転を封じるのに、まず運転者(人間)の道徳(心と社会のモラル)に訴え、飲酒運転は「悪い」ことだからやめなさい、と言う。しかし人間の心モラルは弱い。「悪い」とわかっていても飲んで運転してしまう。次に法律で禁じる。道路交通法で飲酒運転を禁じ、違反した場合は、法的な罰則を科す。しかし運転免許を取得した人なら、誰でも道交法で飲酒運転が禁じられており、違反すれば処罰されることは「知」っている(そもそも、それを受け入れなければ免許試験に通らない)。法律や罰則を知っていたって違反する人は違反する。それから経済的な罰則を科す。飲酒運転で罰金を課し、経済損失によって行動規制する。あるいはもっとラディカルな事態として、飲酒運転で人を殺してしまったら、その賠償で一生棒に振るような金銭的損失があると「脅して」管理する。しかしそれでも、そういう場合のために保険があるのだし、経済損失が気にならない金持ちもいるかもしれない。いずれにせよ、以上の伝統的な行動管理の手法は、どれも効果は限定的であり、完璧ではない。そこに第四の管理方式が現れる。飲酒をした人が車に乗り込んできたら、運転席のどこかに酒量センサーを取り付けておき、一定以上のアルコールが検知されたら、コンピューター制御してエンジンがかからなくしてしまうのだ。車が動かせないのだから事故(出来事)は起こらない。完璧な防衛策である。レッシグはこの新しい第四の管理を「アーキテクチャ権力」と呼んだ。
ここで言うアーキテクチャとは、コンピューター用語で言う、ハードウェア・ソフトウェア両面におけるコンピューターの構成(コンピューター自体の環境構成)のことであるが、それが、人間の住環境を指す建築あるいは建築物になるのである。レッシグが指摘しているのは、まさしくコンピューターが私たちの身の回りの日常に埋め込まれ、ネットワークを形成しているユビキタス社会、人間の生活環境(大げさに言えば、生態系)がコンピューター化した時代の、新たな権力体制である。伝統的な三つの管理手法は、ほぼフーコーが分析したディシプリン型(規律訓練型)権力にあたる。その基本特徴は、知や社会通念・道徳、具体的な暴力や制度などを通して人間に外部から働きかけ(プレシアドの言葉で言えば、いまだ「外科整形的」)、人間の内面を作り上げていく点にあり、その意味では、まだ人間の主観性=主体性(subjectivity)、意識=良心・良識(conscience)、意志や理性をターゲットにし、その観点では(皮肉にも)、まだ人間をあてにして(信頼して)いる。しかし、ドゥルーズの言うコントロール型権力、レッシグの言うアーキテクチャ型権力は、もはや人間(とその意識・良心・良識、思考、意志、理性)などあてにせず、相手にしない。人間が身を置く(生きる)環境そのものを(おもにコンピューターによって)創作・操作することによって、無意識のうちに(知らないうちに)人間に働きかけて管理するのである。文字どおりポストヒューマン的あるいはトランスヒューマン的な管理と言えるだろう。
プレシアドの描く薬物ポルノ権力はこの延長線上、さらなるラディカル化のうちにある。人間の意識をもはや相手にせず(したがって捻じれ現象として、むしろ人々は、内面の「自由」、自由放任されていると感じる)、脳神経のように地球上に張り巡らされた情報ネットワーク(マクルーハンの「グローバル・ヴィレッジ」状態)によるリアリティ工作環境(これが薬物ポルノ体制の「ポルノ」的な側面であり、これは将来アダルトVRなどの普及によってさらに進化=深化してゆくだろう)のなかで、さらに加えて、私たちの身体をもっと直接的に薬物によって工作・操作する権力である。プレシアドが論じているさまざまなホルモン剤や麻薬は少々ラディカルな例だが、もっと身近なサプリメント(デリダ哲学のキー概念の一つでもある)や栄養剤、風邪薬、予防接種などを考えれば、子どもの頃からなんらかの薬の世話になっていない人はいないだろう。またコロナ以前に書かれた本なので触れられてはいないが、コロナワクチンのことを考えれば、一つの同じ薬学製品がこれだけ多くの人間の身体に投与され、同化吸収され、受肉化したのは人類史上初のことであり、画期的かつ驚異的なことである。キリスト教の聖体拝領の理想はコロナワクチンによって実現した(実装された)のかもしれない。
プレシアドは、フーコーが切り開いた生政治、生権力の問題をアップ・トゥ・デートし、ディシプリン体制から薬物ポルノ体制への「系譜学」を描く。本書の醍醐味の一つは、この系譜学が提示する権力変容のきわめて具体的な資料と事例の群れにある。近代化のメカニズムの一環として、中世の魔女狩りから近代薬学の誕生、世界大戦における薬物実験、薬品産業の発展とその植民地主義など、薬物権力の歴史的変遷を掘り起こす作業にはきわめて教えられるところが多く(広く見れば、フーコーがおこなった「医学権力」の批判的系譜学の一環と言える)、またそれがセクシュアリティの統制・管理と根本的につながっていることを明らかにしている点も画期的である(これも晩年『性の歴史』に取り組んだフーコーの衣鉢を継ぐものである)。そして(この点が重要だが)、さらにこの薬物ポルノ系譜学・薬物ポルノ考古学(プレシアドならば、薬物ポルノ哲学と言うだろう)が、その先に描き出すのは、もとはセックスやセクシュアリティやジェンダーを管理【コントロール】し操作【オペレート】(手術)し経営・運営【マネージ】し統治【ガバナンス】するために用いられた薬物が、もとの文脈や環境から遊離して、トランスする身体やトランスする世界を創出する力になっていく未来(モンスターな未来)である。トランス男性哲学者としてのプレシアドにとってのテストステロン(本書のタイトルの「テスト」)とは、この権力変容、権力奪取、権力自体の方向転換【ターン】=革命【レヴォリューション】のトリガーの一つなのだ。敵の武器を再利用=流用=横領(reappropriation)し、敵を打倒する武器に作り変えること。これは労働者階級についてマルクスが描いた戦略であると同時に、デリダの脱構築の戦略でもある。
自伝【オートバイオグラフィ】と哲学——自己理論【オート・セオリー】
本書は「薬物ポルノ権力」の歴史とメカニズムを解明した点で理論的・哲学的な大きな貢献であるが、それだけに目を奪われては一面的だ。本書の最大の魅力は、理論パートと伝記パートとのたえざる交差関係、陥入関係にある。本書は薬物ポルノを論じる理論的な章とプレシアドの自伝的と想像される文学的な章とが交互に展開される構成になっている。この二つのパートの交錯=交接、インタラクションこそが、この本の最も重要な存在様態である。ドゥルーズの多数多様体(le multiple)、デリダの余白(la marge)や代補(le supplément)のように、散種するテクストがハイブリッド体として自転しているのだ。理論パートが自伝パートを意味づけようとしてはその残余をあらわにし、自伝パートは理論パートをたえず逃れ去っては理論パートにその素材を与える。理論が頭でっかちにみずからのロジックを伝記パートに押しつけ、一方的に意味づけ、解釈し、伝記の真理を「啓蒙」しようというのではない。理論はみずからが作り出した内容を、たえず伝記に描かれた出来事によって問い直され、検証されなおす。また実践的な伝記は、理論化できない「現実」とか「本当の私」とか「語りえぬもの」を主張するのではなく、みずからを用いて理論構築に参与し、放っておいたら時間・時代によって押し流され失われてしまうものを理論によって自己確証する(自己モルモット原理による自己実験)。どちらかが優位にあるのではなく、合わせ鏡のように互いを反射させては分散してゆく。その相乗効果のなかで理論と実践が融合し、両者は多様体として実存するのだ。
こうした理論と自伝の相互書き込み(相互エクリチュール)を『フェミニスト実践としての自己理論(Autotheory as Feminist Practice)』(The MIT Press, 2021)の著者ローレン・フルニエ(Lauren Fournier)は「自【オート】‐伝【バイオグラフィ】」ならぬ「自己【オート】‐理論【セオリー】」と呼ぶ。「理論(セオリー)」は語源的に「観照(テオリア)」に由来するので、プラトン以来の西洋形而上学の視覚中心主義(触覚蔑視、身体蔑視)に与する恐れがなきにしもあらずの用語ではあるが、生の書き込み(バイオグラフィ)を自己を見つめることと協働【コーオペレート】させようというプレシアドの意図を表す可能な形容の一つではある。自伝でありながら同時に哲学や社会理論でもある(あるいは自伝がそのまま哲学である)ような作品は、たしかに21世紀のフェミニズム作品の特徴である。フルニエはその代表として、まさにプレシアドの『テスト・ジャンキー』(2008年)やマギー・ネルソンの『アルゴノーツ』(2015年)などを挙げ、理論がプロットの本質的な一部となり、作者が創造した物語世界の原動力となる作品と定義しているが、であればすでにボーヴォワールの『第二の性』(1949年)やモニク・ウィティグの『女ゲリラたち』(1969年)などもそうだと言えるだろう。なぜ伝記的な物語が理論となり哲学的思索になるのかと言えば、まさにフェミニズムが掲げる「個人的なものは政治的である」という標語が示すとおり、セクシュアリティに代表される個人的な事柄は決して個人の身体や心だけの問題ではなく、社会的に構築された工作物や工作権力の問題そのものであり、社会関係や社会権力の交差点だからである。個人的なものは個人的ではなく、個人が望もうが望まなかろうが、つねにすでに「公的【パブリック】」なものなのだ。私たち個々の身体は、保守政治や全体主義で言われるのとは別の意味で、捻じれたかたちで「公共的身体」であり共産的身体である。社会のメカニズムや権力関係によって生産された「個人的なもの」を個人の本質や心(気構えやモラル)の問題にしてはならず、さらには個人の責任に帰してはならない。この点は、ジェンダーだけではなく、人種問題や経済格差問題にも通じており、その観点では、たとえばフランツ・ファノンの『黒い皮膚、白い仮面』(1952年)やクレオール文学の多くの作品も「自己‐理論」の書と言えるかもしれない。
しかしさらに振り返れば、この自伝的なものに潜む哲学的思考、自伝的なものと哲学的なものとの交接は、ある意味で伝統的とも言える。たとえば、西洋の告白文化、告白文学の基礎を築き、キリスト教世界の宗教経験とその物語を規定したとも言える、アウグスティヌスの『告白』は、みずからの放蕩生活から神への信仰(=愛)への「回心」を語りつつ、その語りが同時にキリスト教の哲学思考そのものを生み出した。プレシアドがニューヨークでデリダのもとで博士論文を書こうとしていたときの主題が、まさしくアウグスティヌスであったことは、『テスト・ジャンキー』における「自己‐理論」的な語りを考えた場合、意味深長である(アウグスティヌスの「回心」を、一種のトランスセクシュアルな「転回」として解釈しようとするプレシアドの発想には驚かされるが)。また近代の入口において、その後の個人主義思想への道を切り拓いたルソーの『告白』や『孤独な散歩者の夢想』も、自伝的な語りが哲学へ変換されている良い例だろう。さらに聖書におけるキリストの伝記的な物語(キリストにまつわる証言集)がもつ思想的・哲学的な深さを考えてもよい。実存の語りの強度が政治・社会問題を抉り出し、思考を刺激し、哲学的強度を獲得してゆくプロセスは、ある種の普遍性をもっているのではないだろうか。
いずれにせよ、自己‐理論では、理論化された個人的な逸話や身体化された行為が、哲学の断片と組み合わさり、そのモンタージュ効果のなかから、ジェンダー、政治、学問、文化を領域横断的に貫通する強力なテクストが織り上げられる。本書『テスト・ジャンキー』はまさにその一つの可能性を提示した作品と言えるだろう。みんな、もっと自分の物語を、自分の歴史=来歴を語ってよいのだ。もちろん、単なる自己満足や自己主張、慰めや承認をもらったり、同情や褒めてもらう(「いいね」をもらう)ためではなく、自分の物語は自分だけの事柄ではなく、社会的に共有可能で共有すべき社会構造の問題や現場であることを示し、社会化することによって、そうしよう。重要なのは、まずは問題、問いかけ、応答をシェアすることである。それを「強い」何かに掌握されたり預けてはならない(その強力・強大なものが、神であれ、国家であれ、強いAIであれ)。「弱さ」(脆弱性)が世界のデフォルトであり、世界の存在そのものである。「弱い」存在者たちの連帯的ネットワーク、強力な存在に依存しない弱き力の相互扶助こそが、長い目でみれば、真に持続可能な世界の支えとなるだろう。
翻訳作業について一言。
本書は当初、スペイン語原書を著者プレシアド本人が訳したフランス語訳版から翻訳することになっていた。第8章だけは英語訳を用いるようにプレシアドから指示されたが、私がフランス語を専門とすることを考慮してのことだろう、フランス語訳からの訳出でよいとのことだった。しかしフランス語訳をその英語訳と照らし合わせて読んでみると、あまりの違い(加筆・修正の多さ)に驚き、著者に「本当にフランス語訳からの訳出でよいのか」「決定版は英訳版ではないのか」と何度か問い合わせた結果、フランス語訳からの訳出がほとんど終わった段階になって、英訳版から訳出するようにとの指示が来た。「この期に及んで」とは思ったが、著者の指示であるので仕方がないし、また私自身、英訳版のほうが決定版だろうと感じていたので、作業としては二度手間になったが、あらためて英訳から訳出しなおした。
こうした経緯で、仏訳版と英訳版での異同をすべてチェックし、どのように細かく文言が加筆・修正され、構成自体も変更されているかを網羅した原稿を作っていたが、その異同の訳注だけでゆうに1000を超え、読者にとって煩雑だし、頁数もとんでもない分量になるので、異同については本当に大きな加筆・修正の箇所だけに指摘をとどめた。したがって、翻訳の底本は英語訳書(スペイン語原本をプレシアド本人が訳したフランス語訳をさらに英訳した本)なのだが、これをはたして英「訳」と呼んでよいのかどうか疑問である。プレシアドはスペイン語、フランス語、英語の三か国語を自由に話し書くことのできるポリグロットであり、英訳も明らかに、英訳者が訳した原稿をプレシアドが確認しつつ、(その英訳に刺激されてか)英訳に新たに自分で英語の文言や文章を書き加えていっている。そこではもはや翻訳と創作(オリジナルとされる著者の書き込み【エクリチュール】)との境界が無効になっている。第一言語のスペイン語を著者みずからがフランス語に翻訳し、そのフランス語訳の英訳にまた著者本人が英語を書き加える連鎖の運動。どこまでが原文でどこからが翻訳なのか。翻訳はどこまで翻訳と言えるのか。そして日本語訳者の私はいったい何を訳しているのか。もはやオリジナル/コピー、本物/偽物、現物/複製、起源/派生、出来事/反復、原作者/翻訳者といった伝統的な二項対立あるいは二元論(バイナリー)が失効する交錯的・雑種的な運動様態。毒にも薬にもなる、デリダで言うパルマコンのエクリチュール。これもまさにトランスセクシュアルにつながるトランス体験、文字どおりトランスレーションなのだろう。トランスも一様ではなく、それが生じる場も一つではない。作者をも巻き込み、複数の翻訳者が交錯した——あるいはプレシアドならば「交尾」と呼ぶだろうか——テクスト空間(織物【テクスト】)を読むことで、このハイブリッド体の交わりに読者も参加し、交尾しにやって来てもらえれば幸いである。約束してほしい。「私たちはやって来る」と。「墓に身体をこすりつけ、体液の痕跡を墓石に残す」ために、「変異する狼の群れのように〔……〕吸血鬼のように〔……〕私たちはやって来るだろう」と。
2023年10月3日 「訳者」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
