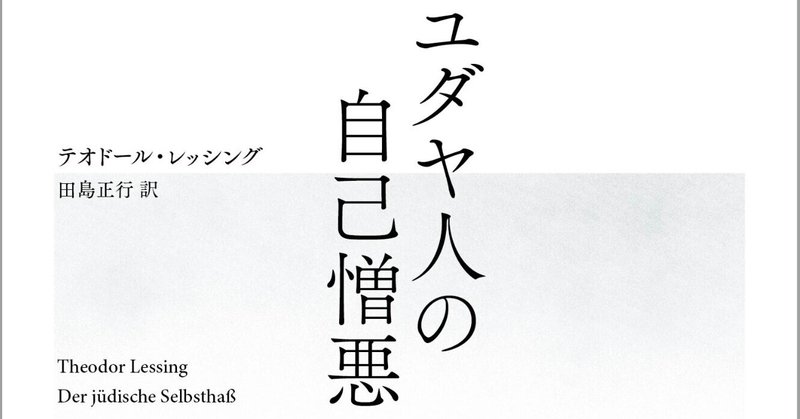
テオドール・レッシング『ユダヤ人の自己憎悪』訳者あとがき(田島正行)
『ユダヤ人の自己憎悪』訳者あとがき
田島正行
本書は、Theodor Lessing: Der jüdische Selbsthaß, Jüdischer Verlag, Berlin 1930の全訳である。翻訳に当たっては、戦後復刊されたDer jüdische Selbsthaß, Matthes & Seitz, Berlin 2004および英訳Jewish Self-Hate, Translated and annotated by Peter C. Appelbaum, Berghahn Books 2021も参照した。
おそらく本書がテオドール・レッシングの著作の本邦初訳であり、しかも著者自身わが国ではほとんど知られていない。それゆえ、ひとまずテオドール・レッシングの生涯を多少詳しく年譜の形で紹介しておきたい。
レッシングの生涯
1872年2月8日、テオドール・レッシングは医師ジークムント・レッシング(1838–96)と妻アデーレ(旧姓アールヴァイラー、1848–1926)の長男として、ハノーファーに誕生した。1年後には、妹ゾフィーが生まれている。父方も母方もともにユダヤ人であった。レッシングという家名は、宗教的寛容を説く『賢者ナータン』が発表された際に、父方の曽祖父が作者ゴットホルト・エフライム・レッシングに感謝の念を表すために改名したのだという。
レッシングの半自叙伝『ただ一度きり』(遺著として1935年に出版)には、「ふたつの地獄」(「家庭の地獄」と「学校の地獄」)と題して、孤独な幼年時代の苦しみがつぶさに語られている。その原因は、父親の結婚の経緯にあった。レッシングの父親は、実家の経済的破綻を救うために、多額の持参金目当てに富裕な銀行家の長女アデーレを妻とした。格別取り柄もなく、美しくもない娘との意に染まぬ結婚ゆえに、父親はその鬱屈した不満をもっぱら妻と、母親似のレッシングに振り向けたのである。そして家庭内では「暴君」として君臨し、両親の間には諍いが絶えなかった。「父は、生まれる前から私を憎んでいた」し、「私は父を憎んでいた」とレッシングは書いている。他方、銀行家の娘であった母親は自立心もなく、安逸な暮らしのみを求め、子供たちの養育をもっぱら乳母に任せていた。「乳母がいなければ、私は生きてはいなかったであろう」とまでレッシングは言っている。愛情のない無理解な両親のもとでの家庭生活は、レッシングの一生に不吉な影を落としている。
不幸な幼少期を過ごしたあと、レッシングは1878年から1888年までの10年間、ハノーファーのリツェーウム(古典高等中学校)に通う。しかし同校では二度落第し、卒業することなく退学している。ただリツェーウムでは、1885年、13歳のときに、同級生のルートヴィッヒ・クラーゲスとの運命的出会いがあった。早生まれのレッシングはクラーゲスより一学年上であったが、落第したため同級となったのである。クラーゲスとの友情は訣別する27歳まで続き、レッシングの思想形成に大きな影響を与えている。
1888年、リツェーウムを退学し、学業には不向きと考えた父親に銀行見習いに出される。だが、そこも長続きせず、新たにハノーファー‐アーレムのユダヤ農業学校に通う。
1891年、ハーメルンのギムナジウムに転校。この年、ベルリンのマクシミリアン・ハルデンを訪れているが、この訪問の顛末については本書に詳しい。
1982年、ハーメルンで高校卒業資格試験に合格したあと、フライブルク大学に入学、医学を専攻する。紆余曲折を経て大学に入ったとき、レッシングはすでに20歳になっていた。
1893年、勉学の地をボンに移すとともに、ユダヤ人ゲマインデ(信徒共同体)を脱退し、プロテスタントに改宗している。この年、自費で小説『喜劇』を処女出版する。
1894年、医師国家試験第一に合格。クラーゲスのあとを追ってミュンヘンに勉学の地を移す。ミュンヘンではクラーゲスを介して、シュテファン・ゲオルゲ、カール・ヴォルフスケール、アルフレート・シューラーなどと知り合う。クラーゲスはすでにゲオルゲ・クライス初期同人のひとりになっていた。レッシングは、「芸術のための芸術」を標榜する高踏派詩人に、そしてゲオルゲにかしずく同人たちに違和感を覚えている。この年、オスカール・パニッツァ擁護のために、ミヒャエル・ゲオルク・コンラートの雑誌『社会』に「パニッツァ事件──〈瀆神行為〉ならびに陪審裁判に引き出された芸術作品に関する批判的考察」を発表し、出版される。これによりレッシングは家宅捜索を受け、警察の監視対象となる一方、一夜にしてミュンヘンで有名となり、シュヴァービング・ボヘミアンたちの共感を得た。「パニッツァ事件」というのは、ドイツの作家オスカール・パニッツァの戯曲『性愛公会議』が反宗教犯罪の廉で訴えられ、著者パニッツァが監獄刑1年を宣告された事件である。
1896年、父の死。臨終間際にレッシングは父親と和解した。母方の祖父アールヴァイラーの援助で勉学を続ける一方、父の呪縛から解放されたレッシングは、テオドール・リップスの影響のもとに専攻を心理学と哲学に変える。
1899年、エアランゲンにおいてユダヤ系ロシア人哲学者を取り上げた「アフリカン・スピルの認識理論」で哲学博士の学位を取得。この年、クラーゲスと訣別する。レッシングとクラーゲスは少年期から無二の親友であったが、長ずるに及んで両者の性格や資質の違いによる齟齬が覆いがたいものとなった。しかし決裂の根本的原因は、クラーゲスの秘められた反ユダヤ主義にあった。
1900年、周囲の高まる反ユダヤ主義に反発したレッシングは、シオニズムに対する共感を強め、ユダヤ人ゲマインデ(信徒共同体)に再び加入する。この年、マリーア・シュタッハ・フォン・ゴルツハイム(1876–1948)と結婚。
1901年、長女ユーディト誕生。同年、チューリンゲンの田園教育舎ハウビンダの教師となる。田園教育舎は教育改革者ヘルマン・リーツが創立した小さな寄宿学校で、レッシングはリーツの教育理念に感激して教師となった。そこには、リツェーウムで自身が受けた教育の苦い思い出が反映している。
1902年、次女ミリアム誕生。
1903年、「ハウビンダ校ユダヤ人騒動」で同校退職。ハウビンダには多数のユダヤ人子弟が学んでいたが、創立者リーツが突如ユダヤ人子弟受け入れ拒否の布告を出し、これに抗議しての辞職であった。この騒動については、本書の原註15を参照。
1904年、ドレスデン近郊の田園教育舎ラウベガストの教師となる。ラウベガストでは男女共学であったというが、これは当時画期的なことであったろう。同年、妻のマリーアが16歳の生徒ブルーノ・フランク(のちに作家となり、トーマス・マンの友人となった)と一緒に出奔する。残されたレッシングは、男手ひとつで幼い二人の娘たちを育てねばならなくなった。この「最も惨めな歳月」のとき、それを忘れようとするかのように、レッシングはさまざまな社会活動に没頭している。レッシングはこう書いている。「同時に私は数年にわたって社会活動に身を投じた。プロレタリアのための最初の授業コースを設立し、社会民主党に加わって労働組合と活動した。また女性の平等、規制された売春の廃止、節酒、平和的国際協調、衣服の改革のために闘った、──その後、この私の最も惨めな歳月のときほど数多くの〈会議〉〈集会〉〈委員〉〈決議〉に参加したことはなかった」。この「プロレタリアのための授業コース」はのちにハノーファーの「自由市民大学」に結実するが、レッシングは最初のゼメスターで10回の講義をドレスデン駅のホールで行なっている。この講義は、『ショーペンハウアー、ヴァグナー、ニーチェ』(1906)として出版されている。
1906年、大学教授資格取得を目指して、テオドール・リップスの勧めでゲッティンゲンのエトムント・フッサールのもとで学ぶ。この間、市立劇場に通い、「夜の批評」の題名で『ゲッティンゲン新聞』に劇評を書いている。また、この年、ガリチア地方を旅行する。この旅行でレッシングは初めて東方ユダヤ人の悲惨な生活を目の当たりにした(この印象記を、1909年「ガリチアの印象」と題して『アルゲマイネ・ツァイトゥング・デス・ユーデントゥームス』に発表している)。その印象は、ユダヤ人問題に対するレッシングの見解に決定的影響を与えている。
1907年、論文「カント倫理学の崩壊」によりハノーファーで大学教授資格取得。マリーア・シュタッハ・フォン・ゴルツハイムと離婚。
1908年、ハノーファー工科大学の哲学私講師となる。『価値公理論の研究』を出版。また、『騒音──我々の生活の喧騒に対する闘争文書』を出版。さらに「反‐騒音‐協会」(ミュンヘン、1908–1911)を設立。機関紙『反‐無作法者──静寂の権利──反‐乱暴者』(1908–1911)を発行。これは産業化の進展に伴う近代的都市生活の騒音を問題にするものであった。
1910年、「ルブリンスキー‐スキャンダル」を惹き起こし、公的にトーマス・マンと論争する。「ルブリンスキー‐スキャンダル」とは、レッシングが『シャウビューネ』誌に発表した「ザムエルが総括する、あるいは小さな預言者―ひとつの風刺」が巻き起こしたスキャンダルである。この風刺文は、当時著名な文学史家で批評家であったザムエル・ルブリンスキーを辛辣に戯画化したものである。問題となったのは、同化ユダヤ人ルブリンスキーの人格をユダヤ人のレッシングがイディッシュ語のユダヤ人差別用語を用いて揶揄した点にあった。この風刺文に対して、フェルディナンド・アヴェナリウス、テオドール・ホイス、シュテファン・ツヴァイクなど33人の知識人が「ジャーナリストに対する懲戒裁判がないことは遺憾である」旨の抗議声明を発表した。そしてトーマス・マンは「レッシング博士」を書いてレッシングを厳しく指弾した。ここに両者の間で数回にわたる論争が繰り広げられたのである。トーマス・マンがルブリンスキーに代わってレッシングと論争したのは、ルブリンスキーに対する恩義を感じていたからにほかならない。すなわち、当時権威ある批評家として文壇に君臨していたルブリンスキーがその著『近代の総括』(1904)の中で、いまだ無名であったトーマス・マンの『ブッデンブローク家の人々』(1901)を激賞した結果、トーマス・マンは文壇デビューを果たすことができたのである。トーマス・マンはそれを忘れることはなかった。レッシングは最終的にこのスキャンダルの一連の経過をまとめ、自分に対する批判文書をも含めた『ザムエルが総括する、そしてトミーがモラル牛の乳を搾る、もしくはふたりの王の転落──風刺を書くドイツ人へのひとつの戒め』(1910)を私家版として出版している(「トミー」とはトーマス・マンの愛称)。とはいえ、レッシングが受けた傷は大きかった。彼は世間における信用を一挙に失ったのである。晩年、レッシングはこう述懐している。「私は当時と同様いまでも、あの高慢でグロテスクな風刺を不法ではないし、適切であると思っている。しかしその点で私が間違っていると言うのであれば、そして思い上がった私のからかい癖によって不正を加えたのであれば、ともかくその償いは大いに果たしたのだ。なぜなら、この20年間にわたって、今日まで、悪意を抱いた者たちはすべて(そして私はジャーナリズム全体の憎悪にしばしば耐えねばならなかった)繰り返しあの文学的風刺から抜粋したいくつかの文章を発掘しては公然と私を中傷し、その結果、私のイメージはまったく歪められたからである」。この年、『女、女性、婦人』を出版。
1912年、次女ミリアム死去。アデーレ(アーダ)・グローテ・アッバーテルン(1883–1953)と結婚。アーダとレッシングは再婚同士であった。アーダはレッシングと共に婦人参政権や成人教育のために積極的に活動し、1932年の帝国議会選挙では社会民主党の候補になった。ちなみに、ドイツで婦人参政権が認められたのは1918年である。
1913年、アーダとの間の娘ルースが誕生。
1914年、第一次世界大戦勃発。大戦中、レッシングは野戦病院医師およびギムナジウムの補助教員として働いた。また、ミュンヘン医学生時代以来の友人であったマックス・シェーラーと訣別する。平和主義者のレッシングと愛国心に燃えるシェーラーは、大戦をめぐって決定的齟齬をきたしたのだろう。この年、『行為としての哲学』を出版。
1915年、著書『ヨーロッパとアジア』が軍の検閲で発禁となる。この書は1918年ようやく出版される(1924年の第四版ではタイトルが『精神による大地の没落』に改められている。1930年の第5版ではタイトルが『ヨーロッパとアジア(精神による大地の没落)』となっている)。
1918年、ハノーファー工科大学の哲学私講師としての教員活動を再開。
1919年、『意味なきものの意味づけとしての歴史』(1927年に第4版、1983年に復刊されている)を出版。
1920年、ハノーファー‐リンデンに「自由市民大学」を開校。支配人は妻のアーダ。この大学はナチ時代に閉校されたが、戦後復活し、現在、「アーダ‐テオドール‐レッシング市民大学」と命名されている。
1922年、『プラハ日刊紙』の自由寄稿者として活動を始める。以後、同紙に多数の記事、論説、書評、時評、エッセイを執筆する。『プラハ日刊紙』は、1876年から1939年までプラハで発行されたリベラルなドイツ語の新聞で、当時の最良のドイツ語日刊新聞のひとつとされていた。
1924年、「ハールマン裁判」について報道し、スキャンダルを惹き起こす。フリードリッヒ(フリッツ)・ハールマン(1879–1925)は、ハノーファー市民を震撼させた同性愛の性的連続殺人者である。少なくとも24件の性的殺害容疑で起訴され、裁判が1924年12月4日から19日まで開かれた。19日、ハールマン、および殺人教唆と協力の廉で共犯者ハンス・グランス(1901–75)は死刑を宣告される。翌1925年4月15日、ハールマンの死刑執行。グランスは、ハールマンの供述が偽りであったことが明らかとなり、懲役刑12年に処せられる。その後、グランスはナチの強制収容所に収監され、釈放されたのは1946年であった。ハールマンは1919年から1924年にかけて多数の青少年を殺害したが、容疑者の発見が遅れた理由として、警察の不手際もさることながら、ハールマンが警察の情報屋として雇われていたことが大きかった。また、ハールマンが男色行為中に犠牲者の喉を嚙み切って殺害するという異常性欲殺人者であったことも世間に衝撃を与えた。さらに警察がハールマンに拷問を加えていたことも発覚した。当局はこの事件の闇が暴露されることを恐れて、この一件をすみやかに処理したのである。レッシングは『プラハ日刊紙』の寄稿者として、この事件を容疑者の逮捕から断続的に報道し、「ハールマン裁判」も傍聴してその模様を報じた。レッシングは報道の中で、ハールマンの犯罪には当局も共同責任があり、容疑者の発見が遅れたことを公然と問題視した。また精神科医によるハールマンの精神鑑定を裁判所に要求すると共に、ハールマンの供述は信用できず、殺害に直接関与していないグランスを死刑に処するのは「司法殺人」であると断じた。さらに事件の社会的背景にも言及している。こうした報道が当局の逆鱗に触れ、レッシングは取材許可書を剝奪され、11回目からの裁判を傍聴できなくなった。レッシングは一連のハールマン事件をまとめ、『ハールマン──ある人狼の物語』(1925)として出版している。ちなみに、レッシングの報道によりハノーファーの地方の醜聞が外国の新聞に暴露され、広く世間に知れ渡ったことで、市当局および市民のレッシングに対する憎悪が高まった。これが、のちの反レッシング・キャンペンーンの温床になったのである。
1925年、「ヒンデンブルク‐スキャンダル」を惹き起こし、レッシングに対する反ユダヤ主義的キャンペーンが始まる。1925年4月26日、初めての直接選挙による大統領選挙が行われ、「タンネンベルクの英雄」パウル・フォン・ヒンデンブルク(1847–1934)が大統領に就任した(在任1925–34)。これはその後のドイツの歴史にとって転機となる宿命的出来事であったが、当時それを予感したものは誰一人いなかった。レッシングは選挙の前日、4月25日の『プラハ日刊紙』に、ヒンデンブルクが大統領になった場合の深刻な影響を懸念して「ヒンデンブルク」のポートレートを記事にした。その中でレッシングはこう書いている。「あらゆる人間の中で最も非政治的なこの人間が、ある政治的役割のために悪用される瞬間から、別なことが決定される。すなわち、この人はあくまで奉仕の人なのである。この人にはいまだに、自分で決定し、考え込み、吟味する人格の萌芽すらないのだ」。そしてヒンデンブルクを「一匹の善良な〈バーナード犬〉」であるとして、次のように結論している。「プラトンによれば、哲学者が民族の指導者になるべきだという。いまやヒンデンブルクと共に玉座に登るのはひとりの哲学者ではないだろう。登るのは、ひとつの代表的象徴、ひとつの疑問符、ひとつのゼロにすぎない。〈ひとつのゼロはひとりのネロよりましだ〉と人は言うかもしれない。残念ながら歴史は示している、ひとつのゼロの背後にはつねにひとりの将来のネロが潜んでいるということを」。8年後のヒトラー政権掌握を予見していたかのようなレッシングの政治的慧眼には驚くほかないが、しかし人々は彼の警告にまったく耳を貸さなかったばかりではない。国民的英雄を、すなわちドイツ精神を誹謗したとしてレッシングに対する反ユダヤ主義的キャンペーンが繰り広げられたのである。
1925年5月8日『ハノーファー新報』に意図的に歪曲された形でレッシングの記事「ヒンデンブルク」が転載されると、5月10日、ハノーファー工科大学の100人の学生組合員と七人の教授が「闘争委員会」を結成し、レッシングから講義委嘱と教授資格認可を剥奪するようプロイセン文化省に要求した(ヒンデンブルクはハノーファー名誉市民であり、ハノーファー工科大学名誉教授であった)。学長と評議会もそれに同調し、レッシングに対して独断で停職を命じた。この年の夏、レッシングは教授活動を一時停止したが、翌年には再開している。文化省はレッシングについて専門家の意見を求めたところ、委嘱を受けた哲学者、マックス・シェーラー、エトムント・フッサール、エドゥアルト・シュプランガーは彼が「気まぐれ」であり、「並外れて卑劣な性格」であり、「自分の破壊活動に喜び」を感じていることを文書で保証したという。結局、1926年に文化省はレッシングの教授委嘱を研究委嘱に切り替えるのである。
1926年5月以降、レッシングに対するテロが激しくなる。レッシングは幾度も武器を持った暴徒によって通りを追い立てられる。5月の終わりには、レッシングの講義室の前庭を一部武器を持った700人の学生たちが包囲し、喚きたてて講義を妨害した。こうしたレッシング追放運動の中で、彼の講義を受講する学生は激減する。レッシングはある新聞記者にこう答えている。「私は、どんなことがあっても、今日の5時から6時までの私の講義は行うつもりです。しかし、受講生たちは私の講義室へ敢えてやっては来ないでしょうから、講義が実際にできるとは思っていません。すでに6時から7時までの私の講義は、あきらめねばなりませんでした。前もってそれの受講登録をしたのは、ただ二人だけでしたから。しかし、この二人も先週の騒動のあとには、講義に出てこなくなりました。確実に言えることは、私はどんなことがあっても、たとえ唯一人の受講生として私の妻が講義室に座っている場合でも、大学へ出かけて行くだろうということです。私には、別の講義室が、つまり本館から隔たった側翼にある講義室があてがわれましたので、私の講義は象徴的行動の意味しかもちません。私は、大学が譲歩するまで、月曜日ごとに非難の渦中へ赴くつもりであることを表明します。さらに本格的な妨害が現れるかどうかは分かりません。おそらく〈干拓方式〉が試みられることと思います。私は誰もいない建物の中に一時間閉じこもったまま、百人もの保安警察に見張られることでしょう。そのあと、喚く群衆の間を通り抜けて、再び家へ帰って行くことでしょう」(ハンス・マイヤー『取り消された関係──ドイツ人とユダヤ人』宇京早苗訳、法政大学出版局、2003年)。6月8日、レッシングが予想した通り〈干拓方式〉が試みられた。ハノーファー工科大学学生組合員および非組合員の学生1400名が授業ボイコットのストライキを行い、ハノーファー中央駅までデモ行進してブラウンシュヴァイク行きの特別列車に乗り込むという示威行動を起こしたのである(これを裏で支え、資金援助し、傘下のメディアを用いて扇動し、示威行動を策謀していたのは、国家人民党のアルフレート・フーゲンベルクではなかったかと言われている)。6月11日、市の公会堂で4000人以上の市民が集まった市民集会が開かれ、市長および学生代表ペールマンが演説した。6月18日、高齢の母親アデーレ・レッシングが息子に対する反キャンペーンに心を痛めて倒れ、78歳で死去する。6月19日、「国家の威信の勝利」との見出しで、プロイセン文化相ベックとレッシングとの間で妥協が成立し、レッシングは教授活動を放棄し、研究活動に専念することになったと新聞が報じた。ここに、レッシングは20年弱にわたるハノーファー工科大学哲学私講師の教授活動から身を引くことになったのである。
1928年、半自叙伝『ただ一度きり』を書き始める。
1930年、『ユダヤ人の自己憎悪』を出版。
1931年、エジプト、パレスチナ、ギリシアへの旅。
1933年1月30日、ヒトラー首相就任。ヒトラー政権掌握後、レッシングは亡命の準備を始める。2月27日国会議事堂炎上事件による波状的大量逮捕が始まり、レッシングは急いでハノーファーを去らねばならなくなった。3月1日、レッシングは娘ルースと共にプラハ行きの列車に乗り込む。逃走の日の夜、突撃隊の一団がハノーファーの彼の住まいを荒らす。数週間後、妻のアーダが彼のあとを追って亡命する。レッシングとその家族は、プラハ経由でボヘミアのマリエンバートに亡命する。その途次、プラハの第18回シオニスト会議(8月21日から9月4日)に参加する。8月30日晩、ズデーデンドイツのナチ党員により銃撃される(レッシングには8万ライヒスマルクの懸賞金が賭けられていた)。8月31日未明、死去。マリエンバート発のニュースは次のように伝えている。「昨夜、9時30分頃、テオドール・レッシング教授が暗殺された。犯人はレッシング教授が宿泊していた別荘〈エーデルヴァイス〉の外壁に梯子をかけ、窓越しに教授に向けて拳銃で発砲した。そのうちの一発が教授の頭に命中し、重傷を負わせた。レッシング教授は九時四五分に意識不明のままマリエンバートの病院に担ぎ込まれた。彼は頭部に命に関わる深い傷を負っていた。銃弾は左の頬を撃ち抜き、右の後部頭蓋を貫通していた。それによって脳の数カ所が破裂していた。マリエンバートの医師団は絶望的な容態と判断した。その後、12時15分に、教授は意識不明の危篤状態に陥った。12時45分に病院から伝えられたところによると、同時刻に教授は瀕死の苦しみに喘いでいた。医師団は臨終を覚悟した。午前1時前、レッシング教授は死亡した」(ハンス・マイヤー前掲書)。9月2日、マリエンバートのユダヤ人墓地に埋葬される。レッシングの棺の上に、ひとりの男が次のように書かれた幕を掲げたという。「真理、人間性、自由のために倦むことなく闘ったレッシング教授を悼んで。数百万の考えを同じくする者を代表して」(ハンス・マイヤー前掲書)。レッシングが暗殺された8月30日、ニュルンベルクで「勝利の党大会」と呼ばれたナチス党大会が盛大に開催されたが、けだし歴史の皮肉と言うべきだろう。
本書について
本書『ユダヤ人の自己憎悪』(1930)は、テオドール・レッシングの数ある著作の中で生前最後に出版されたものである。だが、レッシングはなぜ晩年に至ってこのような著作を出版したのだろうか。というのも、書名だけを見れば、本書が反ユダヤ主義的書物のひとつと見なされる恐れがあるからだ。しかも出版された当時のドイツは、反ユダヤ主義的風潮が強まり、ナチスが党勢を急速に拡大していた時期である。実際、1930年9月の国会選挙ではナチ党は改選前の12議席から107議席に大躍進し、社民党に次ぐ第二党になった。レッシング自身、1925年の「ヒンデンブルク‐スキャンダル」により反ユダヤ主義の大衆運動や暴力の被害を蒙っていたはずである。にもかかわらず、よりによってこの時期に、誤解されかねない『ユダヤ人の自己憎悪』を出版したのはなぜなのか。そこには、レッシング一流の逆説的戦略があったように思われる。すなわち、時勢におもねる書名によって人々の耳目を聳動し、「狂信的人種差別の神話」の中で育てられたユダヤ人子弟の「自己憎悪」の悲劇的実例を紹介することで、反ユダヤ主義の非人道性を告発するという戦略である。「ユダヤ人の自己憎悪」とは「ユダヤ人の反ユダヤ主義」にほかならないが、ある意味、これほど酷いことはないのかもしれない。
しかし、こうした戦略以上に重要なのは、「ユダヤ人の自己憎悪」がレッシングにとって思春期からの年来のテーマであったことである。「自己憎悪」が「みずからの生に逆らう」精神的病弊であるとすれば、レッシングは二重の意味でこの病弊に冒されてきたのである。「祝福されざる子」として生まれ、両親の愛を知らずに育ったレッシングは、孤独の中でつねに両親を憎悪してきた。しかも「父や母への憎悪は、自己分裂に転化する」。「自己の生」を育んでくれた「両親への憎悪」は、とりもなおさず「自己の生への憎悪」以外の何ものでもないが、その際に憎悪する主体は「自己意識」としての「精神」である。「自己憎悪」の基本には、こうした「自己の生」と「自己の精神」との分裂がある。また、「両親への憎悪」は、両親の属する「同化ユダヤ人への憎悪」に発展してゆく。レッシングの「自己憎悪」には、自身の私的な「両親への憎悪」とともに一般的な「同化ユダヤ人への憎悪」という二重の意味が籠められていた。このような「自己憎悪」の精神的病弊を抜け出すにはどうしたらよいのか、この問題意識こそレッシングの思索の原点である。レッシングの『ユダヤ人の自己憎悪』の根底には、みずからの「自己憎悪」との苦闘がある。その意味では、本書はレッシングの思索の総決算とも言えるかもしれない。
内容については本書を読んでいただくとして、ここでは本書の現代的意義について述べておきたい。
本書の結論とも言える「円蓋」の冒頭で、レッシングはシオニストと社会主義者との論争を紹介している。シオニストが「ユダヤ精神はひとつの理論、ひとつの人間団体、ひとつの世界観であるばかりでなく、生命と血の通った現実なのである」と主張するのに対して、社会主義者は「超民族的共同体は生誕のあらゆる偶然よりも深く真理や正義の遵守を義務づける」とし、「民族国家を基盤にしては民族のいかなる問題も解決できないし、また国籍自体の問題も解決できない」と答える。これは、要するに、民族の独自性に固執するシオニストと民族を超えた普遍的価値を唱える社会主義者との対立である。今日で言えば、さしずめ保守的ナショナリストと進歩的リベラリストの対立と見なすことができよう。はたして両者の間に橋を架けることができるのだろうか、これが『ユダヤ人の自己憎悪』の最終的問題であるばかりでなく、また著者自身の課題でもあった。というのも、レッシングはシオニストであると同時に社会主義者でもあったからだ。
哲学者コンスタンティン・ブルンナーと社会改革者ヨーゼフ・ポッパー・リュンコイスは、こう述べているという。「イスラエル民族は驚くべき民族だ。この民族は──精神、数学、論理、倫理のように超国家的に──その特殊で孤立している形態を放棄し、すべての人々の中に生きているひとつの精神の永遠の担い手として、果てしなく、あらゆる形態を纏って諸民族の間に橋を架ける場合にのみ、その歴史的使命を果たすことができるのである」。ブルンナーとリュンコイスは、ユダヤ人の歴史的使命を「ひとつの精神の永遠の担い手」、つまり「普遍的真理と正義の担い手」となることに求めている。この見解にレッシングは全面的に賛同する。ただし、「生命が〈精神〉であるならば、ひとつの教えが世界史をつくることができるのであれば」という留保つきで。この留保条件が重要なのである。なぜなら、「生命」は「精神」ではないし、「ひとつの教えが世界史をつくる」のではないからだ。「ひとつの教え」が世界史を導くことはあるかもしれない。しかし、実際に世界史をつくりあげているのは無数の「名もなき人々」である。「偉大な人物が歴史をつくる、それどころか歴史であるというのは、真実ではない。歴史、民族そして血は、幾兆もの単純な人々、名もなき人々である」、とレッシングは言っている。だとすれば、レッシングはユダヤ人の歴史的使命をどのように考えているのか。
18世紀末から西欧各地のゲットーは解放されていったが、この時期はまさに西欧諸国が産業革命により農業社会から工業社会へと変貌してゆくときにあたっている。その結果、農村から大都市へと大量の人々が流入し、都市のプロレタリアになっていった。こうしてできた工業都市こそ巨大な近代的ゲットーにほかならない、とレッシングは言う。「炭塵が上空に吹き寄せる、草木の繫茂や森のない大都市、青ざめたプロレタリアの子供たちが機械やベルトコンベアで人生の三分の二を過ごす産業地区、これらはまさしく巨大な近代の諸ゲットー以外の何ものでもない。何百万もの産業奴隷たちが心ならずもこうしたゲットーに呪縛されているのだ」。工業社会への移行は、また近代資本主義社会への移行でもあったが、それは時代的にユダヤ人の解放と軌を一にしていた。つまり、「ユダヤ人がやっと牢獄から自由になったその同じときに、諸民族の多くの大衆は牢獄に押し込められたのである」。この点に、「近代世界におけるユダヤ人のあらゆる成功の秘密に対する解答とその特別な地位に対する説明がある」と同時に、人種的反ユダヤ主義が勃興した理由がある。言い換えれば、ゲットーに閉じ込められていたユダヤ人の運命は、「数世紀後には、ヨーロッパ‐アメリカのプロレタリア化され、労働管理に閉じ込められた大衆が同様の運命となる進展を先取りしていたのだ」。それゆえ、ユダヤ人が近代資本主義社会において成功を収めたのも当然なのである。
問題は、近代資本主義社会となって、社会構造がゲマインシャフトからゲゼルシャフトへと徐々に変化していったことである。自然共同体としてのゲマインシャフトが弛緩しているところでは、共通の利害・関心に基づく人為的団体としてのゲゼルシャフトが代替を作り出さねばならなかった。「自然がもはや共通の類型を作り上げないとすれば、社会的目標や理想が自然共同体の原子化を防がなくてはならない」からである。この点に関しても、土地を持つことの許されなかったユダヤ人は先駆的経験をしていた。「共通の土地の代わりに共通の律法がユダヤ人を結びつけた。つまり生きた動物性ではなく、精神の定めがユダヤ人を結びつけた」からである。つまり、「ユダヤ人の故郷は精神であり、ユダヤ人の郷土は紙であり、ユダヤ人の耕地は頭脳であった」のである。こうしたユダヤ人の運命は、産業革命以後の近代資本主義社会の運命となった。そして「根元の弛緩、自然疎外、民族基本要素の解消」に伴う病弊に近代資本主義社会も襲われるようになったのであり、ここにユダヤ人の歴史的使命が存在するとレッシングは言うのである。レッシングはこう書いている。「ユダヤ民族は今日、若い諸々の有機体の間でいままさに猖獗をきわめている疫病ないし感染症をとうに経験してきた、ひとつの有機体の状態にある。我々はすでに〈抗毒素〉を持っている。そして年長の有機体として病毒に対する〈免疫〉を持っているのだ。この病毒を克服することがいままさに地上の全民族の死活問題となっているのである。……すべての諸民族を脅かしている苦しみを、ユダヤ民族は最も古い民族としてきわめて早い時期に耐え忍ばねばならなかった。より若く、より幸福な諸民族にようやくあとになって迫ってきた多くの諸問題を、ユダヤ民族は考えつくし、和解しなければならなかった。ユダヤ民族はそのさまざまな解決をただ自分たちのために見出したばかりではない。それらはすべての苦しんでいるものたちの役に立つのである。まさしくこの点にユダヤ人の意義があるが、しかしまた、この民族を超えた、まったく精神的課題のために消え去ってしまう大きな危険もあるのだ」
さて、以上のようなレッシングの主張は、現代において何らかの意味があるだろうか。私には、レッシングの言葉が今日の我々にも有益な示唆を与えてくれるように思える。もちろん、現代は高度資本主義社会であり、レッシングの時代の資本主義社会とは比べようもないほどに複雑精緻に組織化されている。人権や生存権などに基づく社会的法整備も進んでいるし、労働環境も格段に改善されてきた。技術革新もめざましく、いまやアナログ社会からデジタル社会へと移行しつつある。にもかかわらず、資本主義社会の性格は高度資本主義社会になろうとも本質的に変わっていないのではないか。「根元の弛緩、自然疎外、民族基本要素の解消」は、高度資本主義社会になって加速度的に進んだ。また、現代世界は各種の通信機器によるネットワークで地球全体が繭玉のように張り巡らされているが、これも比喩的な意味でグローバルなゲットー化であると言えなくもない。グローバルなネット空間の中で我々は自由に情報交換が可能になったとはいえ、管理者に監視統制され、プラットホームを運営するグローバル企業は巨大な利益を上げている。しかも効率化、利便化の名のもとに社会のデジタル化が急速に推し進められている。デジタル化された社会は「電脳社会」とも呼ばれているが、この呼称こそまさに現代社会が「唯脳化」されつつあることを示すものだろう。実際、社会においては頭脳の働きが極度に重視され、子供たちは頭脳を陶冶するために幼少期から塾や予備校に通わせられる。「ユダヤ人の故郷は精神であり、ユダヤ人の郷土は紙であり、ユダヤ人の耕地は頭脳であった」というレッシングの言葉は、「郷土」を「紙」から「パソコン」ないし「スマホ」に変えれば、そのまま現代人にも当てはまる。現代社会はまさに「ユダヤ化」されているのだ。こうしたデジタル社会に共通する特徴は、身体性や物質性の欠落であり、直接性の欠如である。その結果さまざま社会的問題が生じている。
だとすれば、レッシングの言う「ユダヤ人の歴史的使命」は現代社会に大きな役割を果たすはずである。しかし現実には、「ユダヤ人の歴史的使命」は一顧だにされていない。ナチによる大量虐殺という酸鼻な体験を経たユダヤ人は、戦後、念願の祖国の地にイスラエルを建国した。しかし4回にわたる中東戦争の結果、パレスチナのガザ地区はイスラエルによって軍事的に封鎖され、文字通りゲットーと化している。ヨルダン川西岸地区も高い分離壁が作られ、イスラエルの軍事支配下の地域ではユダヤ人の入植地が続々と作られている。こうした状況は、「ユダヤ人の歴史的使命」をまさしく裏切るものであるだろう。
本書の最後には、タルムードの中のラビたちの奇妙な論争が紹介されている。「精神の世界が現存せず、人間の中で目覚めた精神が無意識的なものや非人間的なものの中へとふたたび解消されるほうがよいのか、それとも、無意識的なものや非人間的なものが目覚めた精神や知的人間性へと浄化されるほうがよいのか、という問題である。2年半にわたり諸学派は争った。しかし、〈精神的な者たち〉と〈四大的な者たち〉が最終的に合意に至る解決は以下のものであった。我々に意識された現実の世界が現存しないほうがよいであろう、ということにまったく疑問の余地はない」。これを受けて、レッシングはこう断言する。「人類の終焉、人類が限りなきものの中へとふたたび解消されることが最も望ましい目標であることに、まったく疑問の余地はない」。しかし、なぜ「人類の終焉」が「最も望ましい目標」であると言うのか。ひとたび人間という立場を離れて考えてみるならば、レッシングの言葉が真理であることがわかる。地球にとって、大地にとって、人間以外の生きとし生けるものにとって、人類の消滅が最も望ましいことは明らかであるからだ。これは我々人間にとってつらい真理であるにせよ、真理であることに変わりはない。
だが、レッシングのこうした発言をハンス・マイヤーは手厳しく批判している。「レッシングはドイツの状況や彼の才能および性格の矛盾によってのみならず、彼の哲学によっても破滅したのです。レッシングにおける思想家と文化政策家との矛盾は、哲学的ペシミズムと啓蒙主義との対立に帰することができました」(ハンス・マイヤー前掲書)。マイヤーによれば、レッシングは、「文化政策家」としては「実践的啓蒙主義者」であったが、「思想家」としてはクラーゲスと同様の反啓蒙主義的な「後期ロマン主義のペシミスト」であった。その矛盾した哲学によってレッシングは破滅したというのである。マイヤーのような啓蒙主義者がそうした見方をするのは当然であるとはいえ、「自然」にとって「人類の終焉が最も望ましいことである」という真理を彼は否定できるのであろうか。「人間による自然支配」という啓蒙のプロジェクトの行き着く先が破局であることを彼は否定するのだろうか。
レッシングは「啓蒙主義者」にして「反啓蒙主義者」であるとし、その矛盾を指摘する者は多い。しかし、私はレッシングの哲学が矛盾しているとは思わない。先のレッシングの発言には、次のような続きがある。「しかし我々はともかく人間であり、〈世界史〉というこのエピソードを走り続けなければならない以上、我々の課題は、みずからの最も誠実な洞察から見て可能な最善のことを世界史の中で仕上げることである」。レッシングは、実際、「人類の終焉が最も望ましい目標である」という真理を見据えながら、可能な限り社会活動に身を投じてきた。成人教育、女性の平等、女性の参政権、売春の禁止、衣服の改革、平和的国際協調、反騒音協会設立等々。これらの社会活動の大半は中途で挫折したとはいえ、今日ではその先駆性が評価されている。
いまや、高度な物質文明の代償として、世界は地球温暖化という未曽有の危機に直面している。毎年頻発する大規模な山火事、大型の台風やハリケーン、大洪水、干ばつ、それに伴う食糧危機やエネルギー危機などは、破局が迫っていることを我々に教えている。このような危機的状況にもかかわらず、諸国は相も変わらず経済成長を求め、諸大国は覇権を求めて軍事力を増大し、ブロック化を推し進めて、世界を分断している。その結果、戦争や内乱は後を絶たず、大量の難民が発生している。一方、世界中いたるところで貧富の差は驚くほど増大し、生活苦からホームレスになる者や自殺をはかる者も増加している。また核の脅威も世界的に高まっている。核兵器使用の可能性が現実味を帯びているばかりではない。核廃棄物の最終処理ができない中、原発が世界各地に続々と建設されている。とりわけ我が国は唯一の被爆国であり、福島第一原発事故の記憶がいまだ覚めやらないにもかかわらず、政府は原発再稼働に邁進している。
だが、かかる危機的事態も、ことによると「人類の自己破壊衝動」の無意識の表れ、すなわち「人類の自己憎悪」の徴であるのかもしれない。レッシングは「自己憎悪」をユダヤ人特有の現象ではなく、人類全体の普遍的現象であるとしている。そして「自己憎悪」の淵源を、人類が精神に目覚める地点にまで遡らせている。つまり、主体と客体が未分化な万象一体の中から人間の生命に精神が芽生え、主体と客体が分かれる原初的分裂に「自己憎悪」の根を見ているのである。「人間という生きものにおいて、生命がみずから自身に逆らい、生命と対立し、最終的に生命を憎悪するように仕組むのは、精神自体の驚異である」。目覚めた「精神」(知性)が「人間の自然支配」を可能にしたのだとすれば、そしてその行き着いた果てが今日の危機的状況であるとすれば、そこに「人類の自己憎悪」を見て取ることもあながち不自然なことではあるまい。ニーチェはこう言っている。「精神とは、みずからの生命に切り込む生命である。それはみずからの苦しみによって、みずからの知を増すのである」〔後略〕

Wikimedia Commonsより
関連書籍
訳者プロフィール
田島正行(たじま・まさゆき)1949年生まれ。元明治大学教授。専門は近代ドイツの文学・思想。共著に、「〈自然との和解〉という欺瞞──『アンティゴネー』についてのヘーゲルの解釈をめぐって」(『他者のトポロジー』書肆心水、2014年)、「《アウラの喪失》の意味──クラーゲスの思想から見たベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』」(『語りのポリティクス』彩流社、2008年)、「異教的反ユダヤ主義──L. クラーゲスの思想と反ユダヤ主義」(『ツァロートの道』中央大学出版部、2002年)。論文に、「ルブリンスキー・スキャンダル──テオドール・レッシングとトーマス・マンの論争をめぐって」(『明治大学人文科学研究所紀要 第74冊』、2014年)、「二つの永遠──L.クラーゲスのゲーテ批判の一側面」(『ゲーテ年鑑 第55巻』、2013年)など。訳書に、ルートヴィッヒ・クラーゲス『宇宙生成的エロース』(うぶすな書院、2000年)、同『心情研究者としてのゲーテ』(うぶすな書院、2013年)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
