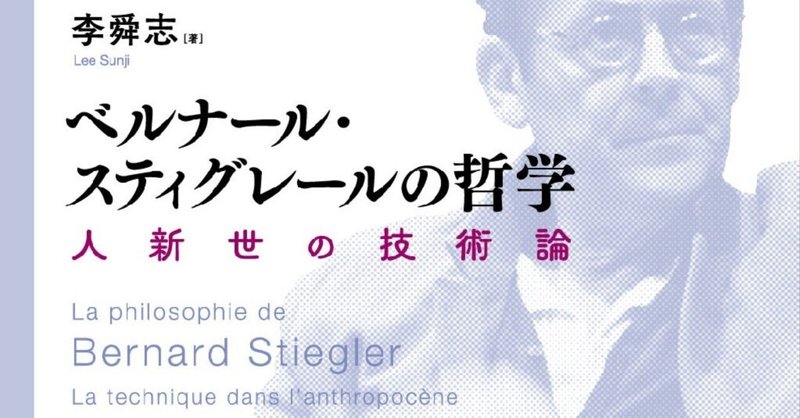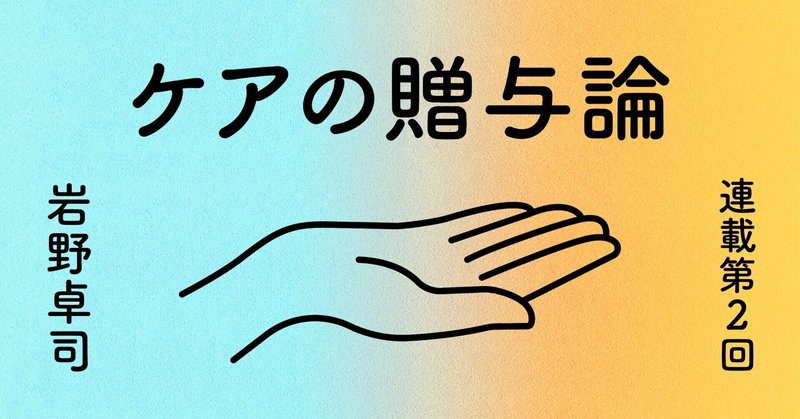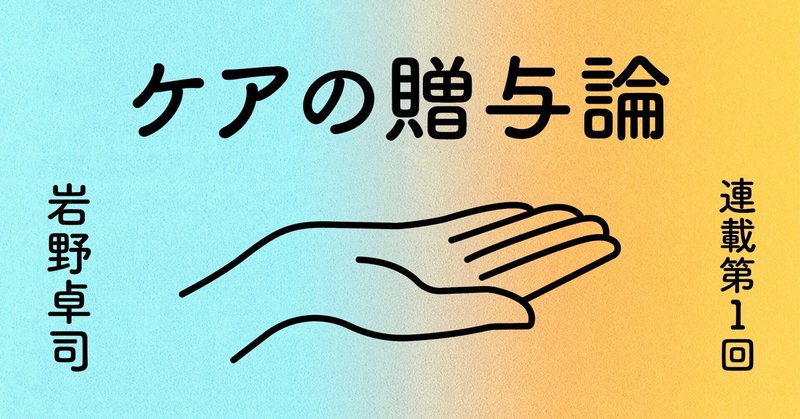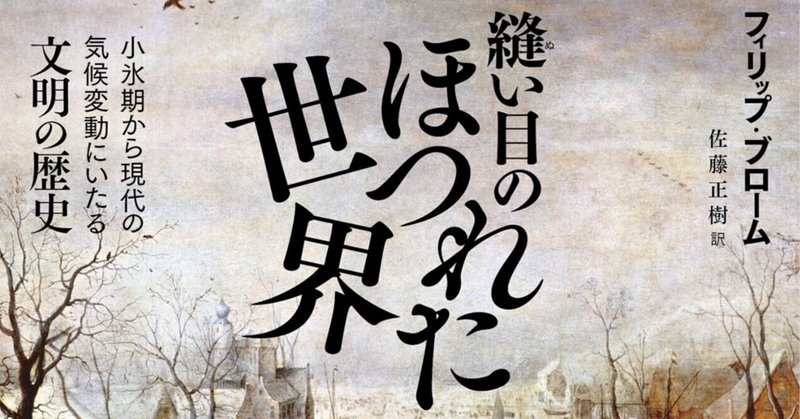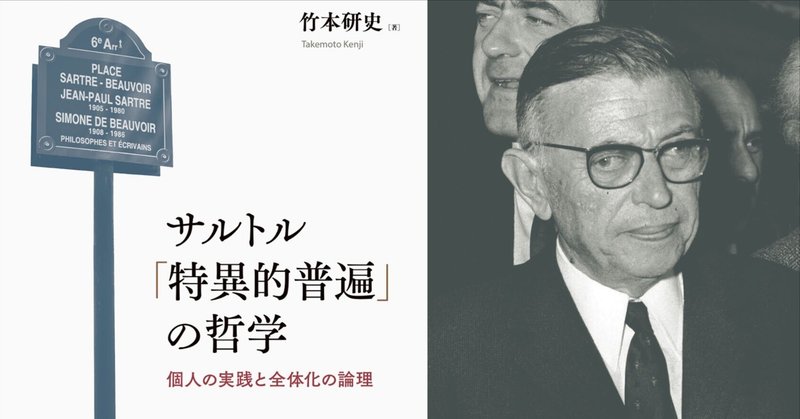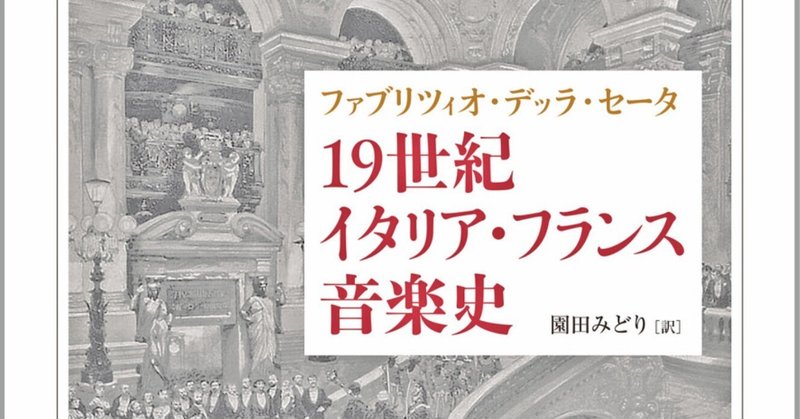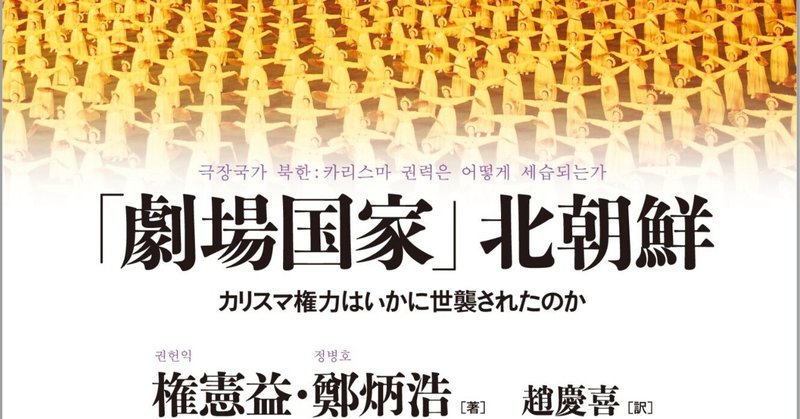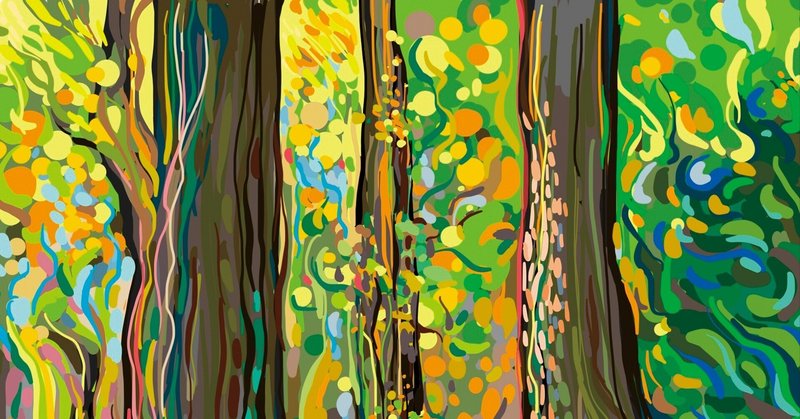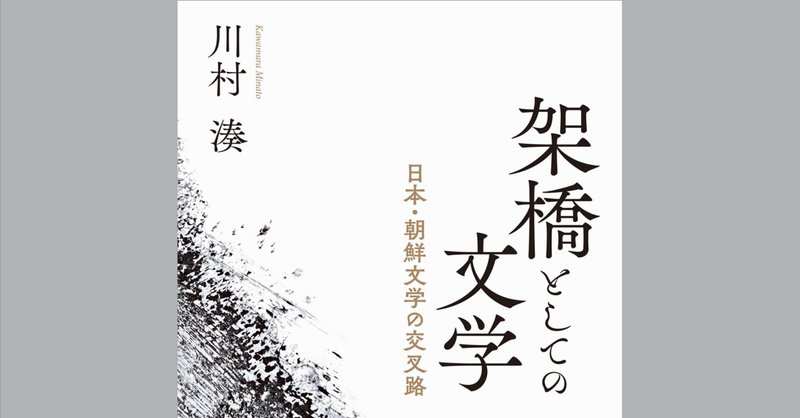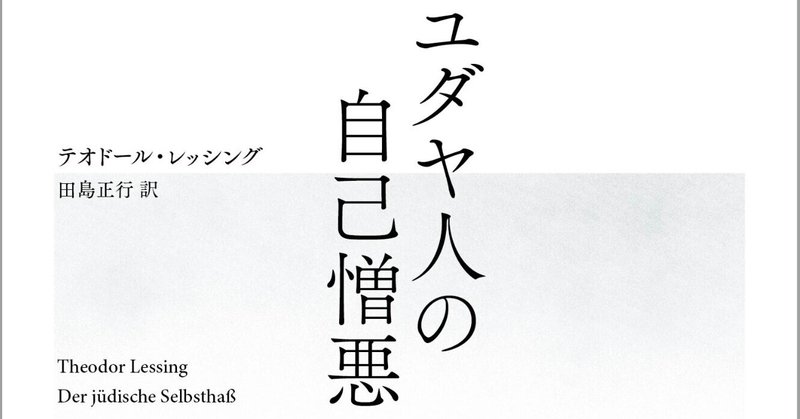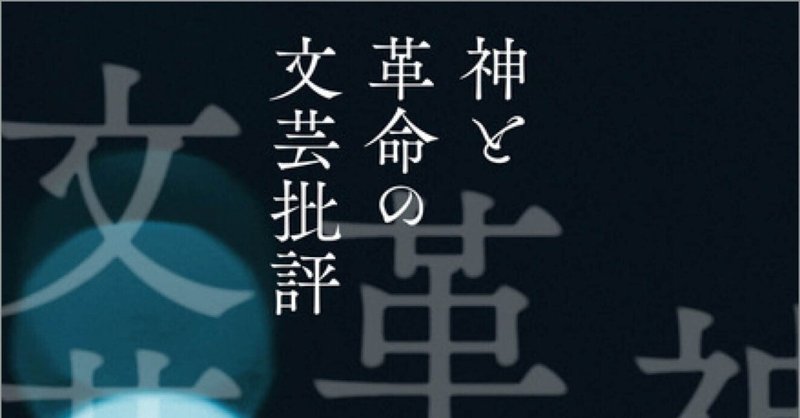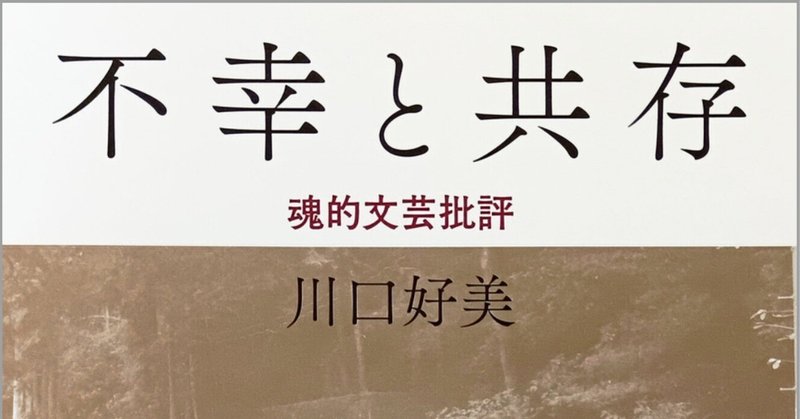記事一覧
連載第2回 『ケアの贈与論』
イントロダクション(後篇) ケアにおける贈与と共同性岩野卓司
他者との非対称な関係、誰も取り残さないという理想と複数の性の声の解放、何も共有しない共同性。これらはケアにおける「根源的な共同性」の条件だ、というのが前回の結論だった。
それでは、このケアにおける「根源的な共同性」と贈与はどう関係しているのだろうか。これを問うていくのが、この連載の主題である。今回のイントロダクションではその方向
連載第1回 『ケアの贈与論』
イントロダクション(前篇) ケアと共同性岩野卓司
今の時代は不安に満ちている。
雇用の不安、老後の不安、先行きの不安。何となく生きづらい、安心できない社会である。
情報が足りないわけではない。メディアやネットには情報はありあまるほどある。たしかに情報は多いのだが、妙に実感に乏しい。正反対のことを言っているものもあれば、やれ陰謀論だ、やれフェイクだと言われているものすらある。何を信じてい
権憲益・鄭炳浩『「劇場国家」北朝鮮──カリスマ権力はいかに世襲されたのか』訳者あとがき(趙慶喜)
訳者あとがき
本書は、Heonik Kwon and Byung-Ho Chung, North Korea: Beyond Charismatic Politics (Rowman & Littlefield Publishers, 2012)の全訳である。翻訳に際しては、著者自身による本書の韓国語版、권헌익・정병호『극장국가 북한: 카리스마 권력은 어떻게 세습되는가』(창비, 2013
川村湊 『架橋としての文学──日本・朝鮮文学の交叉路』 より、「序章 架橋としての文学」 全文掲載!
1 “他者”としての朝鮮
私がはじめて“他者の文学”に出会ったのは、釜山にある東亜大学校の図書館の片隅だった。妻と、幼な子二人の家族とともに、ほとんど着の身着のまま、日本語講師として釜山に赴任した私は、日本語の活字に飢えていた(周りはハングルの森だった)。そのため図書館で「日帝時代(イルチェシデ)」(1910年から1945年の、日本が朝鮮を植民地支配していた時代。日本強占期ともいう)の古い日
テオドール・レッシング『ユダヤ人の自己憎悪』訳者あとがき(田島正行)
『ユダヤ人の自己憎悪』訳者あとがき
田島正行
本書は、Theodor Lessing: Der jüdische Selbsthaß, Jüdischer Verlag, Berlin 1930の全訳である。翻訳に当たっては、戦後復刊されたDer jüdische Selbsthaß, Matthes & Seitz, Berlin 2004および英訳Jewish Self-Hate, T
『ハントケ・コレクション1』 訳者あとがき(服部裕)
『ハントケ・コレクション1』 訳者あとがき服部裕
ハントケの作品について
ペーター・ハントケはデビュー当時からきわめて評価の高い作家である一方で、さまざまな物議を醸してきた作家であるとも言える。それはきわめて斬新かつ挑発的な言語表現に始まり、1990年代以降のユーゴスラヴィア問題との関わりの中でピークに達した。その意味で、ハントケが2019年にノーベル文学賞を受賞したのは、訳者にとってはむ
杉田俊介 『神と革命の文芸批評』 まえがき
まえがき
……思えば、大学生時代に柄谷行人の初期の文芸評論集『畏怖する人間』や『意味という病』、あるいは三浦雅士の批評集——『私という現象』や『メランコリーの水脈』や『小説という植民地』などのいかにも「ポストモダン」な書名を目にしただけで時代的ノスタルジーに溺れかけてしまうのだが——などを愛読していた人間として、雑多な批評文やエッセイを寄せ集めた評論集varietybookを刊行するとい
川口好美 第一批評集 『不幸と共存 魂的文芸批評』 後記
後 記
江藤淳についてのノートを長い “あとがき” を記すような心づもりで書いたので、ここでは簡単な事実確認のみにとどめたい。
本書には、商業誌デビューから現在までに書いた文章のほとんどが、おおよそ時系列で並べられている。一読してくれた方は〈こいつは7年という短くない期間、同じようなことばかり飽きもせず考えてきたのだな〉という感想をお持ちになるだろう。まったく同感で、自分自身呆れ