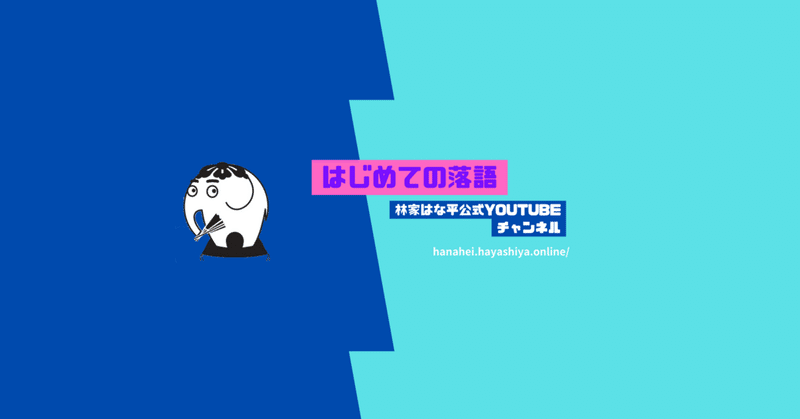
【あなたの知らない落語の世界】第3回 「寄席って何?」
今日は「寄席」について考えてみます。まずWikipediaによるとこのように書いてあります。
寄席(よせ)とは、日本の都市において講談・落語・浪曲・萬歳(から漫才)・過去に於いての義太夫(特に女義太夫)、などの技芸(演芸)を観客に見せる興行小屋である。
講談が先に書いてあるのは歴史が古いからだと思います。演芸を観客に見せる興行小屋というように、落語以外の芸も観られる場所ということがわかります。
その寄席について考えてみますが、主に東京をベースとしての考え方を記します。
①連続性がある
寄席と普通の落語会の違いは、連続してやっているかが鍵だと思います。都内には寄席が5軒存在します。上野鈴本演芸場、新宿末廣亭、浅草演芸ホール、池袋演芸場、国立演芸場(現在建て替え中)です。そのどれもが、ほぼ毎日興行を行なっています。しかも昼の部、夜の部とあるので、一つの寄席で大体700公演くらい興行を打っていることになります。
この連続性、継続性を持っているものを寄席と呼びます。特に、この都内5軒に関しては定席(じょうせき)とも呼んだりしています。
②場所が決まっている
連続性と同時に場所が決まっているのも寄席の特徴で、例えばホール落語の場合は会館などを利用します。なので、落語会以外の催しもやります。ですが、寄席は常設小屋です。
決まった場所で、連続してやるのを寄席というわけです。
③寄席は修行の場でもある(ドキュメント)
寄席の特徴として、「修行の場」というのもあります。落語家はまずどこかの師匠に入門しますが、落語協会や落語芸術協会においては、前座時代は寄席で修行します。
朝は師匠の家の雑用をこなし、それが終われば寄席に行くのです。これを毎日繰り返します。
寄席での仕事は多岐にわたります。お茶出し、着物を畳む、着付ける、ネタ帳を書く、太鼓を叩く、高座に上がる(前座は最初に上がり、プログラムにも載っていない)など、いろいろな仕事に追われます。
はじめて寄席に行くと驚くのが、プログラムには12時開演とあっても、その10分前くらいから前座が上がって落語をはじめます。つまりこれは、寄席側からすると料金外で、プログラムに出ている二つ目(修行が終わった人)からが番組ですよという意味合いもあると思います。
高座では、舞台転換も見せます。めくりと言って芸名の書かれた紙をめくる動作や、座布団をひっくり返す高座返し、手品の道具を出したりしまったり、幕を閉めることなくお客様に見せます。その舞台転換を手伝うのが前座の仕事です。時には失敗もあります。手品の道具を落っことしたり、めくりを間違えたり。でもそういうところも全て見せてしまうのが寄席です。
そういう修行風景も含めて寄席演芸なのかもしれません。この良さは独特な部分で、寄席に何度か通うと味わうことができます。ぜひ通っていただきたいですね。
番外 タイトルに「寄席」と使う話
落語会に「〇〇寄席」と使われている場合があります。もちろんこれはあくまで本当の寄席の意味じゃなくて、タイトルだけです。「寄席」「演芸会」は落語会のタイトルに使われることが多くて、全体的な傾向としては「寄席」をタイトルに用いる場合は、毎月開催など、継続して行われているものに使われているような気がします。
今日寄席というものについて考えてみました。明治に寄席が盛んだった頃は、町内に一軒くらいあって、東京には数百軒あったとされています。
ぜひ、今は貴重な寄席に足を運んでみてください。
落語について、また過去の思い出等を書かせて頂いて、落語の世界に少しでも興味を持ってもらえるような記事を目指しております。もしよろしければサポートお願いいたします。
