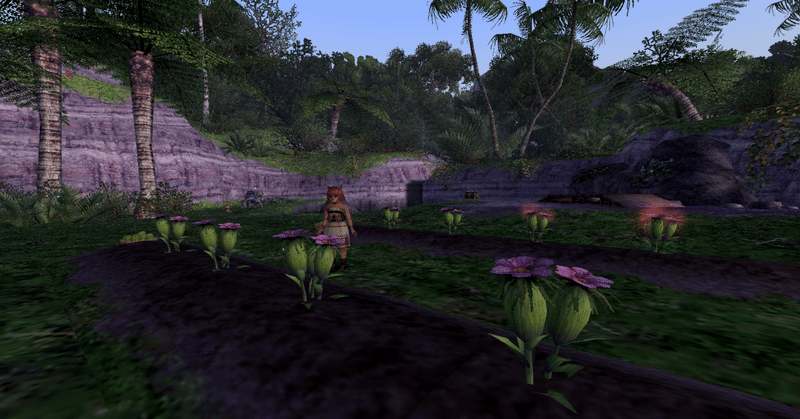
死とベーシックインカム(後編)~メタバース経済とMMTを考える
MMORPGの経済・社会を通じてベーシックインカムの可能性を考える話の最終回です。直接お金を配るのとは違うものの、生活を下支えする意味でベーシックインカム的な要素のうち、今回は残り2つの仕組みを紹介します。が、その前にちょっと寄り道をして、関連要素としての"住宅事情"を踏まえておきたいと思います。
MMORPGの住宅事情に学ぶ

MMORPGはその元祖である『ウルティマオンライン』(UO)の時点で、空き地に家を建てられるシステムがありました。そのため、「MMORPGでは家を建てられて当たり前」という意識が働きます。
ただUOとは方向性の違う、冒険生活シミュレーター的な要素が弱く、バトル主体でヒロイックに遊ぶタイプのMMORPGでは、家を建てられないケースもそれなりにあります。
FF11も、家を建てられません。がっかり。みんながっかりです。
ただFF11では、そのかわりに誰もが"レンタルハウス"を与えられる仕組みになっています。海辺の家だ、森の一軒家だ、というかたちで任意の場所を選んで家を建てることはできないものの、出身国にマンション的な建物の一室が用意され、他国でも別荘のように同様の部屋を利用できるのです。しかも「レンタル」と言っても無料です。
見過ごされがちですが、ここに重要なポイントがあります。
一見、家を建てられる世界の方が良さそうに見えますが、家を建てるには当然それなりの資金が必要になります。そして、家を維持するにも契約(リアルマネーでの課金)を継続するなどの条件が課せられます。表面的には"マイホーム"と呼ばれますが、実際にはこちらの方がよっぽど"借家"なのです。
しかもマイホームの概念がある世界では、逆に"マイホームを持っていないこと"を前提とした設計にする必要があり、野宿だったり、宿屋が休息の基本になってしまいます。これはプレイヤーに対して、自分が「根無し草」だという感情を抱かせます。しかし、全員にいつでも帰れる個室を与えられたFF11のプレイヤーにはこのネガティブな意識がなく、他のMMORPGのプレイヤーと違う「民族性の違い」のひとつになっていると考えられます。
なお宿屋型MMORPGは、冒険の終わりに宿屋で休息(ログアウト)することに対して何らかの特典が与えられることが多いのですが、FF11のレンタルハウスにそんな気の利いたものはありません。にもかかわらず、プレイヤーたちは冒険の終わりにきちんと家に帰ることが普通になっており、これについてはプレイヤーたちの様子をモニターしてきた運営スタッフも意外だったと述べています。今でこそワープ手段が豊富に用意されているのですが、サービス開始初期からしばらくは10分以上かけて歩いて帰ることも普通でした。
いちいち家に帰る理由は人それぞれですが、ゲーム開始時の最初の選択が"所属国の選択"であることも相まって「愛国心」のようなものが醸成されていることが理由のひとつ考えられます。それは、ゲーム内の国への愛着であると同時に、FF11自体への帰属心にもつながっています。単に古いものだから懐かしいだけでなく、世界との距離感が近いのです。
家を建てられるタイプのMMORPGの場合、しばらく休眠していたプレイヤーが復帰すると、まずは「家がなくなっている」という状況に直面しますから、復帰する気を低下させます。まさに「居場所がない」のですから。
「根無し草」意識は現実社会においても、大きな問題です。特に地方では、「若者が都会へ行ってしまう」などと悲嘆に暮れていないで、まずは若者に自分の居場所を与えるべきです。親が少々広い土地を持っていたとしても、巣立ちの時を迎えた20歳前後の若者は親の近くでなんて暮らしたくないものですし、自ら部屋を借りるとなれば遠くへ行ってしまうのも当然です。
親は「将来2世帯、3世帯で暮らすぞー!」と期待して大きな家を建てても、その気持ちを子どもが受け入れるかどうかはまた別です。特に地方において「親元か」「都会か」の2択を強いるような状況を続けることは「若者を追い出しにかかっている」と言われても仕方がありません。
裏庭で資源供給『モグガーデン』

正確に説明するとややこしくなるので誤解を承知で簡単に説明しますが、『モグガーデン』は、前述のレンタルハウスの"裏庭"のようなものです。
この裏庭では、毎日、木を伐採したり、鉱石を掘ったり、畑の農作物を収穫したりできます。前回触れた『ゴブリンの不思議箱』と同じく、出土したアイテムを売ることでお金にできます。得られるものは基本的に安い素材類がたくさんで、希少性が低いため高額品はありません。
これもゲームならではの"無から有を生み出す"ものなので、そのまま現実社会に置き換えることはできません。ここで着目すべきポイントは、意外と時間をとられるため、やると損になる場合があることです。
このシステムの背景には"ネトゲ廃人問題"が見え隠れします。
もともとMMORPGは"Time to Win"(時間をかけた者が勝つ)と言われ、学校に行くでもなく、働きもせず、長時間ゲームで遊んでばかりの「ネトゲ廃人」を生み出したことが問題になりました。逆に言えば時間を浪費できるプレイヤーの存在に頼らなければ、満足にモノが流通しなかったとも言えます。そう考えると、なんだか現実の日本社会とも似ていますね。職をなくせば自分が何者なのかを定義できなくなるような"仕事廃人"を生み出し続けているわけですから。
MMORPG全般では、武器や食事などのアイテムを合成するための素材を入手するには、海へ行って魚を釣り、森へ行って木を刈り、山へ行って鉱石を掘り、としなければならず、猛烈に時間を浪費します。FF11におけるモグガーデンは、この移動の手間を省略し、あまり時間をとれないプレイヤーでも資源の流通に寄与できるようにした仕組みです。現実社会で言えば、テレワークでECサイトの注文伝票管理の仕事をやるようなものでしょうか。
ただ、移動の手間なく作業できると言っても、それでも15分とか、入手した素材類を的確な値段で処理しようとすると30分とか、それなりの時間がかかります。そして、それによって得られるお金は大した額ではありません。
高く売れる戦利品を得られる機会のないビギナーや、今日は30分しか遊べない、という日ならモグガーデンで小銭を稼ぐのもいいのですが、中級以上のプレイヤーが1時間以上時間をとれるなら、モグガーデンでの素材入手はスルーして同じ時間でほかのことをやった方が得になります。
なお、モグガーデンで得られる素材類は、誰かにとっての必需品ではあるものの、供給過多になるため競売での売れ行きは悪く、NPCに売却されるものが多いので、システムから貨幣を生み出す機会にもなっています。
"あまり儲からないけど必要なもの"の供給を貧しい人の仕事にし、余る場合は貨幣の供給源にしている、と捉えると現実社会での置き換えがイメージできることでしょう。学生や求職中の失業者ならこの仕事を受けるけど、ITエンジニアなら絶対遠慮する、という感じです。あるいは単純にお金を配るだけのベーシックインカムのかたちをとるなら、「月5万円あげるけど、所得税は20%増税(=月収25万円を超えると損する)」という感じです。
ところで経済的な意味はほとんどありませんが、モグガーデンではペット(モンスター)の育成も可能です。現実社会で若者に家を与える場合も、ぜひ「ペット可」にしてほしいものですにゃ(誰)。
ついでのポイント換金制度

FF11には『エミネンス・レコード』と『ユニティ』という制度があり、これまた誤解を承知で言うと、スマホゲームとかにもよくある"アチーブメント"的な仕組みです。日常的にゲームをプレイするなかで"一定数のモンスターを倒す"などの目標を達成した際にポイントが付与され、このポイントを換金できます。
なにもせずにお金を貰えるわけではないのでベーシックインカムとは異なりますが、特に意識して行動せずともなんだかんだでポイントが貯まり、気付くとまとまったお金になるので「貰った感」が強めです。現実社会で言えば、1日に5000歩あるくとポイントが貰えるとか、やりとりした職場の上司の人数に応じてポイントを貰えるようなイメージでしょうか。
これも結局は、"モンスターを倒す"というお題を達成することでついでにアイテムも入手することになるため、いらなければそのアイテムを流通させることで社会に貢献し、その報酬としてポイント=お金を得る構造になっています。ゲーミフィケーション(老朽化したマンホールを見つけるためスマホで写真を撮る等)に参加すると、お礼を貰えるようなものです。
なお、数年前までこのポイントを換金する量に制限がなかったので、FF11の経済はみるみるインフレしていきました。現在は上限が設定されて週に約200万Gに抑えられたのですが、以前は集中して頑張れば一晩で数百万G稼ぐことも可能でした。普通に淡々と冒険するだけなら週に10~20万Gもあれば充分ですから、残りは貯金しつつ、月に1回は少し強い武器など大きめの買い物をできる感じです。
ただしポイント換金制度もモグガーデンと同様で、ベテランはベテラン同士で集まるなどして強敵と戦った方が大きな利益を得られます。そして、強敵と戦う機会が多いほどモンスターを倒す数自体は少なくなりがちで、ポイントが貯まりにくくなります。先ほどの現実社会に置き換えた例で言えば、職場のすぐ近くに住める余裕のある人は5000歩も歩きませんし、地位の高い人ほど上司の数が少ないので、得られるポイントが少なくなるイメージです。
社会貢献への帰結
ところで、社会貢献で報酬をもらうというのはいわば公務員さんのお仕事です。実情として、社会に貢献する仕事のうち必要性のより高いものを公務員が担い、それより優先度が少し低いような社会貢献活動・慈善事業をNPOやボランティアなどが行なっています。ここからさらにこぼれたものについて、ゲーミフィケーションのような感覚で携われる機会を作り、そこに少額の報酬を出すことからベーシックインカム的なことを始められるように思えます。
"社会貢献"は広めに捉えることにして、例えば国内の企業が抱えるウェブサービスなどをテストして、使用感や見つけたバグをフィードバックすることも含めていいのではないでしょうか。これは"国力"を高ることにつながりますし、財源として少し法人税をあげるとしても納得感があります(税は財源ではないという話もありますが、それは置いておきます)。
それこそMMORPGにはまっているような人たちは、ユーザビリティ(使いやすさ)について鋭い嗅覚をもっており、力を発揮できるはずです。「廃人」なんて呼ばれてまるで死者のように扱われることもありますが、彼らの多くは一般社会では経験しにくい幅広い層との真剣な交流を通じて、実は多くの社会経験を積んでいます。彼らがMMORPGの世界に閉じこもることがあるとしても、それは必ずしも現実逃避をしているとは限らず、むしろ外の世界こそが死んで見えるせいかもしれません。
モノやサービス、そして人があるべき場所にあるようにするには、システムもまた多様なかたちで社会を支える必要があることをMMORPGは教えてくれます。世の中の変化を求めるとき、ぼくらはなんとなく「偉大なシステム」によってそれがなされることを想像してしまいます。しかし大きなシステムは不器用で、そして流動的な社会に当てはめるのは難しいものです。
今回の記事で紹介した3つの仕組みは、それぞれは「そんなもんか」と思わせるような一長一短ある小さなものです。でも、社会全体も経済も、人と人とが関係し、支え合ってできているわけですから、システムだって同じなのではないでしょうか。システムもまた小さく生まれ、やがて社会に馴染んでいくうちに力を発揮できるようになればいいのですから。
そのために必要なことは、「偉大な者がなんとかしてくれる」という物語を信じることではなく、継続的に細かい部分をよく見ていくことです。日本に限らず、世界の経済はバグだらけなのは間違いありませんから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
