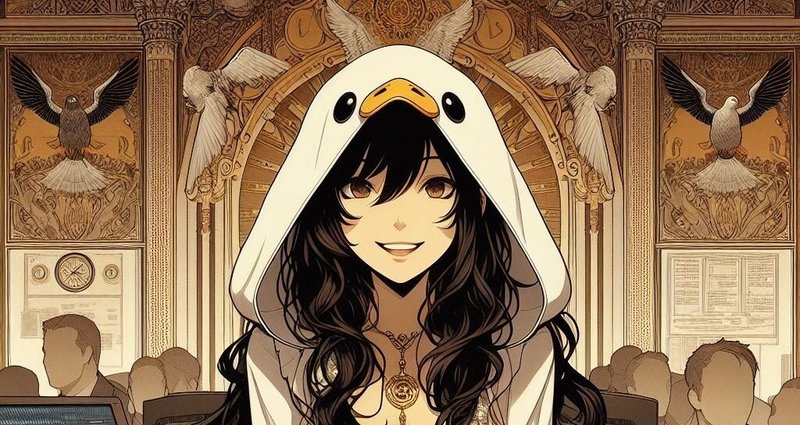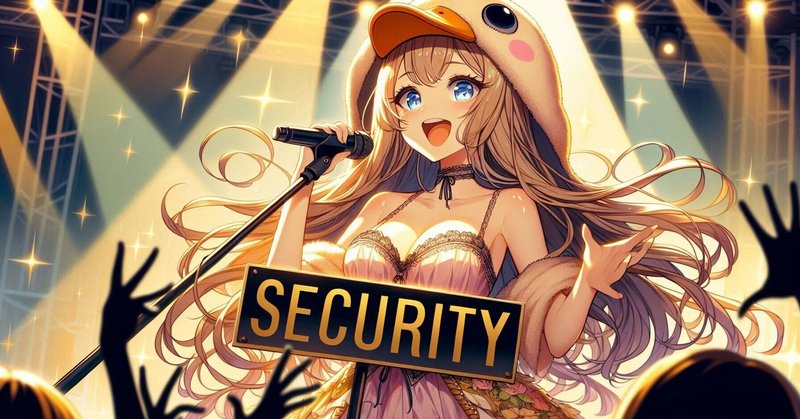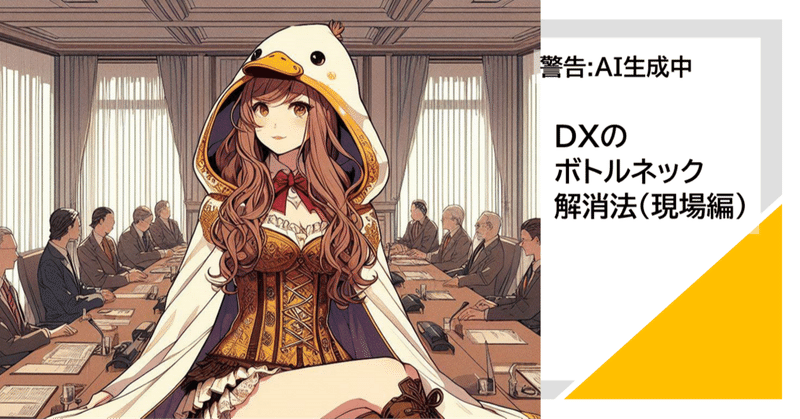記事一覧
DX閑話〜国民的サイバーセキュリティ総選挙
国民のためのサイバーセキュリティサイトが更新されたらしいです、今回、私が注目したのは、PPAPを無効と言い切った事。(以前から?)
日本は上場企業がPPAPソリューションを未だ売っているような状況ですので、なかなか大変だなと。
サイバーセキュリティに無関心な人=社会人失格国民的サイバーセキュリティの「国民的」の意味は、社会人なら、やって当たり前のレベルである事を示しています。
「鍵をかける」
DX閑話~ゴミプロセスをデジタル化したところで、ゴミはゴミ
DXとドヤ顔するならゴミプロセスは捨てようデジタル化の進展は、ビジネスプロセスを根本から見直す絶好の機会を提供しています。
重要なことは、単に既存のプロセスをデジタルの形に変えることではなく、「デジタルという道具を使ってスマートなプロセスを組むこと」です。このアプローチにより、効率性、透明性、そして柔軟性が大幅に向上します。
デジタルツールは、プロセスの各段階で情報の流れをスムーズにし、意思決