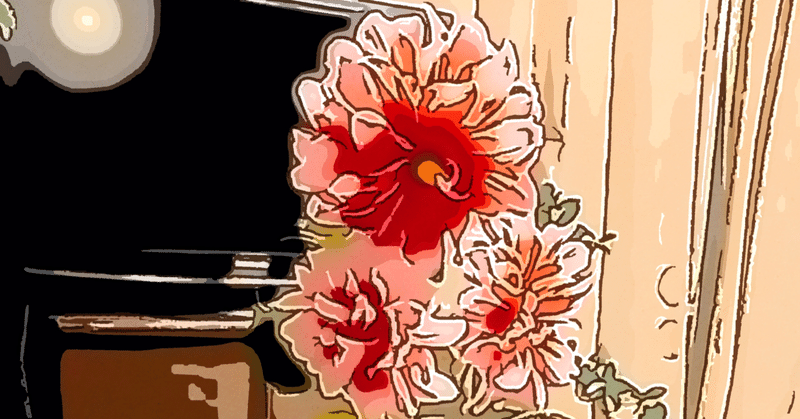
発達段階(7)
最後に参考になるかは分かりませんが、
鳳凰堂の幼少期を振り返ってみます。
1歳前後の記憶や小学一年生時の記憶が鮮明にあり、幼稚園時は泣き虫、小学一年生から急激に自我が発揮されいました。
身体的には小学3年生辺りで小児喘息と言われましたが、当時近所の診療所の先生は運動していれば良いよと言われ、水泳を始めると共になくなっていきました。
今考えると小学六年間、特に後半は必ず協調性がないと書かれ、今小学生だったら確実に発達障害と言われていた可能性が高い少年時代でした。
この時の現代医学の先生は、田舎だったからかもしれませんが、
額に手を当て、目を見て、喉を見て、聴診器でお腹と背中を診てと
真剣に子供と向き合ってくれた印象があります。
現代医学的には、喘息は肺、呼吸器系の疾患ですが、東洋医学では常にお腹と心理状態を考えます。
原因と今できることを分けて、今できることをやりながら、最終的には原因にアプローチする。
小児喘息で、お腹がちょっと出ていたり、体内から水の音がするようなら、飲食(冷たいものや添加物の過剰摂取)について考えたり、誰かの一言やいつもいる場所の空気感によるもの等を考えると言う観点もあります。
何より、発達途中でドンドン変化し、エネルギーが余っている事が多いので、落ち着きがない子であれば、湯沸かし器が沸騰しているようなもの。
しっかりと全身運動をしてもらうとすぐに就寝します(当社比)
あくまで鳳凰堂自身の事例の一部を記載したものですので、様々なバリエーションがありますが参考までに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
