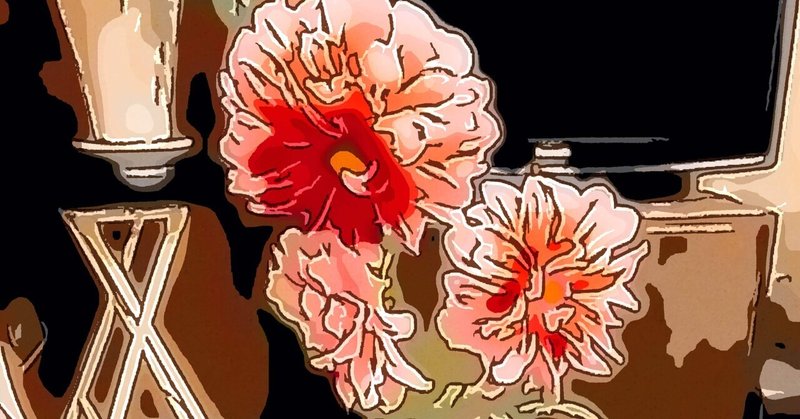
発達段階(1)
東洋医学では人間の発達段階を男女で分けて論じています。
東洋医学最古の古典である黃帝内経素問。
その中の一番最初の篇である、上古天真論篇第一には次のように書かれています。
女子七歳腎氣盛んに歯かわり、髪長ず。二七にして天癸至り、任脈通じ、太衝脈盛んに、月事時を以て下る、故に子あり。
丈夫は八歳にして腎氣実し、髪長じ、歯かわる。二八に腎氣盛んに天癸至り、精気溢れ瀉(そそ)ぎ、陰陽和(か)す。
基準としては、女性が七歳から七の倍数、男性は八歳から八の倍数で書かれています。どちらも変化が起こる様は同じで、第二次性徴期は女性が十四歳、男性が十六歳が基準になります。
近代中医学における小児科学では、小児期は肝氣が旺盛で、脾氣が弱いのが普通です。
つまり、成長期に身長が伸びる事で追いついていない部分は痛みや病気と称される状態になるのは普通で、この場合主に脳及び上半身を調える事でバランスを取ります。
東洋医学では散り気の灸と言って、一般の人に背中の第二・第三番目の背骨の間(身柱と言うツボがあります)にお灸を勧めています。
また、頭を撫でる、軽くトントンと叩いてあげる事で、成長期に脳神経が異常興奮するのを治めてあげたりするのは、夜泣き、疳の虫、小児の癲癇(てんかん)等には効果があります。
纏めると頭で起こる捻挫のようなものだったり、神経と身体の発達のバランスが取れていないのが小児。
十二歳くらいまでは、思考力よりも身体の発達が主体になります。
その分アンテナ(感受性)は鋭く、まだ母親の感性、感情も自分の感覚として受け取っている場合があるので、お母さんは一緒に成長すると共に、
1、お母さん自身の心と身体を整える
2、その為の環境づくりをする
この二つは大切です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
