複雑性、家族、公共性、モノローグーー『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学するII 』丸山俊一+NHK取材班
NHKのディレクターである丸山俊一さんから、著書を頂いた。
丸山俊一さん @shunzzzz1 から頂きました。放送から出版までのスピード感…!
— Y. Tanigawa🦊 (@mircea_morning) April 2, 2020
『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学するII』 https://t.co/AOVWP6HtXm
哲学者の責任として「私たちは呼ばれたら対応する必要がある」、「求められたら答えるべきだ」と述べた箇所が特に印象に残りました。 pic.twitter.com/QojgZH3RJx
新刊の『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する:自由と闘争のパラドックスを越えて』(NHK新書)である。
ぼちぼち思いつくままに、雑感を書いてみようと思う。ちなみに、まだ発売していないので、全世界最速のレビュー。たぶんこれが一番早いと思います。
1.NHKドキュメンタリー
これは話題を呼んだ、2020年春の番組を元にした本で、下記のシリーズを踏襲し「欲望」や「資本主義」に焦点が当てられている。
本編では、デイヴィット・チャーマーズ、クリスチャン・マスビアウ(『センスメイキング』)、カート・アンダーセン(『ファンタジーランド:狂気と幻想のアメリカ500年史』)など、一流の知性たちとの対話も織り込まれていて、私自身は、第三夜と第四夜を見ることができた。(ほかは見逃した。)
個人的には、ガブリエルが街中の人に話をふっかけたり、ふっかけられたりしている姿、その会話はドキュメンタリーのワンシーンとしてとても好きだった。
残念なことに、書籍の中では、知識人との対話や街中の発言は削られており、ドキュメンタリーの雰囲気がどれほど残っているかというと、少し判断に迷う。(この点は最後に取り上げ直したい)
余談だが、前のシリーズについても少し何かを書いていたのでリンクを貼っておく。
2.社会の複雑性をめぐる思索
この本で個人的に興味深く思ったのは二点――社会の複雑性に関する指摘と、哲学者としての自身の役割を語ったことだ。順に見て行こう。
いま世界中で起きていることを人々は脅威と感じ、さまざまな危機を感じているわけですが、それは人々がその複雑性に対応しようとしている証拠です。(p. 21)
複雑性を増す世界の中で、人は、自分が諸々の出来事を十分理解できていないだけでなく、それに有効感を持って関わることができない、ということを痛感している。
そこで生じかねないのが、シニシズム(冷笑主義)と原理主義である。上に名前を挙げたカート・アンダーセンは、狂気と幻想が時代を支配していると考えた点で、原理主義をより重大な問題と見ていた。マルクス・ガブリエルの価値づけは判断しかねるが、原理主義という問題の重要性については、本書でも語られている。
多くの人々は、その複雑性を大幅に減らすべく「社会の本質についての幻想を作り出して対処しようとしている」(p.21)。そこで哲学者にできるのは、理解不能なダイナミクスの犠牲者にならないように、哲学的ツールを使って、「この複雑性の力学を理解する」手助けをすることだ、と(p.22)。
社会の複雑性を問題視する姿勢そのものは、以前からある。例えば、政治学者のウォルター・リップマンは、『漂流と熟達』(1914年)という本でこんな風に述べている。
……私たちは文字通りエキセントリックな〔=中心から遠い〕人間になっており、感情的生活は無秩序で、私たちの抱く情熱も不調をきたしている。ラディカルを自認する人たちは、古びた信条や新しいが未熟な考えの漂流物の只中で、どうすることもできず水流に浮かんでいる。彼らは、自分たちを運んでいる動きを、自分たちの意志によるものだと誤認するきらいがある。理論に秀でているとは思わない人々は、流行つまり「熱狂(crazes)」に激しく振り回される――帽子店や服飾店、演劇プロデューサー、広告キャンペーン、そして、新聞のマッチポンプ的なゴシップのなすがままなのだ。(p.93)
消費主義の問題を織り込んで、社会の複雑性を問題視している点で、リップマンには、ガブリエルの本書の態度に非常に近いものがある。
実のところ、ガブリエルが本書でしているように、リップマンは、その後の仕事で「社会そのもの」の適切な描像を求めているので、両者の仕事は重なるところが多い。
要するに、社会の複雑性をめぐる思索は、古くて新しい問いであり、言ってみれば、未決のままの問いでもある。そしてそれは、「幻想」や「流行」をキーワードにしながら、深いところで「資本主義」や「消費」と結びついた問題でもある。
3.私たちは「家族」ではない
ガブリエルによると、哲学者は、ある概念が本来何であるのかという問いに答えようとする(p.22)。それが哲学者の一つの役割だという。
現代においては、多くの人が「社会の本質」を誤解していることは、大きな問題だと彼は考えた。
……多くの人々は、……社会の本質についての幻想を作り出して〔複雑性に〕対処しようとしているように、私には思えます。これは、この時代の根本的な問題です。(p.21)
ここでいう「幻想」とは、「社会を家族の比喩で捉える見方」であり、彼の社会観は、これを批判した先にある。
pp.77-80の辺りで、古代ギリシアの小都市(ポリス)は実に家族的なコミュニティだとか、イタリアのマフィアの精神性だとか色々な事例を用いて、「社会を家族的に捉えること」が説明されているが、ちょっとわかりにくい。
私の理解する限り、この見方が現代において問題となるのは、この社会観が、同質的で狭い範囲で通用する規則を素朴に押し広げ、スケールさせていくような社会観だからだ。
この辺りの論点を、私なりにざっくり解説すると、以下のような感じ。
現代は、様々な地域や社会が結びつき合って成立しており、私たちは異なる性質を持っているにもかかわらず、この見解の下に社会・経済活動を行う人々は、「一つの社会」という強く均質的な世界を描こうとしてしまう。
家族であるという認識が、ほかの人々の生き方にまで自らの生き方を強要するように働きはじめるのです。(p.83)
社会ダーウィニズム(社会進化論)のような、現在の成功者を肯定するロジックは、現に成功している者のやり方を敷衍することを正当化する「生存」の論理でしかないが、私たちが保護すべきなのは、成功者の論理ではなく、私たちの「生活形式」であり、様々な文化や環境ではないのか。
ガブリエルが「倫理」という言葉を繰り返し登場させるのは、そのことをオーディエンスに思い出させるためだろう。
むしろ、私たちはばらばらであり、違う。それゆえ社会を複数形で理解すべきなのだと彼は指摘する。
ちなみに、リップマンの『幻の公衆』で、社会は単数形でなく複数形で捉えられるべきだと繰り返しており、本書は彼らの共通点を感じさせた。
4.公共知識人の領域侵犯と「迷い」
本書には、哲学者や哲学の役割に関するフレーズが頻出する。
「哲学者は、ある概念が本来何であるのかという問いに答えようとする」という先に見たフレーズは、その好例。
私自身に関しても、象牙の塔を好む人が、私の名声を攻撃したがるというリスクはありますよね。もちろん、あらゆる種類の社会的リスクもあります。それが普通です。(中略)しかし哲学者の責務として、求められたら答えるべきだと思います。責任は恐怖に勝利するでしょう。(p.145)
公共知識人(public intellectual)という、日本ではあまり導入されていない概念があるが、恐らくガブリエルはそれを目指しているということなのだろう。(概念の詳細はググってください)
正直のところ、その態度に私は好感を持っている。彼の主張をよく聞けば、実は突飛なことを言うことは少なく、実に良識的で、穏当であることがわかる。
今すぐプラスチックを止めた方がいい、動物実験には反対などの良識的であるがゆえにラディカルな主張もあるにせよ、彼の主張やその理由は、正論として理解可能だし、自分の主張にするかはさておくなら、「まぁそれはそうだよね、理屈としては」と多くの人が共感可能なものだろうと思う。
ただし、彼が「求められれば何にでもコメントする」という側面を持っているかもしれない点に、読者は注意深くある必要はあるだろう。
丸山真男やエリック・ホッファー辺りが批判しているように、専門性を逸脱して何にでもコメントしたがり、話を聞いてもらいたがるのは、知識人の悪癖である。ガブリエルにそうした悪癖が見出せないでもない。
こんな記事も書いたことだし、私はこのことに大いに同意する。
しかしそれにもかかわらず、トランスサイエンスだ、学際融合だと叫ばれている現状で、「お互いの役割に閉じろ、専門以外には口をつぐめ」と素朴に言ってしまう専門家は、これまでの歴史から、反省から何を学んできたのかと思う。
お互いの役割を踏み越え、領域を多少侵犯し合いながらでなければ、専門家同士が適切かつまともに協働し合うことなんてできるんだろうか。役割に閉じて出ないままの関係性から、専門家同士のまともな協力関係やアウトプットが出てくるとは思えない。
(ここで言っているのは、主張の中身を批判するなという話ではなく、専門家が自身の専門領域を越えていくこと自体は批判されるべきではないという話。)
こうした専門分野の領域侵犯は、「迷い」を抱えながら進めるしかないものだろうし、「迷い」を捨てずに、しかし積極的に領域を踏み越えるガブリエルの態度には好意的なものを感じずにはいられない。
今回の本では、マルクス・ガブリエルも「迷い」を抱きながら発信しているのだと感じるフレーズがしばしば登場したことが印象的だった。(もう少し素朴な人だと思っていた。)
こうして私がカメラを通して哲学を語り掛けることについても、これをご覧になるみなさんの中には哲学の専門家もいることを考えると、実は複雑な感情を抱くのです。(中略)いま私は哲学者としてみなさんに、もちろん自分の活動を通して関わっています。しかしこれが最善の方法ではない場合もありますよね。人間関係は、必ずしも哲学的な反省によってうまくコントロールされているわけではありません。(中略)……心理療法士は、心理療法士である能力を自分の妻や子どもたちに発揮することができません。(p.214)
5.モノローグ的文体
本書の中身とは間接的な関係しか持たないことではあるが、大いに不満を抱いた点がある。それは、いわば「文体」の問題だ。
グローバル資本主義だとか、安易にスケールしていく多国籍企業的世界観を批判しながらも、本書の展開や主張はとても抽象的に感じる。「ニューヨーク」で展開された思索であることは、帯を見なければ気づかないのではないかと思われるほどだ。
本書は、全体を通してガブリエルのモノローグで構成されている。
そこには、街中で出会った人との会話、地下鉄や廊下など移動中のふとした冗談、移動中の景色、説明がなされたときにガブリエルが知覚していただろう光景、彼の対話相手に関する情報の一切が存在しない。
私が見た第三夜辺りでは、かつて住んでいた地域を訪れたガブリエルが、現在その辺りに住んでいる住民と、過去と現在の地価の変化について会話する、というシーンがあった。それは、ドキュメンタリーの全体を構成する微々たるものにすぎないし、重要とも言えない。余談と言ってもいい。
しかし、細部を削った先にあるのは、わかりやすさでも、深みでもない。そこに残るのは、陰影を人為的に平板にした、ぎこちなく抽象的な要約なのではないか。
本書の内容そのものはわかりやすい(と思う)。しかし、映像にはあった細部が削られてしまっていることで、失われた魅力が目につくことも事実だし、いくつかの説明が映像ではわかりやすく感じたのに、文字ではニュアンスが読み取れないこともあった。
もし「欲望の時代を哲学する」に続編があるならば、ドキュメンタリーなら描けていた細部を盛り込んでほしいと感じた。モノローグには、モノや人とのダイアログがあった。
例えば、小説のような文体を用いる――地の文と会話を使う――というのは一つのやり方かもしれない。
文体は些末な問題ではない。西洋哲学史を、主張(だけ)ではなくレトリックの重要性を評価する歴史として捉え直すことができるほど、レトリックや文体は重要な論点だと私は思う。
「忌憚のない批評を」と著者自身に言われたので、一人の読者として感じた問題点を提出しておく。
『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学するII』は、4月10日発売である。You ain't seen nothing yet!
なお、カート・アンダーセンの『ファンタジーランド』については以前書評したことがあるので、こちらもぜひに。
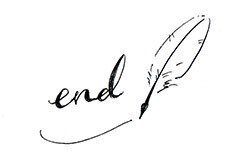
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
