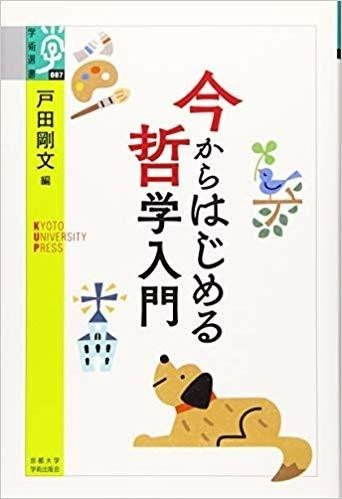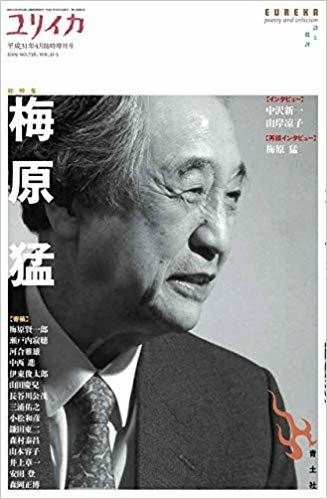研究紹介 2020年度版
研究者の谷川です。
研究業績、社会貢献活動については、こちらをごらんください。
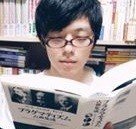
0.自己紹介
主たる専門は「哲学」です。ただし、哲学の知識を活かしたり、哲学で培ったスキルを汎化したり、あるいは、新しく知識やスキルを身につけたりして、やれることは何でもやるという研究スタイルを採用しています。
それゆえ、教育学、観光学、文化社会学など、複数の副専攻、複数の専門を持っています。いずれも論文等の成果を出しています。
修士の頃、大抵の人文社会系の専門の入門書・概説書を各10冊程度読む、各専門分野内の小分野(例えば教育学の「教師論」など)でさらにそれを繰り返す、またさらに……という読書をやっていました。それもあって、人文社会系については、学問上の「地理感覚」があると思っています。
加えて、パズルの制作・解決に向いた頭をしているようで、テーマを見つけると、手持ちの材料と、ありうる調査で何が言えるかということを考え、大抵は何か論文の種になるものが見つかります。
寄稿・講演・調査も、テーマや制約について相談さえできれば、同じように対応できるので、依頼があればご相談ください。
こうした背景ゆえに、副専門が複数に増え、主専門たる哲学でも幅広い研究を数多く行うことができたわけです。また、数が多く、幅広いといっても、表に出た研究の質は一分野に注力している研究者に一切劣らないと自負しています(内容への批判は歓迎です)。
多岐に渡る研究ですが、いずれも相互に関連するキーワード――「創造性」「有限性」「可能性(理念)」「想像力(自発性)」「共同性」――を中心に展開していると説明がつけられます。
マインドマップを作ったら、これらの概念がノードになっているイメージでしょうか。
しかし、これらのキーワードから出ないように思考するわけではありません。
木を切るのにチェーンソーが、空腹を満たすのにチーズケーキが適切であって、それらを逆にできないように、主題や道具に応じた思考があると考えており、必要に応じて異なる概念・方法・語彙を用いています。
1.John Deweyを通したアメリカ哲学研究
これまで、John Dewey, C. S. Peirce, William Jamesといったプラグマティストと、その周辺の社会心理者・神学者・政治学者に焦点を当てて研究してきました。ここでは、学位論文の概略を紹介します。
Deweyについては、二つの仕方で掘り下げました。
Walter Lippmann(政治学・社会心理学), G. Wallas(政治学・社会心理学), R. Niebuhr(神学・社会思想), D. J. Boorstin(歴史学・消費社会論・社会思想), G. S. Hall(心理学・教育学), Erich Fromm(精神分析学・社会心理学)といった同時代人との影響関係を検討する。
R. Rorty(哲学), John Rawls(政治哲学), D. Davidson(分析哲学), S. Cavell(哲学・文学)といった現代の思想家や現代宗教学などの知見との比較を行う。
こうした人名の多さは、私の研究スタイルだけでなく、私が中心に据えた人物の特異性に由来しています。Deweyの天才的なまでの「影響されやすさ」です。要するに、彼は学ぶことにおいて類まれな才能を持っていました。
それゆえ、Deweyは、田舎の森で沈思黙考するような孤高の哲学者ではありません。M. エンデの『モモ』ではないですが、彼は「人の話を聞く」ことができたのです。
同時代の出来事や論争に、注意深い観察とともにコミットし、過去や同時代と会話を積み重ね、学んだ知見を総合する中で、自身の哲学を彫琢しました。
逆に言えば、Deweyの知的総合をほどくようにして調査を重ねることで、同時代の問題状況とそれに対する様々な知識人の応答を見ることができるのです。当代一流の知性によって研ぎ澄まされた、時代の集合知を彼の哲学に見ることができると言ってもいいでしょう。
そのようにして、20世紀のアメリカ知識人が、都市化・商業化・大衆化といった「近代」に伴う社会変動にどのように関わったかを明らかにしました。
具体的には、共同性の構築、原理主義などの宗教的「覚醒」、知的独立性(自律性)、プライバシー、有限性と創造性、共生と協働、政治的疎外、消費者民主主義、知識人と哲学の役割といった、現代にもそのまま通じる問題がそこで扱われました。
2.日本哲学研究――新京都学派と『思想の科学』を中心に
これまで鶴見俊輔を中心に研究を行い、新京都学派の「言葉と教育」という研究会を共同で主催してきました。
いずれも書籍刊行を見据えて活動しています。
3.哲学と社会学をつなぐ――社会学の学説史的研究
デューイは、シンボリック相互行為論の起源の一人とされる人物であり、確かに、H. ブルーマーやT. シブタニらが好意的に彼に言及しています。
哲学の専門知を土台に、アメリカ哲学とアメリカ社会学をつなぐ、具体的な線を明らかにする理論社会学的な研究を進めます。翻訳による貢献も予定しています。
4.テクノロジーに関する理論的研究
私はこれまでメディア論や社会哲学に相当する分野で、新しいテクノロジーの登場が、どのような文化を生み出すか、どのような「感性」の変化をもたらすか、社会のあり方がどのように変わるのかといったことを研究しています。
テクノロジーと、それが生み出す文化に関する研究。具体的には、ボーカロイドのように「ジャンル」を形成しているメディアコンテンツと集団の凝集性など。
理念を伝えるテクノロジーに関わる研究。具体的には、プロパガンダなどのメディアとメッセージの関係、メディアコンテンツと知覚の関係、感性論からみたモビリティやゲームなど。
加えて、テック系企業との協働を進めており、絶えず「現場」からフィードバックを得ながら、テクノロジーに関する言論を適切な場所に届けていきたいと考えています。
5.メディアコンテンツ研究
ゲーム、音楽、アニメーション、マンガ、小説などのメディアコンテンツの研究を進めています。
ブログ等には「好きなもの語り」があります。この種の言説の価値を否定するものではありません。ただ、そうした分析が本当に批評性を持つためには、具体的な分析が議論として洗練されているだけでなく、その分析によって理論的な貢献がなされる方が望ましいのも事実です。
つまり、哲学・社会学・観光学・メディア論など、何らかの分野の「理論」をベースにコンテンツの研究を行うだけでなく、その分析を通じて、理論自体にフィードバックが得られるような研究を行っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?