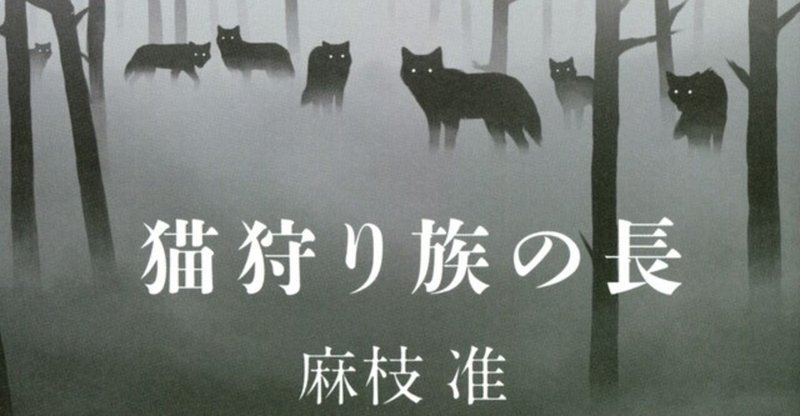
死にたい 願望 生きてほしい 願望
猫狩り族の長を読み終えた。小説作品にこんなことを言うのはなんだけど、もうストーリーについてはあまり触れるつもりがない。それは面白くなかった、破綻しているという意味じゃない。安心してほしい。依然変わりなく麻枝准の言葉は、思想は魅力に満ちていたし、お話の枠には思った以上にカッチリハマっていた。
だけどそれは考えてることを効果的に発するための箱であって、虚構の部分であって、彼がこの小説を発表するに至った理由「初めて本当に思っていることを書きました」って軸を喋るのにブレそうだから出来る限り控える。
この私小説には呪いが詰まっていた。既に分かっている答えに対する自問自答の繰り返しがあった。何度も別作品で提示してきた麻枝准が自分の人生に出しているほんの一筋の綺麗事への縋りが見えた。
恐らく俺を含め読者は麻枝准を理解することも労わることも不可能なんだろうが、そう試みようとする行為には意味が宿ってくれるんじゃないかって俺なりの縋りをやってみたいと思う。少なくとも、ただ「神様になった日」の反応がショックだっただけだ、駄々だと一言で切り捨てるのはまだ待ってほしい。「泣いた」と賛美するのも待ってほしい。
いつしか誰しも土に還る 所詮は遺伝子を運ぶ船 それでも笑って人は生きる 生まれたことさえ疑問を抱かず
この小説に出てくるだーまえの思考ルーティンだとか、言いたいことはSatsubatsu radioをはじめ他媒体でも存分に出されている。わかりやすいのは上に貼った曲。だーまえが恐らく、この小説とそう離れていない時期に作詞作曲したであろう曲だ。
読んだ人間は一発で分かるだろうが、出てきたフレーズが全くもって同じ。ONEぐらいの頃から明確に、繰り返し繰り返し泣きを描いてきた人だったけど、思ってることに関しても同じだったようで、フォーカスを当てる所を変え、何度も何度も解像度を上げて行き着く先は全て死に収束していった。
生きていることは喜びに対し不愉快な時間があまりに多く、自分と同じ疑問の連続を共有する相手もおらず、味方すると言ってくれた奴から敵になり、この息苦しい思考は病気のものではなく生来のものであり、才能があると言われようがあくまで社会人であり、それで自由きままに生きられる訳でもない。やりたい事がある訳でもない。なんとかしようとして失敗する、といった風に。
面白かったのは、十郎丸に比べて明らかにだーまえの要素が薄い、いわゆる一般的な死にたいに対して疑問を持つ方を主人公、時椿に据えた所だ。
そうでない人への共感を狙ったとこもあるのだろうが、十郎丸でグッと誇張させた自分の思考に対して否定の心の部分の抽出もあるんじゃないだろうか。アウフヘーベンの為のアンチテーゼ、みたいな。
内省的な思考を回す際自分の考えていること、至る結論が絶対正しいと思って考え続ける奴はいない。普段考える際は近しい他人、もしくは疑問から派生した主張を何となく心に浮かべて戦わせる程度のことはするんじゃないか。それをだーまえは、もう一人の自分として自問自答する為の思考のシステムを外側に用意した感じがした(書いてて思ったけど、これも世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド思い出すね)。人の幸福を素直に祝福できなかったり、子供みたいな当たり散らし方をしたり、言葉選びを間違えたりする、それを常に心で咎め諫める要素。
で、何よりこの小説が強烈なのは、こんだけ人生に対して生きやすくなるようアプローチして尚分かってくれる他人は一人も存在しないことにある。これだけ解像度をあげたところで、境遇の違う他人は所詮他人であり、理解できる筈がないっていう諦観がずっと付き纏う。理解を求めて紡ぐ言葉に、理解出来るワケねーだろって拒絶が常に織り込まれてる。当たり前っちゃ当たり前の、平凡な絶望。人が超当たり前にどん詰まる所。猫狩り族の長で時椿と十郎丸が分かり合った瞬間が一回として描かれることはなかった。
代わりに描かれたのは分かり合おうと隣に居続けた6日と、その短期間のみ思い合う他人に出会えた二人が始まって、終わるまで。スローモーな灰色人生に楽になる日なんか一回たりとも訪れることがないけど、ずるずると続けてしまう、それってなんで?ってところ。別離によって生まれたのは感動じゃなくて、死にたいって願望を持った人間に生きてほしいって願望を老いるまでかけることができれば、ひょっとして……っていう希望。
頭からケツまでしんどい。「麻枝准の生きている世界はこんなにも苦しくて、理不尽なものだった───。」じゃねえよ。俺らも生きてんの。そこに。大体の人間は鈍感なのか無責任なのかで気楽になるよう目をそらせる性分なだけで、気づいてもお互いに共有できないだけで、なんも変わんない。何から何まで共感出来た訳じゃないけど、分かんなくても言葉にしてぶつけられると、分かり合おうとする行為自体に絶えず意味を見出せる。自意識もあるだろうに、まだ形にして伝えようとしてくれたこの本はそういう価値を見出せるものでした。神日についての感想はそれはそれ、これはこれで撤回しないけど、やっぱり作品に宿ってる思想のコクは傑出してると思うし、別に才能を褒められた所で苦痛は和らがないが、それでもだーまえは話と曲を作る才能が人よりもあるんだと思います。どんなにフォーマットに則った作りをしていようが。
俺は、この結末で描かれたような、生きるための杖になる希望のことを呪いだと思っている。俺にとってそれは他人ではなく、趣味でありコンテンツだけど、それでも理由を見出してなんとか死にたいを誤魔化して生き永らえるような生き方をしている実感がある。だーまえもきっと思ってるだろう(思っててほしい)が、最後のアレは凄く都合的で、払わなくてもいい代償と引き換えの命なんじゃないか、そうすれば「解呪」で終わったんじゃないか。
人は、別に死んでもいいんじゃないか。って疑問に証明をすることなく、都合的でも呪いでも、ひょっとしてに縋ることを選んでいることに俺は最大の業を感じる。あの温かくて短い一瞬が終わっても、その業に向き合い続けることによって、もう一度再会することが出来た、そんな結末を有難がってる俺もそんな結末にした奴もホントに弱い。業まみれ。
そういう生き方しかできないんだろうな。「幸せという夢を叶えてみせるよ」って言っちゃったんだから。死にたくなってもつらくても一人でも、心の奥の明かりに縋って生きるしかないし、俺は解呪されなくてもいい。先達がそういう生き方をしている以上。飛べない翼にも意味はあるらしいから。生きるしかないんだろう。泣きこそしませんでしたが、この本はやはり人の感情を揺さぶるものだったように思います。泣くだけが感動ではないので。良い小説でした。
これ再販しろ。公式で。頼むから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
