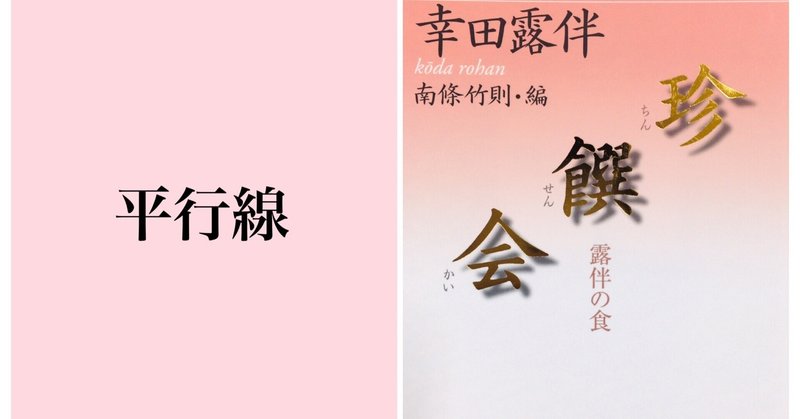
平行線
SNSを眺めていると、定期的に「〇〇は不要である」(例えば、古文)と発言して、酔いしれる人が出てくる。当然のように、反対意見が噴出して、様々な必要論・不要論が飛び交う。虚しいのは、それによって人の意見が反転することは、ほとんどないということだ。平行線を辿ったまま、一日、二日で盛り上がりの火は消える。
*
上記のような光景を目にするたびに、読み返したくなる作品がある。明治20年代に文学で一時代を築いた作家、幸田露伴の「菓子」という短い文章だ。
次に一部引用してみたい。
「必要不必要ばかりが世の中の唯一の標準では堪らない。第一大抵な奴は不必要な動物に違い無い。蝨の不必要、蚊の不必要、蚤の不必要とおなじく不必要の人間も少くはあるまいが、御手元拝見と来られて、貴殿は必要物か拙者は必要物かと論じる日には、国家に取って必要でござると威張れる人間は、そうたんとあるまい。よしんば威張って呉れたにした所で、それは自己存在の弁護に止まるのであるから、傍から認めない以上は何の権威もないことだろう。」
(幸田露伴著、南條竹則編『珍饌会』講談社文芸文庫、P100〜101)
タイトルがタイトルなだけに、読む前は、露伴が自身の好きな銘菓を熱弁する文章なのかと思っていた。冒頭から必要・不要論について語り出すとは、予想外である。
露伴の主張はご尤もで、もしあらゆる事象の価値基準が必要か不要かで決まってしまうのならば、そもそも人間自体不要なのでは、という結論になりかねない。
必要か不要かを論じるには、「誰にとって」というポイントも重要で、多くの「〇〇は不要である」論者は、結局「自分にとって」不要である、というレベルにとどまっている。
もし人間以外の存在が、人間を「必要か不要か」で評価する機会があるとしたら、どれだけ「必要」の側に票が集まるだろうか。明るい集計結果は見込めそうにない。
*
「不必要と必要とで物を論ずるのはおもしろくないと感じている吾人も、菓子を然程に必要の物であるとも思っては居らぬが、菓子があるのと無いのと、どちらがよいかと云えば、ある方がよいと思って居る。」
(幸田露伴著、南條竹則編『珍饌会』講談社文芸文庫、P101〜102)
露伴は必要・不要論を、きちんと「菓子」語りへ展開させ、羊羹類・キャラメル・黒砂糖・駄菓子など、個別の菓子についてコメントをしていく。
「〇〇は不要である」論を熱弁すること自体が、いかに不要であるか。露伴の「菓子」は、そのことを再確認させてくれる。
※※サポートのお願い※※
noteでは「クリエイターサポート機能」といって、100円・500円・自由金額の中から一つを選択して、投稿者を支援できるサービスがあります。「本ノ猪」をもし応援してくださる方がいれば、100円からでもご支援頂けると大変ありがたいです。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
