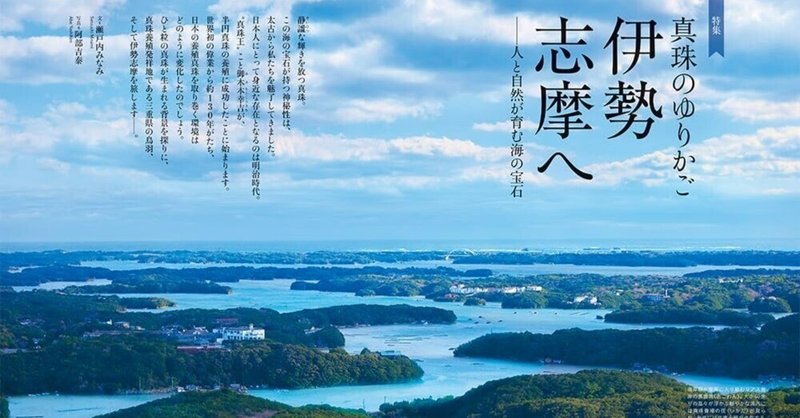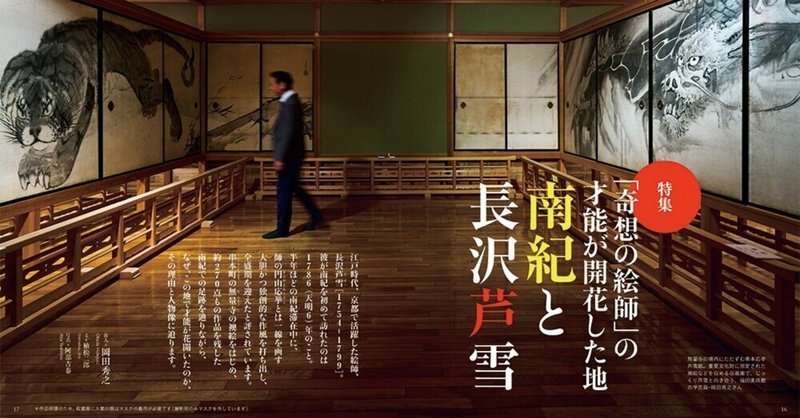#ほんのひととき

[10th anniversary of Mt. Fuji's registration as a World Heritage] SiteScenes of Mt. Fuji Today (Photo by Makoto Hashimuki)
How Japanese people feel about Mt. FujiExplanation by Noritake Kanzaki, folklorist Since antiquity, the Japanese have worshipped mountains, especially those of extraordinary appearance, which they believe are the dwelling places of gods. I