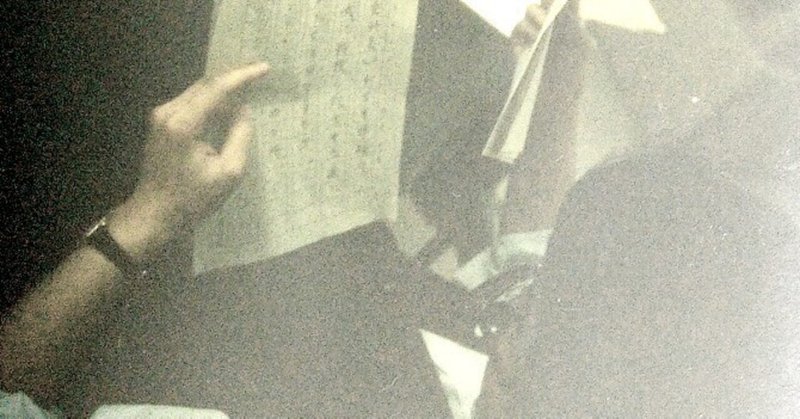
74 小説「ライフタイム」 10 転機
オーセンティックバー
ぼくにとって夜の銀座には、二つのランドマークがあった。交詢社とソニービルである。交詢社の近くには比較的入りやすいカウンターだけのバーがあった。ソニービルの近くにはとても入りやすい焼き鳥屋があって、コリドー街にも近かった。
一年あとから入社してきた殿山は、年齢はぼくと同じだったこともあって気が合った。彼は優秀で先輩たちが教えるまでもなく記事も書け、写真もうまく、インタビューも巧みで、いわばちょっと格が違う存在だった。たちまちエース級である。
「で、どうなったんです、ドライブデート」
その彼が誘ってくれたのが、交詢社近くのバーだった。交詢社は福沢諭吉が作った社交場として知られ、早慶戦で慶応が勝つとこのあたりを練り歩くのが風物詩となっていた。殿山はその大学の出身で、彼の父親もOBで日本長期信用銀行に勤めている。ロンドン、ニューヨーク、ケイマンでの勤務経験もあり、いまは銀行業務から離れて、数年前に作られたばかりの経営研究所に所属している。どちらかといえば、ぼくの作っている専門誌の執筆者の候補であり、その翌年ぐらいには、執筆を殿山を通して依頼し、連載してもらったこともあった。
「雨だったからなあ。ハンバーグ食べて、彼女が希望したんで早めにちゃんと送り届けたけど」
「なるほど」
その店はバーテンダーとして名の知れた人物で、多数の教え子が育っていた。ちょっと怖いのだが、ユーモアたっぷりの江戸っ子で、なぜかぼくたちを気に入って、いろいろな「味見」をさせてくれた。味見なので、タダだ。なぜか決まってぼくたちの会計はひとり五千円だった。それ以上は取らなかった。
殿山とぼくは週に一回、多いときは三回ほどそこで飲んだ。殿山はエース級でありながら、業界紙の仕事は誰より早くこなしてしまうので、自由な時間も多かったのだ。
気になる
「気になりますよね、松本奈美江」
殿山とエンドウは同期で、エンドウは彼をライバル視している。一度などまこさんに「なんで彼を優遇するのか」と噛みついていた。「私が女だからですか」と。
優遇しているわけではなく、殿山は仕事ができるので、ふさわしい仕事を与えただけだろうと、社内の多くは見ていた。それもまた鼻っ柱の強いエンドウ女史には気に入らないらしかった。
カワムラは「あれは辞めるね」と例によって言っていたのだが、その予言はいまのところ外れていた。
「……と付き合っているのかなと思ってたけど」と殿山は、ベテラン記者の名を挙げた。広島出身で甲子園には出られなかったが名門高校の野球部出身。野球で大学へ入り、いまも報道健保の草野球ではピッチャーで四番だ。もちろん妻帯者である。
「そうなのかな」とぼく。だったら、ぼくの助手席に乗ったりはしなかっただろうし、デートの間もとくにそんな様子はなかった。もっとも早く帰る点は気になったが。最初から、ぼくとの付き合いにはなんらかのリミッターを取り付けていた。
日曜日だったから、すでに月曜の仕事が気になっていたのだろう。ぼくもそうだったから。早く切り上げることは、ぼくにとってもいいことに思えたのだ。
職場では奈美江との親密度はまったく変わらない。部署が違うし、フロアも違うので仕事での接点はほとんどないのだ。
「たぶん、辞めちゃうだろうと思うけど」と殿山も、カワムラみたいなことを言う。「まこさん、正直、エンドウさんとはまったく反りが合わないけど、エンドウさんの仕事は認めている。だけど松本奈美江の仕事は気に入っていないみたいだから」
「そうなの?」
「エンドウはしたたかだよ。ネタを取るのに女を武器にしているのは確かだけど、一度会ったら忘れない点ではまこさんと同じぐらいの存在感だからね。松本さんは、仕事にあまり本気で取り組んでいない気がする」
殿山の分析は的確だった。
「『蓄財時報』って知ってますか?」と奈美江から聞かれて、ぼくは驚いたのだ。ハングリータイガーのハンバーグに魅了され、小さな口でそれを小気味よく食べる奈美江の姿に魅了され、こうした状況に満足していたのに。
倒れる
ぼくは殿山に、奈美江との会話を話すつもりはなかった。デートでありながら、彼女はぼくから「蓄財時報」について聞き出そうとし、ぼくはなにも隠すことはないので自分の体験を彼女に話した。まこさんや梅宮から得た情報も含めて。
それはどちらかといえば、「蓄財時報」を貶しているように聞えたに違いない。ぼくはいまの会社側の人間だと奈美江に宣言したようなものだ。
「私にも声がかかったんです」と奈美江は言う。「新しい雑誌を作る。それは専門誌ではなく、一般の雑誌として全国の書店に並ぶんだとか」
「うん。そこは確かに魅力的なんだけど、問題はスポンサーだよね。詐欺とまではいかないけど、やっぱり投資関係となると際どいことをしている会社もあるからさ」
もちろん、ぼくたちは、豊田商事事件を知っている。全国に二千億円ほどの被害総額を出した現物まがい商法だ。表向きは「金地金」に投資するとしてカネを集め、出資者には証券しか渡さない。金地金を買い付けていなかったのだ。社名もトヨタ自動車をはじめとるする豊田グループを連想させるようにあえてつけていた。衝撃的だったのは、その会長が隠れていた場所で刺殺された事件も起きたためだ。多数のメディアが隠れ場所を発見して押し寄せていた目の前で起きたのである。
奈美江は「蓄財時報」に行くとは言わなかったが、行きたそうに見えたし、ぼくも力尽くで止めることはしなかった。
翌日も仕事があった。前の晩に夜遅くまでバーで飲んだとしても、むしろ早めに会社に来て仕事をするのがぼくのやり方だった。
夢中になって仕事をしていたからか、気づいたら十一時を過ぎていた。なんだか騒がしい気がした。特に総務経理が珍しくバタバタしている。
血相を変えたカワムラがぼくのところに来て「まこさんが倒れた」と告げた。
「え?」
(つづく)
──この記事はフィクションです──
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
