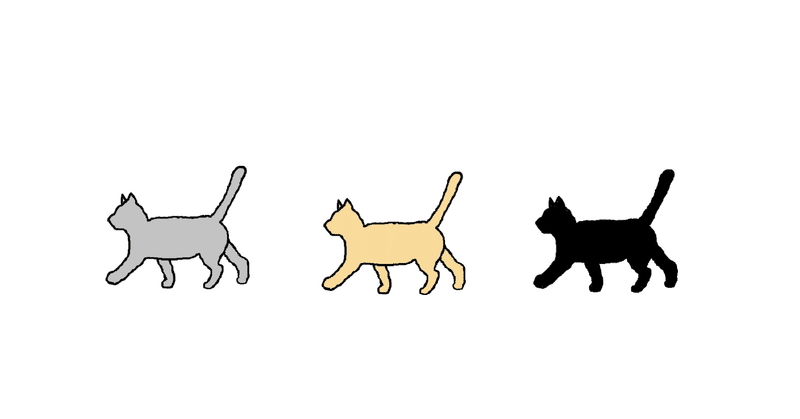
父とねこ
古い記憶。
それはまだわたしがおそらく5、6歳のころの。
父と幼いわたしは散歩に出かけた。
花が咲いていた。
わたしはそれを時々摘んでは歩いた。
季節は春だったのか、秋だったのか。
それとも夏の夕方なのか、寒くなかったことだけはなんとなく覚えている。
にゃー。
道よりも低いところから鳴き声が聞こえた。
父と声のする方へ近づいていくと、深い側溝の中にねこがいた。
フタはされていなくて、どうやら落ちて出られなくなってしまったようだった。
にゃー。
黄金色のしましま模様のねこ。
こちらを見上げて助けを求めていた。
父はしゃがんで、片足を側溝の中のねこの方へと伸ばした。
「ここをのぼったらええ。」
すねのあたりをぽんぽんと叩き、ねこに説明する。
ここやで、ここのぼるんやで。
すると、しばらくしてその黄金色のねこは駆けあがった。
色落ちして水色になったジーンズをはいた父の、すねからひざのあたりまでのぼり、そこからトンとジャンプ、無事地上にあがることができた。
そして父の足に何度も頭や体をこすりつけ、八の字にくるくるとまわった。
その後は家のすぐ近くまでついてきた。
父のことを恩人だと思ったのだろうか。
わたしが父のことを「すごい」と思った、一番古い記憶だ。
時は流れ、わたしは中学生。
いとこが捨てねこを2匹拾い、1匹飼って欲しいと言う。
元気なオスの子猫をもらうことになった。
このねこ、とんでもなく野生的だった。
素足で歩いていると、ネコ科特有の獲物を狙う格好で跳びかかってくる。
悲鳴をあげて逃げたものだ。
撫でようとすれば、わたしの手を両前足で押さえ、噛みつき、さらに体勢をかえて裏返り、両足で蹴る。(本人、いや、本猫的には遊んでるつもり。)
何度流血したことだろう。
ただお腹が空いた時は甘え、帰宅時には頭や体をこすりつけにくる。
とんでもないツンデレねこだった。
野生モードに入ると本当に怖くてわたしはお手上げだったのだけれど、ある日父が新しいアイテムを購入して帰ってきた。
革の手袋である。
これなら野生モードのねこを撫でてもケガをしない。
ねこも思う存分遊べる。
「おー、噛んでる噛んでる。強いなー。蹴ってる蹴ってる♫」
ムツゴロウさんばりに噛まれてうれしそうな父。
またも、父のことをねこ絡みで「すごい」と思った瞬間だった。
また月日は流れ。
わたし、社会人。
野生的なねことはお別れをし、また新たなねこが我が家にやってきた。
きれいな毛並みのチンチラ。
おとなしいねこだった。
その子がくる前に、母は亡くなっていたし、その後はわたし、弟、と順番に結婚して家を出た。
父とねこ、1人と1匹。
その絆は深かった。
その子は温厚で、あまり大きな声で鳴くことはなかったのだけれど、一度、父が旅行で家を空け帰った際、それまで聞いたことのないような大きな声で一言
「にゃ!!」
と言ったそうだ。
父いわく目も怒っていて、
「どこ行っててん!!」
と言われたと思ったのだと。
そのあとはすりすり、父にずっとくっついて離れなかったのだとか。
父はそのねこにもとても愛されていたのだなあと思った。
やっぱり「すごい」と思った。
父は70歳目前だがずっと変わらない。
単純で、子供みたいで、おおらかで、細かいことは気にしない、超マイペース、ポジティブ人間である。
正直、理解できないと思うことも多々ある。
でも父の愛は人類だけにとどまらず、「てのひらを太陽に」のように、みんなみんな友達なんだーと思っているのだと思う。
(傷ついたカラスを保護したこともあれば、カマキリのたまごを家の中で孵化させたこともある。)
無邪気な父に「いつまでも子供みたいなこと言って。。」とついつい思ってしまうけれど、そういう父の、ある意味大規模な愛に目を向けたい。
いい歳になった父といい歳になった娘だけれど、幼い記憶の中のようにどこかで「わたしのお父さんはすごいんだ」と思っていたい。
父はこの夏、70歳になる。
自由で楽しい日々を、できるだけ長く過ごせますようにと娘は祈っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
