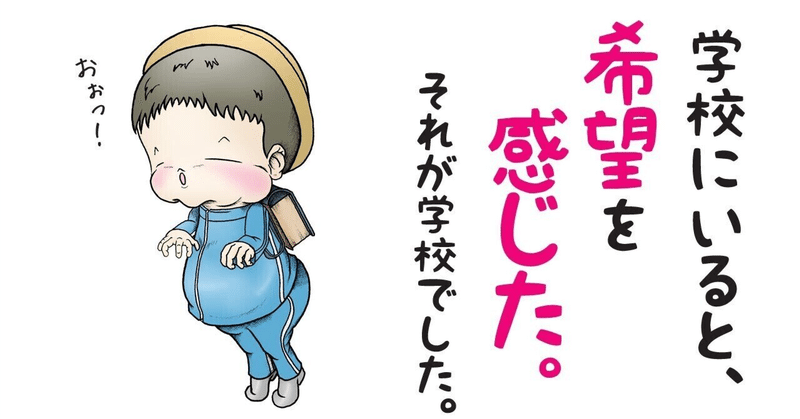
日本の学校は中世から始まった
江戸時代後期には、幕府や諸藩が領内に設けた学校と寺子屋、私塾等が相当整備されていた。
このことが学制による全国的、統一的な教育計画とその実施の素地となった。
(1)藩校:後の中等・高等諸学校の母体 約270校あった
(2)郷学:後の小学校の母体
(3)寺子屋:後の小学校の母体 1830~1844年に急増した。仁孝天皇。徳川家斉。
(4)私塾:後の私立学校の母体
「寺子屋」とは、上方で子供たちに文字の読み・書き、場所によってはそろばんを教える庶民の教育施設のことです。
寺子屋の起源は、中世の寺院での学問指南に遡ると言われる
江戸における町人の子弟の学問施設は「手習い所」「筆学所」「幼童筆学所」
全国に16560軒の寺子屋(に相当する施設)があった。
最古の学校とされる足利学校は、図書館のように書物が置かれ自習する場所だったようです。
大学という用語は、古くから有ったようです。
明治以降に、小学校・中学校・高等学校という用語が使われ始めます。
頭の悪い民族は奴隷(植民地)にされる運命
未開の民族と侮り日本を植民地化しようとした欧米諸国は、日本民族の教育水準・識字率・計算能力の高さに植民地化を諦めたといわれる。
現代の若者の教育水準は下がり続けており、半植民地(奴隷化)状態となっているとも言われる。
恵まれすぎると勉強しなくなる子供たち。
クルド人の親は、子供に教育を施さずに奴隷のように使うようです。
明治4年(1872年)に学制が敷かれる
明治5年~12年
教員養成
・明治5年(学制発布と同年):東京に直轄の師範学校設立
・明治6・7年:各大学区に官立師範学校を設置
・各府県は、これらの学校の卒業生等を招いて教員養成機関を設置
・明治10年頃から府県の師範学校が整備
・明治13年 各府県に師範学校設置義務化
・明治14年 師範学校教則大綱により師範学校の教則を統一
・明治20年 高等師範学校の拡充
・大正8年 大学や専門学校で所定の単位を修めた者に無試験で中等学校・高等学校の教員免許授与
・大正11年~昭和3年までに15の臨時教員養成所を設置(生徒総数1996人(S3))
・昭和10年 青年学校教員養成所を設置
・昭和19年 官立(国立)青年師範学校が設置される
学校
・尋常小学:下等4年(6歳~9歳)と上等4年(10歳~13歳)に二分
明治8年、学校数約2万4500校 就学率35.4%、明治16年には53.1%
・中学校:下等3年(14歳~16歳)と上等3年(17歳~19歳)に二分
初等教育
・明治33年尋常小学校を4年に統一。4年の義務制が実現。
・明治33年の小学校令:尋常小学校の授業料原則廃止
・明治33年「市町村立小学校国庫補助法」により、市町村立小学校教員の俸給の一部を補助。
・明治38年に就学率は95%を超える。
・明治40年尋常小学校を6年、義務教育年限を6年に延長。
・大正7年高等学校令も改正
高等科 3年、尋常科 4年の 7年制を原則。公立・私立も可。
・昭和16年に国民学校令公布。
・国民学校は初等科6年、高等科2年
・義務教育年限は高等科までの 8年と定めたが、戦時非常措置によりその実施は延期
・昭和16年 尋常小学校を国民学校初等科に、高等小学校を国民学校高等科に改める
中等教育
・明治32年:三系統に体系化
①男子の高等普通教育(中学校:5年制)
②女子の高等普通教育(高等女学校:4年制を基本)
③実業教育(実業学校:3年制)
・明治27年 高等学校令 高等学校創設(明治41年までに8校)
・小学校教育の継続教育機関及び中学校教育を補完するものとして、男子青少年について、
昭和14年から学年進行で義務化実施(7年制:普通科2年、本科5年)。
大東亜戦争終戦後の学校教育法が制定されるまで存在した。
※参考 昭和18年 青年学校数:16,267校 生徒数:約306万人
明治30年帝国大学令 戦後の国立大学
・明治30年京都帝国大学
・明治40年東北帝国大学
・明治43年九州帝国大学
北海道帝国大学(T7)、京城帝国大学(T13)、台北帝国大学(S3)、大阪帝国大学(S6)
工業大学、商業大学も作られた。
専門学校の拡大(明治 36年専門学校令制定)
大正9年に専門学校が昇格、慶應義塾大学、早稲田大学等が認可
青年学校
実業補習学校と青年訓練所の後継で、当時の義務教育期間である尋常小学校(のちに国民学校初等科)6年を卒業した後に、中等教育学校(中学校・高等女学校・実業学校)に進学をせずに勤労に従事する青少年に対して社会教育を行っていた。
普通科 - 入学資格を尋常小学校卒業者(12歳以上)、修業年限を男女ともに2年とする。
本科 - 入学資格を普通科2年修了者または高等小学校卒業者(14歳以上)、修業年限を男子5年・女子3年とする(1年の短縮も可能)。
12歳(13歳) 青年学校普通科1年 →中学1年
13歳(14歳) 青年学校普通科2年 →中学2年
14歳(15歳) 青年学校本科1年 →中学3年
15歳(16歳) 青年学校本科2年 →高校1年
16歳(17歳) 青年学校本科3年 →高校2年
17歳(18歳) 青年学校本科4年 →高校3年(男子のみ)
18歳(19歳) 青年学校本科5年 →大学1年(男子のみ)
研究科 - 入学資格を本科修了者、修業年限を1年以内とする。
専修科 - 入学資格を本科修了者とする(修業年限の規程なし)。
青年学校の教育内容
普通科
男子 - 修身および公民科・普通学科・職業科・体操科
女子 - 修身および公民科・普通学科・職業科・家事および裁縫科・体操科
本科
男子 - 修身および公民科・普通学科・職業科・教練科
女子 - 修身および公民科・普通学科・職業科・家事および裁縫科・体操科
研究科 - 本科の科目に関連して必要に応じて定める。ただし修身および公民科は必須科目とする。
・昭和18年 中等学校令:従来の中・高女・実業学校を中等学校として統一(修業年限4年制)
1947年(昭和22年)4月1日 学校教育法の施行に伴い、青年学校令が失効。
従来、教育者と学生らは警察不介入を貫いていましたが、大学などでは反体制左翼(過激派)の拠点となり下がりました。
現在の学校警察連携制度は、違法行為(非行)を繰り返している子どもの立ち直りや、犯罪被害に遭うおそれがある子どもを守るために、学校と警察が相互に児童・生徒の個人情報を提供して、学校、家庭、警察が一体となった指導や支援を行うものです。
地域と学校の連携、体験学習
地域と学校が連携・協働することで、新しい人と人とのつながりも生まれ、地域の教育力の向上につながる。
地域の教育力の向上は、地域の課題解決や地域振興、さらには、持続可能な地域社会の源となりうる。
義務教育
誰もが教育を受けられる環境が整備されていて恵まれている
しかし、勉強しないままでいると、学力はもちろんのこと、勉強に対する自信もなくなってしまいます。
学力が下がるとテストで良い結果を残せなくなることが増え、自己肯定感が低下する。
最終的に勉強以外でも自信を失ってしまいかねません。
また、学力低下によって先生からの注意や補習の呼び出しが増えると、自信がなくなってしまう生徒もいます。
当横キッズ(薬中、アル中、児童買春)、半グレ集団、反社構成員になっていくものもいる。
高校不要説
高校の3年間が無駄という考え方もある
小学校>中学校>大学>大学院で良いのでは?という指摘。
学校教育法第50条によると、高校は「中学校における教育の基礎の上に、心身の発達および進路に応じて高度な普通教育、専門教育を施すことが目的」とされています。
大学に進学する資格を得る目的もある?
優秀な学生は飛び級
いわゆる「飛び入学」とは、特定の分野について特に優れた資質を有する学生が高等学校を卒業しなくても大学に、大学を卒業しなくても大学院に、それぞれ入学することができる制度です。年数を無駄に過ごさない制度。
・大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること
・特に優れた資質の認定に当たって、高等学校の校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫していること
・自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと
ADHD(注意欠陥・多動性障害)に理解がなかった時代は劣等生扱い
天才もうまれるが、昭和ではバカ扱いされることが多かった。
ADHDの特性として、注意散漫や集中力の低下が挙げられます。
周囲の音や視覚的な刺激に気を取られやすく、ひとつのことに集中することが難しいのです。
また、ADHDの子どもは、持続力が弱いこともあります。
同じことを続けるとすぐに飽きてしまい、勉強に集中する時間が短くなります。
ADHDの子は、もともと勉強が苦手ということはありません。
偉人にもADHDの人がいて、好きな学科はものすごい集中力で勉強することがある。
独学で授業を追い越してしまう子供もいる。
逆に、興味のない学科は完全に捨てる。関心がないことは一切勉強しない。
全科の学習を無理強いすると学校に登校しなくなる。
ADHDの人は、顔つきに特徴があるとわれています。
例えば、実年齢より幼くみられたり、目が離れていたり、歯並びが悪かったり歯磨きしていなかったりすることがあります。
また、無気力な目つきや肌の白さも特徴的だといわれています。
外見や学習状況を見て、親や教師が早期に気付いて、小児精神神経内科を受診させるべきでしょう。
好きなことは飽きずに何年でも何十年でも継続できるのも特徴です、そこを見つけて伸ばすべきです。
ウィル・スミス
黒柳徹子
さかなクン
5つの特徴
1. 自分のこだわりを貫く
2. 過剰な集中力
3. 同時にいくつものことができる
4. エネルギッシュで活動的
5. 発想が豊かすぎる
職人・天才養成所?
日本も得意分野を伸ばす教育が始まっているので、そう言う学校だと天才が誕生するかもしれない。
勉強はできなかったが職人としての腕は一級
勉強しなかったが演者として認められている
芸は身を助ける
逆に勉強できたのにうだつの上がらない人の特徴
・ こだわりがない
・ ゲーム以外に集中力がない
・ 一つのことしか出来ない
・ 与えられた仕事だけやってる
・ 発想が貧素である
・ 口だけは達者で、他人を論破したがる
・ 世間知らずで非常識である
・ プライドが高く横柄である
・ 他人を見下し優越感に浸る
・ 破産しやすい
東京大学を卒業したが出世できない会社員や平凡な官僚で終わる人もいる
出世を目指したが挫折すると立ち直れないなど、二の手がない人。
人手不足で売り手市場
バカでも正社員になれちゃう
企業側もバカとハサミは使いようで良く切れると考えてる
ただし、百均のハサミと同じで切れなければ捨てられる。
コロナ禍で勉強せず遊び呆けた人は、勉強した人と差がつく
切れ者は、記憶力が良く頭の回転が速い人を言う。
記憶力が無く、頭の回転も悪い人は政治家くらいしか仕事がない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
