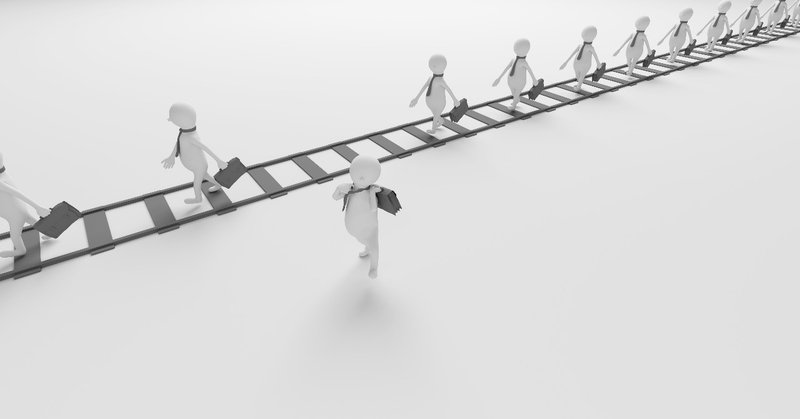
離職率の高いベンチャーが成長しない理由(1)
こんにちは。Hondaです。今日は離職率の件に関してベンチャー経営者の視点から触れてみようと思います。
離職率というのは社員が会社を辞める割合ですが、実際の計算方法は定まっていません。場合によって違うのです。
1)1年間で全体の社員数で離職した社員数を割って計算
離職した人の数 / 全体の社員数 = その年の離職率2)新入社員が1年間に離職した数で表示(1年間)
新入社員の辞めた数(1年間) / 新入社員の全体数 = 新入社員の離職率新卒社員の数を基準にすることもありますし、その年に入った人(中途採用者数)も含めて表示させるなど様々です。
離職率の大体の定義は行いました。まちまちですがこの数字が高いことはつまり「会社に人が定着しない」ことになります。50%なら10人入って5人辞めるということです。
結果。5人は残りますが1年目にこの離職率だと3年経つと誰も残って居ない可能性が出て来ます。怖い話です。
ここから今回のお題であるベンチャー企業の経営の視点からの話をしたいと思います。私が住んでいる福岡市は日本の地方都市では最も成功したロールモデルと言われています。界隈にはベンチャー企業だらけですし、私の会社もFUKUOKA growth nextというベンチャー企業育成を目的とした施設に入居しています。
ベンチャー企業は最初は社長一人という場合も多くあります。自営業・個人事業主・フリーランサーと対して変わりません。ここから会社を大きくしていくには売上・利益・社員の数の3要素の増加を果たして行かないと行けません。

自社の商品ないしサービスを販売して行く場合、自分の扱っているモノの性質を考えてください。例えばプログラミング開発を請け負っている場合、案件の数が増えて行くと単純に売上が比例して上がって行くというイメージが描けます。
売上 = その月の消化案件数
受ける案件の数が増えれば増えるほど良く、消化可能な案件の数の容量を増やすには人の数が比例して多くなることが判ります。簡単な話ですね。
1人の力 = 1 = 消化可能な数
10人の力 = 10 = 消化可能な数
入社していきなり仕事が出来る人が増えて行けば単純な話で上の式で済みますが、実際は入社した人を自社の仕事に馴染むように色々と教えて行く係が必要になります。教育係の必要性です。
会社を大きくして行くのに必要な事業とメンバーのイメージが定まっているか?

上の方で「社長一人」というケースに触れました。1人から社員を採用して数人、採用したとします。この場合、3としておきましょうか。
社長が今まで会社の売上の100%を上げる体制を取っている場合、社長のタスクは会社の売上を100%上げながら3人を教育して行かないと今までの体制を維持して行けなくなります。
それがどのくらいの期間になり、どれくらいの経費が掛かるか計画ができているでしょうか?
3人に社長が今までやっていた仕事を振り分けて行くのか、それとも別にことをやらせて行くのか?という方針で指導の内容も全く違って来ます。
経営の分岐点です。あなたが経営者ならここで大きな判断を迫られます。
同時にリスクを抱えることになります。社長の仕事が職人芸であればあるほど、社員は社長の仕事を覚えた途端に独立して居なくなるリスクが発生します。一昔前の職人芸の世界で後継者不足が嘆かれていることもありますが、大半の経営者兼伝統職人はこのリスクがあったから、伝統芸的な職人芸を社員に教えなかったのです。
教えた技術は盗まれ、教えた経費は損失に変わり、社長の稼働時間を減らした分だけ売上が下がり、社員が少ないうちのベンチャー企業では社員が離職することの損失はそのまま会社を倒産させかねないリスクに変わります。
経営上のリスクを少なくするなら初期メンバーないし創業メンバーには、あなたが専門でない分野の人材を取り込んで分業を出来るメンバーを選ぶべきでしょう。
そしてもし、そのメンバーが欠けたときに代替となる人物を思い浮かべられるように、そのメンバーの仕事の内容をよく理解しておくことです。
今一度、あなたの会社のサービスを考えて見てください。職人芸のサービスを持っているなら食べるには困りませんが、会社を大きくして行く、スケールして行くという事業の成長経路がとても難しいことがわかるはずです。それは採用/離職リスクがとても大きいからです。
とりあえず今回はここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
