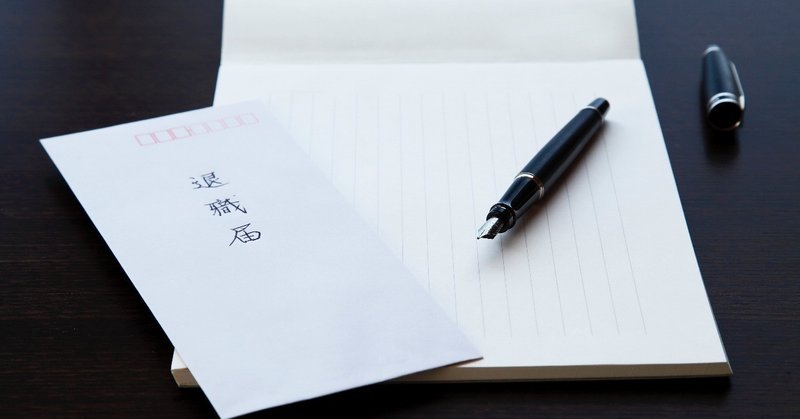
離職率の高いベンチャーが成長しない理由(2)
猛暑という言葉がぴったりな18年の夏ですね。先週は豪雨で避難していたのに今度は熱中症にかかりそうな猛暑と季節の変化が恐ろしいくらいのギャップを感じます。
このシリーズでは前回は職人芸が事業の根幹であると、離職された場合の損失はとんでもない積算になるということに触れました。今回は離職率が高いと会社の生産性を下げることに触れようと思います。
17年の初めあたりから政府が働き方改革に関しての法案を可決しようとしています。今回はこの内容には触れませんが、社会的に見て日本は生産性が低く、長時間労働や残業が当たり前になっているのでこの慣習を無くしたいと思っている人々が数多くいることは事実です。
会社は様々な役割を果たす人々が集まっている場所です。経理や総務、営業や開発などです。生産して富を生み出す役割が営業や開発なら、経理や総務は会社が社会に対して負うべき税金や厚生年金などの義務を果たす役割の箇所です。よって経理だけ、総務だけでは会社の生産的な役割を果たすことが出来ません。
この営業や開発の部署はある程度のスキルを要求される部署でもあります。顧客が満足するレベルのサービスや生産品を消費者に販売することでお金を得られます。消費者が満足しないレベルの商品やサービスは思うように対価が得られません。
つまりある程度の水準のサービスがないと会社は成り立ちません。そのある程度の水準のサービスを開発する部署の離職率が高いとどういう状況になるでしょうか?
例えば10人必要な部署で1年間の離職率が3割とします。
10人で稼働している状態を100%とすると、3割の離職率なら4ヶ月に1名抜けますから、4ヶ月目に90%、8ヶ月目に80%、12ヶ月目に70%の稼働率になります。
そして13ヶ月目にまた3名の補充がされる。というサイクルにいます。

一見すると稼働率が70%を切るタイミングで上手く人員を補充するサイクルが出来ているように見えますが、これが数字の罠というものです。
新しく入って来た3名が熟練した社員と同じ数字を挙げるとは限らない訳ですし、その3名を指導する役割の人物が必要になって来ますから、この部署の平均的な稼働率は実際は管理職ないし教育係が1名と4名の部員の5人チーム2名と見た場合は50%程度しかこの部署では生産に回れていない時期があることになります。

「一人前」の社員が5名残っているのは離職率3割の会社では「まれ」でしょう。3年間でほぼすべての社員が入れ替わり立ち代りしてしまうと見るべきなのが数学的な見地から正しい見方と言うべきで、そのような会社の部署はリーダーを担う役割の人が育たないのでこの部署は常にシロウト同然で開発や営業を行っていると見るのが正しいでしょう。
こうして見るとベンチャー企業では離職率が3割もあると企業自体が成長していくことはとても難しいことが判ります。なんせ実際に生産をしている人員は5〜60%で、その補充に掛かる費用など経費の掛かり具合が会社の利益を圧迫するからです。
下手をするとブラック企業では稼働率は実質的には30%程度という場合もあるのではないでしょうか?よほど粗利が高く、ボッタクリが許される業界体質なのかも知れないですね。
いくら人が居ても生産している人数の稼働率が低ければ仕事量が10としても10人の稼働率が70%なら1.4、50%なら2。30%なら3.3となり、と仕事を消化する時間は50%を切った時点からすごい勢いで増えていきます。
この稼働率を見直すだけでも会社が離職率を減らす努力をする価値があることに経営の重点をおくべきと理解しますし、生産性の向上/働き方改革で取り沙汰される残業時間の軽減に直結することがわかります。
このように離職率が高い企業では稼働率が低いことで開発生産性が低くなり、生産性が低くなることでサービスの質が落ち、サービスの質が落ちることで売れなくなる or 顧客が居なくなっていくという負のサイクルに入ってしまうことがあります。
離職率が高くなる要因は別に経営者が社員に無理を強いるだけでなく、社員がやりたい仕事をさせて貰えないとか、努力に応じた裁量権を与えて貰えないなどの場合もありますし、要因は様々です。
それでは今回はこれまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
